ブランドいちご大競争
2025年4月22日(火)午後5時から放送予定の『午後LIVEニュースーン』(NHK総合)では、「ブランドいちご大競争」という特集が組まれます。いちごの輸出が近年急速に伸びている中で、各地では新品種の開発が進み、さらにIT技術を活用したスマート農業も急成長しています。今回は、番組の事前情報をもとに、日本のいちご産業の最新事情を詳しくご紹介します。放送後には、実際の番組内容を反映した追加情報をお届けする予定です。
いちごの輸出が伸びる背景と現状

日本のいちごは、その甘さ・香り・美しさが評価され、特にアジア圏で人気が高まっています。これまでは国内消費が中心でしたが、近年は台湾、香港、シンガポール、タイなどへの輸出が増加。農林水産省も、いちごを「輸出重点品目」と位置付け、輸出額を2030年までに253億円に増やす目標を掲げています。
・日本のいちごは完熟で収穫されるため味が良い
・輸送中の品質保持技術の向上が後押し
・現地の富裕層や贈答品需要とマッチしている
こうした流れの中で、輸出を前提にした新品種の開発や栽培技術の改良が急務となっているのです。
全国で進む新品種の開発とブランド戦略

各地域では、独自の気候や土壌条件を活かしたブランドいちごの開発が進んでいます。たとえば、栃木県の「スカイベリー」や佐賀県の「天使の実」は、大粒で甘味が強く、見た目も美しく、海外でも人気があります。
・長崎県「ゆめのか」…酸味と甘味のバランスが良く、輸送にも強い
・福岡県「あまおう」…粒が大きくジューシーで、海外の展示会でも高評価
・岐阜県「美人姫」…超特大サイズで話題性があり、ギフト用として人気
これらの品種は、地域の農業を活性化させるだけでなく、日本の果実ブランド力を世界に発信する重要な資源となっています。
種子繁殖型品種の登場とその意義
従来のいちごは、ランナーと呼ばれるつるで苗を増やす「栄養繁殖」が一般的でした。しかし、今注目されているのが「種子繁殖型品種」です。これは種から育てる方法で、以下のような利点があります。
・苗のウイルス感染リスクが減る
・生育がそろいやすく、機械化が可能
・苗の流通コストが削減できる
農研機構では、収量・病害虫耐性・輸送性を重視した14系統を選定しており、これらは今後の輸出戦略の中核になると期待されています。
スマート農業で変わるいちご栽培の現場
いちご栽培では、AIやIoT技術を活用したスマート農業の導入が全国的に進んでいます。経験や勘に頼っていた農作業が、データ分析や自動制御によって再構築されているのです。
・カメラ+AIによる収穫予測…花や実の状態をAIが画像解析し、収穫時期を正確に判断
・環境センサーによる自動管理…温度・湿度・二酸化炭素を自動制御し、最適な環境を保つ
・クラウドに蓄積されたデータの活用…農場ごとの最適な育成条件を学習し、改善に役立つ
・収穫ロボットや選果ロボットの導入…人手不足の解消と作業の精密化に貢献
これにより、品質が安定し、効率も大幅に向上しているだけでなく、農業が新たな若者世代にとって魅力的な職業へと変わりつつあります。
環境と調和した持続可能ないちごづくり
輸出先の多くでは、農薬残留基準が日本より厳しく設定されているため、環境負荷の少ない栽培法の開発が進んでいます。
・天敵生物の活用…害虫を食べる昆虫を導入し、農薬を減らす
・捕虫器やフェロモントラップの導入…害虫を誘引して被害を抑制
・特殊フィルムや太陽光を活用した温室栽培…エネルギー効率を高め、環境への影響を軽減
福岡県のある農園では、特別栽培農産物認証を取得したいちごが台湾市場で高い評価を得ており、こうした取り組みは今後の標準になっていくと見られています。
ブランドと技術の融合で未来へ
いちごは、日本を代表する果実のひとつであり、農業の未来を示す指標にもなり得る存在です。新品種の開発、スマート農業の導入、輸出戦略、そして環境への配慮。これらすべてが一体となることで、日本のいちごはさらに進化を続けています。
今回の『午後LIVEニュースーン』では、こうした最前線で活躍する農家や研究者の取り組みが紹介される予定です。放送を通じて、私たちの食卓に届くまでの“努力と工夫”に光が当たることでしょう。
放送後、詳しい内容が分かり次第、最新の情報を更新します。
※本記事は事前情報をもとに構成されており、実際の番組内容とは一部異なる可能性があります。ご了承ください。

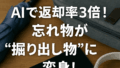
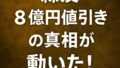
コメント