意外に知らなかった輪ゴムの世界と進歩
2025年4月26日(土)12:15~12:40にNHK総合で放送された『探検ファクトリー』では、大阪府泉佐野市にある株式会社共和 泉佐野工場が舞台となり、輪ゴムの製造現場が特集されました。出演は中川家(礼二さん・剛さん)とすっちーさん。身近な輪ゴムの世界に、これほどの技術と歴史が詰まっているとは知らなかったという驚きの内容となりました。今回の放送内容を詳しくまとめてご紹介します。
100年以上続く輪ゴム作りの歴史と泉佐野工場
探検の舞台となったのは、大阪府泉佐野市にある株式会社共和 泉佐野工場です。ここは、日本の輪ゴム文化を支える重要な拠点のひとつで、創業は1923年。100年以上もの間、輪ゴム作りを続けています。工場では、年間およそ2000トンもの輪ゴムを製造しており、取り扱う輪ゴムの標準的な種類だけでも73種類にのぼります。泉佐野市といえば芸人の間寛平さんの出身地としても知られ、町の人々にも親しまれている土地です。
泉佐野工場では、ゴムの原料に使われる天然ゴムを厳選しています。原料は東南アジアで栽培されているゴムの木の樹液を固めたもので、特に高純度の原料のみを使用しているのが特徴です。このこだわりが、伸びがよく、透明感があり、丈夫な輪ゴムを生み出す秘密のひとつになっています。
輪ゴムができるまでの詳しい工程
番組では、輪ゴムの製造工程が細かく紹介されました。硬い天然ゴムの塊が、どのようにして柔らかくなり、きれいな輪ゴムに生まれ変わるのか、その流れはとても興味深いものでした。
-
天然ゴムと配合剤をミキサーで混ぜ合わせる
まず、天然ゴムに硫黄や各種配合剤を加え、大型のミキサーで練り合わせます。ここでゴムの基本的な性質が決まります。 -
巨大ローラーでさらに練り、異物を取り除く
次に、ローラーで何度もゴムを伸ばしながら練り、異物を除去してなめらかな状態に仕上げます。この工程はとても重要で、ゴムの均一性を高める役割を持っています。 -
熟成を経て、押し出し成形へ
練りあがったゴムは一定期間寝かされ、適度な弾力を持つように熟成されます。その後、押し出し機により空気を含ませながらチューブ状に成形されます。 -
加硫(バルカナイズ)処理を行う
押し出したゴムチューブに熱を加える「加硫処理」を行います。これにより、ゴムの弾力性と強度が一気に高まります。 -
切断、洗浄、乾燥、検査、包装
加硫されたチューブを一定幅で切断し、輪ゴムの形にします。その後、洗浄と乾燥を行い、最後に厳しい品質検査を経て、包装され出荷されます。
輪ゴム一つを作るために、ここまで多くの工程と手間がかかっているとは驚きです。株式会社共和の泉佐野工場では、すべての作業に細心の注意が払われ、熟練の技術者たちが品質を守り続けていました。
輪ゴムに込められた職人たちの誇り
番組では、工場の社員が「利き輪ゴム」に挑戦するシーンもありました。目隠しをして触った輪ゴムが自社製品かを当てるという企画で、見事に正解。輪ゴムの質感や伸び方にまで精通している社員たちのプライドと製品への愛情が伝わってきました。
また、工場の広報担当者が、輪ゴムを使った簡単なマジックを披露。
輪ゴム同士が自然に絡まったり外れたりする様子に、出演者たちも大きな関心を寄せていました。輪ゴムが持つ「しなやかさ」と「強さ」が、こうした楽しい使い方にも活かされていることを知ることができました。
日常生活を支える多彩な輪ゴムたち
株式会社共和では、輪ゴムの基本的な形だけでなく、さまざまな用途に対応した製品も開発しています。
-
電気コードを束ねるために耐久性を高めた輪ゴム
-
ノートや書類をまとめるための幅広タイプの輪ゴム
-
作業効率を上げるために色分けされたカラフルな輪ゴム
-
食品工場や医療機関向けに開発された耐熱・耐油タイプの輪ゴム
このように、輪ゴムは私たちが普段気づかないところでも、さまざまな形で活躍しているのです。
まとめ
今回の『探検ファクトリー』では、「輪ゴム」という小さな存在の裏に、100年以上積み重ねられた技術と情熱があることを知ることができました。株式会社共和 泉佐野工場では、天然ゴムという自然の恵みを丁寧に加工し、熟練の技と最新の技術を融合させて、私たちの生活を支える輪ゴムを作り続けています。
輪ゴムは、ただの文房具ではありません。一本一本に、人の知恵と努力、そしてものづくりに対する誇りが込められているのだと、今回の放送を通じて実感しました。これから輪ゴムを見るたびに、きっとその背景にある「物語」を思い出すことでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

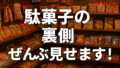
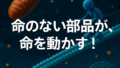
コメント