人体III 第1集「命の源 細胞内ワンダーランド」
2025年4月27日、NHK総合で「NHKスペシャル 人体III 第1集 命の源 細胞内ワンダーランド」が放送されました。司会を務めたのは、これまでも人体シリーズでおなじみのタモリさんと、iPS細胞研究で知られる山中伸弥さんです。今回のテーマは「命とは何か」。私たちの体をつくる細胞の中に広がる不思議な世界に迫り、命の根源を探る内容となっていました。
細胞が命を動かす舞台に

人間の体には約37兆個から40兆個の細胞が存在すると言われています。それぞれの細胞が、体の中で大切な役割を担っており、日々休むことなく働いています。今回の番組では、その細胞の中でどのように命が営まれているのかを、最新のCG技術と精密な顕微鏡映像を使ってリアルに描き出しました。まるで体内を冒険するかのような感覚で、細胞の世界が表現されていました。
特に注目されたのは、1951年に誕生したHeLa細胞です。アメリカ・テネシー州出身の女性、ヘンリエッタ・ラックスさんが子宮頸がんで闘病中、医師によって採取されたがん細胞がもとになっています。この細胞は特別で、体の外でも生き続け、異常なほどの増殖力を発揮しました。それまでの細胞は、体外に出ると短期間で死んでしまうのが当たり前だったため、HeLa細胞の存在は大きな衝撃を与えました。
-
HeLa細胞は、世界で初めてヒトの細胞を長期培養できた細胞
-
採取された1951年から70年以上経った今も、世界中の研究施設で使われ続けている
-
これにより、ポリオワクチンの開発やがん治療薬の研究などに多大な貢献を果たしました
-
ワクチン開発だけでなく、遺伝子研究やエイズ治療の研究にも欠かせない存在となっています
番組では、HeLa細胞の広がりを示すため、バルセロナやロンドン、仙台など世界各地の研究施設を映し出し、今もこの細胞が命の研究に欠かせないことを具体的に紹介していました。東北大学やヴァンダービルト大学など、さまざまな場所でHeLa細胞が科学の最前線に生かされている様子が伝えられました。
細胞一つ一つの命の営みが、私たちの未来を支える力になっていることを、改めて強く感じる場面でした。一人の命から生まれた細胞が、無数の命を救ってきたという事実は、命のつながりを実感させる象徴的な出来事として番組でも丁寧に描かれていました。
命をつなぐ細胞内キャラクターたち

細胞の中は、ただの小さな部品が集まっているだけの場所ではありません。そこには、命を支えるために動くたくさんのキャラクターたちがいます。番組では、その中でも特に重要な役割を果たしている「キネシン」というモーターたんぱく質に注目していました。
キネシンは大きさがわずか80ナノメートルというとても小さな存在です。それなのに、細胞の中で2本足を使って歩くようにして物質を運んでいるのです。エネルギー源は、私たちが食べ物や酸素から作るエネルギー。このエネルギーを使って、キネシンは休むことなく働き続けています。
-
キネシンは、細胞内にある小胞(物質の袋)を運びます
-
1歩ずつレールの上を進み、荷物を目的地まで届けます
-
神経細胞では、感情に関わる神経伝達物質を運ぶ役割も担っています
このキネシンがなければ、私たちは喜怒哀楽の感情を持つこともできず、体を動かすこともできないのです。細胞の中で起きているこの地道な作業が、実は私たちの生きる力そのものになっています。
さらに、番組ではキネシンと反対方向に進む「ダイニン」についても紹介されました。ダイニンは、外から取り込んだ荷物を細胞の中心に運ぶ役割を担っています。
-
ダイニンは、レールである「微小管」を使って細胞内を移動します
-
キネシンとダイニンはそれぞれ進む方向が逆で、細胞内輸送をバランスよく支えています
この微小管も細胞の中に張り巡らされ、絶えず作られたり壊されたりしながら、目的地に合わせて臨機応変に伸びていくという柔軟な働きをしていることが番組で詳しく描かれていました。
細胞内の世界は、単なる物質運搬ではなく、奇跡のようなチームワークで成り立っていることが、鮮やかなCG映像を通じて実感できました。小さなキャラクターたちが力を合わせて命をつなぎ、私たちが感じ、考え、動くことを支えているのです。
喜怒哀楽も細胞から生まれる

脳の中には約1千億個もの神経細胞が存在し、それぞれが網の目のようにネットワークを作りながら、私たちの感情を生み出しています。喜び、怒り、悲しみ、楽しさ──こうした喜怒哀楽は、すべて神経細胞同士のやりとりによって生まれているのです。
神経細胞が感情を生み出す仕組みはとても精密です。細胞からは神経伝達物質と呼ばれる特別な物質が放出され、それを別の神経細胞が持つ受容体がキャッチすることで、感情の信号が伝わっていきます。この一連の過程がスムーズに進むことで、私たちは日常の中で自然に感情を感じることができるのです。
この重要な流れを支えているのが、先ほど紹介されたキネシンです。キネシンは、神経細胞の中で神経伝達物質を小さな袋(小胞)に包んで運び、決まった場所まで届けます。運ばれた小胞は、必要なタイミングで中身を放出し、感情を司る信号として働きます。
-
1つの神経伝達物質を運ぶために必要なキネシンの数は約200万〜1000万個
-
それぞれのキネシンが2本足で歩くように移動しながら、正確に荷物を届けています
-
キネシンがいなければ、感情を伝える物質が届かず、喜怒哀楽を感じることができなくなります
このように、私たちの感情は自然に湧き上がるものではなく、細胞の中で何百万もの小さなキャラクターたちが協力して生み出しているのです。感情一つにも、見えないところで大きな努力と緻密な連携が支えられていることが、番組を通して深く伝わってきました。
細胞たちが織りなすチームワークのすごさを知ると、私たちの感情もよりいっそう尊いものに思えてきます。
体を動かすエネルギーと細胞の役割

私たちが体を動かしたり、元気に活動したりできるのは、糖質というエネルギー源があるからです。この糖質を体内に取り込んで利用するためには、筋肉などの細胞にグルット4というたんぱく質が必要不可欠です。グルット4は、細胞の表面に現れて糖を取り込み、体のエネルギーに変える役割を果たしています。
しかし、グルット4は自然に細胞の表面に現れるわけではありません。ここでもまた、細胞内キャラクターたちの見事な連携プレーが必要になります。
-
食事をすると血糖値が上がり、すい臓からインスリンというホルモンが分泌される
-
インスリンの合図を受けた細胞内で、キネシンがグルット4を必要な場所まで運搬する
-
グルット4が細胞表面に到達することで、糖質を取り込む準備が整う
この一連の動きが正常に進まないと、血糖値をコントロールできず、高血糖や低血糖といった命に関わる重大な問題を引き起こしてしまいます。細胞の中の運搬作業が、私たちの健康を左右しているのです。
番組では、スペインのサッカー選手セルジ・サンペールさんの例も紹介されました。彼は1型糖尿病を患っており、体内でインスリンを作ることができないため、毎日インスリン注射を欠かすことができませんでした。サンペールさんの体験を通して、糖質をエネルギーに変える細胞のしくみが、どれほど繊細で大切かが、より具体的に伝えられました。
-
1型糖尿病では、インスリンが分泌されないため、グルット4を適切に働かせることができない
-
そのため、血糖値の管理が難しくなり、運動や生活に影響が出る
-
サンペールさんも、毎日の注射と血糖コントロールを続けながらプロ選手として活躍してきた
糖質を取り込み、エネルギーに変えるという当たり前に思える体の機能も、細胞たちの緻密な連携によって初めて成り立っていることが、番組では丁寧に描かれていました。細胞の中の小さな動きが、私たちの日常を支えていることを改めて知ることができました。
細胞内で繰り広げられる奇跡のチームプレー

私たちの体の中では、目に見えない世界で約10万種類ものたんぱく質キャラクターたちが働いています。それぞれが役割を持ち、細胞内で絶え間ない連携プレーを繰り広げることで、私たちの命は支えられています。番組では、この驚くべきチームワークがどれほど精密で、奇跡的なものであるかが丁寧に描かれていました。
細胞内のキャラクターたちは、さまざまな役割を分担しています。
-
遺伝子を読み取るキャラクター:DNAから必要な情報を取り出し、次に必要な作業を指示します
-
たんぱく質を組み立てるキャラクター:設計図に従って、体を作る材料や道具を正確に作り上げます
-
物質を運ぶキャラクター:キネシンやダイニンのように、必要な物資を目的地まで運搬します
このように、すべてのキャラクターが息を合わせて役割を果たすことで、細胞は活動を続けることができるのです。どれか一つでも働きが止まると、細胞全体の活動が止まり、命に関わる事態を招いてしまいます。
番組では、この連携の大切さが静かに、しかし重みをもって伝えられました。細胞内のたんぱく質たちが、まるで見えない指揮者に導かれるように動き、命のオーケストラを奏でている様子がCG映像で表現されていました。
-
細胞内のチームワークは、一瞬たりとも休むことなく続いている
-
キャラクター同士の連携が失われたとき、それは細胞の死、そして私たち自身の死につながります
命を支えるしくみは、壮大でありながらとても繊細です。小さなキャラクターたちが力を合わせ、毎瞬毎瞬、私たちの命を守ってくれていることを知ると、何気ない日常にも、感謝と驚きの気持ちが湧いてきます。番組を通して、細胞の中で起きている奇跡を、より深く感じることができました。
環境によって細胞も変わる

番組の後半では、環境の違いが細胞に与える影響についても紹介されました。刺激の多い環境と刺激の少ない環境で育てられたマウスを比較するという、興味深い実験が行われたのです。
-
刺激の多いグループ:おもちゃがたくさん置かれ、15匹という大人数で集団生活を送りました
-
刺激の少ないグループ:狭いケージで3匹だけで飼育され、周囲の変化も少ない環境でした
1か月後、両方のグループの脳の中を調べたところ、刺激の多い環境で育ったマウスは、脳内のキネシンの量が約1.7倍にも増えていたことがわかりました。キネシンの量が増えると、神経細胞同士の情報のやりとりが活発になり、脳の働きがより良くなることが示唆されました。
-
環境が豊かだと、神経細胞間の連携が強まり、高次脳機能が向上する
-
刺激が少ないと、神経細胞のネットワークが発達しにくくなる
この結果は、マウスだけでなく私たち人間にも当てはまることがわかっています。新しいことに挑戦したり、たくさんの人と交流したり、未知の体験を増やしていくことで、脳の中の細胞たちも元気になり、人生をより豊かにできるのです。
番組では、「細胞内キャラクターたちは、私たちの行動によって活性化できる」という希望のメッセージが込められていました。たとえ小さな変化でも、日々の選択が自分自身の脳を育てることにつながると考えると、毎日の過ごし方が少しずつ変わっていくかもしれません。
環境と細胞、そして命。すべては密接につながっていることが、番組を通してやさしく、力強く伝えられていました。
命の源を見つめて
今回の「人体III」第1集では、私たちの命が小さな細胞の中にある無数のキャラクターたちの奇跡のチームプレーによって支えられていることが、鮮やかに描かれました。命のない部品が協力し、生命を営むという事実は、見る人すべてに深い感動を与えたに違いありません。
次回以降も、「命とは何か」を探る旅が続きます。新しい科学の発見と、私たち自身の命への理解がさらに深まることを期待して、注目していきたいです。
放送の内容と異なる場合があります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

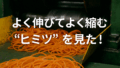
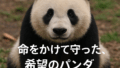
コメント