岡本太郎と太陽の塔の真実に迫る
2025年5月3日に放送されたNHK総合の『歴史探偵』では、日本万国博覧会(大阪万博)で生まれた象徴「太陽の塔」に迫る特集が放送されました。番組では、芸術家・岡本太郎がこの作品にどんな思いを込めたのか、秘蔵スケッチや証言、そして塔が残された背景に至るまで、貴重な記録と共に描かれていました。
太陽の塔は「勝手に作った」ものだった?

1970年に開催された大阪万博は、アジアで初めての万国博覧会でした。当初のメイン展示は、建築家・丹下健三が手がけた「大屋根」構想でした。この巨大な屋根の下に、未来都市を思わせる展示空間が設けられる予定で、その中に各国のパビリオンや技術展示が並ぶ計画でした。
岡本太郎は当初、芸術作品の担当ではなく、テーマ展示の構成を担う立場として関わっていました。しかし、大屋根の模型を見た瞬間、彼の中に抑えきれない創作意欲が湧き上がります。
・岡本は「大屋根をぶち破って塔を建てたい」という衝動にかられた
・屋根の模型を目にしたその場で、「屋根に穴を開けて塔を突き立てる」という案を思いついた
・当初の予定には存在しなかった「塔」を、自らの強い意志でプランに組み込んでいった
この時点で、太陽の塔の構想が現実に動き出しました。通常であれば、大規模展示の計画には多くの審査や合意が必要ですが、岡本の情熱と影響力により、そのまま大屋根を突き破るように塔を設置する案が通ったのです。
・丹下健三は岡本太郎の芸術性を高く評価しており、「一緒にやるなら岡本しかいない」と語っていた
・万博事務総長・新井真一も岡本の参加を強く望み、関係者の後押しが実現を支えた
・岡本は、塔をただのオブジェとしてではなく、“人類の生命力”を象徴するシンボルとしてデザインした
結果として、太陽の塔は大屋根を突き破る形で空に向かって立ち、未来都市的な展示とは対照的な、生命と原始のエネルギーを象徴する存在として万博の中央にそびえ立つことになりました。
万博のテーマである「人類の進歩と調和」に対し、岡本太郎は太陽の塔を通して「進歩だけではなく、人間の根源的な力や混沌にも目を向けるべきだ」というメッセージを託したのです。彼の行動は、決して計画通りではなく、むしろ“勝手”とも言える突発的な発想でしたが、それがかえって太陽の塔を唯一無二の象徴へと押し上げたのです。
顔に込めた命の表現
太陽の塔には、「現在の顔」「未来の顔」「過去の顔」という3つの顔があることが広く知られていますが、番組ではさらに深く、「顔とは命の象徴である」という岡本太郎の考えが紹介されました。塔の構想段階で残された多数のスケッチには、顔がどのようにして塔のデザインに取り込まれていったかが克明に記されています。
・初期のデザインでは、塔は“木”をモチーフにして描かれていた
・途中から“顔”が描かれるようになり、塔全体が命のシンボルへと変化
・岡本は「顔には喜怒哀楽がすべて表れる。つまり、命そのものだ」と考えていた
これらの顔には、それぞれに意味が込められています。「現在の顔」は正面にあり、来場者と向き合う形で立ち、「未来の顔」は塔の頂上に輝くように設置され、「過去の顔」は塔の背後に静かに存在しています。そして、最も見えにくい場所にあったのが「地底の太陽」と呼ばれる第4の顔です。
・「地底の太陽」は地下空間に設置され、生命の根源や宇宙的なエネルギーの始まりを象徴していた
・展示では、世界各地の神像や仮面が周囲に配置され、その中央に「地底の太陽」が鎮座していた
・来場者は地下から塔の内部へと進み、この顔を最初に目にすることで「生命の誕生」を体感する構成だった
岡本が塔に4つもの顔を与えたのは、人間の命の時間軸を過去・現在・未来だけでなく、もっと深い根源的なところからとらえようとしたからです。地中に置かれた第4の顔は、視覚的なインパクトだけでなく、塔全体の思想を支える土台としての意味も担っていました。表に見える3つの顔だけでは語れない、命の始まりと終わり、そしてその循環を表現するために、この「地底の太陽」は欠かせない存在だったのです。
岡本太郎は壊されてもいいと思っていた?
1970年の大阪万博では、会場に建てられたすべての建築物や施設は閉幕から半年以内に撤去するというルールが定められていました。太陽の塔も例外ではなく、当初はこの規則に従って撤去される予定だったのです。驚くことに、塔を作った本人である岡本太郎も、この撤去に特に反対する姿勢を見せていませんでした。
・岡本太郎は「芸術に執着しない」というスタンスを持っていた
・自身の作品に後から加筆することもあり、「完成」という概念にとらわれていなかった
・芸術は常に動き続けるものであり、変化し続けるのが本来の姿だと考えていた
そのため、太陽の塔が壊されることについても、岡本は「それもまたひとつの流れ」と受け入れていたようです。しかし、多くの人々の反応がこの流れを変えました。万博終了後、全国各地から「太陽の塔を壊さないでほしい」「残して後世に伝えてほしい」という声が次々と寄せられたのです。
・太陽の塔に感動した高校生が新聞社に投書し、それが全国に広がる
・テレビや新聞でも保存の是非が取り上げられ、社会的な議論へと発展
・岡本自身も、そうした人々の熱意に触れるうちに心境が変化していった
こうして、1975年1月23日、太陽の塔の永久保存が正式に決定しました。当初はあくまでも“期間限定”の展示だったこの塔が、今も吹田の地に立ち続けているのは、岡本太郎の意思だけでなく、それ以上に人々の強い願いがあったからこそなのです。芸術家自身の考えを超えて、多くの人にとって“生きる象徴”のような存在となった太陽の塔。それはまさに、芸術が社会とつながった瞬間でもありました。
民衆の中にある芸術
今回の番組では、岡本太郎の芸術観にもしっかりと焦点が当てられていました。岡本が語っていたのは、「芸術は特別な人だけのものではなく、生活の中にあるべきものだ」という考え方です。これは、彼の創作スタイルにもよく表れていました。
・岡本太郎は、絵画や彫刻を富裕層に売ることを避けていた
・「売ったら、富裕層のもとに行ってしまって表に出なくなる」と考えていた
・その代わりに、ウイスキーのおまけやポスター、パブリックアートなど、誰もが目にする場所に作品を発表していた
彼にとって芸術とは、美術館やギャラリーに飾られる高級なものではなく、人々の目に触れ、心を動かすことのできる身近な存在であるべきでした。太陽の塔や、各地にある壁画や彫像は、その思いを形にした代表的な作品です。
また、番組に登場した岡本の親族で評論家の平野暁臣氏も、こう語っています。「今の時代だったら、太陽の塔のような巨大な作品は“税金の無駄遣い”と言われてしまうかもしれない。でも、説明できないからこそ価値がある。芸術は意味で縛られるものではない」と。
・太陽の塔は“意味を持たせない”ことこそが意味だった
・だからこそ、人それぞれに感じ方が違い、長く愛されてきた
・「なんだこれは!」という驚きや衝撃が、岡本の考える“美しさ”そのものだった
岡本太郎は、生涯を通して「芸術は民衆のもの」「誰もが感じ取れるものであるべきだ」と信じ、それを作品というかたちで貫きました。太陽の塔がこれほどまでに長く語り継がれているのは、そうした思いが人々の心にしっかりと根づいているからにほかなりません。
残された塔と「宇宙」
万博閉幕後、大屋根が撤去されたことで太陽の塔だけがぽつんと残されました。その姿を見た岡本に「今、何と対峙しているのか」と問うと、「宇宙だよ」と答えたという逸話も紹介されました。時代や場所を超えた存在として、太陽の塔は今も立ち続けています。
この回の『歴史探偵』は、芸術家・岡本太郎の情熱と行動力、そして社会や未来への問いかけを感じられる内容でした。単なる万博の展示物ではなく、命と時間、そして人間の存在そのものに挑んだ芸術作品として、太陽の塔の重みを改めて感じさせてくれました。万博の遺産としてではなく、今も生きる「問いの塔」として、これからも語り継がれていくでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

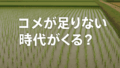

コメント