アラスカにかけた謎の日本人を追う
2025年7月21日にNHK総合で放送された『大追跡グローバルヒストリー』では、「アラスカにかけた謎の日本人」として、100年以上前にアメリカ・アラスカで活躍した実業家・川部惣太郎にスポットが当てられました。今回の調査では、彼の歩みを追うためにアラスカ各地やシアトルにまで取材が行われ、その足跡や功績が明らかになっていきました。
アラスカ州立の施設から始まる調査の旅
番組の舞台となった最初の地は、アラスカ州の州都・ジュノーです。ここには、アラスカの風土や文化を知るための貴重な資料が集まるアラスカ州立博物館とアラスカ州立図書館があります。博物館には先住民の生活道具や交易品など、アラスカの自然と歴史にまつわる展示物が約2万7千点、図書館には新聞や手紙、行政文書など18万点を超える資料が保管されていて、追跡調査の第一歩として最適な場所でした。
日本人の名が記録される資料から浮かぶ人物像
最初に登場したのは、極地探検で知られる植村直己と、伝説の犬ぞり師とされる和田重次郎です。どちらも過去にアラスカで活躍したことで知られており、記録にもしっかりと残されていました。しかし、さらに調査を進める中で、「ハリー・カワベ」という名で呼ばれ、地元住民に深く愛された日本人の存在が新たに浮かび上がります。この人物こそが、今回の主役・川部惣太郎でした。
港町スワードに残る功績と“名前”
川部惣太郎が暮らしていたのは、アラスカ南部の小さな港町スワード。風光明媚で観光地としても知られ、アラスカ鉄道の出発点としても栄えた歴史ある場所です。ここで現地住民から話を聞いた追跡班は、「カワベパーク」という名の公園があると教えられ、早速足を運びました。
市議会記録と証言で判明したランドリー経営の事実
市役所に残されていた記録によると、2002年のスワード市議会でこの公園の名称が決定され、背景には川部がこの地で長年ランドリー業を営み、市の発展に大きく寄与したことがありました。議会に参加していた歴史研究家のダグ・カプラ氏は、川部がスワードにランドリーを構えた当時の資料や記憶をもとに、彼の名前を地名として残すことを強く提案したといいます。
川部の軌跡をたどってシアトルへ
川部の人生をより深く理解するため、番組ではアラスカからアメリカ本土のシアトルへと調査の舞台を移しました。ここには「カワベ メモリアル ハウス」という高齢者住宅が存在し、これは川部の遺言により設立された施設で、今もアジア系住民が多く暮らしています。
16歳で単身渡米した少年の挑戦
残された履歴書や古い写真から、川部は16歳の若さでひとり日本を出てシアトルへ渡ったことがわかります。当時のシアトルには約5,000人の日本人が暮らす日本人街が形成されており、川部もその近くで生活を始めました。最初は「ハウスボーイ」として住み込みで働き、英語を覚えながら生活基盤を築いていったようです。
初めての起業と挫折、そして新たな出発
やがて彼はワシントン州のモンローという農村地帯でホテルとカフェの経営に挑戦しますが、立地が悪く客足も少なかったため、数ヶ月で事業は行き詰まり、18歳で破産。すべてを失った川部でしたが、料理人としての経験を活かせる場所を探していると、アラスカでは料理人の給料が高いという情報を聞きつけ、新天地を目指す決意を固めます。
ポートグラハムから始まるアラスカでの挑戦
アラスカのポートグラハムに到着した川部は、造船会社で料理長の職を得ることができました。ここから「ハリー・カワベ」と名乗るようになり、人生の第二章が始まります。
人種差別との向き合いと転職
しかし、そこで目の当たりにしたのは白人とのあからさまな待遇の差。皿洗いの白人が自分の倍の給料をもらっている現実に愕然とし、川部は職場を離れ、次の町・コルドバへ移動します。そこで再び料理人として働いていた矢先、近郊のシュシャナで金が見つかったという話を聞きつけ、今度は金鉱採掘に関わる事業に挑みます。
ゴールドラッシュに乗った新たなビジネス
23歳の川部は商店を開き、採掘者を相手に生活用品などを販売するビジネスを始めます。しかし、金の採掘ブームは長くは続かず、客は減り、多額の借金だけが残る結果となってしまいます。それでも川部は再び立ち上がり、水運びの仕事をして借金を完済。25歳のとき、新たなチャンスを求めてスワードへと向かいました。
スワードで築いたランドリービジネス
鉄道建設が始まったばかりのスワードでは、川部のビジネスチャンスへの読みが当たり、生活必需サービスとしてのランドリー業を始めます。1921年の新聞では彼の店が「アラスカで最も近代的なランドリー」と報じられ、その存在感は一気に広がりました。
洗濯物回収サービスなどの先進的展開
川部は港に停泊する船に目をつけ、洗濯物を回収し、洗って届けるという画期的なサービスも始めます。こうした工夫により、地元住民からの信頼も高まり、事業はますます拡大していきました。
反日感情と法規制への対応
1924年、アメリカでは移民排斥の動きが強まり、日本からの移民を事実上禁止する法律が成立。川部もこの影響を受けますが、地元市長が川部の働きぶりを評価し、差別的な発言をした船長に対して停泊を拒否するほど支援。川部は訴訟を起こし、法律を乗り越えて酒類販売の許可も獲得し、アラスカ鉄道や陸軍とも契約を結ぶなど、その影響力は地域全体に広がっていきました。
福祉への貢献と人間性
晩年の川部は、自分の子どもはいなかったものの、事情を抱える子どもたちを支援し、一緒に暮らすようになります。生活の安定と地域への貢献、そして人としての温かさが、今もアラスカで語り継がれている理由です。
和田重次郎――道なき道を拓いた犬ぞり師
番組後半では、アラスカに渡ったもう一人の日本人、和田重次郎にもスポットが当てられました。彼は17歳で渡米し、極寒の中で犬ぞりを使った輸送ルートを開拓。今も残るスワード〜アイディタロッド間の約900キロにおよぶ道の整備に尽力しました。
和田の業績とスワード市の評価
現在もその功績を称える銅像がスワードに立ち、元市長の証言によると、和田の犬ぞりルートが今の高速道路や鉄道の基礎になっているといいます。アラスカの生活と物流を大きく変えた和田の働きは、国際的な犬ぞりレースなどの文化として今も続いています。
番組から感じた教訓と希望
アラスカという過酷な自然環境の中で、異国の文化や人種差別と向き合いながら、自らの力で道を切り開いていった川部惣太郎と和田重次郎。どちらも日本人としての誇りと強い信念をもって行動し、地域に欠かせない存在となっていきました。今回の番組は、今を生きる私たちにも大きな勇気を与えてくれる内容でした。
番組情報まとめ
| 放送日 | 2025年7月21日(月) |
|---|---|
| 番組名 | 大追跡グローバルヒストリー |
| サブタイトル | アラスカにかけた謎の日本人を追う |
| 放送局 | NHK総合 |
| 放送時間 | 19:30~20:15 |
| 出演者 | 上田晋也、劇団ひとり、佐藤大史 |
出典:NHK『大追跡グローバルヒストリー』公式サイト
https://www.nhk.jp/p/ts/X1JX2K95WP/episodes/
川部惣太郎が遺した寄付と慈善活動の実像

ここからは、私からの提案です。川部惣太郎(Harry S. Kawabe)は、アラスカやシアトルで成功した実業家として知られるだけでなく、自身の晩年には地域社会に多大な貢献を残した人物でもあります。彼が築いたのは、ただの資産ではなく、地域に根ざした支援の仕組みと、将来世代への温かいまなざしでした。ここでは、彼の行った具体的な寄付・慈善活動について詳しく紹介します。
高齢者のための住まい「カワベ・メモリアル・ハウス」
川部は1969年、自身の資産をもとに高齢者向け集合住宅の設立を計画し、その実現に向けて尽力しました。1972年に完成した「Kawabe Memorial House」は、全154ユニットを備えた大規模な住宅施設で、当初から日本人移民やアジア系住民を対象に、低料金かつ安心できる生活の場を提供することを目的としていました。建物内にはエレベーターや集会所なども備わっており、高齢者が孤立せずに暮らせる環境を整える設計がなされています。
この建物は現在も稼働しており、数世代にわたって地域の高齢者に利用されてきました。単なる住宅にとどまらず、福祉とコミュニティの拠点としての役割を果たし続けています。
地域に根ざした助成基金「カワベ・メモリアル・ファンド」
川部の遺志により1971年に設立された「Kawabe Memorial Fund」は、福祉や教育に関わる活動を支援するための財団として機能しています。これまでに3,000件を超える申請が受理され、累計で510万ドル以上の助成が実施されており、今なお地域に大きな影響を与えています。
助成金の使途は多岐にわたり、主に以下の4つに分類されます:
| 支援対象 | 内容の概要 |
|---|---|
| 福祉団体 | 生活困窮者・子ども・高齢者を対象としたNPOの運営支援や事業資金 |
| 宗教施設 | 教会や寺院などの修繕や設備更新の費用援助 |
| 教育関連 | 教師や牧師を目指す若者への奨学金制度 |
| アラスカの高校生 | スワード高校の卒業生を対象とした学業支援金の給付 |
こうした助成を通じて、移民の子孫や地域住民が安心して教育や宗教、福祉の現場に関わり続けられる基盤が築かれています。
日常生活でのさりげない支援と信頼の積み重ね
川部は単なる寄付者という枠を超えて、地域の一員として積極的に関わる姿勢を持っていました。道路が整備されていなかった時代には、地元の子どもたちを自らの車に乗せて遠足に連れていくといった、心温まる行動を実践していました。また、地元新聞には、川部の家が火災の危機に瀕した際、地域の消防士たちが全力で消火にあたったというエピソードが記録されており、彼の人望の厚さを裏づける事実として今も語られています。
このように、川部の活動は単発的な寄付にとどまらず、制度として残る建物や基金、地域の記憶の中に生き続ける日常の支援として、広がりをもって継承されています。成功者としての経済力を、自身の出自と向き合いながら移民や社会的弱者への支援へと転化させたその姿勢は、現在の社会にも通じる示唆を与えています。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


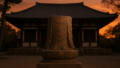
コメント