- グンタイアリ、フラミンゴミルク、キックするカエルまで!驚きのへんてこ動物大集合
- パプアニューギニアのへんてこ生物と熱帯雨林の巨大ヘビ
- まるで彫像!動かない鳥・ハシビロコウの生き残り戦略
- 赤い液体の正体は?フラミンゴのミルクの秘密
- 垂直の壁を登る!アルプスアイベックスの驚異のバランス能力
- キックで子を守るカエル!アマガエルモドキの勇敢な行動
- 恐竜のような行進!ハナグマの群れが森をゆく
- ジャンプできない毒カエル!カボチャヒキガエルの悲劇と進化
- 脱力系動物たちの本当のすごさ
- カピバラの集団行進と、最恐グンタイアリの驚きの知恵
- シロザケの命がけの行進と、足ぐるぐるエミュー呼び男
- インディアンスが慣用句と動物を結びつけて紹介
- SNSで話題!ウッドチャックの推し活と人気生物たち
- フクロモモンガに学び、全国チャンピオンへ
- 超勤勉!働き者のビーバーたち
- まとめ
- 気になるNHKをもっと見る
グンタイアリ、フラミンゴミルク、キックするカエルまで!驚きのへんてこ動物大集合
2025年4月29日(火)19時30分から放送されたNHK総合『へんてこ生物アカデミー』は、第9弾にふさわしい超豪華な内容で、72分間ずっと目が離せない構成でした。番組では、世界中の「なんじゃこりゃー!」と叫びたくなるほど不思議な生き物たちを、さまざまな角度から紹介。珍行動・生態の謎・驚きの適応力・愛らしい一面まで、生物の持つ個性を楽しく学ぶことができる回でした。司会は林修さんと大谷舞風さん。ゲストには中川翔子さん、ナイツの土屋伸之さん、インディアンスの田渕章裕さんときむさんが出演し、それぞれの“推し生物”や慣用句に絡めたプレゼンも展開されました。
パプアニューギニアのへんてこ生物と熱帯雨林の巨大ヘビ

冒頭では、パプアニューギニアで撮影された不思議な生き物が登場しました。人目を避けるように森の中を歩くその姿はまるで映画のワンシーンのようで、視聴者に「これ本当に実在するの?」と疑いたくなるインパクトを与えました。続いて登場したのは、熱帯雨林に生息する巨大なヘビ。湿った木の葉や枝を器用にすり抜けるように進むその姿には、爬虫類ならではのしなやかさと迫力がありました。
まるで彫像!動かない鳥・ハシビロコウの生き残り戦略

ウガンダの湿地帯に生息するハシビロコウも特集されました。長時間全く動かずにじっと佇む姿は、まるで置物のよう。ですがそれは生き残るための立派な戦略です。ハシビロコウは、動かずに獲物が油断した瞬間を狙って一気に捕らえる「待ち伏せ型ハンター」なのです。さらに、鳴き声を持たない代わりに「クラッタリング」と呼ばれる、くちばしを激しく鳴らす行動でコミュニケーションを取ります。番組ではこのクラッタリングの迫力ある音も紹介され、視聴者を驚かせました。
赤い液体の正体は?フラミンゴのミルクの秘密

ホラー映画のような映像も登場しました。頭から赤い液体を流しているフラミンゴの姿です。ですが、これは流血ではなく、親鳥がヒナに与える「フラミンゴミルク」。この赤いミルクは、親が赤い色素を含む藻類を摂取することで生成される特別な栄養液で、子育ての過程で不可欠なものです。赤い液体という見た目に驚きつつも、フラミンゴの深い愛情が込められた行動であることが明かされました。
垂直の壁を登る!アルプスアイベックスの驚異のバランス能力

続いて紹介されたのは、イタリアのダムに現れたアルプスアイベックス。高さ数十メートルの垂直に近いコンクリート壁を、滑ることなく軽やかに登っていく姿が映し出されました。彼らの蹄は特殊な構造をしており、わずかな突起にも引っ掛けて登れるグリップ力を持っています。この行動はミネラルを摂取するためと考えられており、生きるために極限の環境にも適応する動物の知恵が見事に表れていました。
キックで子を守るカエル!アマガエルモドキの勇敢な行動

アマガエルモドキの雄が、天敵に対して自分の脚を使ってキックする映像も紹介されました。これは、卵や子どもを守るために行うもので、敵がスズメバチのような危険な存在であっても立ち向かう姿が映し出されました。父親の強さと愛情が伝わるシーンで、昆虫に勝る動物の意外な一面が浮き彫りになりました。
恐竜のような行進!ハナグマの群れが森をゆく

恐竜が群れで移動するような映像として登場したのは、ハナグマでした。長い鼻と機敏な動きが特徴で、列を作って森の中を進むその姿は、まさに“現代の小型恐竜”のようでした。安全性の確保や情報伝達のために群れで行動するという習性があり、集団の中での連携の重要性がよくわかる映像でした。
ジャンプできない毒カエル!カボチャヒキガエルの悲劇と進化

ブラジルの森に住むカボチャヒキガエルは、その鮮やかな色と小さな体が特徴です。ですが、このカエルには致命的な弱点があります。それはジャンプが極端に下手なこと。これは三半規管が未発達であるため、空中でバランスを取ることができず、着地に失敗してしまうからです。結果として、背中から転げる姿がたびたび見られます。それでも地面を這い、毒と警告色で身を守りながら生き抜くこのカエルの姿には、進化の多様さを感じます。
脱力系動物たちの本当のすごさ
番組では「やる気がなさそうに見える動物」たちも紹介されました。
-
ツマジロオコゼは底にじっとして動かず、魚というより岩のよう。
-
ゴマフアザラシやハイイロアザラシは水辺でゴロゴロ。
-
ニホンリスも動かず木にしがみついたまま。
一見すると怠け者に見えるこれらの行動も、エネルギーを無駄に使わない「省エネ戦略」であることが解説されました。
カピバラの集団行進と、最恐グンタイアリの驚きの知恵

ブラジルで撮影されたカピバラの集団行進では、リーダーに従って他の個体が同じ道をたどる社会性の高さが紹介されました。
また、コスタリカで発見された謎の動く塊の正体は、グンタイアリが自分の体をつなげて作った「アリの橋」。この橋を使って障害物を越え、スズメバチの巣まで襲撃するという、圧倒的な集団戦術が解説されました。
シロザケの命がけの行進と、足ぐるぐるエミュー呼び男
アメリカでは、道路を横断するシロザケの行進が紹介されました。産卵のために本能に従って進むその姿から、自然界の“命のリレー”の厳しさが伝わりました。
オーストラリア・クイーンズランドでは、足をぐるぐる回してエミューを呼び寄せようとする男性が登場。独特な動きで近づいてきたエミューでしたが、最終的には逃げてしまうという結末に思わず笑いがこみ上げるシーンでした。
インディアンスが慣用句と動物を結びつけて紹介
お笑いコンビ・インディアンスによるプレゼンでは、「目が飛び出る」「胸を張る」「猫をかぶる」などの慣用句と、それに当てはまる動物が映像とともに紹介されました。ボウエンギョやミツマタヤリウオといった深海魚の姿が、言葉と生き物の意外な一致として印象に残る構成でした。
SNSで話題!ウッドチャックの推し活と人気生物たち
SNSで大人気となったカニのかわいい動きやハエトリグモの行動、家庭菜園を荒らしたウッドチャックなど、笑えるけど癒される生物たちが取り上げられました。特にウッドチャックに恋した男性が、専用のピクニックテーブルを作って餌をあげる姿は話題性も高く、動物との関係性の深さを感じさせました。
フクロモモンガに学び、全国チャンピオンへ
横浜市在住の升水翔兵さんが紹介されました。柔道の構えに悩んでいたとき、飼っていたフクロモモンガの滑空姿からヒントを得て3連勝し、全国チャンピオンになったという実話です。現在では、フクロモモンガの飼育相談や普及活動をライブ配信などで行っており、飼い主とモモンガの橋渡しを担っています。
超勤勉!働き者のビーバーたち
番組の終盤では、長崎の動物園で暮らすビーバーたちの生態が詳しく紹介されました。1日平均10時間ほど活動し、木をかじってダムを作る様子が紹介されました。ビーバーはカピバラに次いで大きいげっ歯類でありながら、建築士のように巣とダムをつくる知恵を持っていることが解説されました。園内を自由に移動するビーバーの姿は、可愛さと勤勉さの両方を兼ね備えていました。
まとめ
『へんてこ生物アカデミー』第9弾は、自然界の驚きと面白さ、そして生き物の奥深さをたっぷり感じられる内容でした。笑えるシーンもあれば、感動させられる行動、学びになる進化の工夫もあり、子どもから大人まで誰もが楽しめる構成となっていました。次回もさらなる“へんてこ生物”に出会えることを楽しみにしています。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

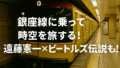
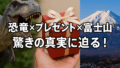
コメント