万博と日本|1900年パリ・幻の1940東京・1970大阪…万博が映す日本の夢
2025年4月16日(水)放送予定のNHK総合「歴史探偵」では、「万博と日本」というテーマで、日本と万博の関わりを振り返る特集が放送されます。番組では、163年にわたる万博と日本の関係を、歴史的資料と専門家の知見を交えて徹底調査。取り上げられるのは、1900年のパリ万博、幻に終わった1940年の東京万博、そして歴史的成功を収めた1970年の大阪万博です。それぞれの時代において、日本はなぜ万博に参加し、何を見せようとしたのか――。その背景には、国の理想や時代のビジョンがくっきりと浮かび上がります。放送前の段階で分かっている内容をもとに、番組の見どころを一足早くご紹介します。
明治日本が世界に示した“文化力”とは?1900年パリ万博

1900年にフランス・パリで開催された万国博覧会は、近代文明のショーケースといえるものでした。動く歩道や高架式電車など、当時の最先端の科学技術が展示され、多くの人々が未来を感じる場となっていました。そんな中、明治日本が出展したのは、意外にも埴輪や仏像、仏教絵画などの古美術品でした。
この選択は、ただの文化紹介ではありませんでした。日本が目指していたのは、単なる工芸国という評価を超え、歴史と深みを持つ芸術大国として認識されることでした。当時、欧米では浮世絵や陶磁器が「かわいらしい日本趣味」として人気を集めていましたが、いわゆる“高級美術”とは見なされていませんでした。
そこで動いたのが岡倉覚三(天心)や林忠正ら知識人たちです。彼らは、奈良や京都に伝わる仏教美術、古墳時代の埴輪など、日本の文化的深層を示す作品を厳選しました。また、ただ展示するだけではなく、フランス語で書かれた『日本美術史(Histoire de l’art du Japon)』を発行し、学術的な裏付けも加えました。
こうした周到な準備のもとで行われた展示には、以下のような特徴がありました。
-
出展作品はすべて本物の歴史的資料。レプリカではなく、信頼性のある文化財を用意
-
展示方法は西洋の美術館スタイルを意識。仏像や絵画は余白を大きく取り、静かに鑑賞できる空間を演出
-
解説パネルは仏教や歴史の背景にも言及し、日本文化の独自性と普遍性を強調
この展示は大きな反響を呼び、仏教美術に対する評価も高まりました。フランスをはじめとした欧米諸国の美術関係者からは、「日本にもギリシャやローマに並ぶ芸術の歴史がある」との声も上がりました。
また、この展示がもたらしたのは国際評価だけではありません。日本国内でも、忘れられつつあった古美術の価値が再認識される契機となり、明治以降の美術行政や保存活動にも大きな影響を与えました。これにより、近代日本における国宝制度や文化財保護の意識がさらに進みました。
つまり1900年パリ万博における日本の古美術出展は、“芸術国家・日本”を世界に示す文化外交の成功例だったのです。そしてそれは、単なる一時のブームではなく、日本が国際社会において文化的にも独自の地位を築いていくための、確かな一歩となりました。
幻となった1940年東京万博の構想とは

1940年に開催されるはずだった「紀元2600年記念 日本万国博覧会」は、日本が初めて世界に向けて開こうとした壮大な国家イベントでした。この万博は、神武天皇の即位を起点とする“紀元2600年”という節目の年に合わせて計画されたもので、日本の近代国家としての自信と誇りが込められていました。
計画された会場は、東京都内の晴海(4号地)、豊洲(5号地)、そして神奈川県の横浜・山下公園の3か所です。
-
晴海会場では、伝統文化を象徴する日本建築が並ぶ予定で、神殿のような荘厳な建物群が設計されていました。建物の外観は木造を模した様式で、精神性や歴史性を重視した空間づくりが想定されていました。
-
豊洲会場には、当時の最先端技術を象徴する近代的なモダン建築が配置される計画でした。こちらでは日本の産業力や都市計画の先進性をアピールするため、鉄筋コンクリート造やスチール構造の建築が中心となる予定でした。
-
横浜・山下公園では、海洋国家日本をテーマにした水族館や海運展示が行われる計画で、世界の海とつながる国としての姿勢を打ち出そうとしていました。
また、会場間の移動には、当時としては革新的だった自動走行バスや水上交通システムの導入も検討されており、まさに未来都市を思わせる構想が広がっていました。
この万博は、以下のような数値目標と計画のもとに動いていました。
-
会期は1940年3月15日から8月31日までの170日間
-
来場者は4,500万人を想定
-
予算は4,450万円(現在の価値で数百億円相当)
-
世界50カ国以上の参加を予定
ところが、1937年に始まった日中戦争の影響が年を追うごとに強まり、政府内でも「国家予算を戦費に回すべきだ」との声が高まる中で、1938年7月には正式に延期が決定されました。その後、戦局の悪化に伴い開催の可能性は完全に失われ、この万博は幻のイベントとなってしまいました。
それでも、当時の設計図や建築模型、広報用ポスター、参加国との交渉記録などは現在も各地の資料館に保管されています。特に、当時のポスターに描かれた光り輝く未来都市のビジュアルは、日本が国際社会の舞台に立とうとした強い意志と夢の象徴として、今でも人々を魅了しています。
この幻の万博は、開催されなかったにもかかわらず、日本が文化と技術の両面で世界とつながろうとしていた姿勢を今に伝える貴重な証拠であり、後の1970年大阪万博へとつながる布石となったと言えるのです。
日本の技術力と未来への希望が結実した1970年大阪万博

1970年、日本で初めて実現した万国博覧会――大阪万博は、「人類の進歩と調和」をテーマに、183日間にわたって開催されました。来場者は実に6,422万人にのぼり、これは当時の日本の総人口の約6割にも相当する驚異的な数字でした。国内だけでなく、海外からの注目も集まり、万博史上に残る大成功となりました。
この万博が特別だったのは、展示されていた内容にあります。どのパビリオンも、当時としては信じられないような“未来の生活”を体験できる場として設計されていました。
-
アポロ12号が持ち帰った月の石が日本に初めてやってきたことは大きな話題となり、実物を一目見ようと長い行列ができました。
-
IMAX方式の大型映像が世界で初めて上映され、まるでその場にいるような臨場感に来場者は驚かされました。
-
磁気浮上式リニアモーターカーの模型と実演も話題を呼び、夢の超高速交通手段として日本の技術力が強く印象づけられました。
-
中でも注目されたのが、“人間洗濯機”と呼ばれる自動入浴装置。カプセル状のマシンに横たわると、機械が自動で洗浄から乾燥までを行うという仕組みで、近未来的なライフスタイルに子どもたちは大興奮でした。
これらの展示物は、単に技術の見本ではなく、日本が“未来型社会”をどう描いているかを世界に提示するものでした。
また、会場整備に合わせて地下鉄御堂筋線や中央環状線などのインフラが急速に整備されました。これにより大阪市内や関西圏からのアクセスが向上し、遠方からの来場者も多数訪れることが可能になりました。交通と都市開発が一体となって進められた万博は、その後の都市構造にも大きな影響を与えました。
会場のシンボルである岡本太郎による「太陽の塔」も万博の象徴として大きな存在感を放ちました。生命の進化と未来への希望を込めたこの造形物は、単なる建築ではなく、日本人の精神を表す芸術作品として今も高く評価されています。
このように1970年の大阪万博は、日本が高度経済成長の只中で培った技術力と創造力を世界に発信した場であり、さらに、国民一人ひとりに未来の生活の姿を実感させた“体験型未来ショー”でもありました。この成功を通じて、日本は文化・技術・経済の3分野で世界の先進国としての地位を確立したのです。
万博から見える“日本の夢”
番組では、このように3つの万博を通じて、それぞれの時代の日本が何を目指し、どのような世界像を描いていたのかを読み解きます。万博という舞台を通じて表現された日本の「夢」と「戦略」が、明治から昭和、そして現代までの日本社会の変化とともに浮かび上がってきます。
「歴史探偵」らしく、貴重な文献や映像資料、専門家の解説を交えながら、視聴者に分かりやすく丁寧に語られる構成が期待されます。
放送後、詳しい内容が分かり次第、最新の情報を更新します。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

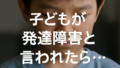
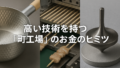
コメント