100人いたら100通り 発達障害の“適切な支援”とは?
2025年4月15日放送のNHK「クローズアップ現代」では、発達障害の早期発見と支援体制の課題について取り上げられました。番組では、5歳児健診の全国的な拡大を背景に、早期発見後の医療・教育の現場での支援の現状、保護者の悩み、そして多様性を尊重する社会のあり方について、さまざまな視点から深掘りされました。
発達障害の早期発見と5歳児健診の意義

2025年1月から、国は5歳児健診の実施を全国に広げるため、補助金の増額などを通じて取り組みを強化しました。この健診の目的は、自閉スペクトラム症やADHD(注意欠如・多動症)、学習障害などの発達障害を早く見つけて、必要な支援につなげることです。
この健診は、1歳半健診や3歳児健診のように法律で義務化されているものではなく、あくまで各自治体の判断によって実施される任意の健診です。そのため、現時点での全国の実施率はわずか13%ほどにとどまっており、地域によって差があるのが現状です。
5歳児健診の具体的な内容は、以下のようなものです。
-
保健師や医師が子どもと遊ぶ中で行動や反応を観察し、発達の特徴を見極めます
-
保護者への聞き取りも行われ、日常生活での様子や困っていることなどが共有されます
-
ことばの発達や注意力、対人関係、感情のコントロールなどが評価の対象になります
こうしたアプローチにより、発達の遅れや気になる行動が見られる子どもに対して、早い段階で必要な支援を届けることができます。発達障害の特性は見えにくいため、保護者が気づかないまま就学してしまうケースも多く、健診によってそれを防ぐ効果が期待されています。
しかしながら、健診を実施するかどうかは自治体の裁量に委ねられており、地域ごとに格差が生じている点が大きな課題です。
-
一部の自治体ではすでに健診が導入され、医師や支援者と連携した仕組みが整っている
-
一方で、多くの地域では体制が整っておらず、5歳児健診を受ける機会すらない子どもがいます
このように、「どこに住んでいるか」によって子どもが受けられる支援のスタートラインが変わってしまう状況が問題視されています。さらに、発見された後に専門医の診察や福祉的支援につながるルートが地域によって異なるため、支援がスムーズに行われないケースも見られます。
今後は、全国どこに住んでいても等しく健診を受けられる環境づくりと、早期発見から支援につながる体制の整備が求められています。5歳というタイミングは、就学前の重要な時期です。この時期に子どもの特性を理解し、必要な支援を早めに始めることは、本人にとっても家族にとっても大きな助けになります。
支援が遅れた家庭のエピソード

番組では、5歳児健診がなかった地域で暮らしていた斉藤さん(仮名)の娘の事例が紹介されました。娘さんは3歳の頃から発語の遅れや突然のパニックなど、周囲の子どもと明らかに違う様子を見せていたそうです。けれども、行政機関に相談しても「発達がゆっくりなだけ」と受け止められ、専門医による診断を受けることなく過ごすことになります。
-
3歳時点で見られた主な兆候は「言葉が出るのが遅い」「些細なことでパニックになる」などでした
-
行政機関に相談したが、医療機関での詳しい診察にはつながりませんでした
-
家族は「そのうち成長とともに落ち着くのではないか」という期待を持ちながら、日々の生活を続けていました
そのまま小学校に進学した娘さんは、周囲の子どもたちとコミュニケーションがうまく取れず、からかわれるようになります。適切な支援がないまま、本人の特性が理解されないまま時間が経ち、やがて8歳で不登校に。家庭でもどう対応すればよいか分からず、困り果てる日々が続きました。
-
小学校ではクラスメートと意思疎通が難しく、からかわれることが増えていきました
-
教員側も特別な支援を提供する準備がなかったため、本人が孤立する状況が続きました
-
結果として、本人の心身への負担が重なり、登校できない状態にまでなってしまいました
その後、ようやく10歳のときに医療機関を受診し、アスペルガー症候群と診断されました。これにより、娘さんのこれまでの困りごとが「性格の問題」ではなく、「特性によるもの」だったと明らかになりました。
-
発達障害の専門医による診断がつくまでに約7年の時間を要しました
-
保護者自身も、もっと早く気づいていれば、もっと早く支援が受けられていたのではないかという思いを抱えています
5歳児健診が地域にあれば、もっと早く専門的な視点で子どもの状態に気づけた可能性が高かったと、斉藤さんの事例は伝えています。もし早期に支援が受けられていたなら、学校での人間関係や学習の支援が整い、本人の自信や安心感も育てられていたかもしれません。
このエピソードは、発達障害の早期発見と支援の必要性を象徴する事例として、多くの視聴者に強い印象を残しました。子どもの成長のタイミングを逃さずに、適切な支援へとつなげる仕組みの重要さを改めて感じさせられる内容でした。
医療体制の課題と専門医の不足

5歳児健診で発達障害の兆候が見つかっても、その後すぐに医療に繋がるとは限りません。番組では、井上さん(仮名)の娘が診断を受けるまでに長期間かかったケースが紹介されました。5歳というタイミングで健診を受けたものの、その後の診察までに何ヶ月も待たされ、必要な支援の開始が遅れてしまったのです。
-
初診を受けるための予約がすぐには取れず、診察日まで何ヶ月も待機しなければなりませんでした
-
診察までの間、家庭ではどのように対応すればよいのか分からず、保護者は不安な日々を送ることになりました
-
幼稚園や学校との連携も取れず、支援の手が差し伸べられない状態が続きました
この背景には、児童精神科医の絶対数が少ないという現実があります。発達障害の診察には、短時間では終わらない丁寧な観察と聞き取りが必要です。そのため、1人の医師が対応できる人数には限界があります。
-
発達障害の診察では、子どもへの面接だけでなく、保護者からの詳しい聞き取りや生活状況の確認も行われます
-
検査や観察の時間を含めると、1人の診断に数時間かかることも珍しくありません
-
こうした事情により、1人の医師が1日に診られる患者数は限られており、結果的に予約が取りづらくなります
矢野瑞季さん(児童精神科医)は、「発達障害の診察や検査には時間がかかる」ことと、「そもそも専門医が少ない」ことが、受診の遅れの原因になっていると説明しています。さらに、初診までの待機期間は平均で2.6か月とされ、半年〜1年以上かかるケースもあるとのことでした。
-
地域によっては、専門医が数名しかおらず、1年先まで予約が埋まっていることもあります
-
地方ではさらに深刻で、そもそも専門医がいないため、遠方まで通院しなければならない家族もいます
-
その間、子どもの状態が変化することもあり、受診のタイミングを逃すケースもあるそうです
こうした状況を受けて、医療の現場では「健診だけではなく、その後の医療や支援にどうつなげていくかが今後の大きな課題」とされています。単に健診を広げるだけでは不十分であり、受診までの流れや支援の手配までを含めた包括的な体制が必要です。
5歳児健診の成果を生かすためには、発見の後に「どう動くか」「どう支援に繋げるか」まで見据えた仕組み作りが求められているのです。親が孤立せず、安心して相談できる環境、そして子どもが適切な時期に必要な支援を受けられる社会の整備が急務です。
教育現場でのギャップと保護者の悩み

番組では、発達障害の子どもが学校で適切な支援を受けられず、学びの機会を十分に得られない現実が伝えられました。特に、学習障害があるケンタさん(仮名)の事例は、多くの家庭が抱える悩みを象徴しています。母親は、文字を読むことが苦手なケンタさんのために、「プリントの文章を音読してほしい」と学校にお願いしましたが、学校側の対応は得られませんでした。
-
学校側が支援を拒んだ結果、ケンタさんは授業内容を理解できず、学習意欲を失っていきました
-
周囲と同じペースで進められることを求められ、自信をなくしてしまったのです
-
保護者にとっては「ただのひと工夫」で子どもが救われるはずの支援が届かないことに、大きなショックがありました
さらに番組では、発達障害のある子どもたちのために用意されている複数の教育の場も紹介されました。それは以下の通りです。
-
通常の学級(一般の子どもたちと一緒に学ぶ場)
-
通級指導教室(週数回、特別な支援が必要な教室に通う形式)
-
特別支援学級(障害の程度に応じて小人数で授業を行う学級)
-
特別支援学校(より専門的な支援を受けるための学校)
これらの制度は一見整っているように見えますが、どの形態を選ぶかは家庭の希望だけでは決められず、自治体や学校の判断も関わるため、希望が通らないことも多くあります。
-
地域によっては「通級指導教室」が設置されておらず、支援を受ける手段が限られているケースもあります
-
「特別支援学級」は設置されていても定員がいっぱいで、入れない子どもが順番待ちになることもある
-
通常の学級で学ぶ場合でも、担任の先生に特別支援の専門知識がない場合は、十分なサポートが期待できません
こうした実情から、「制度はあっても実際に利用できない」「学校ごとに対応が違う」というギャップが、保護者の間で強い不安と不満を生んでいます。また、子どもたちが求める支援を受けられないことで、学習についていけなくなり、学校生活がつらいものになってしまうことも少なくありません。
番組は、このような現場の声を紹介することで、形式だけではない実効性のある教育支援の必要性を強く訴えていました。子どもたちの「学びたい」という気持ちに応えるためには、柔軟で現実的な対応ができる教育現場の体制づくりが不可欠です。支援の量や質を地域によらず安定させること、それが本当の意味での「平等な学び」の実現につながるのです。
支援体制の先進事例と新たな取り組み
番組では、全国に先駆けて効果的な支援体制を整えてきた自治体の取り組みが紹介されました。中でも大分県竹田市、東京都江戸川区、埼玉県戸田市の3つの事例が、「発見のあと」にどう繋げるかという点で注目されました。
竹田市では、18年前から5歳児健診を実施しており、健診後のフォロー体制が整っています。この市では、健診で発達に課題が見られた子どもや育児に不安を抱える家庭に対し、2か月ごとの相談会を開催しています。
-
相談会には医療・福祉・教育など複数の分野の専門家が参加
-
その場で状況を共有し、即座に支援につなげる「ワンストップ型」の体制を採用
-
地域の限られた資源を最大限に活用し、支援の抜け漏れを防いでいます
この仕組みにより、健診後に保護者が不安を抱えたまま放置されることなく、すぐに相談・支援へと繋がる流れができています。
東京都江戸川区では、発達相談・支援センターにおいて「オーダーメイドの支援プログラム」が用意されています。この地域の取り組みは、子どもだけでなく保護者にも目を向けた内容となっており、多方面からのアプローチが特徴です。
-
支援は週1回の通所形式で、子どもの発達特性に合わせたプログラムを提供
-
保護者には「ペアレントトレーニング」を実施し、家庭での接し方や関わり方を丁寧に伝授
-
支援の内容や子どもの反応を記録できるアプリを使って、「成長の見える化」を実現
-
3歳以上の子どもは自治体と国の費用負担により無料で利用可能
これらの仕組みによって、家庭でも継続的な支援が可能となり、親子で一緒に成長を支える環境が整えられています。
さらに、埼玉県戸田市の喜沢小学校では、多様な学び方を受け入れる「インクルーシブ教育」が導入されています。ここでは、子どもたちが自分に合った方法で学べる仕組みが実践されています。
-
子ども自身が「誰と、どこで、どの教材を使って学ぶか」を選ぶことができる
-
特別支援学級に在籍する児童も、他の教室で授業を受ける選択が可能
-
授業中に友達から教えてもらうことが励みになり、学ぶ意欲が高まるとされている
この教育スタイルにより、子どもたちが「自分に合った学び」を通じて自信を持てるようになり、学校がより安心できる居場所となっていることが紹介されました。
これらの先進事例に共通しているのは、「子ども一人ひとりの違いを前提にした支援」が実現されていることです。単なる制度の導入ではなく、地域全体で連携しながら柔軟に対応する姿勢が、今後の支援のあり方に大きなヒントを与えてくれます。どの子どもも安心して育ち、学べるように、こうした取り組みが全国に広がることが期待されます。
専門家の視点とこれからの支援の方向性
番組の終盤では、長年にわたり発達障害の診療と研究に携わってきた児童精神科医・神尾陽子さんが、現在の健診制度と教育現場の在り方についての見解を示しました。神尾さんは、5歳児健診について「新たに分かることは少ないかもしれないが、これまでに行ってきた支援を振り返る意味では有意義」と評価しています。
-
5歳児健診は、必ずしも新しい問題を発見する場ではなく、それまでの支援の効果や課題を整理する大切なタイミングとされています
-
1歳半から3歳ごろまでに支援を受けてきた子どもの成長の経過を確認することで、今後どんな支援が必要かを見直すきっかけにもなります
さらに、神尾さんが強調したのは、「発達障害は病気ではなく、脳の特性や個性のひとつである」ということです。つまり、何かを「治す」ことが目的ではなく、その子が持っている力をどのように生かしていくかが重要だという視点です。
-
発達障害は「直す」対象ではなく、「理解し、支える」対象である
-
子どもが自分の力を発揮できるような環境づくりや接し方の工夫がカギになる
-
そのためには、周囲の大人たちが子どもの特性を知り、尊重することが求められます
また、国際的な視点からも課題が指摘されています。国連からは、日本の教育制度における「分離教育」が続いていることへの懸念が示されています。障害がある子どもが、特別な環境に置かれることで、社会全体の多様性が損なわれてしまう恐れがあるというのがその理由です。
-
「通常の学級」と「特別支援学級」が完全に分けられていることで、互いの理解や交流の機会が失われやすくなる
-
多様な子どもたちが共に学ぶことで、社会の中で共存する力が育まれる
-
インクルーシブ教育の推進が、今後の教育現場の大きなテーマになると考えられています
こうした課題に対し、こども家庭庁では「保健・福祉・医療・教育」の4つの領域が連携し、必要な支援を届けられるよう制度を整備する方針を進めています。支援が必要な子どもに、早く、そして継続的にアプローチできるよう、地域ぐるみでの体制づくりが進められています。
-
地域による格差をなくすため、自治体ごとの取り組みを国がサポートする仕組みが検討中
-
医療や教育の現場、行政などがつながり、一人の子どもを多方面から支える体制が理想とされています
-
保護者が迷わず相談できる窓口や、専門家にすぐ繋がる仕組みも重要なポイントです
このように、番組は専門家の視点を交えながら、子どもたち一人ひとりの個性を尊重し、力を伸ばしていける社会づくりの必要性を訴えていました。発達障害という言葉にとらわれるのではなく、その子が持っている「らしさ」をどう支えるか。これからの支援のあり方は、そこにかかっているのです。
発達障害支援の未来に向けて
今回の放送を通じて明らかになったのは、発達障害の早期発見と支援の重要性だけでなく、その後の支援体制の格差や課題がいまだ多く残っているという現実です。一方で、地域によっては先進的な取り組みも広がっており、「100人いたら100通り」の支援を実現するには、制度と意識の両面での改善が必要です。
子どもたち一人ひとりが持つ“個性”を尊重し、それを育てる環境を社会全体で支えていくことが、これからの日本の未来につながると強く感じさせる内容でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


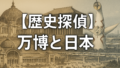
コメント