「なぜ父はわたしを殴ったのか」
2025年8月26日に放送予定のクローズアップ現代「なぜ父はわたしを殴ったのか 戦後80年・連鎖する“心の傷”」は、戦争がもたらした深い心の傷と、その影響を受けた家族の苦しみをテーマにしています。本記事では放送前にわかっている内容を整理し、読者が気になる疑問に答えられるようまとめました。放送後には実際の証言や専門家の解説を追記し、さらに充実させる予定です。
戦争体験が家庭に与えた影響とは
番組の大きなテーマは「戦争で負った心の傷が家庭内暴力につながった可能性」です。戦地から戻った父親たちが、戦争体験によるトラウマを抱えたまま家庭生活に戻ったことが背景にあると指摘されています。当時は心のケアや精神的サポートが整っておらず、戦場での体験を語ることさえ「恥」とされた社会風潮が強く残っていました。その結果、苦しみを抱えた父親が怒りや暴力の形でしか感情を表せず、子どもや妻に向けられてしまったケースが多くあったのです。
こうした事例は今になってようやく語られるようになり、当時の子どもたちは「父に殴られた記憶」と「なぜそうされたのか」という疑問を長年抱えてきました。この問いに答える手がかりを探ることが番組の狙いです。
放置された“心の傷”と世代間連鎖
虐待を受けた子どもたちの中には、数十年経ってもその体験に苦しむ人が少なくありません。トラウマは心だけでなく体調不良や人間関係にも影響を与え、生活全体を左右します。さらに、その影響は子どもから孫の世代にまで及ぶ場合もあります。これは「世代間連鎖」と呼ばれ、戦争が終わっても家庭に影を落とし続ける深刻な問題です。
番組では、虐待を受けた子どもが自分の家庭を持ったときに「同じことをしてしまうのでは」という不安を抱いた人の証言も紹介される予定です。心の傷を理解し、語ること自体が連鎖を断ち切る大きな一歩であることが示されます。
海外との比較で見えてくる日本の課題
海外では、戦争から帰還した兵士の心のケアを早くから取り入れてきた国があります。たとえばアメリカではPTSD(心的外傷後ストレス障害)という概念が広く知られ、医療やカウンセリングの制度が整備されました。兵士本人だけでなく、その家族を支える仕組みもありました。
一方、日本では「戦争の傷を語ることが許されにくい」風潮が長く続き、心のケアは後回しにされてきました。その結果、元兵士が抱えた苦しみは家庭内に閉じ込められ、暴力という形で噴き出してしまった可能性があります。海外との比較を通じて、日本がどこで立ち遅れたのか、そして今後どのように学ぶべきなのかが見えてきます。
よくある質問
Q. 父親の暴力は戦争だけが原因なの?
A. 戦争は大きな要因の一つですが、社会的な状況や家庭環境も関わっています。番組では「戦争が背景にあるかもしれない」という視点を軸に、多面的に考えるよう促しています。
Q. 今も被害に苦しむ人は多いの?
A. はい。番組の取材では、高齢になった今でも父親の暴力を思い出し、眠れない夜を過ごす人もいます。心の傷は時間が経っても自然には消えにくいのです。
Q. 私たちができることは?
A. まずは戦争の心の影響を知り、理解することです。そして被害を語れる場をつくることが、次の世代への連鎖を断ち切る手がかりになります。
専門家とキャスターの役割
今回の放送には福島県立医科大学の前田正治教授が登場します。精神医学の専門家として、戦争がもたらした心の傷とその後遺症について詳しく解説します。また、キャスター桑子真帆さんが体験者の声を受け止め、視聴者にわかりやすく伝えていきます。体験者の生の声と専門的な解説が重なり合うことで、問題の本質がより深く浮かび上がる構成になると期待されます。
番組を通して考えるべきこと
この番組は単なる過去の話ではありません。戦争の影響は「終わった」ものではなく、今も続いている現実です。父の暴力に苦しんだ人の体験は、戦争体験がどのように家庭に入り込み、何十年も影響を及ぼすのかを教えてくれます。これは「戦争の記憶をどう受け継ぐか」という課題とも直結しています。
視聴者にとっても、今の社会に生きる自分自身の問題として考えるきっかけになるでしょう。「もし自分の家族が戦争に巻き込まれていたら…」という視点で番組を見ることで、理解が深まるはずです。
まとめと放送後の追記予定
クローズアップ現代「なぜ父はわたしを殴ったのか」は、戦争が残した“心の傷”と世代を超えて続く影響を真正面から描きます。父親の暴力の背景に何があったのか、私たちはそれをどう理解すべきなのか――。この放送は、戦争と家庭、そして心のケアについて考える大切な時間になるはずです。
この記事は放送前の情報をもとに構成しています。放送後には実際の証言や具体的な事例、海外取材の内容などを追記し、さらに詳しい記事に更新する予定です。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

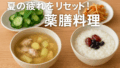
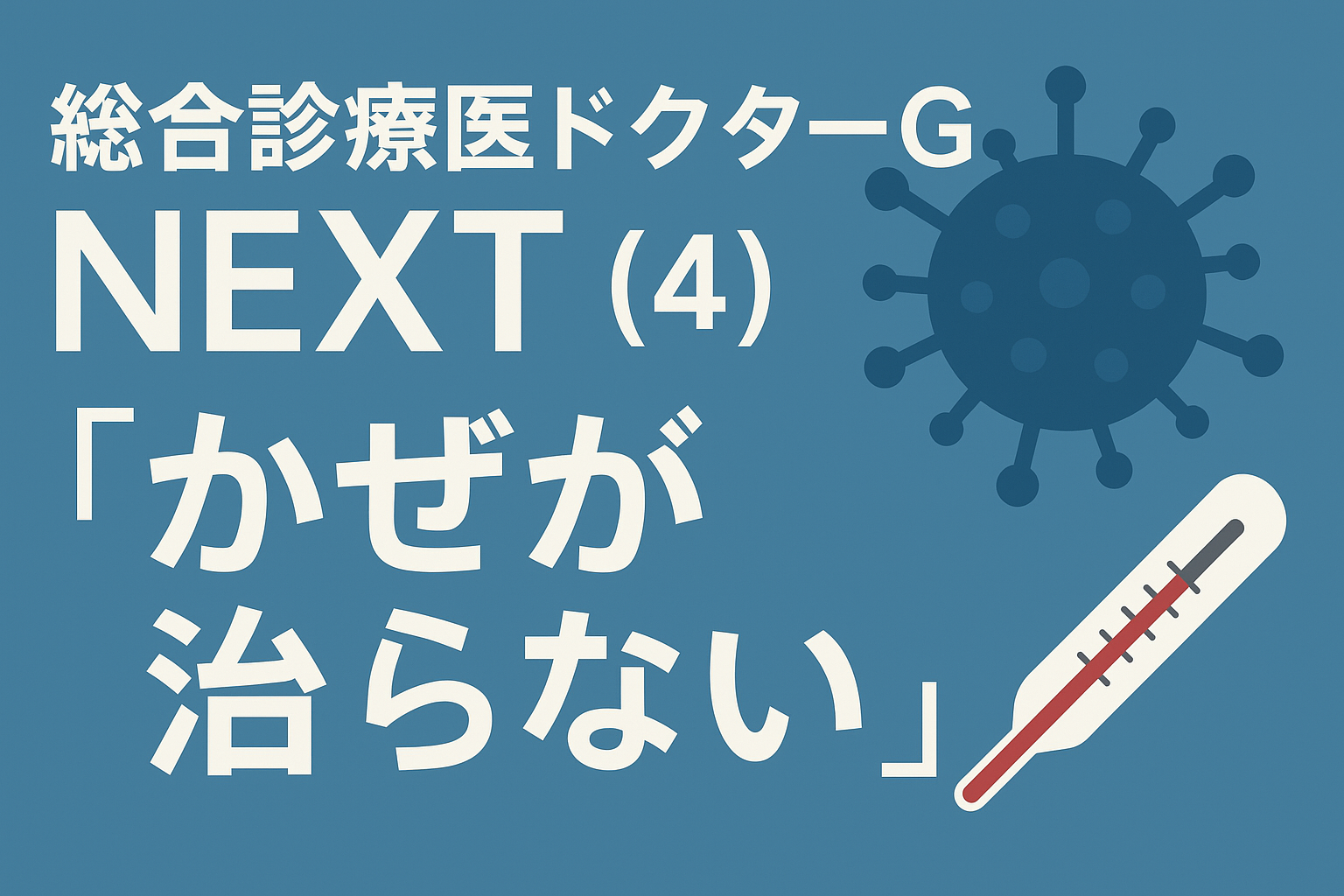
コメント