豚こま肉をおいしく使いこなす!あさイチ最新レシピと保存術
豚こま肉って安くて便利だけど「パサパサしてしまう」「硬くなる」と悩んでいませんか?実は下味や調理法を工夫するだけで、驚くほどジューシーに仕上がります。2025年9月16日放送のあさイチでは、鈴木奈穂子アナ、博多大吉・華丸のお二人、ゲストの倉悠貴さんや坂下千里子さんと一緒に、料理研究家の長田絢さん、舘野鏡子さんが「豚こま肉を柔らかくおいしく仕上げる技」を紹介しました。この記事では放送内容をすべてまとめ、家庭ですぐに使えるレシピと冷凍術を整理します。
【あさイチ】豚こまとピーマンのねぎポン酢がけ|エダジュン流さっぱり簡単おかずレシピ(2025年5月8日)
【ZIP!】料理研究家・樋口直哉が直伝!厚切り肉を30秒ごとにひっくり返す焼き方でジューシーに仕上げるコツ|2025年9月16日
豚こまがパサつく原因と解決法
結論から言うと、豚こま肉が硬くなるのは「塊のまま調理する」「ほぐしすぎる」のが原因でした。ポイントは調理の直前に塩をふり、表面に軽く片栗粉をまぶすこと。これだけで水分を閉じ込めてジューシーに仕上がります。また、焼く前に5分ほど常温に戻し、肉同士を重ねないことも重要です。
豚こまポークソテー
身近な食材「豚こま切れ肉」を使った極上の豚こまポークソテーが紹介されました。安価で手軽な豚こまを、下ごしらえと調理法でまるでステーキのように仕上げるレシピです。
材料(2人分)
| 材料 | 分量 | 補足 |
|---|---|---|
| 豚こま切れ肉 | 300g | 脂身と赤身が混ざったものがおすすめ |
| おろし玉ねぎ | 大さじ2(1/8個分) | 下味用 |
| 片栗粉 | 大さじ1と1/2 | 肉をまとめてジューシーに仕上げる |
| 塩 | 小さじ1/4 | 下味用 |
| 砂糖 | 少々 | 味をやわらげる |
| 粗びきこしょう | 少々 | 香りづけ |
| サラダ油 | 適量 | 焼き用 |
ソースの材料
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| おろし玉ねぎ | 大さじ2(1/8個分) |
| しょうゆ | 大さじ1 |
| みりん | 大さじ1 |
| 酒 | 大さじ1 |
| 砂糖 | 小さじ2 |
作り方の手順
-
下味をつける
豚こま切れ肉をパックのまま使い、おろし玉ねぎ・片栗粉・塩・砂糖・粗びきこしょうを加え、肉全体にしっかりと味が行き渡るように混ぜ合わせます。ここで赤身と脂身が均等になるように混ぜるのがポイントです。下味と片栗粉の効果で、焼いたときに肉がまとまりやすくなり、柔らかく仕上がります。 -
ステーキ状に成形する
混ぜた肉をパックの中で2等分し、それぞれを10×12cm・厚さ1.2cm程度に形を整えます。薄切り肉をまとめることで「こま肉なのにステーキ」という食べごたえのある一枚肉風に仕上がります。 -
フライパンで焼く(片面)
フライパンを強めの中火で熱し、サラダ油をひいたら、成形した肉をそっと置きます。このときは動かさず、ふたをして約3分加熱します。蒸し焼き効果で中まで火が入りやすく、外は香ばしく焼けます。 -
裏返して焼く
片面がカリッと焼けたら裏返し、再びふたをして2〜3分加熱します。透明の肉汁が出てきたら火が通った合図です。豚肉は火の通りが大事なので、この確認をすると安心です。 -
ソースを加えて仕上げる
焼き上がったら、用意しておいたおろし玉ねぎ入りソース(しょうゆ・みりん・酒・砂糖を混ぜたもの)をフライパンに加えます。1〜2分ほど肉にソースを絡めながら煮詰めると、香ばしい香りと照りが出て完成です。
仕上がりの特徴
このレシピは、薄切りの豚こまを使いながらも、ボリューム感と柔らかさを兼ね備えたソテーになるのが魅力です。おろし玉ねぎで下味をつけることで肉質がやわらかくなり、ソースに同じ玉ねぎを加えることで一体感のある深い味わいに仕上がります。
豚こまと野菜のつまみ揚げ
安価で手軽に使える豚こまを野菜と合わせ、衣はカリカリ・中はジューシーに仕上げるおかずです。冷めてもおいしいので、お弁当にもぴったりです。
材料(作りやすい量)
| 材料 | 分量 | ポイント |
|---|---|---|
| 豚こま切れ肉 | 200g | 脂と赤身が混ざったものがおすすめ |
| 砂糖 | 大さじ1 | 下味用 |
| しょうゆ | 大さじ1 | 下味用 |
| 酒 | 大さじ1 | 下味用 |
| にんにく(すりおろし) | お好みで | 香りづけ |
| ごぼう・にんじん | 合わせて150g | 薄切りにする |
| 小麦粉 | 大さじ5 | 衣用 |
| 片栗粉 | 大さじ3強 | 衣用 |
| 塩 | ひとつまみ | 衣用 |
| 水 | 大さじ5 | 衣用 |
| 揚げ油 | 適量 | フライパンに1.5cmの深さ |
作り方の手順
-
豚こまの下味をつける
パックのままの豚こま切れ肉に、砂糖・しょうゆ・酒・にんにく(すりおろし)を加え、しっかりと手でもみ込みます。脂身と赤身が均一になるように混ぜることで、ジューシーさと柔らかさが増します。 -
野菜の準備をする
にんじんとごぼうは薄切りにします。特にごぼうはアクが出やすいので水にさらしてから使うのがポイントです。 -
衣を作る
ボウルに小麦粉・片栗粉・塩・水を加えて混ぜ、そこに下味をつけた豚こまと野菜を入れます。衣が全体に絡むように混ぜ合わせます。 -
揚げる(片面)
フライパンに油を深さ1.5cm程度入れ、170℃に加熱します。具材を食べやすい大きさで入れ、4〜5分ほど触らずにじっくり揚げます。衣が固まるまで動かさないのがカリッと仕上げるコツです。 -
裏返して仕上げる
返したらさらに約4分加熱し、全体に火を通します。表面はこんがりときつね色、中はジューシーに仕上がれば完成です。
出来上がりの特徴
衣はカリカリに揚がり、噛むと豚こまの旨味とごぼう・にんじんの香ばしさが広がります。冷めても油っぽくならず、弁当に詰めても食べやすいのが魅力です。ポン酢やレモンをかければさっぱりとした味わいになり、夕食のおかずにもおつまみにもぴったりです。
豚こま大容量パックの下味冷凍レシピ紹介
家庭でまとめ買いすることの多い豚こま切れ肉を上手に保存しておいしく食べられる方法として「豚こま大容量パックの下味冷凍」を紹介しました。下味をつけてから冷凍することで、解凍後すぐに調理ができ、肉も柔らかく仕上がる実用的なテクニックです。
材料(4人分)
| 材料 | 分量 | 備考 |
|---|---|---|
| 豚こま切れ肉 | 約600g(550~650gまでOK) | 大容量パックを使用 |
| 酒 | 大さじ2 | 下味A |
| しょうゆ | 大さじ2 | 下味A |
| みりん | 大さじ2 | 下味A |
| かたくり粉 | 小さじ2 | 下味A |
| こしょう(パウダー) | 適量 | 下味A |
作り方の手順
-
下味をつける
豚こま切れ肉のパックを開け、そこに酒・しょうゆ・みりん・かたくり粉・こしょうを直接加えます。全体を1分ほど混ぜ合わせ、水分がなじんで肉全体がまとまるまでしっかりもみ込みます。このとき、大きな肉が混じっていたらキッチンバサミで食べやすい大きさにカットしておきます。 -
小分けにする
使いやすさを考えて、1袋あたり300g程度を目安に小分けにします。これで炒め物や煮物など幅広い料理に使いやすくなります。 -
冷凍用ポリ袋に入れる
小分けにした肉を冷凍用の袋に入れ、空気をしっかり抜きながら平らに整えます。厚みは2~3cm程度が目安です。さらに、解凍を均一にするために袋の中央を少しくぼませるのがポイントです。 -
急速冷凍する
準備した袋を金属製のバットにのせて冷凍庫へ。金属の熱伝導で冷凍スピードが速まり、肉の食感を損なわずに保存できます。
ポイントと保存期間
・下味をつけているため、解凍後はすぐに調理できる便利さが魅力です。
・保存期間は15~20日が目安。早めに使い切ることで風味を保てます。
・下味にかたくり粉を加えているので、炒めたときにタレがよく絡み、肉がやわらかくジューシーに仕上がるのも特徴です。
出来上がりの特徴
この方法なら「まとめ買いしたけど余ってしまう」という悩みを解消できます。調理の直前に解凍するだけで、豚こまが柔らかく仕上がり、忙しい日の夕食やお弁当作りにも役立つ実践的な保存法です。
豚こま肉の部位と選び方
愛知・名古屋の老舗精肉店では、肩・バラ・モモを合わせて豚こまにするとのこと。部位ごとに特徴があり、赤身が多いとカレーや豚汁に、脂が多いと炊き込みご飯や野菜炒めに向いています。長田絢さんのおすすめは『赤身2:脂身1』のバランス。これなら万能に使え、味も安定します。
夏にぴったり!豚こま冷しゃぶ
硬くならない『豚こま冷しゃぶ』も紹介されました。鍋に酒と砂糖を入れて沸騰させずに豚こまを投入。片栗粉を薄くまぶすのがポイントです。ゆでたら氷水でしめて冷蔵庫で15〜20分冷やすと、しっとり食感の冷しゃぶが完成します。
いまオシ!LIVE 宮城・塩竈市から
料理コーナー以外にも、宮城・塩竈市の塩釜水産物仲卸市場から中継がありました。クロマグロ・メバチマグロの水揚げ量は日本一で、好きな具材を選んで作る『MY海鮮丼』が観光客に大人気。屋外のバーベキューコーナーで買った魚介を焼いて食べられるのも魅力です。
みんな!ゴハンだよ『えびとトマトの冷製パスタ』
最後は『えびとトマトの冷製パスタ』。ミニトマト・オクラ・えびをオリーブ油で和え、バジルをちぎって加えます。氷水で締めたカッペリーニとワインビネガーを合わせ、爽やかに仕上げる夏向きの一皿。ゲストも「バランスがいい」と大絶賛でした。
まとめ
この記事のポイントは以下の通りです。
・豚こまは塊やほぐしすぎに注意し、下味と片栗粉でジューシーに
・『豚こまポークソテー』『野菜のつまみ揚げ』『冷しゃぶ』で家庭料理が格上げ
・冷凍保存は平らに下味冷凍、アルミ箔蒸し焼きで失敗なし
・宮城・塩竈市市場の『MY海鮮丼』や『えびとトマトの冷製パスタ』も必見
豚こま肉を使いこなせば、節約と美味しさを両立できます。あなたも今日から『柔らか極上ソテー』や『冷しゃぶ』に挑戦してみませんか?次回は他の節約肉レシピや市場グルメも深掘り予定です。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

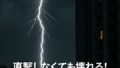

コメント