知床半島の番屋に生きる「ユリばあちゃん」の物語
「もし電気も水道もない場所で暮らすとしたら…あなたはどんな毎日を思い描きますか?」北海道・知床半島の赤岩には、その問いに答えるように生きた女性がいました。藤本ユリさん、通称“ユリばあちゃん”。79歳になっても昆布漁を続け、孤独ではなく自然と共にある日々を送っていたのです。この記事では、2025年9月19日に放送された『時をかけるテレビ』で描かれたユリばあちゃんの姿から、生きる強さと自然との向き合い方を探ります。
番屋での暮らしと拾い昆布漁

知床半島の赤岩にある番屋は、町から船でおよそ1時間半の距離にあります。そこには道路もなく、もちろん電気も水道もありません。暮らしに必要なものはすべて自然から得るしかなく、流れ着いた流木を集めて薪とし、水は近くの沢から汲み上げて使います。風呂も自分で作った簡素なものですが、寒さの厳しい知床で身を温めるためには欠かせない工夫でした。こうした生活は一見不便に思えますが、自然の恵みを最大限に生かす知恵が息づいていました。
拾い昆布漁の厳しさと日課
ユリさんが毎日行っていたのは『拾い昆布漁』です。これは海に自然に打ち上がる昆布を浜辺で拾い集める漁法で、沖に出る必要はありません。しかし、その作業は想像以上に過酷です。夏の初めであっても水温は10℃以下。冷たい海に腰まで浸かり、手作業で昆布を拾い上げるのです。体が冷え切る中で、毎日2時間以上も続けなければならず、並の体力ではできません。
一日の収穫量と流れ
1日の収穫量はおよそ150kg前後。これをただ集めるだけでなく、海水をしっかり切ってから浜に広げ、太陽の光で乾燥させます。湿気が残っていると商品にならないため、天候を見ながら慎重に干していきます。乾燥させた昆布は倉庫に大切に保管し、漁の終盤にあたる9月下旬、まとめて町まで運び出します。町に戻るときには船に山積みになり、赤岩の番屋での数か月間の労働の成果が形となって現れるのです。
高齢でも続けた理由
驚くべきは、この過酷な作業を高齢になっても毎日続けていたことです。昆布を担ぎ、干し場で裏返し、風や日差しを読みながら乾かす。すべてが重労働であるにもかかわらず、ユリさんは若いころと変わらぬ手順で黙々と取り組みました。その姿は、知床の自然と共に生きる強さそのものを示しています。
拾い昆布漁の流れ
| 作業の流れ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 海で拾う | 水温10℃以下の海に腰まで浸かり、昆布を手作業で拾う | 毎日2時間以上、約150kg前後 |
| 浜で干す | 海水を切り、浜に広げて太陽で乾燥 | 天候を読み、風や湿気に注意 |
| 倉庫に保管 | 乾燥後の昆布を集めて倉庫に保存 | 9月下旬まで蓄える |
| 町へ運ぶ | 船に積み、まとめて出荷 | 収穫の成果が生活の支えに |
ユリさんの番屋での暮らしと拾い昆布漁は、ただ生計を立てるためではなく、自然と共に呼吸するように日々を積み重ねる営みでした。
嵐と昆布漁の関係

自然は時に人の営みを壊し、時に大きな恵みをもたらします。赤岩の番屋で暮らす中で、ユリさんも幾度となくその現実を体験しました。過去には嵐によって番屋が高波にさらわれ、全壊したこともありました。しかし一方で、しけの後には昆布の根が緩み、普段以上に大量の昆布が浜へ打ち寄せられます。破壊と恵み、両極端を同時に見せるのが知床の自然でした。
嵐の後に訪れる収穫の好機
ある日のこと、ユリさんは4時間以上も浜辺で昆布を拾い続けました。その日だけで300kgもの昆布を収穫。普段の倍以上にあたる量であり、しけの後ならではの大漁でした。拾った昆布は長く太く、肉厚で質も良く、まさに最高の状態。しかし、この豊かな恵みは長くは続きませんでした。
雨がもたらす落とし穴
昆布は乾燥させることで商品になりますが、雨に濡れてしまうと一瞬で商品価値を失ってしまいます。せっかく大量に拾い集めても、雨に打たれると表面に斑点が出たり、乾燥が進まずに腐ってしまうこともあります。そのため、大漁の日ほど天候とのにらみ合いが続きました。
自然と向き合う知恵
こうした経験を重ねてきたユリさんは、自然を相手に焦っても意味がないことをよく知っていました。嵐の後であっても、雨にさらされればすべて無駄になる。だからこそ「急いで倒れたって何にもならない」「ゆっくりやったほうがあきらめが付く」と話しました。その言葉には、自然を敵にせず、あるがままを受け入れる知恵と覚悟が込められていました。
孤独と仲間の存在

知床の番屋での生活は、一見すると孤独そのものに見えます。町からは船で数時間、電気も水道もなく、日々の生活を支えるのは自分自身の力と自然の恵みだけ。しかし、ユリさんの暮らしは完全な孤立ではありませんでした。岬の反対側に住む友人を訪ねて酒や手紙を届けたり、時には街から長女のキエさん一家が船で訪ねてきて、屋根の修理や風呂の手直しをしてくれることもありました。
家族の願いとユリさんの選択
家族は常に「もう番屋暮らしをやめてほしい」と願っていました。特に高齢になってからは、嵐や野生動物の危険が増える中で、街に戻って安全に暮らす方が安心だと考えていたのです。しかし、ユリさんはその声に耳を貸さず、「ここが自分の居場所」と強い気持ちを貫きました。便利さや安全を求めるよりも、大自然とともにある時間を選び続けたのです。
孤独とつながりの両立
番屋での暮らしは孤独に耐える強さを必要としますが、その中には人との温かなつながりも確かにありました。友人に会うことで心を支えられ、家族が訪ねてきてくれることで安心を得る。そしてそれ以上に、知床の雄大な海や空、山々と向き合うことで得られる心の充足感が、ユリさんの暮らしを支えていました。30年以上にわたり自然と共に生き続けたその姿は、「孤独を抱えながらも仲間とつながる生き方」の象徴といえるでしょう。
野生動物との共生

知床の番屋で暮らすということは、野生動物と常に隣り合わせで生きることを意味します。特にこの地域はヒグマの生息地として知られ、ユリさんの番屋も何度か被害を受けました。過去には番屋が襲われ、蓄えていた食料が食い荒らされ、さらには大切に飼っていた犬が犠牲になる出来事もありました。自然の中で暮らす以上、こうした危険から完全に逃れることはできません。
犬が知らせる危険の気配
番屋で暮らすユリさんにとって、犬はただの伴侶ではなく、命を守る存在でもありました。ある夜、犬が一晩中吠え続けたことがありました。それは、ヒグマが近くに潜んでいる合図。静かな番屋に響き渡る吠え声は緊張感を漂わせ、外に出ることさえ命がけとなります。
自ら考えた対策
ユリさんは危険を減らすため、番屋の周囲の草を刈り取り、見通しを良くする工夫を続けていました。草木が茂るとヒグマが近づいても気づきにくくなり、急に遭遇する危険が増えるからです。自然に挑むのではなく、共に暮らすための知恵を働かせること。それが長年の番屋生活で身についた生きる術でした。
覚悟としての言葉
ユリさんは「怖くないとは言わないが、見てしまってからはどうしようもない」と語っています。その言葉には、恐怖を無理に押し殺すのではなく、恐怖を受け入れたうえで生きるという覚悟がありました。自然と正面から向き合う姿勢こそ、知床の厳しい大地で長年生き抜いてきたユリさんを象徴しています。
80歳を迎える頃の暮らし
79歳の夏、番屋で暮らすユリさんのもとで飼い犬が3匹の子犬を出産しました。犬は番屋生活において単なるペットではなく、大切な家族であり、生活を守る存在でもあります。ヒグマの気配を知らせる役割を果たし、孤独になりがちな日々に寄り添う心の支えにもなっていました。子犬が加わったことで、番屋での暮らしはさらににぎやかさを増していきました。
崖の上から見つめるオホーツク海
80歳を目前にしたユリさんは、岬の突端にある崖に腰を下ろし、オホーツク海をじっと眺める時間を大切にしていました。広大な海原は、30年以上にわたり共に生きてきた相棒のような存在。ここに自分が生きていること、その事実そのものが大きな喜びであり、生きる意味でもあったのです。便利なものが何もなくても、心の豊かさを育むのは自然とのつながりでした。
昆布漁の成果と驚異的な働きぶり
この年の昆布漁では、収穫した昆布が小舟3艘分にものぼりました。水温の低い海に毎日入り続け、昆布を拾い集め、乾かし、保管する。その一連の重労働を高齢になっても休むことなくこなし続ける姿は、ただ驚きと尊敬の一言に尽きます。
人と自然を結ぶ暮らしの象徴
80歳を迎えようとしていたユリさんの生活は、単なる番屋暮らしではなく、人と自然が共に生きる姿を体現したものでした。犬や子犬たちと共に海を見守り、昆布とともに生きるその営みは、知床の大地と深く結びついた人生の集大成といえるものでした。
晩年とその後の知床
高齢になってからも、ユリさんは番屋での暮らしをあきらめませんでした。くも膜下出血などの病に倒れた後もリハビリを続け、再び赤岩の番屋へ戻ることを選んだのです。自然と共にある生活こそが自分の生き方であり、たとえ体が思うように動かなくなっても、その気持ちは揺らぎませんでした。
97歳まで続いた拾い昆布漁
ユリさんは2023年に97歳で亡くなるまで拾い昆布漁を続けていたと伝えられています。晩年はデイサービスに通うようになり、そこで出会う人たちに「赤岩の番屋での暮らし」を誇らしげに語っていたといいます。番屋での日々は彼女にとってただの生活ではなく、生きた証であり、誰よりも胸を張って話せる大切な時間だったのです。
2025年に残る赤岩の風景
現在、2025年の知床半島にはユリさんが暮らした赤岩の番屋が残されています。しかし、今ではそこで拾い昆布漁をする人はもういません。昆布漁の形は変わり、人々の暮らしも便利な方向へ移りましたが、番屋に宿る空気や海を見渡す景色は、ユリさんの時代と変わらずそこにあります。
人々の心に残る存在
厳しい自然と共に生きたユリさんの姿は、ただの漁師ではなく「知床そのもの」を象徴する存在でした。孤独と不便の中に豊かさを見いだし、自然を受け入れて暮らしたその生き方は、多くの人々の心に強く刻まれています。ユリさんの人生は終わっても、赤岩の番屋に立つと今も彼女の息づかいが感じられるようであり、その物語はこれからも語り継がれていくでしょう。
まとめ
この記事のポイントは以下の通りです。
-
藤本ユリさんは知床半島の赤岩で、電気も水道もない番屋暮らしをしながら『拾い昆布漁』を続けた
-
嵐やヒグマなど自然の脅威に立ち向かいながら、自然の恵みを受け入れた暮らしを実践
-
97歳まで生き抜き、その生涯は「自然と人の共生」を体現する物語となった
知床半島の物語は、便利さの中で暮らす私たちに「本当の豊かさとは何か」を問いかけてきます。この記事を読んで心に響いた方は、ぜひ羅臼昆布や知床の自然に触れてみてはいかがでしょうか。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

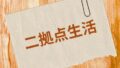

コメント