「桜紀行〜名金線・もう一つの旅〜」
2025年4月11日、NHK総合で放送された『時をかけるテレビ』では、1984年に制作されたドキュメンタリー「桜紀行〜名金線・もう一つの旅〜」が紹介されました。案内役は池上彰さん、ゲストには俳人の夏井いつきさんが出演し、桜に人生を捧げた一人の国鉄バス車掌の姿を現代の視点で見つめ直しました。今回の番組は、太平洋と日本海を“桜の道”でつなぐという壮大な夢を描いた、佐藤良二さんの生涯を丁寧にたどる内容でした。
名金線を舞台に咲いた、夢の桜の道

かつて名古屋と金沢を結んでいた国鉄バス「名金線」は、全長およそ270kmにも及ぶ長距離路線でした。その沿線に、一人の車掌・佐藤良二さんが黙々と桜を植え続けたという物語があります。彼の出身地は岐阜県白鳥町。15歳で国鉄に入り、バスの車掌として働くようになります。
佐藤さんは、若い頃に人生の目標を見失い、生きる意味を感じられなくなっていたといいます。その時、作家・武者小路実篤の著作に出会い、「自分の道を探すことが大切だ」と学びます。この言葉が、彼の心に深く残りました。
やがて佐藤さんは、地元にある御母衣ダムを訪れます。そこに、ダムの建設により水没した村から移植された、樹齢400年の「荘川桜」がありました。この桜は、新たな場所でも根を張り、見事に花を咲かせていたのです。その姿に強く心を打たれた佐藤さんは、「自分も桜を植えたい」と決意します。
・荘川桜は、重機も入らない山の中で、人々の手により大切に運ばれた移植桜
・新天地でも咲いたこの桜は、希望と再生の象徴として語り継がれている
・桜を見た佐藤さんは、「この木のように、自分も何かを残したい」と思うようになる
この出会いをきっかけに、佐藤さんの第二の人生が始まりました。仕事の合間を縫って、スコップと苗木を持ち、バス路線沿いに桜を植えていく日々がスタートします。沿線の土地を一つひとつ歩き、穴を掘って桜を植える作業は、体力も時間もかかるものでしたが、誰にも頼まれることなく、自らの意思だけで続けていきました。
彼が目指したのは、「太平洋から日本海までを桜でつなぐ道を作ること」。そのために、ただ仕事をこなすだけではなく、バスの路線そのものを“夢の道”に変えようとしたのです。
・名金線の沿線には、当時から自然が多く、桜が映えるロケーションが多数存在
・佐藤さんは、植えるだけでなく、定期的に水やりや手入れも欠かさなかった
・彼の活動は目立たず、表彰もされなかったが、その想いは土地に根を張っていった
こうして始まった佐藤良二さんの桜植樹の旅。それは、ただ花を咲かせるだけでなく、自分の人生を桜とともに歩むという覚悟に満ちた旅でもありました。名金線は、彼の思いを乗せて走る、もう一つの人生の舞台となったのです。
穴を掘り、桜を植え、そして生きた証を残した日々

佐藤良二さんが描いた夢は、名古屋から金沢までのおよそ270kmを30万本の桜で埋め尽くすことでした。ただの思いつきではなく、強い意志と覚悟に裏打ちされた挑戦でした。彼の活動はまず、自身のふるさと岐阜県内から始まります。地元である白鳥町を起点に、美濃市、八幡町、大和村、高鷲村といった、冬には雪深くなる山間地を一つひとつ歩き、自らの手で穴を掘り、桜を植えていきました。
・植樹に使った苗木は、地元の人から譲り受けたものや自費で購入したもの
・山の中腹ではスコップを持って登り、時には雪をかき分けながら作業
・手伝いを頼まず、自分の手で植えることに意味があると信じていた
良二さんにとって、この桜植樹は誰かのためではなく、自分の心と向き合う大切な時間でもありました。バスの車掌としての仕事を終えた後も、彼の一日は終わりません。車庫に戻った後、道具を積み替え、そのまま山へと向かう日々が続いていました。
そんな彼を、唯一支えたのが幼なじみで運転手の佐藤高三さんです。高三さんは、良二さんの情熱に心を打たれ、植樹に必要な場所への送り迎えを買って出たり、寒い中での作業を手伝ったりしました。二人は、言葉少なでも心が通じ合う“戦友”のような存在だったといいます。
・高三さんは運転手の仕事の合間に、穴を掘る作業や苗木の運搬も手伝った
・桜の植樹地には、バスの運行中に目をつけ、休みの日に再訪することもあった
・二人の絆があったからこそ、厳しい山道にも負けず続けられた
記念すべき100本目の桜は、岐阜と福井の県境・油坂峠に植えられました。その場所は標高も高く、春でも雪が残る厳しい環境です。良二さんは、この場所に「いつか桜の公園を作りたい」と話していたそうです。実現こそ叶いませんでしたが、その木は今も根を張り続けています。
雪が積もった冬には、良二さんの兄や姉がその木を掘り起こし、桜が傷まないように雪から守ってきました。家族もまた、良二さんの意志を受け継ぎ、静かに支え続けてきたのです。
・油坂峠の桜は、毎年雪に埋もれるため、開花の準備が人の手で行われる
・兄姉は「今年もあの木を守らなければ」と雪をかき分け、木の周囲を整える
・亡き弟の夢を、家族が静かに守っている姿に、多くの人が心を打たれた
こうして佐藤良二さんは、言葉にすることなく行動で示し続けました。穴を掘り、桜を植え、そして生きた証を大地に残す。そのひとつひとつの桜が、今も名金線の跡を彩り、人々の記憶の中で静かに花を咲かせ続けています。
2000本目の桜と、輪島まで広がった想い

佐藤良二さんが植えた2000本目の桜は、金沢市の兼六園にあります。日本三名園のひとつとして知られるこの名所で、春になるとその桜は見事な花を咲かせ、多くの人々の目と心を楽しませています。ただの記念としてではなく、そこには良二さんの生涯をかけた活動の“節目”としての意味がありました。
・兼六園は、江戸時代からの伝統と風情を残す日本有数の庭園
・その一角に咲く桜に、良二さんが植えた苗木が成長し続けている
・2000本目は、彼にとって「到達点」であると同時に「通過点」だった
良二さんの想いは、その土地に留まりませんでした。石川県輪島市の教師・平松さんは、良二さんの行動と信念に深く感動し、自らも桜を植えようと決意します。二人は「桜並木を能登の先端・輪島まで伸ばそう」と約束を交わし、平松さんは実際に良二さんから苗木を譲り受け、能登半島の土地に植樹を始めました。
・平松さんは当時、地域の教育に力を入れていた人物で、子どもたちにも桜の大切さを伝えた
・良二さんから受け取った苗木を、自らの手で能登の山や道沿いに植えた
・名金線の精神が、路線外の土地にも広がっていった瞬間だった
そんな中、昭和51年に良二さんは病に倒れます。進行する病の中でも、「まだ植えなくちゃいかん」と語り続けていたと伝えられています。決して諦めることなく、病床でも桜への想いを失いませんでした。翌年の昭和52年、47歳の若さでその短くも濃い人生に幕を下ろします。
・病名は明かされていませんが、体調を崩しても活動を止めることはなかった
・最期まで“次に植える場所”を考えていたという
・「桜とともに生き、桜とともに死ぬ」その覚悟が言葉に表れていた
また、共に桜を植え続けた佐藤高三さんも、昭和57年に52歳で逝去。幼なじみとして、運転手として、そして心の支えとして、良二さんの活動を支え続けた人物でした。
・高三さんは、良二さんの没後も、桜の世話を続けていた
・病気で亡くなる直前まで、「あの桜はどうなったか」と話していたとも伝わる
・二人の“静かな挑戦”が、道沿いの景色を変えていった
こうして、良二さんと高三さんの命と想いは、沿線に咲く桜となり、今も訪れる人々の心に語りかけています。花びら一枚一枚が、彼らが流した汗と時間の結晶なのです。彼らの姿は見えなくなっても、春になるとその証が、やわらかな花となって咲き誇っています。
「美しい花を見て死にたい」…良二さんの言葉
番組では、1984年に放送されたドキュメンタリーの映像とともに、佐藤良二さんが遺した日記の一節が紹介されました。そこには、彼がどのような気持ちで桜を植え続けていたのかが、静かに、しかし力強く記されていました。
「一人で穴を掘り そして美しい花をさかせ そして死んでゆくのがオレの人生だ」
「人のためにやる仕事ではない」
「美しい花を見て死んでゆきたい」
これらの言葉には、派手な表現や大きな夢ではなく、自分の手で成し遂げることに意味を見いだしていた彼の生き方が映し出されています。
・穴を掘る作業は誰に見られるわけでもなく、地道で孤独なものでした
・桜が咲くのは数年後。植えた本人がその満開を見届けられないことも多かった
・それでも、「やるべきこと」として、一歩一歩積み重ねていた
良二さんは、桜を「誰かのため」に植えていたわけではありませんでした。それはあくまで、自分が生きている証として残す行為。誰に頼まれたわけでもなく、誰から賞賛されることも求めていなかったのです。だからこそ、言葉には、重く、真っ直ぐな想いがこもっていました。
・「人のためではない」と書いた裏には、自分の意思で行うことへの誇りがある
・「美しい花を見て死にたい」は、人生の終わりをどう迎えたいかという願いでもある
・桜は彼にとって、“生”と“死”をつなぐ象徴のような存在だった
そんな良二さんの想いは、彼が亡くなったあとにも語り継がれていきます。妻が自宅の桜を見て、ぽつりとつぶやいた言葉――「お父ちゃんが花になって帰ってきよった」――その一言は、良二さんが最後に目指していた境地に、確かにたどり着いていたことを物語っています。
・植えた桜の木は、家族にとって「遺された存在」ではなく「帰ってきた存在」
・その桜が咲くたびに、家族も近所の人も、彼の姿を思い出すようになった
・桜の花は、良二さんそのものとして、今も人々の心に咲いている
こうして佐藤良二さんの人生は、一人で始め、一人で貫いた道でありながら、多くの人の心に深く根を下ろす道にもなりました。春の風に舞う花びら一枚一枚に、彼の歩んだ人生が今も生き続けています。
続編ドキュメンタリー「ふるさとの桜 ~荘川桜 50年の物語~」も紹介
番組の後半では、良二さんの活動を追った続編ドキュメンタリー『ふるさとの桜 ~荘川桜 50年の物語~』(2011年放送)もダイジェストで紹介されました。ここでは、良二さんが病床でまいた荘川桜の種が5年後に芽を出し、各地に届けられていったエピソードが語られました。
特に高知県の別枝、名古屋市の枇杷島小学校など、遠く離れた地でもその桜は今なお残り、地域の記憶や希望の象徴として大切にされています。枇杷島小学校ではこの日も入学式が行われ、新一年生が良二さんの桜に迎えられて入学しました。
俳人・黒田杏子の句と夏井いつきさんの解説
ゲストの夏井いつきさんは、「桜は俳句にとって特別な存在」と語りました。日本には桜にまつわる季語が豊富にあり、それが俳人たちが桜を愛する理由でもあります。師匠である俳人・黒田杏子さんの句として、
「花を待つ ひとのひとりと なりて冷ゆ」
「身の奥の 鈴鳴りいづる さくらかな」
といった詩が紹介され、桜が持つ“待つこころ”“響くこころ”を丁寧に読み解いていきました。
災害に負けない桜と、未来へのバトン
そして最後には、2025年の輪島市にある輪島漆芸美術館の桜も登場。この桜は、佐藤良二さんが残した苗から育ったもので、昨年の災害にも耐えて、今年も見事に咲いています。人の想いが時を超えて生き続ける、そんな姿が印象的でした。
『時をかけるテレビ』は、過去のドキュメンタリーを単に再放送するだけではなく、現代の視点から新たな意味や価値を掘り起こす番組です。今回の放送は、「一人の行動が、長い時間をかけて人の心を動かす」ことの大切さを、改めて私たちに教えてくれる内容となりました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


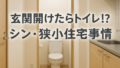
コメント