「写真の中の水俣」胎児性患者・6000枚の軌跡
2025年5月9日(金)夜10時30分からNHKで放送された『時をかけるテレビ』では、1991年に放送された九州スペシャル「写真の中の水俣 ~胎児性患者・6000枚の軌跡~」を取り上げました。水俣病が公式に確認されたのは69年前の5月1日。この時期に合わせて放送された今回の回では、胎児性患者である半永一光さんの人生と、彼が撮り続けた6000枚の写真に込められた思いが紹介されました。司会の池上彰さんが時代を超えてその意味を掘り起こし、ゲストには熊本出身の宮崎美子さんが出演。水俣で何が起き、いま何が伝えられるべきなのか、深く考えさせられる特集でした。
胎児性患者・半永一光さんが写し出した“静かな声”

番組の中心にいたのは、胎児性水俣病の当事者である半永一光さん。彼は生まれる前、母親の胎内で有機水銀により発症し、生まれながらにして歩行や発話が困難な身体でした。漁業で栄えていた水俣の海にチッソ水俣工場からの排水が流れ込み、それが原因となった水俣病。魚は天の恵みであり、生活の糧であるはずの海が命を奪う場所へと変わってしまったのです。
半永さんは昭和30年代、代々続く漁師の家に生まれましたが、父もすでに水俣病を発症しており、母は彼が3歳のときに家を出て行ったと伝えられています。半永さんは1歳で入院し、7歳のときに水俣市立明水園に入所。以来19年間、そこで暮らしていました。明水園は公的な福祉施設であり、重度の患者や在宅療養が困難な人の受け入れ先として常に満室の状態が続いています。
・日課は新聞を読むこと。言葉を話せなくても、内容を理解していると主張
・「分かっていることを伝えられない」というもどかしさが、彼の内面を静かに描き出していた
・周囲からは話しかけられるものの、彼の反応が理解されづらい現実が続いていた
そんな中で、彼が17歳のときに出会ったのがカメラでした。いつもは自分に向けられていたレンズを、自分の手で握り返す瞬間。最初に撮影した写真は、モデルの人がカメラ位置に移動してくれた1枚でした。写真を撮るとき、彼は笑顔になったといいます。自分の思いを言葉にできない代わりに、レンズを通して社会とつながることができる。カメラは半永さんにとって、世界に心を開く扉だったのです。
・自分のことを見てほしいという願いが、レンズにこめられていた
・6000枚を超える写真には、日常、風景、そして“水俣の記憶”が詰まっている
・写真は単なる記録ではなく、「声のない声」の代弁者となっていた
仲間たちの想いと歩みを映す
番組では、他の胎児性患者たちの姿も丁寧に紹介されました。鬼塚勇治さん(35歳)は、自由に動くことができませんが、演歌を聞くことが趣味であり、かつては石川さゆりさんのショーにも出かけたことがあると語られました。また、金子雄二さん(36歳)はパチンコが日課で、仕事に就きたいという夢を持ち、大分県の施設まで自ら出向いたこともあります。ですが、障害の程度から入所を断られ、悔しさをにじませていた様子が映し出されました。
坂本しのぶさん(35歳)は、姉を幼くして水俣病で亡くした過去を持ち、自らも機織りを習い始めていました。「恋人のような人がいれば嬉しいけど、胎児性の子どもが生まれるのが怖い」と語る坂本さんの言葉には、自分の未来への不安と向き合う力強さが感じられました。
・患者一人ひとりに生活があり、思いがあることを映像で丁寧に伝えていた
・障害があっても“日常を楽しむ心”と“未来への希望”は失われていなかった
・患者たちの姿が、社会の無理解と希望の狭間を物語っていた
また、元舞台俳優の砂田明さんが登場。彼は石牟礼道子の『苦海浄土』に共鳴して水俣に移住し、半永さんをモデルにした一人芝居を続けています。芝居の中で、「どうしてそんな身体で生まれてきたのか?」という問いを投げかける場面が印象的でした。演劇という表現が、現実の痛みを社会に届ける手段として力を持っていることを感じさせました。
水俣国際会議と写真展に込めた願い

1991年11月に行われた「水俣国際会議」では、国内外から専門家や学者が集まり、重金属汚染などの事例を報告し合う形で開かれました。半永さんはこの会議に合わせ、自らの初の写真展を開くことを決意。友人たちの協力もあり、写真展は実現へと動き出します。
しかし、熊本県と水俣市の間で会場利用の調整が進まず、一時は開催が危ぶまれる事態に。施設側の職員から「父親が止めているから立ち会えない」と伝えられるなど、当事者不在のやり取りに疑問の声も上がりました。それでも、周囲の支援を受けて写真展は無事に開催。海外からの視察団とも直接交流があり、「あなたたちの存在は大切」と言葉をかけられる場面も印象的でした。
・写真展の開催は、彼にとって「はじめて心を見てもらえた」時間だった
・国際会議では患者の発言の機会が当初なく、批判の声が上がる
・最終的に発言が認められ、「水俣病は解決していない」という声が響いた
そして、会議の3日目。参加者から「患者の声がなぜないのか」という問いが出て、ようやく患者の意見が受け入れられました。これこそが、社会の中で“聞かれるべき声”が何かを考えさせる大きな瞬間でした。
終わらない“水俣”を見つめ続けて
番組のラストには、再放送の制作に携わった吉崎健ディレクターが登場。水俣病の真実と向き合い続けてきた背景や、患者たちとの出会いが自身の人生に与えた影響について語りました。また、フィリップ・グランジャン教授など、水俣病を研究する海外の専門家の姿も紹介され、水俣の記憶は世界に広がっていることが伝えられました。
「裁判が終わっても、症状は終わらない」「過去の問題ではない」。番組を通して、視聴者にそう訴える声が重く響いていました。写真を通して自分の思いを伝え続けた半永さんの姿は、これからも水俣の“記録者”として残り続けることでしょう。今なお続く水俣の現実を見つめ直し、一人ひとりが何を知り、どう受け止めるかが問われています。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


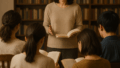
コメント