“レペゼン埼玉”でめぐる春日部・越谷の旅
埼玉県の春日部と越谷には、地域を愛して活動する人たちや、長く受け継がれている名物があります。今回の旅で紹介されるのは、春日部を代表するラッパー、歴史ある麦わら帽子の工場、そして越谷の寺で長年親しまれる名物だんごです。
NHK【ドキュメント72時間】バイヨンでメダルゲーム三昧!埼玉・ふじみ野の“シングルマシン聖地”で見た72時間の人間模様|2025年4月11日NHK放送
春日部と越谷の魅力が濃縮された“代表者たち”
春日部には、地元を背負いながら全国に存在感を示すラッパーがいます。さらに、春日部の産業として長く地域を支えてきた麦わら帽子の工場があり、越谷にはお寺の境内で半世紀近く親しまれる名物だんごがあります。それらを守るのは地元の家族や兄弟たち。こうした「土地を象徴する人々」が集まっているのが、この旅の面白さでもあります。
春日部を象徴するラッパーの背景とまちへの思い
春日部を代表するラッパーといえば、地元出身の崇勲さんです。MCバトルの大会で優勝した実績を持ち、テレビ番組への出演も多く、今や全国的に知られる存在になっています。しかし、活動の中心には常に地元・春日部があり、その姿勢が多くのファンを惹きつけています。
『春日部鮫』というアルバムのタイトルにも象徴されるように、春日部で生まれ育った経験を音楽として表現し続けてきました。地元の風景や人の雰囲気を盛り込むことで、春日部の空気そのものがラップという文化の中で息づいています。
また、春日部にはTKda黒ぶちさんなど、同じ地域から育ったラッパーもおり、それぞれが春日部の名前を背負って活動しています。何気ない地方都市のなかに、こうしたカルチャーがきちんと根付いていることは地域にとって大きな誇りです。今回の旅では、春日部の音楽文化の空気感や、地元で活動を続けることの意味がどのように語られるのか注目が集まります。
伝統を手でつなぐ春日部の麦わら帽子工場
春日部は、実は麦わら帽子の一大産地だった歴史を持っています。この伝統を今も守り続けているのが田中帽子店です。創業は明治期にさかのぼり、100年以上にわたり天然素材の帽子をつくり続けてきました。
工場では、細く割いた麦わらを何本も編んでつくる「麦わら真田(さなだ)」をつなげながら、職人が一つずつ帽子の形に整えていきます。大量生産の時代になっても、手作業でしか出せない美しさや質感を大切にし続けてきた工場です。
現在は六代目である田中優さんが技術と理念を受け継ぎ、春日部の伝統産業を未来へつなぐ役割を担っています。麦わら帽子は涼しくて軽く、夏の風景にもぴったりのアイテムであり、春日部の土地の記憶を今に伝える工芸品ともいえます。
今回の旅では、そうした歴史的背景や職人の手しごとがどのように紹介されるか期待が高まります。
越谷の「寺のだんご」を支える兄弟の温かい物語
越谷を訪れる人たちが必ずといっていいほど立ち寄る名物が、大相模不動尊大聖寺の境内で焼かれる虹だんごです。1970年代から続く名物で、もちもちとした食感と醤油だれの香ばしさが人気です。
この「寺のだんご」を守っているのが、先代と縁の深かった冨田兄弟です。彼らはもともと店の常連客家族であり、先代が亡くなった後に味を絶やさないため事業を引き継ぎました。
兄弟は店を支える力そのもので、毎日のお参りや散歩のついでに訪れる人たちの思い出も一緒に守り続けています。長年地域の人に愛されてきた味を続けるというのは簡単なことではなく、素材選びや焼き方、タレの仕上げまで変わらぬこだわりを保ち続けている努力があります。
寺院の静かな空気の中で焼き上がるだんごは、越谷の“帰ってきたくなる味”として語られることも多く、この旅でも温かい時間が描かれるはずです。
まとめ
春日部と越谷の旅には、地域を象徴する人物と文化が凝縮されています。
崇勲さんに代表される春日部の音楽カルチャー、100年以上伝統をつないできた田中帽子店、越谷の寺で続き、多くの人に愛される虹だんごとそれを守る冨田兄弟。
どれも“レペゼン埼玉”と呼ぶにふさわしい存在で、地域の歴史や誇りが日常の中にしっかり根付いています。
【オモウマい店】埼玉・羽生の味のイサムが熱い!1日限定50組“豚からラーメン”が爆誕!行列が止まらない理由とは|2025年10月28日
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

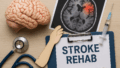
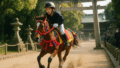
コメント