眠っていた“ツボ”の真実──科学が証明する東洋医学のチカラ
「ツボって本当に効くの?」「お灸は気休めじゃないの?」そう感じる人は少なくありません。けれども、今、世界中の科学者たちがその“神秘”を解明し始めています。古来より伝わる東洋医学の知恵が、最新の脳科学や免疫学の研究によって、実際に効果があることが証明されつつあるのです。
2025年10月6日放送のNHK総合『フロンティアで会いましょう!』では、最新研究を通して“ツボと漢方の科学的な力”を多角的に紹介していました。
まず取り上げられたのは、アルプス山脈の氷河から発見された約5300年前のミイラ、通称アイスマン。その体には60か所以上の入れ墨が刻まれていましたが、驚くことに、それらの位置が現代の鍼灸で用いられるツボと一致していたのです。腰痛や関節痛に効く“ツボのライン”と重なっていたことから、アイスマンはすでに“ツボ治療”のような方法を実践していたのではないかと考えられています。
さらに、持ち物の中から見つかった乾燥きのこには、抗菌作用や整腸作用のある成分が含まれており、古代ヨーロッパでも“生薬”が使われていた可能性が浮上しました。
この調査を主導したのが、イタリアのアルベルト・ツィンク博士。また、ドイツのヨハネス・グーテンベルク大学のトーマス・エファース教授も、「東洋医学が西洋医学で治せない病気の手助けになる」と確信を語りました。科学者たちは、古代の人類が体験的に見出した“ツボの原理”を、いま改めてデータで裏づけようとしているのです。
世界が注目する「足三里」——身体を整える万能のツボ

番組の中で特に取り上げられたのが、足三里(あしさんり)。膝の下にあるこのツボは、胃腸の調子を整えるだけでなく、免疫機能や自律神経の安定にも関係しているといわれます。
舞台は南アフリカの港町ダーバン。貧困層が多く、医療機関に行けない人々のために設けられたベルヘブンメモリアルセンターでは、鍼灸による無料治療が行われています。ここで特に大切にされているのが足三里へのお灸。足三里を温めることで体内のエネルギーが巡り、ストレスによる不調や免疫低下が改善するといいます。
科学的には、ツボを刺激すると神経を通じて脳に信号が届き、自律神経やホルモン分泌を調整。結果として、内臓の働きや免疫系に良い影響を与えることが分かっています。
このツボの可能性を信じ続けたのが、“お灸博士”と呼ばれた原志免太郎氏。彼は自ら毎日、足三里にお灸を据え、結核治療にも応用。104歳まで現役医師として活動し、108歳で亡くなるまで生涯現役を貫きました。彼の長寿は、お灸とツボの力を象徴する存在となりました。
うつ症状をやわらげる3つのツボ
現代社会で増えている「心の不調」にも、東洋医学は注目されています。番組では、うつ症状の改善に効果があるとされるツボとして「内関(ないかん)」「合谷(ごうこく)」「百会(ひゃくえ)」の3つが紹介されました。
・内関:手首の内側にあり、ストレスによる動悸や不安を落ち着かせる。
・合谷:親指と人差し指の付け根にあり、頭痛や緊張、イライラを和らげる。
・百会:頭頂部にあり、自律神経の乱れを整え、気持ちをリセットする。
これらを日常生活で意識的に刺激することで、薬に頼らず“自分で整える”習慣が生まれます。科学的にも、ツボ刺激によって副交感神経が優位になり、脳内でセロトニンやドーパミンが適切に分泌されることが確認されています。
鍼灸が命を救う——敗血症治療の最前線
西洋医学でも治療が難しい病気のひとつが敗血症。感染によって免疫が暴走し、体の組織を破壊してしまう病です。
ペニート・フアレス自治大学の外科医で鍼灸師でもあるラファエル・トレス・ロサス氏は、この敗血症に対して鍼治療が有効であることを実験で示しました。
彼の研究では、敗血症に感染させたマウスを2つのグループに分け、片方には鍼刺激を与えました。すると、何もしなかったマウスは全滅したのに対し、鍼刺激を受けたマウスの半数が生存。ツボ“足三里”への刺激が、神経を介して副腎を活性化し、ドーパミンを分泌。暴走した免疫を鎮めたのです。
ロサス氏は「鍼灸はもはや“東洋の神秘”ではなく、科学が認める生理学的メカニズムだ」と語りました。
「生薬」と「漢方薬」——その違いを正しく理解する
東洋医学のもう一つの柱が“漢方薬”。まず押さえておきたいのが、“生薬”と“漢方薬”の違いです。
生薬は、植物の根・茎・葉・鉱物・動物などを乾燥・加工したもの。たとえばショウキョウ(生姜)やケイヒ(シナモン)などがこれにあたります。
一方の漢方薬は、複数の生薬を一定のバランスで組み合わせたもの。たとえば『葛根湯』には、カッコン・ケイヒ・シャクヤク・タイソウ・カンゾウなど7種類が含まれています。それぞれの作用が補い合い、体のバランスを整え、自然治癒力を引き出すのです。
驚異の歴史! 5万年前から続く薬草の知恵
番組では、東洋医学の源流をさらにさかのぼる研究も紹介されました。
グラスゴー大学のカレン・ハーディ教授は、スペインのエルシドロン洞窟で発見されたネアンデルタール人の骨を調査。その結果、止血作用のある『ノコギリソウ』の成分アズレン、鎮静作用を持つ『カモミール』の成分クマリンを検出しました。
つまり、5万年前の人類はすでに薬草を使って体を癒していたのです。狩りの傷を治し、痛みを和らげるために“自然の力”を活用していたことがわかります。東洋・西洋の区別を超え、医療のルーツは“人間と自然の共生”にあったのです。
腸炎・肝疾患の治療にも光る漢方の力
現代の研究でも、漢方薬の効果が科学的に解明され始めています。
理化学研究所の佐藤尚子さんは、サンショウ・ニンジン・カンキョウを主成分とする『大建中湯』の研究を進めています。マウスの腸炎モデルに投与したところ、腸内の乳酸菌“ラクトバチルス”が増え、炎症を鎮めることが確認されました。腸内で作られる“プロピオン酸”が免疫細胞(3型自然リンパ球)を活性化し、粘膜のバリアを強化する仕組みです。
一方、名古屋大学医学部附属病院の横山幸浩医師は、胆管がんの手術前に『茵蔯蒿湯(インチンコウトウ)』を投与する研究を実施。この漢方から腸内細菌によって生成される“ジェニピン”が肝臓に作用し、黄疸を改善させることを突き止めました。
これらの成果は、漢方が西洋医学の限界を補う“共存の医療”として見直されていることを示しています。
東洋医学が描く未来図
近年、世界中の研究機関が注目するのが『アルテミシア・アヌア(クソニンソウ)』という植物に含まれる“アルテミシニン”。マラリアの治療薬として知られるこの成分が、がん細胞の増殖を抑える作用を持つことが確認されています。
かつて原志免太郎氏が語った「灸法の研究は医学の最終目的に近づく保証を与えた」という言葉が、今まさに現実のものになりつつあるのです。
東洋医学は、ただの伝統ではなく、未来の医学の“もう一つの軸”として再評価されています。人類が長い時間をかけて蓄積してきた「自然の叡智」を、AI時代の科学がようやく理解し始めたとも言えるでしょう。
まとめ:古くて新しい、“人を癒す知恵”へ
この記事のポイントは次の3つです。
・ツボやお灸の効果は、神経やホルモンを介した科学的作用として説明できる
・漢方薬は腸内細菌や免疫システムを整え、現代医療を補う力を持つ
・東洋医学は過去の遺産ではなく、未来の医療の礎になりつつある
5万年の時を越え、人類が受け継いできた「癒しの知恵」。それがいま、科学の言葉で語られる時代に入りました。体を温め、呼吸を整え、自然とともに生きる。その“当たり前”の知恵こそ、これからの医療の原点になるのかもしれません。
出典:NHK総合『フロンティアで会いましょう!』(2025年10月6日放送)
https://www.nhk.jp/p/frontier/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

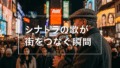
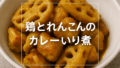
コメント