進化する自転車の秘密に迫る!電動アシストから町の自転車屋さんまで
2025年5月25日放送の『有吉のお金発見 突撃!カネオくん』(NHK総合)では、「街乗りからレジャーまで!進化する自転車!」と題し、電動アシスト自転車や町の自転車屋さんにスポットを当て、自転車にまつわる「お金のヒミツ」を深掘りしました。自転車の魅力は移動手段だけでなく、観光資源やライフスタイルの変化にも影響を与えており、今回の放送ではその進化の裏側が紹介されました。
電動アシスト自転車は今や定番!製造現場を大公開
いまや通勤や育児、買い物にも活躍する電動アシスト自転車は、1993年に日本で販売が始まりました。当初はまだ珍しかったこのタイプの自転車も、2018年以降は通常の自転車よりも販売台数が多くなるほどの人気となり、今では私たちの暮らしに欠かせない存在です。
大阪・柏原市にある工場では、製造の様子が詳しく紹介されました。工場ではまず金属パイプの切断・加工を行い、続いてロボットが自動で溶接・塗装を担当しています。ここで使われているロボットは精密に動作し、製品にムラのない仕上がりを実現しているそうです。モーターとバッテリーは改良が重ねられ、昔に比べて軽く、寿命も長くなっていることが映像でも明らかになりました。完成品の最終組み立ては今でも人の手で行われており、丁寧な手作業が品質を支えています。
こうした製品は、実際に使う人たちの声を取り入れて進化しています。たとえば育児中の家庭に向けては、子どもを乗せても安定するように重心が低くなる設計に変更。押して歩く場面でも電動アシストが使えるようにし、坂道や重い荷物のあるときでも負担を軽減できるようになっています。さらに、電子キーが付いたり、空気圧の残量が一目でわかるディスプレイが搭載されたモデルもあります。
-
アシストが効く速度は法律により時速24kmまでと定められている
-
ペダルをこがなくても進むタイプは自転車ではなく「原動機付自転車」扱い
-
免許やヘルメットの着用が必要で、自転車のように気軽には使えない
こうしたルールも、安全性を確保するためにしっかり設けられているのです。
さらに注目されたのは、駐輪場でも困らないよう工夫された新しい設計です。カゴがぶつからないように縦にスリムな形状に変えたタイプや、サドルが変形してロックになる機能など、盗難防止の面でも技術が進んでいます。とくにサドル一体型ロックは、見た目がスマートで鍵の管理も簡単なため、ユーザーから好評とのことです。
-
タイヤそのものに空気入れ機能を内蔵した製品も登場
-
開発は大阪・堺市の町工場によるもので、日本の大手メーカーにも採用されている
-
タイヤ単体でも販売されており、交換時の選択肢も増えている
こうした小さな工夫や技術革新が、自転車全体の快適性や安全性を高めています。毎日の移動手段としてはもちろん、家族全員が安心して使える乗り物へと進化し続けていることがよくわかる内容でした。今後もさらに利便性の高いモデルが登場していくことが期待されます。
自転車屋さんの裏側を密着取材

今回の放送では、東京・中野区で91年もの歴史を持つ老舗自転車店の様子が紹介されました。この店舗は地域に根ざした営業を続けており、月に約40台の自転車を販売。売上は月平均で約120万円にのぼるといいますが、その内訳の多くを支えているのが修理やアフターサービスです。
とくに多いのがパンク修理で、1日に50件近くの依頼が来る日もあるとのこと。スタッフは常に忙しく作業しており、店舗の一角には修理中の自転車が並んでいました。中でも印象的だったのは、空気入れの無料サービスです。これは長年の利用者が多い地域だからこそできる配慮で、気軽に立ち寄れる安心感が提供されています。
-
バルブキャップがなくても空気が抜けることはない
-
ただし、キャップは雨水やゴミがバルブに入り込むのを防ぐために必要
-
劣化やトラブル防止にもつながるため、見落とされがちだが重要なパーツ
店ではこうしたちょっとした知識もしっかり説明しており、ただの修理屋ではなく「自転車の相談所」のような存在となっています。
最近では、ライフスタイルの変化に合わせたカスタムの依頼が増えています。たとえば、子どもが成長してチャイルドシートが不要になった家庭からは、代わりにカゴを取り付けるカスタムの注文がよくあるとのことです。このような要望に対応することで、長く同じ自転車を使い続けられるようサポートしています。
-
サドルの交換や補助輪の取り外しなども日常的な依頼
-
ハンドルの高さやブレーキの調整など、細かなカスタムも要望に応じて対応
-
子ども用から通勤用まで、ライフステージに合わせた対応力が強み
また、店では地域の公園や保育園への出張修理も行っており、急なトラブルにもすぐに駆けつける体制を整えています。地域に密着しながらも、現代のニーズに柔軟に応えていくその姿勢は、昔ながらの商店の温かさと現代的な機動力が共存する姿といえます。
自転車は乗るだけでなく、使い続けるためのサポートがあってこそ便利な移動手段になります。今回紹介されたような町の自転車屋さんは、まさにその役割を担い、これからも必要とされる存在であり続けるでしょう。
観光資源としても注目される自転車

今回の放送では、自転車が観光資源として活用される例にも注目が集まりました。とくに取り上げられたのが、広島県と愛媛県を結ぶ「瀬戸内しまなみ海道」です。全長約70kmにわたって美しい島々と橋が連なるこのルートは、サイクリストにとっては憧れのスポットとして知られています。海を望みながら走ることができるため、国内外の観光客に人気で、年々その利用者は増加しています。
-
サイクリング用の専用レーンが整備されていて初心者でも安心
-
各所にレンタサイクルステーションが設置されており、利便性も高い
-
地元の飲食店や宿泊施設とも連携し、地域全体で自転車観光をサポート
さらに注目されたのが、「サイクルトレイン」と呼ばれるサービスです。これは自転車をそのまま解体せずに列車内へ持ち込める仕組みで、観光客にとって非常に便利な移動手段となっています。長野県や広島・愛媛の一部地域ではすでに導入が始まっており、今後さらに広がる可能性があります。
-
自転車を折りたたむ必要がなく、手間を減らしてスムーズに移動できる
-
電車とサイクリングを組み合わせることで移動範囲が大きく広がる
-
車を使わず環境にも優しいため、エコツーリズムとの相性も良い
こうした取り組みは、単なる移動手段としての自転車にとどまらず、地域の魅力を発信するツールとしての役割を担っています。特に、交通の便が限られた観光地でも自転車が活用されれば、訪れる人の自由度が高まり、滞在時間や消費金額の増加にもつながると考えられています。
このように、自転車は今や暮らしの道具を超えて、観光振興の柱のひとつとしての可能性を広げています。今後も、地域と連携した取り組みや、新たなサービスの展開が期待されます。
まとめ
今回の『カネオくん』では、自転車の技術革新や地域とのつながり、そして観光資源としての新たな価値まで、多面的に紹介されました。普段当たり前のように使っている自転車が、実はたくさんの人の努力やアイデアで支えられていることがよくわかる内容でした。今後も私たちの生活に欠かせない乗り物として、自転車はさらに進化していくことでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

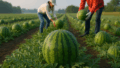
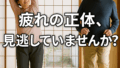
コメント