実は春こそ甘さ抜群!すいか〜熊本市〜
すいかといえば夏の果物というイメージが一般的ですが、実は5月から6月にかけてが旬の「春すいか」という新しい常識が熊本県では広がっています。『うまいッ!』の今回の放送では、全国一の出荷量を誇る熊本市北区植木町のすいかに注目し、春ならではの甘さの秘密や栽培方法、すいかを使った料理法まで詳しく紹介されました。生産現場の工夫や地元の努力、そしてすいかの魅力を余すところなく伝える内容となっており、これからの季節にぴったりの情報が満載です。
熊本市植木町は春すいかの一大産地

熊本県はすいかの出荷量が全国1位で、中でも熊本市北区の植木町は有名なすいかの産地です。この地域では江戸時代からすいかの栽培が行われてきたとされており、土壌や気候に恵まれた土地ならではの歴史があります。植木町は盆地に位置しており、昼と夜の寒暖差が大きいという地形の特徴を活かし、糖度の高いすいかが育ちやすい環境が整っています。
春先は朝晩が冷え込む一方で昼間は暖かくなるため、光合成が活発に行われ、すいかにぐんぐんと栄養が蓄えられます。これにより、春に収穫されるすいかは甘みがしっかりと乗り、果肉もシャリっとした食感に仕上がるのが特徴です。
出荷の最盛期は5月から6月。真夏に出回るすいかよりも、春すいかの方が甘くて美味しいという声も多く、近年ではその認識が地元だけでなく広い地域に浸透してきました。熊本では「春すいかが一番うまい」という言葉がすっかり定着しています。
実際に、番組内では道の駅「すいかの里植木」の様子も紹介されており、春のすいかシーズンになると朝早くから人が並び、すいか売り場には行列ができるほどの人気ぶりです。
-
店頭には見事に大玉のすいかがずらりと並び、1玉ずつ糖度や見た目など厳しくチェックされたものだけが並ぶ
-
すいか目当てで県外から訪れる観光客の姿も珍しくない
-
春すいかを贈答用に購入する人も多く、「母の日」や「父の日」のギフトとしても人気
また、「春すいか」という名称は、4月から6月にかけて出荷されるすいか全般を指しています。春すいかは栽培期間中の気温管理も難しく、生産者の手間がかかる分、味の安定感が求められます。番組で紹介されたように、春すいかはゴールデンウィークの時期からすでにスーパーや道の駅で出回っており、家庭の食卓にも並ぶ定番のフルーツになりつつあります。
このように、春すいかは「夏の果物」という常識をくつがえす存在となっており、熊本県植木町はその中心的な産地として多くの注目を集めています。今後もさらに春すいかの魅力が広がっていくことが期待されています。
家族で育てる信頼の味 久富さん一家の取り組み

熊本市植木町のすいか農家・久富将功さんは、30年以上にわたりすいか作りに携わる熟練のベテラン農家です。今回の番組では、その畑に密着し、家族全員で取り組む春すいかの栽培風景が丁寧に紹介されました。現在は両親と息子さんも加わり、親子三代が力を合わせて約7000玉のすいかを育てているという、まさに地域の誇りとも言える家族です。
春の畑は、まだつるが地を這う前から大切な準備が始まっています。苗の植え付けでは、つるや葉がしっかりと広がるよう、十分なスペースを確保。この間隔を広く取ることで、葉が隣の苗と重ならず、太陽の光をまんべんなく浴びられるようになります。光合成が活発になれば、そのエネルギーは葉からつる、そして実へと届き、甘くみずみずしい果実へと育っていくのです。
実が膨らみ始め、直径が7cmを超えると、久富さんは畑に棒を立てて記録します。棒の色は作業した日によって分けており、いつその実が一定のサイズに達したのかが一目で分かるようになっているのです。これは、正確な収穫時期を把握するための重要な工夫。7cmを超えた日から35日後が最も美味しい収穫タイミングとされており、このルールを守ることで、どの実も安定した品質で出荷されます。
出荷直前の作業にも、久富さん一家のこだわりが光ります。すいかは地面に接している部分が日陰になるため、色ムラができやすいのですが、それを防ぐために、一玉一玉手作業で少しずつ回転させます。地面に接していた部分が日に当たるようにすることで、全体が均一な緑色に仕上がり、美しい見た目になります。この工程は非常に手間がかかりますが、すいかを買ってくれた人に少しでも良いものを届けたいという気持ちから、手を抜くことはありません。
-
畑には約7000玉のすいかが育ち、それぞれが個別に管理されている
-
棒の色分けは、畑作業の記録と品質保持の両面に役立つ重要な工夫
-
収穫の前には色の均一さを保つため、家族全員で重たいすいかを1玉ずつ手で動かす
こうした細やかな管理と家族の協力体制が、「久富さんのすいかはおいしい」と言われる理由です。すいか作りには、土づくり、間引き、水やり、温度調整など、多くの工程がありますが、そのどれもが丁寧で真剣な姿勢で行われていることが、テレビの映像からも伝わってきました。
このように、久富さん一家が大切に守っている伝統と工夫の積み重ねが、春すいかの「信頼の味」につながっているのです。甘さ、食感、見た目すべてにおいて妥協のない栽培が行われているからこそ、消費者からの評価も高く、地元だけでなく全国にその名が知られる存在となっています。
春に育てる理由と厳しい基準
熊本で春すいかの栽培が盛んなのは、真夏の厳しい暑さを避けるためでもあります。気温が高くなりすぎると、すいかは光合成をうまく行えなくなり、糖度が上がりにくくなるばかりか、高温障害で赤黒く変色したり、発酵してしまう恐れもあります。そのため、春の気温が安定している時期が、すいか栽培に最適とされているのです。
さらに、「すいかの里植木」では、出荷されるすいかの品質を守るために独自の厳しい基準が設けられています。
-
大玉すいかの場合、中心部の糖度は11度以上
-
中心部と皮に近い部分の糖度差は2度以内
-
味や食感も実際に人が食べて確認
このように、数値だけでなく実際の味覚でも判断する二重のチェック体制があり、基準をクリアしなければ店頭に並ぶことはできません。生産者にとっては、毎回が真剣勝負であり、自分のすいかが選ばれるかどうかが誇りにもつながるのです。こうした取り組みが、春すいかの信頼と美味しさの裏付けになっています。
すいかを使ったおいしいアレンジ料理

番組の後半では、すいか農家であり野菜ソムリエプロの片山さんが、すいかを使った意外で美味しいアレンジ料理を紹介していました。すいかといえばそのまま食べるものという印象がありますが、料理に使うことで新しい楽しみ方が広がるという提案はとても新鮮でした。
すいかとトマトの冷製パスタの詳しい作り方
暑い日にぴったりな「すいかとトマトの冷製パスタ」は、すいかの甘みとトマトの酸味がバランスよく合わさった、爽やかでさっぱり食べられる一品です。果汁も無駄にせずソースとして活用することで、味に深みと清涼感が加わります。
作り方のポイントは、香りを引き出したガーリックオイルと、冷やして旨みを凝縮させたすいかとトマトを、しっかり水気を取ったパスタにからめることです。
<材料>1人分
-
パスタ麺:60g(細めのスパゲッティがおすすめ)
-
すいかの果肉:50g(赤い部分、タネは除く)
-
トマト:50g(完熟のものを使用)
-
にんにく:2片(香りを引き出すためつぶして使用)
-
オリーブ油:50ml(エクストラバージンがおすすめ)
-
レモン:1/8個(果汁を絞る)
-
塩:小さじ1(下味と仕上げ用に使用)
-
黒こしょう:少々(香りづけに)
-
すいかの果肉(飾り用):20g(食感のアクセントに)
-
生ハム:適量(塩気と旨みをプラス)
-
ハーブ(お好みのもの):少々(バジルやミントなどが合う)
<作り方>
-
フライパンにオリーブ油とつぶしたにんにくを入れて弱火にかける
-
じっくり火を通して香りが立ち、にんにくがきつね色になったら取り出す
-
すいかとトマトは1cm角にカットし、バットなどに並べて塩をふる
-
冷蔵庫で約1時間冷やして、果汁を引き出す(これがソースのベースになる)
-
パスタをたっぷりのお湯でゆでる(表記時間よりやや長めに)
-
ゆで上がったら冷水でしっかり冷やし、ザルにあげる
-
キッチンペーパーなどで水気をしっかり拭き取る(水分が残ると味が薄まるため)
-
パスタにガーリックオイル、冷やしたすいかとトマト、レモン汁を加えて全体を混ぜる
-
塩、黒こしょうで味を調える(ここで全体のバランスを確認)
-
皿に盛りつけ、飾り用のすいか、生ハムを乗せ、お好みのハーブで彩る
-
仕上げにオリーブ油を少し回しかけると風味が引き立つ
-
冷やした器に盛ると、最後までひんやり感が続く
-
生ハムの塩気がすいかの甘みを引き立て、全体の味にメリハリが出る
見た目も鮮やかで、前菜にも主食にもぴったりな夏限定の爽やかパスタです。時間をかけずに作れるのに見栄えもよく、おもてなしにもおすすめです。
すいかの皮の牛肉煮の詳しい作り方
すいかを食べたあとの皮の白い部分(中果皮)を無駄なく活用する、家庭にやさしい煮物料理です。シャキッとした食感が残りやすく、味もしっかり染みるため、ごはんのおかずとしても、お酒のつまみとしても活躍します。
<材料>1人分
-
すいかの皮:250g(緑色の外皮は取り除き、白い部分だけを使用)
-
牛こま切れ肉:60g(火の通りが早く、味がよくなじむ)
-
しいたけ:40g(旨みと風味をプラス)
-
にんじん:40g(彩りと甘みを加える)
-
だし汁:150ml(昆布とかつおの和風だしが最適)
-
酒:大さじ1(臭み消しと風味付け)
-
砂糖:大さじ1(甘辛い煮物の基本)
-
濃口しょうゆ(九州しょうゆ):大さじ1+1/4(甘みのある九州タイプが相性抜群)
-
みりん:大さじ1+1/2(コクと照りを出す)
-
サラダ油:大さじ1/2(炒め用)
<作り方>
-
すいかの皮は、緑の固い表皮をむいて白い部分のみを使用
-
白い部分を5mm幅に細長くカットして、火の通りをよくする
-
しいたけは薄切りにして香りと旨みを引き出す
-
にんじんはいちょう切りにして食べやすく、煮崩れしにくい形に整える
-
鍋にサラダ油を熱し、すいかの皮・しいたけ・にんじんを中火で軽く炒める
-
全体がしんなりしてきたら、酒・だし汁・砂糖・牛肉を加える
-
牛肉を加えるタイミングで鍋の温度を下げすぎないように注意する
-
煮立ったら丁寧にあくを取り除く(仕上がりがすっきりする)
-
ふたをして中火で5分煮る(具材にだしがしみる時間)
-
次に、濃口しょうゆとみりんを加え、落とし蓋をして弱火に
-
そのまま10分間じっくり煮込むことで、すいかの皮にも味が染み込みやすくなる
-
最後に火を止めてそのまま10分ほど蒸らすと、味が全体になじむ
-
すいかの皮は煮ても煮崩れず、ほんのり甘くて食べ応えがある
-
九州しょうゆのやさしい甘みが牛肉とよく合い、全体の味に深みが出る
-
しいたけの旨み、にんじんの甘みがバランスを整え、箸が止まらない味わいに
冷めてもおいしく、お弁当のおかずにもおすすめ。夏のすいかを最後まで楽しめる、知恵と工夫のつまった一皿です。
春すいかが教えてくれる新しい旬のかたち
今回の『うまいッ!』では、春すいかの美味しさの秘密や、生産者の努力、そして意外なアレンジ料理までを通して、すいかに対する新しい見方を教えてくれました。
春すいかは、単なる早採りではありません。気候や地形、技術、そして何より人の手によって育まれた特別な味わいです。自然のリズムと丁寧な作業が一体となって生み出される甘さは、夏とはひと味違った感動を与えてくれます。
これからの季節、スーパーや道の駅で春すいかを見かけたら、ぜひ一度手に取ってみてください。初夏の風物詩として、心に残る一品になること間違いなしです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

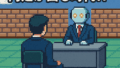
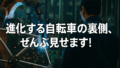
コメント