AI面接で内定!?“志望動機も自動生成”驚きの就活最前線
2025年5月24日放送の『所さん!事件ですよ』(NHK総合)では、「就活の最新事情」をテーマに、AIを活用した面接や“ゲームの腕前”を評価される採用方法、さらには応募すれば即内定という驚きの企業まで、現代の就職活動がどれほど変化しているのかを深掘りしました。AIが面接官になる時代、志望動機も自動生成、SNSで内定を勝ち取る方法まで登場するなど、就活の常識が大きく揺らいでいます。
AI面接の実態と導入企業の狙い

番組の冒頭では、「面接官ガチャ」という言葉が紹介されました。これは、就職活動で誰が面接官になるかによって評価が大きく変わることを指します。人によって質問内容や評価基準が異なるため、公平性に欠けるという課題があるのです。こうした課題を解決する方法として注目されているのが「AI面接」です。
今回は、お笑い芸人でありながら企業での勤務経験もあるぐんぴぃさんがAI面接を体験。受験先は、従業員1898人、総資産5兆8000億円の地方銀行。この銀行では、エントリーシートの提出を廃止し、代わりにAI面接を受ける方式を導入しています。
AI面接では、以下のような特徴がありました。
-
質問形式はSTAR法(状況・課題・行動・結果)に基づく
-
質問数は全部で12問
-
所要時間は約30分
-
面接後15分でAIによる評価レポートが送信される
-
10項目を10点満点で数値化(例:バイタリティ、イニシアチブ、感受性など)
ぐんぴぃさんの評価では、「感受性」が最も高く評価されました。しかし、「対人影響力」が弱いとされ、AIの評価結果は不合格という判断でした。このAI面接では、受験者の発言内容が自動で文字起こしされ、話の中での「状況」「課題」「行動」「結果」に色分けされて記録されます。企業はそれをもとに、より客観的な人物理解を進めることができるようになっているのです。
この銀行の担当者によると、「従来のエントリーシートよりも人物の本質に迫れる」との実感があり、導入後の手応えも大きいようです。受験者が記載する情報と、実際に語る内容に整合性があるかどうかを確かめる意味でもAIは有効だとされています。
また、同様のAI面接は芸能プロダクションにも広がっています。大手芸能事務所では、書類選考の後、オンライン面接を経て、最終のAI面接だけで採否を決定する体制がとられています。
去年この方式で入社した菊地さんは、AI面接に約2時間かかったものの、その中で以下の資質を高く評価されました。
-
バイタリティ
-
イニシアチブ
-
感受性
-
ストレス耐性
AIは、彼女の発言の一貫性や深掘りに対する反応などから総合的に評価を行い、人間の評価ともほぼ一致する結果だったといいます。入社後の菊地さんは、人気タレントのイベント企画や打ち合わせにも関わる存在となり、名マネージャーを目指して奮闘中です。
このように、AI面接はもはやサブ的な役割ではなく、採用の中核を担う存在になりつつあります。評価基準が明確で、情報処理も迅速、かつ受験者の特性を数値で可視化できることが、多くの企業での導入を後押ししています。今後、さらに多様な業界でAI面接が広がっていくことが予想されます。
AIで就活対策!志望動機も自動生成
番組では、就活におけるAI活用の広がりについても詳しく紹介されました。中でも注目されたのが、「AIによる志望動機や自己PRの自動生成サービス」です。
このサービスは、学生が自身の情報を入力するだけで、短時間で完成度の高い応募文を作成できるというものです。入力項目は以下のようなものです。
-
志望する業界や職種
-
学生時代に力を入れた活動内容や経験
-
企業に対する思いや関心のあるキーワード
これらを入力すると、AIがわずか数秒で、自然な言い回しの志望動機文や自己PR文を自動で生成します。文体も丁寧で、一見人間が書いたような文章に仕上がるため、就活生の文章作成にかかる負担を大幅に軽減してくれるのが特徴です。
さらに、次のような活用メリットが番組で紹介されていました。
-
複数企業へのエントリーに対応できる時間短縮
-
書類作成が苦手な学生でも質の高い応募文が用意できる
-
他の学生との差別化に悩むときのヒントや参考になる
番組によると、就活中の学生の約4割がすでにこうしたAIツールを活用しているというデータも紹介されており、就活生の間で急速に浸透していることがわかります。
ただし、AIが自動生成した文章をそのまま提出するのではなく、自分の言葉で修正・補足しながら本音と熱意を込めて仕上げることが大切だという点も示されました。企業側も、AIによって“うまく整った文章”が増えていることを認識しており、本当にその人が書いたのか、内容に矛盾はないかを見極める視点で書類をチェックしているのです。
このように、AIは就活における“下書き作成”の心強い味方となりつつあります。テクノロジーを活用しながらも、自分自身の本質や強みをどう表現するかが、今後ますます重要になっていくといえるでしょう。
ゲーム履歴書で内定!?鎌倉の広告会社の挑戦
神奈川県鎌倉市に本社を構える従業員612人、年商167億円の広告会社が導入しているのは、これまでにない斬新な採用方法——「ゲーム履歴書選考」です。これは、ゲーム経験を通じた個人の思考力や表現力を評価する制度で、就職活動の常識を覆す取り組みとして注目されています。
応募者は、以下のようなゲームに特化した質問に答える形式です。
-
「やり込んだゲームで、どのような工夫をしたか」
-
「自分の好きなゲームの面白さを、相手に伝えるとしたら?」
どちらも、単に好きなだけではなく、そのゲームの魅力を言葉にして伝える力や、どれだけ深く没頭し、戦略的に考えてプレイしたかを問う内容です。選択制で2問に答える形式のため、得意な角度から自分をアピールすることができます。
去年この制度で採用されたのが古川さん。彼は、ある一つのゲームを4000時間以上プレイした経験を持ち、その熱量と、体験を言語化する能力が評価されました。評価されたのは単なるプレイ時間の長さだけでなく、以下のような点でした。
-
長時間のプレイから得た戦略的思考や課題解決力
-
ゲームを通して得た協調性や対話スキル
-
その魅力を言葉で論理的に伝えるプレゼン能力
彼は入社後、スマートフォン向けゲームの開発に携わり、これまでに20作品以上をリリース。その中には、150万ダウンロードを記録したヒット作も生まれました。この成果は、趣味としてのゲームを仕事に昇華させた成功例として紹介されました。
また、この会社では採用方法にも柔軟性があります。SNSで「内定が欲しい」と企業に向けて投稿すると、反響次第で書類選考を免除するという驚きの制度も存在します。実際にその制度を活用して採用された人もおり、SNSの影響力を活かした現代的なアプローチがなされています。
-
投稿に多くの「いいね」や「シェア」がつけば、企業側が直接反応
-
面白いアピール方法であれば、書類選考を飛ばして選考に進むことが可能
-
発信力や創造性を、実際の就職評価に反映する体制が整っている
このような取り組みは、従来の学歴や資格では測れない人材の可能性を発掘するための新しい仕組みとして、業界内外で注目されています。自分らしい方法で自己表現を行い、それが企業に伝わる社会へと、就職活動のあり方が大きく変わろうとしていることが感じられます。
応募すれば即採用!?驚きの企業の実態
番組で紹介されたのは、東京都新宿区の高層ビルにオフィスを構える従業員128人・年商39億円の企業。ここでは、これまでの常識を覆すような「即採用制度」が導入されています。書類選考も面接も一切不要で、ホームページ上で入社希望日と電話番号を入力するだけで採用が決定するという仕組みです。
この制度が生まれた背景には、人手不足への切実な課題がありました。社長は15年前に大手不動産会社から独立し、当初はわずか11人の社員と共に事業を開始。業績は順調に伸びたものの、従来の方法で採用を募っても応募がほとんどなかったため、「いっそ全員採用してみよう」と思いついたのがこの制度でした。
実際にこの制度を利用して入社したのが、東京大学を卒業した永嶋宗さんです。彼は就職活動の中で10社以上の面接に連続で落ち続けた経験があり、「自分が世界に必要とされていないような気持ち」になっていたと語っています。そんなときに偶然見つけたのがこの企業の“即採用”制度。迷いながらも応募ボタンを押し、入社を決意しました。
-
永嶋さんのように精神的な負担を感じていた就活生にとって、面接不要の採用は大きな救い
-
応募から採用までのスピード感が、安心感と自信につながった
-
入社後は社長からの期待を背負い、実務でも高い成果をあげている
また、同じくこの制度を活用して入社した女性社員も紹介されました。彼女は、形式的な面接を繰り返すことが苦手で、自分の本質が伝わらないというストレスを感じていたそうです。そのため、この即採用制度は非常に魅力的だったとのこと。入社後は社内で実力を発揮し、現在では採用や人事部門を担当する立場にまで成長しています。
この企業の取り組みが示すのは、「適性ややる気は、面接では測れない場合もある」という視点です。形式的な選考プロセスを省略することで、潜在的な能力を持つ人材がチャンスを得られる仕組みが整いつつあるのです。
-
入社のハードルを下げることで、より多様な人材の採用が可能
-
実際の業務の中で評価し、成長を促す“現場主義”の人材育成方針
-
就活で挫折感を抱えていた人々に、再スタートの機会を与える社会的意義
このように、「応募=採用」というシンプルな制度の背景には、企業の柔軟な考え方と、既存の就活文化に対する問いかけがあります。今後、このような取り組みがさらに広がることで、就職活動における新たな価値観が定着していくかもしれません。
就活が大学1年から始まる時代に

番組では、就職活動の低年次化が進んでいる実態にも焦点が当てられました。かつては大学3年の終わりから動き始めるのが一般的だった就活も、今では大学1年生のうちから準備を始める学生が珍しくなくなっているのです。
実際、就活解禁となる3月時点で、すでに58.7%の学生が内定を得ているというデータが紹介されました。つまり、多くの学生が大学3年の前半までに就職活動を終える流れとなっており、スタートラインそのものが大きく前倒しされていることがわかります。
番組では、早稲田大学のキャリア研究会の活動も取材されました。ここでは、就活に備えて以下のような取り組みが行われています。
-
グループディスカッションの練習を定期的に実施
-
ケーススタディ形式の模擬面接
-
業界研究や企業分析の共有会
-
内定者による体験談の発表など
こうした活動の成果として、外資系コンサルティングファーム3社から内定を得た学生も登場。大学に入学して間もない時期から計画的に準備を進めたことが成功のカギとなったとされています。
さらに、就活におけるSNSの活用も進化しています。番組では、名前や顔写真を公開せず、匿名で同じ業界を目指す仲間とつながる手法が紹介されました。学生たちは以下のような工夫をしながら情報を共有していました。
-
企業名を絵文字や略語で隠すなどして情報の漏洩を防ぐ
-
SNSのDMやグループチャットで面接練習の壁打ち(模擬応答)を行う
-
志望動機や質問内容の共有テンプレートを作成して活用
このように、表に出にくいが濃密な就活情報がSNS上に集まり、参加者同士で戦略的な対策を練るコミュニティが形成されています。顔を出さずに参加できるため、心理的なハードルも低く、情報の非対称性を解消する場として機能しているのが特徴です。
こうした傾向は、「正解のある就活」を求める学生の思考にも表れています。番組に登場したマライ・メントライン氏は、“検索すれば答えが出る”という感覚を学生が持っていることが特徴的だと述べており、AIやSNSの普及がもたらす情報依存型の行動様式が、就活にも色濃く影響を与えていることが明らかになりました。
いまや就活は、限られた時期に集中して行う活動ではなく、大学入学直後から意識すべき“長期戦略”へと変化しています。時代の変化に合わせ、学生の姿勢や手段もより戦略的・効率的になっているといえるでしょう。
終わりに
今回の放送では、「AIで面接」「ゲームで評価」「SNSでアピール」「即採用ボタン」など、就職活動が劇的に変化している現状が多角的に紹介されました。従来の形式的な面接や書類選考では測れなかった個人の魅力やスキルを評価するために、企業側も柔軟な採用戦略を取り入れていることがよく分かります。
今後さらに技術が進化すれば、就活のスタイルはますます個人最適化され、「正解のない時代」の就活にどう向き合うかが問われていくことでしょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

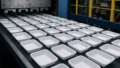
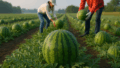
コメント