北極圏で太ったホッキョクグマが見られる理由とは?
「ダーウィンが来た!」2025年8月24日放送回では、北極圏で太ったホッキョクグマが目撃されるという不思議な現象に迫りました。本来なら夏は氷が溶けて狩りができず、絶食状態になるはずのホッキョクグマ。なのに近年、カナダ・バフィン島では太った姿が報告されています。この記事では、その背景にある動物たちの関係や気候変動の影響、そして番組内で紹介されたシマフクロウの保護活動まで詳しく紹介します。
夏は絶食のはずのホッキョクグマに何が起きたのか
ホッキョクグマの暮らしは海氷に大きく左右されます。秋から春にかけては氷の上でアザラシを狩り、たっぷりの脂肪をたくわえながら過ごします。しかし5月を過ぎると氷が解けはじめ、やがて海が広く開けてしまいます。すると狩りの舞台を失ったホッキョクグマは陸地に移動し、夏の間は食べ物をほとんど得られない「絶食の季節」を迎えます。長い時には3か月以上、脂肪を消費して耐えるしかないのです。ところが近年、カナダの北極圏では夏になっても太ったままのホッキョクグマが次々に報告されています。これは本来の生態から考えると非常に珍しく、研究者たちにとって大きな謎となっています。
バフィン島に集まる生き物たちと変わる環境
取材が行われたのはカナダ・バフィン島のアドミラルティインレット。この場所は夏になると多くの生き物が集まる特別な環境です。番組では、氷が減ってもなお食物連鎖の複雑な関係が働いていることが示されました。特に注目されたのが、近年数を増やしているシャチの存在です。シャチは海の頂点捕食者として強大な力を持ち、その影響は他の動物たちの行動にまで及びます。
シャチが増え、イッカクの行動が変化
これまでバフィン島周辺ではあまり見られなかったシャチが、温暖化による氷の減少とともに進出してきました。シャチは獲物を求めて浅瀬までやってきます。すると、普段は深海で暮らしているイッカクが、シャチを避けるために浅い海域に追いやられるのです。結果として、ホッキョクグマが岸近くでイッカクを捕らえるチャンスが生まれました。これはまさに、気候変動が生態系の関係性を変化させた一例といえます。
セイウチやホッキョククジラの存在も
さらに夏のバフィン島にはセイウチやホッキョククジラといった大型の海獣も現れます。これらの動物が同じ場所に集まることで、ホッキョクグマの餌となる機会が従来よりも増えている可能性があります。陸で植物や小動物を少し食べて飢えをしのいでいた従来の夏とは違い、今の北極圏では大きな海獣が「夏のごちそう」となり得るのです。太ったホッキョクグマの存在は、その証拠の一つといえるでしょう。
気候変動が生む矛盾と新しい現実
この現象は一見するとホッキョクグマに有利な変化のように思えますが、必ずしもそうではありません。氷が減ることでアザラシを狩る期間は短くなり、種全体にとっては厳しい状況が続きます。その一方で、新たな獲物との出会いが夏の栄養源となることもある。つまり「太ったホッキョクグマ」は、気候変動が引き起こす複雑で矛盾した影響の象徴でもあるのです。長期的には生態系のバランスが崩れる危険性があり、この先どうなるのかは誰にも予測できません。
ダーウィンNEWS:シマフクロウの保護活動
番組後半の「ダーウィンNEWS」では、舞台を日本に移し、シマフクロウの現状が紹介されました。シマフクロウは北海道に生息する世界最大級のフクロウで、翼を広げると180センチにもなる迫力ある鳥です。しかし開発による生息地の減少や乱獲で数が激減し、一時は国内で100羽以下にまで減少しました。現在は国をあげた保護が進み、北海学園大学をはじめとする研究者や地元団体の努力によって、生息環境の整備や給餌活動が続けられています。その結果、シマフクロウが暮らせる森や川が少しずつ広がり、個体数も回復の兆しを見せています。番組では、地道な努力が絶滅危惧種を救う大きな力になっていることが伝えられました。
まとめ:ホッキョクグマの未来を考える
今回の「ダーウィンが来た!」は、北極圏の生態系における驚きの変化を紹介しました。太ったホッキョクグマという現象は、シャチの増加、イッカクの行動の変化、さらにはセイウチやホッキョククジラの存在など、複数の要因が重なって生まれた結果でした。一方で、気候変動がもたらす影響は決して単純ではなく、今後の北極圏の自然や動物たちに大きな課題を投げかけています。そして日本のシマフクロウの保護活動は、私たち人間が自然とどう向き合うかを考えさせるものでした。ホッキョクグマの未来を守ることは、地球全体の環境を守ることにつながります。番組を通して、身近な暮らしの中でも自然を大切にする意識を持つことが大切だと改めて感じさせられました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

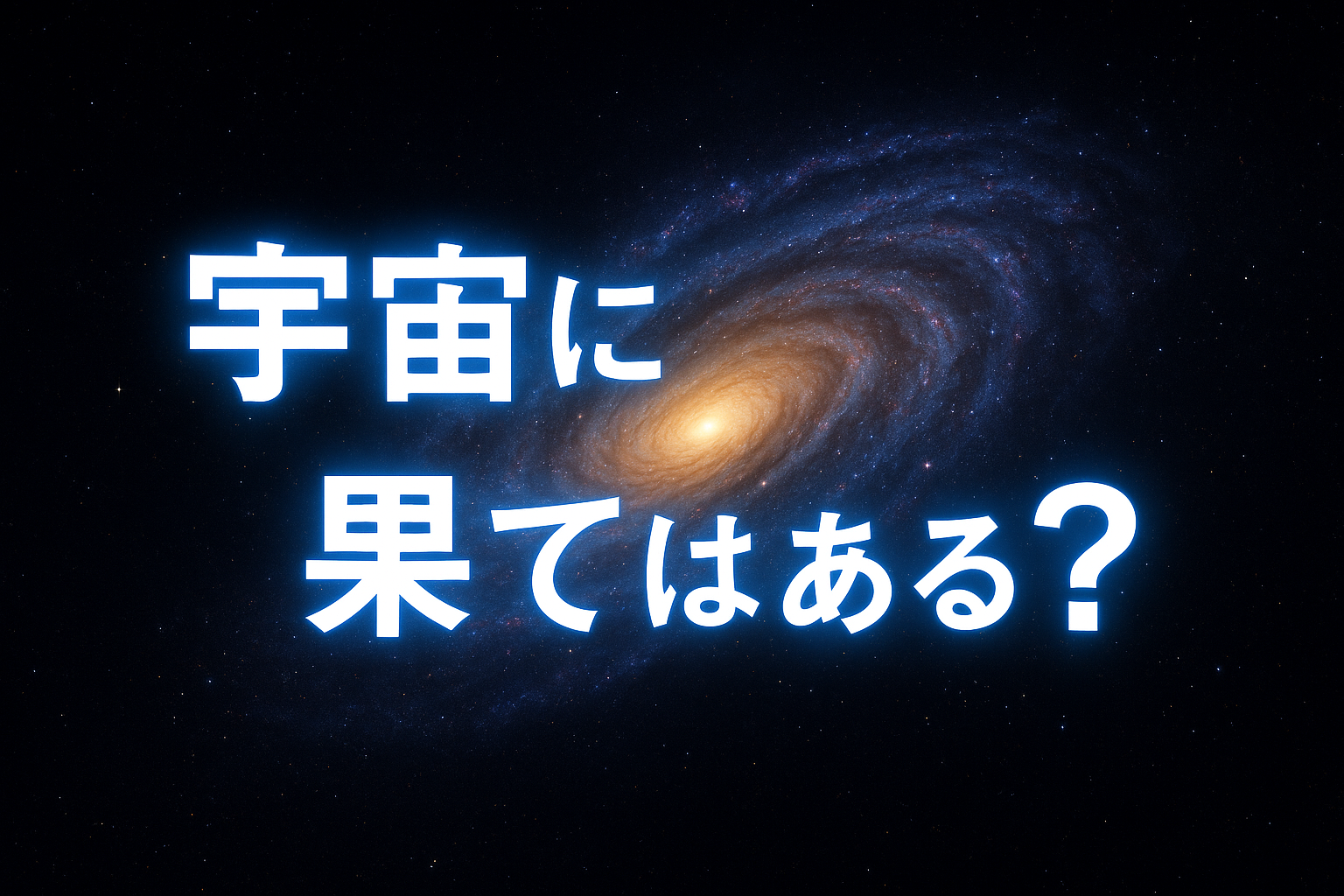

コメント