海を泳ぐネコ!?ツシマヤマネコの驚きの暮らし
「ネコは水が嫌い」というイメージを持つ人は多いでしょう。しかし、日本にしか生息しないツシマヤマネコは、その常識をくつがえす特別な存在です。彼らはなんと海や川を泳ぎ、時には大きな鳥をも狙うハンター。現在は野生で約100匹しかいないとされ、まさに絶滅寸前の動物です。2025年9月28日放送の『ダーウィンが来た!』では、その貴重な映像と最新研究を通して、ツシマヤマネコの生き抜く知恵と自然環境の大切さが紹介されました。この記事では、番組で明らかになった全エピソードを詳しく振り返り、その驚きの生態に迫ります。
幻の存在だったツシマヤマネコ

ツシマヤマネコが暮らすのは、九州最北端に位置する対馬。海に囲まれ、険しい山と深い森が広がる島は、野生動物にとって豊かな環境です。けれども警戒心の強いツシマヤマネコは、長年「幻」と呼ばれてきました。2010年に撮影が始まった当初、姿をとらえることすら難しかったといいます。
研究者たちは田んぼのU字溝や三差路など、動物がよく通る場所にカメラを10台以上設置。すると、ネコ科としては珍しい光景が映し出されました。ツシマヤマネコは水路を平気で歩き、時には泳いで移動していたのです。これは『ベンガルヤマネコ』の仲間であることに由来します。ベンガルヤマネコはアジアの湿地に広く生息し、水辺での狩りを得意とする種。ツシマヤマネコにもその特徴が受け継がれていたのです。
下島に渡った?新たな発見
対馬は大きく上島と下島に分かれています。森の伐採や開発が進んだ下島では、ツシマヤマネコはすでに絶滅したと考えられてきました。ところが近年、下島での目撃情報が相次いでいます。研究者は、彼らが海を泳いで渡った可能性を指摘。海を越えるというダイナミックな行動は、彼らの生き抜く力を物語っています。
撮影技術と保護活動の進化
15年前、ツシマヤマネコの知名度は低く、保護活動も十分ではありませんでした。しかし番組の放送をきっかけに関心が高まり、保護の取り組みが加速しました。現在は環境省 野生順化ステーションや佐護ヤマネコ稲作研究会などが地域と連携して活動しています。
撮影機材も大きく進化しました。かつては部品が多く設置に手間がかかったカメラも、今では小型で高性能。動くものに反応して自動で録画し、ツシマヤマネコの自然な姿を映し出せます。さらにライバルであるツシマテンとの関係も映像で確認され、島の生態系の複雑さが浮かび上がりました。
水辺で繰り広げられる狩りの作戦
今回の撮影で最も注目されたのは、ツシマヤマネコの狩りの様子です。彼らは昼間でも水辺に現れ、時には自分より大きなサギに襲いかかります。森と田んぼを行き来しながら暮らしていますが、最近は水辺に依存する度合いが増しています。その背景にはシカの増加による森の荒廃があり、主食のネズミが減少したためです。
冬になると田んぼの稲が刈られ、生き物の姿は激減。そんな中、ツシマヤマネコはカモを狙いました。警戒心の強いカモに先回りし、奇襲を試みるも、あと一歩で気づかれて失敗。しかしその後、小鳥に20cmという短距離から飛びかかり、見事に捕らえる姿が映し出されました。これは冬の狩りを克明に記録した初の映像であり、ツシマヤマネコの驚異的な身体能力を示すものでした。
ツシマヤマネコが示す自然とのつながり
ツシマヤマネコの行動から見えてくるのは、生態系の変化と動物の適応力です。森が荒れれば餌が減り、新たに水辺に活路を見出す。こうした柔軟な対応力は称賛に値しますが、同時に人間の活動が彼らの生活を大きく左右している現実を突きつけます。保護活動が続く一方で、私たち自身が自然環境にどう向き合うかが問われています。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
-
ツシマヤマネコは水を恐れず、泳ぎも得意とする特別なネコ科動物
-
下島での目撃例から、海を渡った可能性が注目されている
-
最新のカメラ映像で、冬の狩りやライバルとの関係が初めて明らかになった
ツシマヤマネコは、私たちに自然の奥深さと命のつながりを教えてくれます。わずか100匹前後という危機的な状況だからこそ、彼らの存在を知り、守る意識を広げていくことが大切です。未来の世代にも、この「日本の宝」を残せるよう、環境を守る一歩を私たち一人ひとりが踏み出す必要があります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

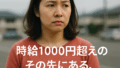
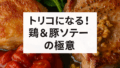
コメント