あなたに合う治療はどれ?更年期の薬えらび最新ガイド
40代〜50代を迎えるころ、体と心の調子がなんとなく違うと感じたことはありませんか?
「暑くもないのに汗が止まらない」「夜眠れない」「イライラする」「肩がこる」「気持ちが落ち込む」——そんな症状の裏には、更年期に起こるホルモンの変化が関係していることがあります。
この時期に起こる『更年期障害』は、人によって出方も強さも違います。そのため、治療薬の選び方がとても重要。
同じ“更年期”でも、合う薬が違うのです。
この記事では、2025年11月11日放送予定のNHK「きょうの健康」更年期障害 治療&対策ガイド『ホルモン補充療法(HRT)ほか』の内容を参考に、治療薬の選び方や最新研究のポイントをわかりやすくまとめました。
Eテレ【きょうの健康】更年期障害 治療&対策ガイド「あなたの症」状タイプは?」更年期タイプ別診断×SMIスコアで見直す治療継続の秘訣|2025年11月10日
症状タイプに合わせた薬の選び方
まず大切なのは、「自分の症状がどんなタイプか」を知ることです。
たとえば——
・顔のほてりや発汗がつらい人は、ホルモン補充療法(HRT)が有効なケースが多いです。
・肩こりや冷え、腰痛などが中心の人には、漢方薬が合う場合もあります。
・気分の落ち込みや不眠が強い人は、抗うつ薬や自律神経調整薬が組み合わされることもあります。
症状が複数にわたるときは、薬を組み合わせて使うこともあります。
つまり、更年期治療は“一択”ではなく、“オーダーメイド”の時代なのです。
ホルモン補充療法(HRT)とは?
HRTは、女性ホルモン(エストロゲン)と必要に応じて黄体ホルモン(プロゲステロン)を補う治療法です。
閉経前後にホルモンが急激に減ることで起こる体調の変化——たとえば「ホットフラッシュ」「夜の発汗」「膣の乾燥」「骨粗鬆症予防」など——に効果があります。
【選び方のポイント】
・子宮がある方は、エストロゲン単独ではなく、黄体ホルモンを併用するのが一般的(子宮体がんのリスクを防ぐため)
・閉経から10年以内、60歳未満で始めると、メリットがリスクを上回るとされています
・経口薬・貼り薬・塗り薬・膣内薬など、ライフスタイルに合わせて選べる
・血栓症や乳がん既往歴がある場合は、使用を慎重に検討
この治療は、正しく使えば大きな効果が期待できますが、自己判断は禁物です。必ず医師の指導のもとで行いましょう。
漢方薬という選択肢
HRTに抵抗がある人や、体質的に合わない人には漢方薬も有効な選択肢です。
体全体のバランスを整えることで、ホルモンや自律神経の乱れをやわらげます。
代表的な漢方には——
・加味逍遙散(かみしょうようさん):イライラ・不安・不眠に
・桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん):のぼせ・肩こり・血行不良に
・当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):冷え・貧血・疲れに
副作用は比較的穏やかで、長く続けやすいのも特徴です。ただし、自己流ではなく専門家の診断が必要。
「気」「血」「水」のどこに乱れがあるのかを見極めるのが成功のカギです。
治療を続けるコツ
治療を途中でやめてしまう人は少なくありません。
理由として多いのは、
・「効果を感じない」
・「副作用が不安」
・「通院が大変」
などです。
大切なのは、「なぜこの薬を使うのか」「どんな変化を目標にしているのか」を自分でも理解しておくこと。
医師と二人三脚で進めることで、治療を継続しやすくなります。
また、薬だけに頼らず、運動・食事・睡眠・ストレス対策を整えることで、より効果的な改善が期待できます。
副作用と注意点
どんな薬にも副作用があります。HRTでは、
・頭痛
・胸の張りや痛み
・吐き気
・むくみ
・出血・不正出血
といった症状が出ることがありますが、多くは一時的です。
重い副作用としては、血栓症・脳卒中・乳がんなどが報告されています。
特に閉経から時間が経過している人や基礎疾患がある人は、医師とよく相談して判断しましょう。
一方、漢方薬でも胃の不快感や下痢などが出ることがあります。服用中の薬がある場合は、必ず薬剤師や医師に相談を。
最新研究:ホットフラッシュのしくみ
更年期の代表的な症状「ホットフラッシュ」は、体温の乱れではなく、脳の温度センサーの異常反応によって起こることがわかってきました。
女性ホルモンの減少が視床下部に影響し、「体温が上がった」と勘違いして血管を広げ、汗をかくという現象です。
さらに最新の研究では、Kiss1神経回路やNK3受容体と呼ばれる神経伝達の働きが関係していることも分かっています。
この研究は新しい治療薬の開発にもつながり、「ホットフラッシュを根本から抑える」治療の可能性が広がっています。
まとめ
この記事のポイントは3つです。
-
更年期の治療薬は「症状タイプ」に合わせて選ぶことが大切。
-
HRT・漢方・併用療法など、自分に合った方法を医師と相談して選ぶ。
-
最新研究では、ホットフラッシュの原因解明が進み、新しい治療法にも期待が高まっている。
更年期は、体と心のリズムを見直すチャンスでもあります。
焦らず、自分の体と向き合いながら、最適な治療法を見つけていきましょう。
最後に、番組の内容と異なる場合があります。
症状タイプに合わせた薬の選び方
まず最初に理解しておきたいのは、「人によって症状のタイプが異なる」ということです。
例えば——
・顔がほてり、汗が止まらない「血管運動神経型」
・イライラ、不眠、気分の落ち込みが中心の「精神神経型」
・肩こりや冷え、腰痛、関節痛などが目立つ「運動器型」
このようにタイプによって、必要な治療法も変わります。医師の診察では、問診や「SMIスコア(簡略更年期指数)」などの質問票をもとに、どのタイプが強いかを見極めて治療を組み立てていきます。
多くの場合、HRT(ホルモン補充療法)・漢方薬・自律神経系の薬などを単独または組み合わせて使うのが一般的です。
ホルモン補充療法(HRT)とは
HRTは、減少した女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)を補い、体のバランスを整える治療法です。
ほてり・発汗・のぼせなどの血管運動神経症状をはじめ、骨粗鬆症の予防、膣の乾燥や性交痛などにも効果があることが科学的に証明されています。
HRTにはいくつかの方法があります。
・経口タイプ(飲み薬):全身に作用しやすいが、肝臓で代謝されやすい
・経皮タイプ(貼り薬・塗り薬):副作用が少なく、血栓リスクが低い
・膣内薬:膣の乾燥や痛みに効果的で、全身にはあまり影響しない
選び方のポイントは、閉経からの年数・年齢・既往歴を踏まえて医師が判断すること。
特に「閉経から10年以内」または「60歳未満」で始めると、効果が高く副作用のリスクも比較的低いとされています。
また、子宮がある人はエストロゲン単独ではなくプロゲステロンを併用するのが原則。これは、子宮内膜が過剰に増殖し、がん化するリスクを避けるためです。
HRTの効果は数週間〜数か月で現れますが、長期間続けるほど安定した効果が得られるため、医師と相談しながら定期的に見直すことが大切です。
漢方薬というもうひとつの道
HRTが合わない、または副作用が心配な人には、漢方薬も選択肢のひとつです。
漢方の特徴は、体全体のバランスを整える「根本治療」。体質や気候、生活リズムの乱れに合わせて調整できるのが魅力です。
代表的な処方として、
・加味逍遙散(かみしょうようさん):イライラ・不眠・気分の浮き沈みがある人に
・桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん):血流の滞りによる肩こり・冷え・のぼせに
・当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):冷え・貧血・むくみ・疲れやすい体質に
このほかにも、体力のある人・ない人、のぼせ型・冷え型などによって細かく調整されます。
医師や薬剤師が体質を見て選ぶため、自己判断での服用は避けましょう。
漢方の良さは、副作用が比較的穏やかで長期的に使えること。
ただし即効性はないため、数週間〜1か月ほどかけて体調の変化を観察するのが一般的です。
治療を継続するためのコツ
更年期の治療では、3〜4割の人が途中で治療をやめてしまうと言われています。
理由として多いのは、
・思ったより効果を感じない
・副作用が怖い
・通院が負担
・「もう年だから仕方ない」とあきらめてしまう
しかし、治療をやめてしまうと症状がぶり返したり、骨粗鬆症や心疾患のリスクが高まることもあります。
大切なのは、「自分の症状を正しく知り、納得して治療を続けること」。
医師に「どの症状を優先して改善したいか」「いつごろ効果を感じるのか」「副作用が出たらどうすればいいか」を遠慮なく相談しましょう。
さらに、薬だけでなく運動・睡眠・食事・ストレス対策といった生活改善も並行して行うと、治療効果が高まります。
副作用と注意点
HRTの主な副作用には、頭痛・胸の張り・吐き気・むくみ・不正出血などがあります。
多くは一時的で、投与法や量を変えることで改善できます。
ただし、血栓症・脳卒中・乳がん・子宮体がんなど、重い副作用が出ることもまれにあるため、定期的な検診(血液検査・乳腺・子宮超音波など)が欠かせません。
また、漢方薬でも胃の不調や下痢などの軽い副作用が起こる場合があります。
市販薬やサプリとの併用には注意が必要で、薬剤師に必ず相談しておくと安心です。
「ホットフラッシュ」はなぜ起こる?
更年期の代表的な症状である『ホットフラッシュ(ほてり・発汗)』。
これは単に「暑い」わけではなく、女性ホルモンの低下で脳の体温調整中枢(視床下部)の働きが変化し、体がちょっとした温度変化にも過敏に反応してしまうことが原因です。
最近の研究では、Kiss1神経回路やNK3受容体という神経伝達の経路が関係していることがわかってきました。
これにより、血管拡張や発汗を引き起こす信号が過剰に出てしまうのです。
さらに、大豆イソフラボンやポリフェノールなどの成分がこの経路に作用する可能性があり、栄養学的なアプローチも注目されています。
HRTが最も効果的な治療法とされていますが、近年は非ホルモン療法(抗うつ薬・神経調整薬・ライフスタイル改善など)も研究が進んでいます。
まとめ
この記事のポイントは次の3つです。
-
更年期の治療薬は「症状タイプ」に合わせて選ぶのが基本。
-
HRT・漢方・非ホルモン療法など、組み合わせることで効果が高まる。
-
最新研究で『ホットフラッシュ』の仕組みが明らかになり、新しい治療の可能性が広がっている。
更年期は、人生の中で誰もが通る自然な変化です。
「年だから仕方ない」とあきらめるのではなく、正しい知識と医師との対話で、自分に合った治療を見つけましょう。
無理せず、安心して次のステージを迎える準備を始めてください。
最後に、番組の内容と異なる場合があります。
参考・出典リンク
・厚生労働省「更年期障害の理解と支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188801.html
・日本産科婦人科学会(JSOG)「ホルモン補充療法(HRT)ガイドライン2023」
https://www.jsog.or.jp/modules/publication/index.php?content_id=9
・Cleveland Clinic「Hormone Therapy for Menopause Symptoms」
https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/15245-hormone-therapy-for-menopause-symptoms
・Mayo Clinic「Menopause hormone therapy: Is it right for you?」
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/menopause/in-depth/hormone-therapy/art-20046372
・NHS(英国国民保健サービス)「Side effects of hormone replacement therapy (HRT)」
https://www.nhs.uk/medicines/hormone-replacement-therapy-hrt/side-effects-of-hormone-replacement-therapy-hrt/
・国立がん研究センター がん情報サービス「ホルモン補充療法と乳がんリスク」
https://ganjoho.jp/public/cancer/breast/patient/hormone.html
・日本女性医学学会(JWOM)「更年期とホルモン補充療法の基礎知識」
https://www.jmwh.jp/general/menopause.html
・Frontiers in Global Women’s Health「Neuroendocrine Mechanisms of Hot Flashes: Kisspeptin and NK3R Pathways」
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgwh.2025.1514960/full
・MDPI Nutrients Journal「Isoflavones and Vasomotor Symptoms: Mechanistic Insights」
https://www.mdpi.com/2072-6643/16/5/655
・日本漢方生薬製剤協会「女性のための漢方ガイド」
https://www.nikkankyo.org/seibun/kampo_woman.html
・PMC(PubMed Central)「Timing Hypothesis in Hormone Therapy: Ten-Year Window of Opportunity」
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8034540/
・日本更年期と加齢のヘルスケア学会「更年期女性の健康マネジメント」
https://www.jmwh.jp/general/index.html
以上の資料をもとに構成しています。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

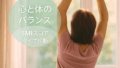
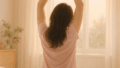
コメント