肩こり・腰痛広告に惑わされないために知っておきたいこと
肩こりや腰痛に悩んで「整体やマッサージに行こうかな…」と考えたことはありませんか?つらい症状をなんとかしたい気持ちは自然なものです。ですが、実は広告の中には誤解を招く表現や、国家資格を持たない人が医療まがいの行為をしているケースもあります。知らずに施術を受けてしまうと、かえって体を痛めてしまうリスクもあるのです。今回紹介された内容は、そんな後悔をしないために、広告の見極め方や施術を受ける際の注意点を整理したものです。あなたの体を守るために、ぜひチェックしてみましょう。
【あさイチ】冷え性対策特集!耳引っ張りマッサージやドライヤー活用術で即効ポカポカ温活|2025年1月21日放送
相次ぐ事故報告と背景
肩こりや腰痛に悩む人が選ぶ手段のひとつに、あん摩マッサージ指圧、整体、カイロプラクティックといった「医業類似行為」があります。器具を使わずに手で施術を行うため身近に感じられ、日常的に利用する人も多い分野です。しかし、その中には国家資格を持たない人が施術を行っているケースが存在し、実際に事故につながる事例も少なくありません。
総務省が2020年11月に公表した報告書によると、平成26年度から29年度までの間に「医業類似行為」に関連する事故件数は1534件にのぼりました。事故の内訳は、神経・脊髄損傷が274件、擦過傷・挫傷・打撲傷が181件、骨折が134件と、軽いけがにとどまらず深刻な健康被害も報告されています。この中で医療機関を受診したケースは626件あり、そのうち251件は治療に1か月以上を要した重症例でした。
背景には、資格制度の有無や施術内容の違いを理解せずに利用する人が多いことが挙げられます。国家資格を持つあん摩マッサージ指圧師やはり師・きゅう師、柔道整復師と、資格が不要な整体やリラクゼーションとの違いを利用者が正しく認識していないと、思わぬトラブルにつながる危険があります。
さらに、厚生労働省の調査では、こうした事故の一部は「広告に誤解を招く表現があったために施術を選んでしまった」ケースもあるとされます。例えば、「治る」「改善する」といった確実性を示す表現や、国家資格がないのに「マッサージ」と称する広告が利用者を惑わせ、結果として事故を招く要因になっているのです。
事故の多くは「肩こりや腰痛を和らげたい」という切実な思いから施術を選んだ人々に起きています。安全に施術を受けるには、国家資格の有無を確認すること、そして不安な場合にはまず医療機関での診断を受けることが重要だといえます。
厚生労働省が示した新しいガイドライン
厚生労働省は、医業類似行為による事故が相次いでいる現状を重く受け止め、2025年2月に『あはき・柔整広告ガイドライン』を公表しました。ここでいう「あはき」とはあん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうを指し、「柔整」とは柔道整復のことを意味します。これらはすべて国家資格が必要であり、専門学校や大学で3年以上の教育を受けたうえで国家試験に合格しなければなりません。さらに施術所を開設する際には、都道府県知事や保健所への届け出が義務づけられています。利用者が安心して施術を受けられるように、制度として厳密に定められているのです。
新しいガイドラインでは、国家資格を持つ施術師は資格を広告してよいと明記され、むしろ利用者が資格の有無を判断できるよう積極的な情報提供が求められました。一方で、「整体」「伝統鍼灸」といった国家資格に基づかない名称を使った広告は不可とされました。これは民間資格や外国の類似資格を、あたかも国家資格のように誤認させる危険があるからです。
さらに、施術所の名前についても細かい規制が設けられています。例えば「治療所」や「メディカル」といった名称は、病院や診療所と誤解させる恐れがあるため禁止されました。同様に、「女性専門」「アスリート専門」など特定の対象を強調する表現や、「姿勢改善」「背骨矯正」など技能や効果を直接示すような名称も使えません。こうしたルールは、利用者が広告のイメージだけで過度な期待を抱かないようにするための重要な仕組みといえます。
このように『あはき・柔整広告ガイドライン』は、利用者が施術を選ぶ際に正しい判断を下せるよう、広告の在り方を明確化したものです。安全に施術を受けるためには、広告の表現を鵜呑みにせず、国家資格の有無を最優先に確認することが大切です。
保険が使える施術と注意点
国家資格を持つ施術師による施術の中には、一定の条件を満たせば健康保険が適用されるケースがあります。これは利用者にとって大きなメリットであり、安心して施術を受けられる重要なポイントとなります。
まず、あん摩マッサージ指圧では、単なる疲労回復やリラクゼーション目的では保険の対象になりません。しかし、筋肉まひや関節の拘縮といった医学的な理由がある場合には、保険が適用されます。このときには必ず医師の同意書が必要で、治療目的であることが前提です。
次に、はり・きゅうの施術です。こちらも慰安目的では対象外ですが、五十肩や神経痛、頸腕症候群、腰痛症など、慢性的で長引く痛みがある場合に限り、医師が必要と認めたときに保険が使えます。西洋医学だけでは改善が難しい慢性疾患に対し、補完的に活用されることが多いのが特徴です。
さらに、柔道整復による施術では、骨折や脱臼の初期対応に加えて、打撲やねんざも対象となります。骨折や脱臼は緊急時のみで、継続治療には医師の同意が必要です。一方で、打撲やねんざは日常生活で起きやすく、合併症や後遺症が残るリスクが比較的低いため、医師の同意がなくても保険の対象として認められています。
こうした保険適用の範囲は、利用者にとって経済的にも安心材料となる情報です。そのため、厚生労働省が定めたルールに従い、広告でもきちんと記載することが認められています。施術を受ける側としても、「どんな症状なら保険が使えるのか」を知っておくことで、治療費の負担を減らしつつ、必要な施術を安心して受けることができます。
補足として、保険を利用する際には、あくまで医師の診断や同意が前提である点が大切です。これにより、利用者は不適切な施術や不正請求から守られ、正しい形で治療を受けられる仕組みが整えられています。
国家資格のない施術と広告の落とし穴
問題となるのは、国家資格を持たない人があたかも専門的な施術を行っているかのように「マッサージ」という言葉を使ってしまうケースです。本来「マッサージ」という言葉は、あん摩マッサージ指圧師という国家資格を持つ人だけが広告や施術で使用できるものです。しかし、資格のない人が安易にこの言葉を使うことで、利用者が「国家資格を持った施術者が対応してくれる」と誤解してしまう危険があります。
また、広告において「腰痛に効く」「ひざ痛を改善」といった病名を直接示す表現も禁止されています。こうした表現は医療行為に近い印象を与え、医業と誤解させる可能性が高いためです。腰痛やひざの痛みの原因には重い病気が隠れている場合もあり、適切な診断を受けずに施術を選んでしまうと健康を損なうリスクにつながります。
さらに、利用者の不安や期待をあおるような広告表現も規制の対象です。たとえば「安い」「すぐ治る」といった即効性や低価格を強調する言葉、あるいは「口コミ1位!」「絶対安全」といった根拠のない誇大な表現は禁止されています。これらは利用者に過度な期待を抱かせ、冷静な判断を妨げてしまうからです。
特にウェブ広告においては、より詳しい情報公開が求められています。施術を受ける際にかかる費用、施術によるリスクや副作用といった情報は、利用者が正しく判断するために必ず記載することが必要とされています。一方で、「絶対に治る」「副作用は一切ない」といった確実性を保証するような表現は、科学的根拠がない限り認められていません。
補足として、近年はインターネットやSNSを通じて広告が広く拡散されやすくなっています。そのため、規制が整えられたことで、利用者が誤った情報に惑わされるリスクを減らし、正しく施術を選べるようにすることが目的とされています。
施術を受けるときに大切なこと
実際に施術を受ける際には、いくつか大切な注意点があります。まず、持病がある人は必ず医師に相談することが重要です。例えば腰痛の原因には、単なる筋肉疲労だけでなく、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、さらにはがんの転移など思いがけない重大な病気が隠れている場合もあります。そのような状態で安易に施術を受けると、症状が悪化してしまう危険があるのです。
施術を受ける前には、自分の体調や希望をきちんと伝えることも欠かせません。どの部位がつらいのか、どのような方法を希望するのかを事前に伝えておくことで、施術者も安全に対応できます。そして、もし施術の最中に「痛みが強すぎる」「違和感がある」と感じた場合は、我慢せずにすぐ中止を申し出て、医師に相談することが大切です。無理に続けてしまうと、思わぬけがや体調不良につながりかねません。
さらに、施術を受けた後に異常を感じた場合には、早めに施術を受けた施設へ連絡し、状況を説明しましょう。それでも不安が残る場合や対応に納得できない場合は、消費生活センターなどの相談窓口を利用する方法もあります。ここでは施術に関するトラブルや費用の問題などについても相談でき、利用者を守る仕組みが整っています。
補足として、特に高齢者や基礎疾患を持つ人は体への負担が大きくなりやすいため、施術を受ける際のリスク管理がより重要となります。安全に施術を受けるためには、施術者任せにせず、自分自身も正しい知識を持って行動することが求められます。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・肩こり・腰痛の施術広告には誤解を招くものがある
・厚生労働省のガイドラインで国家資格の有無や広告ルールが明確化された
・施術を受ける際には、資格の確認と医師への相談が不可欠
正しい情報を見極める力を持つことで、自分の体を守り、安心できる施術を受けることができます。体の不調に悩むときほど冷静に、信頼できる専門家を選びましょう。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

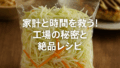

コメント