年のせいじゃないかも?薬の副作用に気づくポイント
「最近、なんとなく体がだるい」「立ち上がるとクラクラする」「夜眠れない」――そんな症状を、つい“年齢のせい”だと思っていませんか?実はそれ、薬の副作用が原因かもしれません。
高齢者は若いころよりも薬の影響を受けやすいといわれています。しかも、症状が出ても「老化」と勘違いして気づかないことが多く、放っておくと転倒や骨折、寝たきりにつながる危険もあります。
今回の記事では、なぜ高齢者に薬の副作用が起きやすいのか、注意すべき薬の種類、そして安全に薬を使うための具体的な工夫まで、専門家の視点から分かりやすく解説します。自分や家族の健康を守るヒントとして、ぜひ最後まで読んでください。
Eテレ【チョイス@病気になったとき】高齢者の不眠症は生活改善で変わる!むずむず脚症候群と最新睡眠薬の選び方(2025年9月14日)
なぜ高齢者は薬の副作用が起きやすいのか
加齢とともに体の中では多くの変化が起きます。薬の効き方は「年齢に関係ない」と思われがちですが、実際には体の“薬を処理する力”が大きく変わっています。
まず大きいのが体内の水分量・筋肉量の減少です。年齢を重ねると、体の中の水分が減り、脂肪の割合が増えます。薬には「水に溶けやすいもの」と「脂に溶けやすいもの」がありますが、水に溶ける薬は体内濃度が高くなり、脂に溶ける薬は逆に体の中に長く残りやすくなるのです。これによって、若い人よりも強く薬が効きすぎてしまうことがあります。
次に、肝臓や腎臓の働きの低下です。薬は体の中で分解され、最終的に尿や便として排出されます。ところが、高齢になるとこれらの臓器の機能が低下し、薬の成分が体の外に出にくくなるため、同じ量を飲んでも体内に薬がたまりやすくなります。その結果、眠気やめまい、便秘、意識の混濁などの副作用が強く出てしまうのです。
さらに見逃せないのが「ポリファーマシー(多剤併用)」の問題です。高齢者は高血圧や糖尿病、関節痛など、いくつもの慢性疾患を同時に抱えることが多く、それぞれに薬が処方されます。その結果、5種類以上の薬を飲んでいる人も珍しくありません。薬が多くなるほど、成分同士の“相互作用”によって効果が強くなったり、逆に効きすぎてしまうリスクが上がります。
例えば、降圧薬と睡眠薬を併用すると立ちくらみが起きやすくなったり、抗うつ薬と痛み止めを一緒に使うと便秘が悪化するケースもあります。
また、脳や神経の働きの回復が遅くなることも、高齢者特有の問題です。眠気やふらつきを感じても若いころのようにすぐに回復できず、転倒や骨折につながる危険性が高まります。こうした理由が重なり、高齢者では“薬が効きすぎる”状態になりやすいのです。
注意したい薬の種類と特徴
薬の中でも特に副作用に注意すべきタイプがあります。以下の薬を服用している場合は、症状の変化に敏感になりましょう。
・睡眠薬・抗不安薬(ベンゾジアゼピン系・Z薬など)
不眠や不安の改善に使われますが、眠気・ふらつき・集中力の低下を招くことがあります。夜中にトイレに行く際に転倒するケースが多く、長期間使用すると記憶力の低下を起こすこともあります。
・抗うつ薬・抗精神病薬・抗てんかん薬
心のバランスを整える薬ですが、脳に作用するため、めまいやぼんやり感、ふらつきなどが起きることがあります。薬の種類や量の調整がとても重要です。
・降圧薬(血圧を下げる薬)
高血圧の治療には欠かせませんが、下がりすぎると「起立性低血圧」を起こし、立ち上がるときにクラッとする危険があります。朝や夜など、飲むタイミングによってリスクが変わることもあります。
・抗コリン作用のある薬(アレルギー薬・尿失禁治療薬など)
“抗コリン作用”とは、神経の働きを抑える効果のこと。便秘・口の渇き・尿が出にくい・認知機能の低下などの副作用が出やすくなります。特に認知症を悪化させるケースもあるため、慎重な使用が求められます。
・鎮痛薬・オピオイド系の痛み止め
がん性疼痛や慢性痛に使われますが、強い眠気や便秘を起こすことがあり、量を調整しながら使う必要があります。
こうした薬を飲んでいる高齢者が「ふらつく」「眠い」「便秘が続く」と感じた場合は、副作用の可能性を考えることが重要です。
年のせいではなく薬の副作用かもしれないサイン
薬の副作用は、病気や老化と見分けがつきにくいのが厄介な点です。次のような変化があったら、薬の影響を疑ってみましょう。
・立ち上がるとクラッとする、めまいが増えた
・転びやすくなった、歩くとふらつく
・便秘やお腹の張りがひどくなった
・夜眠れない、昼間ぼんやりしている
・最近、物忘れが急にひどくなった
・薬を変えた、または新しい薬を飲み始めてから調子が悪い
これらの症状は“加齢”ではなく、“薬が合っていない”サインかもしれません。特に薬を増やした直後に症状が出た場合は、すぐに医師や薬剤師に相談しましょう。
薬を安全に使うための工夫とコツ
-
薬の一覧を作る
今飲んでいる薬をすべてリストにしておきましょう。病院で処方された薬だけでなく、市販薬やサプリメント、漢方も含めるのがポイントです。家族や介護者と共有しておくことで、重複服用や飲み忘れを防げます。 -
定期的に薬を見直す
半年~1年に一度は「この薬はまだ必要ですか?」と医師や薬剤師に確認しましょう。不要になった薬を減らす取り組みは『デプリスクリプション』と呼ばれ、転倒や骨折、認知機能低下を防ぐ効果があると注目されています。 -
飲むタイミングを工夫する
降圧薬を朝から夜に変えることで立ちくらみを防げることもあります。眠気が出る薬は活動時間を避けて服用するなど、生活リズムに合わせて調整するのが大切です。 -
生活習慣も見直す
便秘を防ぐためには、水分と食物繊維をしっかり摂ることが基本です。また、転倒を防ぐために部屋の段差を減らす、手すりをつける、靴底の減りをチェックするなど環境づくりも忘れずに。 -
症状が出たら早めに相談する
「このくらいなら大丈夫」と我慢せず、少しでも体調に変化があれば医師や薬剤師に伝えましょう。薬の種類や量を調整するだけで、体調がぐっと改善するケースもあります。 -
薬の相互作用にも注意
複数の薬を同時に飲むことで、効果が強まりすぎたり、逆に効かなくなったりすることがあります。複数の医療機関を受診している場合は、薬剤情報を一元管理することがとても大切です。
薬を“味方”にするために
薬は、体を治すための大切なパートナーです。しかし、高齢になるとそのパートナーシップのバランスを取り直す必要があります。自分の体の変化を理解し、薬と上手に付き合うことができれば、健康で安心な暮らしを長く続けることができます。
「年のせいだから」と片付けるのではなく、「薬のせいかもしれない」と一度立ち止まって考えること。それが、副作用を防ぎ、元気に暮らすための第一歩です。
この記事のポイントは以下の3つです。
・高齢者は体の変化と多剤併用によって薬の副作用が起きやすい
・眠気や便秘、ふらつきなどは“年のせい”ではなく薬の影響の可能性もある
・薬の一覧作成・定期的な見直し・生活改善で副作用を防ぐことができる
自分に合った薬の量や飲み方を見直すことで、薬は「リスク」ではなく「味方」になります。今日から、薬の使い方をもう一度見直してみましょう。
【NNNドキュメント】move your heart医療機器開発に挑む医師|シンフォリウムパッチ誕生の裏側とガウディプロジェクト・福井経編興業の挑戦【2025年9月15日放送】
最後に、番組の内容と異なる場合があります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


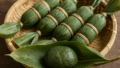
コメント