不眠症とむずむず脚症候群に悩むあなたへ
眠れない夜が続くと、体も心も疲れてしまいますよね。布団に入っても眠れない、夜中に何度も目が覚める、朝すっきり起きられない…。そんな悩みを抱えている人は多くいます。特に高齢になると眠りの質が浅くなり、日中の活動にも影響が出やすくなります。2025年9月14日に放送予定の 「チョイス@病気になったとき」不眠症・むずむず脚症候群 治療情報 では、そうした悩みに寄り添いながら最新の治療法や生活改善のヒントが紹介されます。
【明日から使える“新”東洋医学】夏のイライラと寒熱の乱れを整えるセルフケア(2025年8月25日放送)
不眠症の原因はひとつではない
不眠症といっても、その背景はとても多様です。心理的なストレス、生活習慣の乱れ、加齢による変化、そして病気の影響など、複数の要因が重なり合って起こることが少なくありません。
例えば、仕事や人間関係のプレッシャーなど日中の強いストレスが続くと、夜になっても頭が休まらず眠れなくなることがあります。一方で、むずむず脚症候群のように脚の不快感が原因となり、寝ようとしても落ち着かず、夜中に何度も目が覚めてしまう人もいます。
今回の番組では、こうした「不眠の原因はひとつではない」という点に注目しています。実際には、ストレスと生活リズムの乱れ、あるいは加齢と身体の不調といったように、複数の要因が重なって眠れなくなるケースが多いのです。そのため、原因を正しく見極めないままに薬だけを使っても改善しないことがあり、より丁寧な対応が必要になります。
むずむず脚症候群とは?
不眠の大きな原因のひとつが むずむず脚症候群(RLS) です。この病気は脚に「虫が這うような」「ムズムズする」「チリチリする」といった不快な感覚があらわれ、じっとしていると症状が強くなるのが特徴です。特に夕方から夜にかけて悪化する傾向があり、寝つきを妨げたり、眠りを浅くしたりする大きな要因になります。
この症状は、脚を動かすと一時的に楽になるため、夜中に何度も目が覚めて歩き回ってしまう人もいます。その結果、十分な睡眠が取れず、翌日も疲れが取れない、集中力が続かないといった生活への影響が出てしまいます。
背景には、鉄分不足や神経伝達物質ドパミンの働きの異常が関わっていると考えられています。場合によっては、慢性腎臓病や糖尿病など他の病気が関係していることもあるため、放置せず医師の診断を受け、適切な治療や生活改善に取り組むことがとても大切です。
睡眠薬の種類と特徴
番組では、不眠症の治療に使われる代表的な睡眠薬の種類についても紹介される予定です。まずは基本となる3つを知っておきましょう。
GABA受容体作動薬
脳の興奮を抑える作用があり、即効性に優れているため「寝つきが悪い」という入眠障害に効果的です。ただし長期間の使用で依存や耐性がつきやすく、副作用として翌日の眠気やふらつきが出ることもあるため注意が必要です。
メラトニン受容体作動薬
体内時計を整えるホルモン「メラトニン」に似た働きをし、自然な眠りを促します。副作用が少なく比較的安全に使えるのが特徴ですが、効果が実感できるまで時間がかかることがあり、強い不眠には単独では不十分な場合もあります。
オレキシン受容体拮抗薬
覚醒を促す物質「オレキシン」の働きをブロックし、入眠と睡眠維持の両方をサポートします。自然な睡眠に近いとされ、依存性も低い新しいタイプの薬として注目されています。ただし薬ごとに効き目や持続時間に違いがあるため、症状に合わせた使い分けが必要です。
このように、どの薬にも利点と注意点があり、人によって合う合わないがあるため、必ず医師と相談して選ぶことが大切です。
生活改善でできること
薬に頼る前に実践できる工夫もたくさんあります。番組でも取り上げられると考えられる生活改善のヒントを、先取りして整理してみましょう。
朝はカーテンを開けてしっかり朝日を浴びる
起床後に自然光を浴びると、体内時計がリセットされ、夜に自然な眠気が訪れやすくなります。
毎日同じ時間に寝起きして生活リズムを整える
休日もできるだけ同じ時間に起きることで、睡眠と覚醒のリズムが安定します。
寝る前のスマホやテレビを控える
ブルーライトや強い光は脳を覚醒させます。寝る1時間前からは画面を避け、心を落ち着ける時間にしましょう。
寝室を暗く静かに保ち、快適な温度に調整する
光や騒音、暑さ寒さは眠りを妨げます。自分に合った寝具を選び、睡眠環境を整えることが重要です。
日中に軽い運動を取り入れる
ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は、夜の睡眠を深めます。ただし、寝る直前の激しい運動は逆効果です。
カフェインやアルコールを控える
コーヒーや緑茶、アルコールは眠りを浅くします。特に夕方以降は控えるのが安心です。
むずむず脚症候群の人は鉄分を意識してとり、ストレッチやマッサージで脚をケアする
鉄分不足は症状を悪化させることがあります。食事やサプリで補い、寝る前に軽く脚をほぐす習慣をつけると症状が和らぎやすくなります。
これらの工夫は単独でも効果がありますが、薬の治療と組み合わせることでさらに改善が期待できる点がポイントです。
専門家の視点から
番組に出演予定の 井上雄一教授(東京医科大学客員教授) は、睡眠障害治療の第一人者です。教授は、薬に頼りすぎず「睡眠衛生」の改善を土台にすることの大切さを強調してきました。さらに、新しい薬の活用や、認知行動療法(CBT-I)といった非薬物療法の組み合わせが長期的に有効であると指摘しています。
放送でも、こうした専門的な視点から「眠れない夜」を改善するための実践的な情報が紹介されると期待されます。
まとめ:放送前に知っておきたいこと
-
不眠症は原因が一つではなく、複数が絡み合う
-
むずむず脚症候群は見逃されやすいが、不眠の大きな要因
-
睡眠薬は種類ごとに特徴があり、医師の指導のもと選ぶ必要がある
-
生活改善や認知行動療法も重要な治療の一部
-
放送では専門家による最新情報が解説される予定
放送前にこれらを押さえておくと、番組内容がぐっと理解しやすくなります。
📺 出典:NHK Eテレ「チョイス@病気になったとき」2025年9月14日放送予定回
🔗 番組公式サイト
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


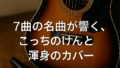
コメント