前立腺がんの検査・治療・合併症対策をわかりやすく解説
前立腺がんは男性で最も多いがんのひとつですが、初期にはほとんど症状がなく、気づかないうちに進行してしまうことがあります。そのため「早期発見」と「適切な治療の選択」、さらに「合併症への対策」がとても大切です。この記事では、NHK番組「チョイス@病気になったとき」で紹介された内容をもとに、前立腺がんの基本から検査方法、治療の種類、合併症とその対策までをまとめました。
前立腺がんはなぜ気づきにくい?
前立腺がんは尿道から離れた辺縁領域で発生することが多いため、排尿障害などの自覚症状が出にくいのが特徴です。さらに進行が非常に遅く、初期の段階では無症状のまま過ごせることもあります。実際に症状が出るのは、がんが尿道や膀胱を圧迫して排尿困難や血尿を起こしたり、骨やリンパ節に転移して腰痛や体重減少が現れる段階です。そのため、「症状がない=安心」とは限らず、定期的な検査が重要となります。
早期発見に役立つPSA検査
早期発見に欠かせないのがPSA(前立腺特異抗原)検査です。血液検査でPSA値を測定し、高ければ直腸診や超音波検査、生検などにつなげます。PSA検査によって、症状が出る前にがんを見つけられるため、生存率を大きく高められるのです。ただし、前立腺肥大や炎症でもPSA値は上がることがあり、偽陽性や過剰診断のリスクもあるため、医師と相談しながら受けることが望ましいです。
主な治療法とその特徴
前立腺がんの治療は、がんの進行度や年齢、生活の質をどう優先するかによって選び方が変わります。
-
監視療法
リスクが低い場合は治療を急がず、定期的にPSA検査や画像検査を行い経過を観察します。副作用を避け、生活の質を保ちやすい方法です。 -
手術療法
前立腺を摘出する根治的な治療です。最近はロボット支援手術が主流となり、出血や痛みが少なく回復も早いですが、尿失禁や性機能障害のリスクは残ります。 -
放射線治療
体の外から放射線を当てる外照射や、前立腺内に放射性の小さなシードを埋め込む小線源療法があります。手術に比べて体への負担が少なく、根治を狙える選択肢です。 -
ホルモン療法
男性ホルモンを抑えることでがんの進行を遅らせる方法です。進行がんや転移のある場合に用いられ、内服薬や注射薬があります。副作用として骨密度低下や筋力低下に注意が必要です。 -
その他の先進治療
高強度集束超音波(HIFU)、凍結療法、免疫療法など新しい治療法も研究・導入が進んでいます。
合併症のリスクと対策
前立腺がん治療には副作用や合併症が伴いますが、多くは対策が可能です。
-
尿失禁
手術後に起こりやすく、数カ月で改善することが多いです。骨盤底筋トレーニングや人工尿道括約筋による改善法があります。 -
性機能障害
勃起障害や射精障害が起こることがあります。薬物治療や陰茎ポンプなどの補助具、神経温存手術によるリスク軽減が対策になります。 -
排尿・排便障害
放射線治療後に頻尿や残尿感、直腸炎による下痢や出血が出ることがあります。スペーサー挿入や整腸剤、内視鏡治療で軽減可能です。 -
ホルモン療法の副作用
骨粗しょう症や筋力低下が起こりやすいため、運動や栄養管理が重要です。
合併症があっても生活は続けられる
治療の過程で合併症があっても、リハビリや心理的サポートによって生活の質を維持している方は多くいます。骨盤底筋体操や適度な運動、緩和ケアの利用などで、再び日常生活を取り戻せます。早期に発見された前立腺がんでは長期生存率も高く、治療を受けながら家庭や社会生活を続けることが可能です。
どの治療法を選ぶべきか?
結論として「どの治療法が正解か」は一人ひとり異なります。がんのリスク分類や年齢、生活への影響、そして本人の価値観によって選択肢が変わります。低リスクなら監視療法、高リスクなら手術や放射線+薬物療法の組み合わせなど、ケースに応じた最適解があります。大切なのは医師と十分に話し合い、自分に合った治療を納得して選ぶことです。
まとめ
前立腺がんは症状が出にくいからこそ、定期的なPSA検査が重要です。治療法は監視療法から手術・放射線・薬物療法まで多様で、それぞれに利点とリスクがあります。合併症があってもリハビリや医療的支援により生活を続けられるため、決して諦める必要はありません。早期発見と自分に合った治療選択で、前立腺がんと共に前向きな生活を送ることができます。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


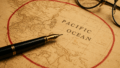
コメント