「シミュレーション昭和16年夏の敗戦 後編」
2025年8月17日に放送されたNHKスペシャル「シミュレーション昭和16年夏の敗戦 後編」は、戦前の総力戦研究所で行われた机上演習をもとに、もし昭和16年に日本が開戦を決めたらどうなっていたのかを検証するドキュメントドラマです。この記事では、番組内容をわかりやすく整理し、検索者が知りたい疑問に答える形でまとめます。なぜ研究所は「敗戦」を予測できたのか、またその結論がなぜ無視されたのかが明らかになります。東京裁判での研究所の追及や、石油確保の虚偽の見通しなど、現代にも通じる教訓が多く含まれていました。
総力戦研究所とは何だったのか
昭和15年に設立された総力戦研究所は、日本の国力を徹底的に分析し、戦争をシミュレーションする組織でした。産業、資源、食料、治安といった幅広い分野のデータを収集し、戦争継続の可能性を数字で導き出しました。机上演習に参加したのは官僚、軍人、経済学者など幅広い人材で、その分析は後に「現実の戦争展開とあまりに一致していた」と注目されます。実際、空襲の時期や対策まで予測されており、驚くほど正確でした。
ドラマで描かれた研究所の人物たち
ドラマ部分では、所長をモデルにした飯村穣や、研究所を代表して東京裁判に立った堀場一雄陸軍大佐をもとにしたキャラクターが描かれました。堀場は裁判で「研究所はあくまで調査と研究を行っただけで、実際の作戦には関与していない」と強調し、戦争責任の追及をはねのけました。また、机上演習で日銀総裁役を務めた佐々木直が、後に本物の日本銀行総裁になった事実も紹介されました。番組は、研究所が自由な議論を認め、敗戦シナリオの公表を許した飯村所長の姿勢にも光を当てています。
なぜ「敗戦」の予測が無視されたのか
研究所の分析では「日本がアメリカと戦えば敗北する」という結論が出ていました。すでに日中戦争で18万人の将兵が戦死しており、これ以上戦争を続ける体力はなかったのです。アメリカとの開戦を避けるには、要求通りに中国からの撤退が必要でした。しかし、陸軍はメンツを重視し、海軍は軍備拡張に巨額の予算を投じていたため、「戦わない」という選択肢を取れませんでした。番組では、この軍の論理と国民の期待が、冷静な判断を覆したことが描かれていました。
開戦を決めた御前会議と石油問題
最終的に開戦を決めたのは御前会議でした。決定を後押しした理由の一つが「十分な石油を確保できる」という見通しでした。しかし、この数字には根拠がなかったことが、関係者の証言で明らかになっています。石油問題は日本の生命線でありながら、希望的観測で処理されていたのです。NHKスペシャルは、データと証言を重ね合わせ、この誤った見通しがどれほど国を破滅へと導いたかを浮き彫りにしました。
東京裁判での研究所の立場
戦後の東京裁判で総力戦研究所は「戦争計画を立てた組織ではないか」と疑われました。堀場一雄大佐は法廷で弁明し、「調査研究の場にすぎない」と説明しました。現実の戦争展開と研究所の予測があまりに一致していたために追及されたのです。この事実は、研究所がいかに正確に日本の国力を把握していたかを示しています。
現代に残る教訓
番組が強調したのは、「不都合な真実が無視されると、国全体を誤った方向に導く」という点でした。戦前の日本では、敗戦を示す分析結果がありながら、国民や軍の期待、政治的な思惑に押しつぶされました。これは現代社会でも無関係ではありません。エネルギー問題や国際関係など、都合の悪いデータを軽視すれば、同じ過ちを繰り返す危険があります。
まとめ
NHKスペシャル「シミュレーション昭和16年夏の敗戦 後編」は、戦争シミュレーションが現実となった驚きと、無視された警告の重さを伝える番組でした。総力戦研究所の机上演習は、もし聞き入れられていれば戦争を回避できた可能性を示しています。私たちが学ぶべき教訓は、どんなに苦い結果でも「データが示す事実」に耳を傾けることです。歴史を振り返ることで、未来に同じ過ちを繰り返さない道を選べるのではないでしょうか。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


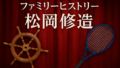
コメント