茶の湯の“心”が世界とつながる夜 〜NHKスペシャル「千家十職」密着記録〜
茶の湯という一見静かな世界。その裏側では、受け継がれた技と覚悟、そして“ものの見方”そのものを問い続ける人々の営みがあります。今回のNHKスペシャルでは、千利休の精神を450年以上守り続けてきた千家十職と、現代世界との新しい響き合いが描かれていました。
番組を通じて見えてきたのは、「派手さではなく本質を求める姿勢」がどれほど強く、深く、そして今の世界の価値観とも交差しているかということです。茶碗、柄杓、棗、掛軸など、ひとつひとつの道具には“作り手の哲学”が染み込み、その背景には驚くほど豊かな物語があります。
Eテレ【心おどる 茶の湯(4)】茶室のにじり口に込められた意味 表千家・千宗左が紐解く一期一会の美学|2025年10月28日
茶碗づくりの根っこにある問い 〜樂家400年の営み〜

安土桃山時代から続く樂家は、今も手捻りで茶碗を作り続けています。ろくろを使わず、手のひらと指で土を押し上げて形を作る技法は、手作りであるがゆえに“作り手の個性と心”がそのまま土に刻まれます。
今年、樂直入が息子に家を譲ったことで行われた「手始め式」。この日は唯一、家族以外も手仕事を見ることが許される特別な瞬間で、無言で土を込める姿が凜としていました。言葉を語らずとも、技と覚悟の深さが伝わる場面でした。
樂家の歴史の象徴とも言えるのが、初代長次郎の黒い茶碗。当時の日本では華やかな舶来品が持てはやされていた中、黒の漆黒を選んだ長次郎の作品は非常に革新的でした。利休がこの黒い茶碗に“美とは何か”という問いを託したと言われ、歴代当主もずっとその問いと向き合ってきたと番組で語られていました。
竹が“ゆっくり老いる”姿を支える黒田家の仕事

柄杓や花入を作る黒田正玄の家は、利休の時代から竹の道具すべてを託されてきた家系です。竹は成長が止まってから十数年で朽ちる繊細な素材。そこに「どう老いるか」という美意識が存在します。
まず竹探しから始まり、厳選した竹を炭で炙って水分を抜き、表面に滲み出る油を肌にのせることで、竹は数百年かけてゆっくりと美しく老いていきます。虫食いや割れのリスクを避け、道具に使えるのはわずか数割だけという厳しい世界です。
初代の花入『帰雁』は、400年を経てなお美しさが深まっており、素材と技が一体となって“時間に耐える美”を生み出していることの象徴でした。
利休の“形”を守る中村宗哲の漆の世界
漆で棗や平棗などを作り続けてきた中村宗哲の家。ここには利休の好んだ道具の「切り型」が残されており、細かな寸法から曲線まで、形のすべてが伝承されています。
利休の月命日には、表千家・裏千家・武者小路千家の3家元が祈りを捧げる場面も紹介されました。職人たちが“道具を通じて利休を支える”という言葉は、伝統の重みをありありと感じさせるものでした。
海外で広がる茶の湯の精神

番組後半では、海外で茶の湯に心を動かされた人々も登場します。
パリでは、ネシム・コーエンが友人を招いて毎月茶会を開き、自ら茶碗作りに挑んでいました。茶の湯に向き合うことで、漠然とした不安から解き放たれると語っていたのが印象的です。
シカゴのアーティストシアスター・ゲイツは、茶道具の持つ“精神の重さ”に惹かれ、職人の姿勢そのものが創作の核にもなっていると話しました。技の深さ、哲学、覚悟が、ジャンルを超えてアーティストの心に響いています。
ベルギーの美術商アクセル・ヴェルヴォールトは森の中に質素な小屋を建て、わびの精神を自分なりに表現する空間を作っていました。「現代は整いすぎた世界に進んでいるが、わびの精神はその反対にある」という言葉には、茶の湯が現代人に響く理由が凝縮されていました。
失われた技を未来につなぐ挑戦
焼物師の十八代 永樂善五郎は、100年以上途絶えていた黒い『土風炉』の技を復活させるため、植物の葉を使った燻しの研究を重ねています。土の種類、温度、時間の調整を繰り返し、窯に向き合う姿には“挑戦し続ける人の強さ”がありました。
一閑張細工師の飛来一閑は、和紙を何層にも張り重ねて作る「張抜き茶碗」をもう一度取り戻そうと努力してきました。父を亡くし技を受け継げなかった悔しさを胸に、子とともに技術を探り続け、今年ようやく納得できる器を生み出したという場面が紹介されました。
利休の精神を次の世代へ渡す力
茶道具を包む袋を作る十三代 土田半四郎は、手仕事にデジタル技術を取り入れ始めた様子を映していました。受け継ぎながらも、未来へ手渡すための工夫が少しずつ進んでいることが分かります。
表具師の十三代 奥村吉兵衛は「掛軸は100年単位の消耗品。次に扱う人が困らないように残していく」と語り、技の継承が“時間のリレー”であることを示していました。
また、裏千家十五代家元 千宗左が「今は心の豊かさを求める時代になっている」と話した言葉は、利休の精神がなぜ今再び注目されているのかを象徴していました。
アマースト大学のサミュエル・モース教授は、利休の“ものの価値は環境の中で見つかる”という教えを紹介し、シアスター・ゲイツは「不完全さにこそ自然な美が宿る」と語りました。海外の視点から利休の価値が再評価されていることがよく分かる内容でした。
まとめ
今回のNHKスペシャルは、茶の湯がなぜ今世界で注目されているのか、その理由を丁寧に示す内容でした。千家十職の手仕事には、完成よりも“道具と向き合う姿勢”そのものが刻まれています。竹、土、和紙、漆といった身近な素材に、どれだけ深い世界が宿るのかを教えてくれる回でした。
茶の湯が伝えてきたのは、「派手ではなく本質を見る」「不完全さの中にこそ美がある」という価値観。変化の激しい時代だからこそ、利休の精神が再び世界と響き合っているのだと強く実感できる特集でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

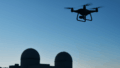

コメント