原子雲の下を生き抜いて 長崎・被爆児童の80年
2025年8月9日に放送されたNHKスペシャル「原子雲の下を生き抜いて 長崎・被爆児童の80年」は、原爆投下から80年が経った今も、その記憶と影響を抱えて生きてきた人々の歩みを追いました。舞台は長崎市立山里小学校。原爆により約1300人もの児童が犠牲になり、生き残った子どもたちは、自らの体験を手記に残しました。その後もNHKは彼らの人生を記録し続け、今回の番組では80〜90代となった彼らの現在の思いや、生きてきた道のりが紹介されました。
山里小学校と「原子雲の下に生きて」
1945年8月9日午前11時2分、長崎市の浦上天主堂近くで原子爆弾が炸裂しました。その衝撃は爆心地から数キロにわたり広がり、山里小学校の児童たちにも直撃しました。当時、学校には約1500人の児童が在籍しており、そのほとんどの自宅は爆心地からおよそ2km以内にありました。爆風や熱線、さらに続いた火災によって建物は倒壊・焼失し、約9割の児童が命を落としました。助かった子どもたちも重い火傷や怪我、そして家族を失う深い悲しみに直面しました。
世界初の子どもによる被爆記録
過酷な経験をした生存者の中から37人が選ばれ、自らの体験を文章にまとめました。その記録は「原子雲の下に生きて」という本として出版され、世界で初めて子ども自身が書いた被爆証言集となりました。本の中には、爆心地近くの地獄のような光景や、自らの傷の痛み、友人や家族を失った悲しみ、生き延びた者としての複雑な思いが率直に描かれています。この書は国内外で高く評価され、今も戦争の悲惨さと平和の大切さを伝える貴重な資料として読み継がれています。
山崎千鶴代さんの人生
山崎千鶴代さんは4歳のとき長崎で被爆し、爆風と熱線によって両親を失い、突然孤児となりました。親戚に引き取られましたが生活は厳しく、十分な食事を与えられない日々が続き、その影響で栄養失調となり体調を崩すことも多くありました。
戦後の生活と職歴
中学校を卒業すると、生計を立てるために働き始めましたが、仕事は長続きせず、工場や飲食店などさまざまな職を転々としました。やがて身寄りも少なくなり、福祉施設「恵の丘長崎原爆ホーム」で暮らすようになりました。この施設での生活は半世紀近くに及び、日常の場として落ち着いていきました。
明かされた心の傷
今回の取材で山崎さんは、中学時代に性的被害を受けた過去を語りました。この出来事は深い心の傷となり、人との関わりを避けるようになったきっかけでもありました。その告白は、被爆による苦しみだけでなく、戦後の社会で重なった別の苦難をも伝えるものでした。
野口貞子さんの思い出
9歳のときに被爆した野口貞子さんは、原爆によって一家8人のうち生き残ったのは姉と2人だけでした。家族を失った悲しみの中で、親戚に引き取られ、新しい生活が始まりました。しかし、その日々は決して楽なものではなく、朝から晩まで農作業に明け暮れる厳しい暮らしが続きました。そんな中、叔母のツヨさんが親代わりとなり、日々の生活を支えてくれました。ツヨさんの存在は、心の拠り所であり、大きな支えとなりました。また、野口さんは両親と一緒に通っていた教会にも足を運び続け、そこで平和への祈りを欠かすことはありませんでした。長い年月を経ても、その祈りは変わらず、失った家族や平和への願いを静かに心に刻み続けています。
石原秋光さんとの交流
被爆体験記の著者37人のうち、すでに17人がこの世を去っています。その中の一人、石原秋光さんは10歳で被爆し、幼いながらも深刻な火傷を負いました。44歳のときにNHKが取材した際には、火傷の痕を理由に差別を受け、仕事を長く続けられずに職を転々としてきたことが明らかになりました。生活の苦しさや心の痛みから、酒に頼ることも多かったといいます。日本被団協の横山照子代表理事は、そんな石原さんを気にかけ、病院への付き添いや、妻が抱える悩みを聞くなど、日常的に支えとなっていました。しかし妻は59歳で亡くなり、その後、石原さんは語り部として学生たちに自らの被爆体験を語る活動も行いました。ただ、その活動も長くは続かず、時間が経つにつれて横山さんとも疎遠になっていきました。最終的に石原さんは76歳で生涯を閉じ、その歩みは戦争の爪痕と共に刻まれたものでした。
下平作江さんの語り部活動
10歳で被爆した下平作江さんは、その後の人生をかけて被爆体験を語り継いできました。これまでに行った語り部活動は1万回以上にのぼり、国内外の多くの人々に直接、自らの体験を伝えてきました。妹は原爆による後遺症に苦しみ、体の傷や病気に加えて周囲からのいじめにも遭い、18歳という若さで命を絶ちました。この深い悲しみから、下平さんは「どんなに辛くても、苦しくても生きてほしい」という強い思いを持つようになり、その言葉を講演の場で繰り返し伝えてきました。ところが3年前から介護が必要な生活となり、さらに認知機能の低下も進んだため、長年続けた語り部活動を終えることになりました。取材の最後、下平さんは今も世界の各地で戦争が続いている現実に触れ、静かに怒りをにじませました。この番組は、戦争や原爆の惨禍だけでなく、その後を必死に生き抜いた人々の姿を丁寧に描き出しており、その語りは平和の尊さを強く心に刻むものでした。
番組を見て感じたこと
番組を見ながら、原爆を生き延びた山里小学校の子どもたちが、その後の人生で背負い続けてきた重さに圧倒されました。4歳で両親を失った山崎千鶴代さんの孤独、そして語るのもつらい過去をようやく口にする姿には、言葉を失いました。野口貞子さんが叔母ツヨさんの支えを受けながら、家族の面影を求めて教会に通い続ける場面も、祈りの深さが画面越しに伝わってきました。
また、石原秋光さんの人生は、被爆者が戦後社会で直面した現実を突きつけます。差別、職の不安定さ、心のよりどころを失いながらも、最後には語り部として若い世代に体験を伝えたこと。その道程は決して平坦ではなく、支える人とのつながりの中で成り立っていたことがよく分かりました。
下平作江さんが1万回以上も語り続けてきたのは、妹を原爆の後遺症といじめで失った痛みがあったから。「どんなにつらくても生きてほしい」という言葉は、過去の体験だけでなく、現代を生きる私たちにも向けられた強い願いに感じました。
この番組は、被爆の瞬間だけでなく、その後80年の生き方を丁寧に追うことで、「生き延びる」という言葉の本当の意味を教えてくれます。戦争や原爆の悲惨さと同時に、人が生き続け、語り継ごうとする力の尊さを深く心に刻む時間でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

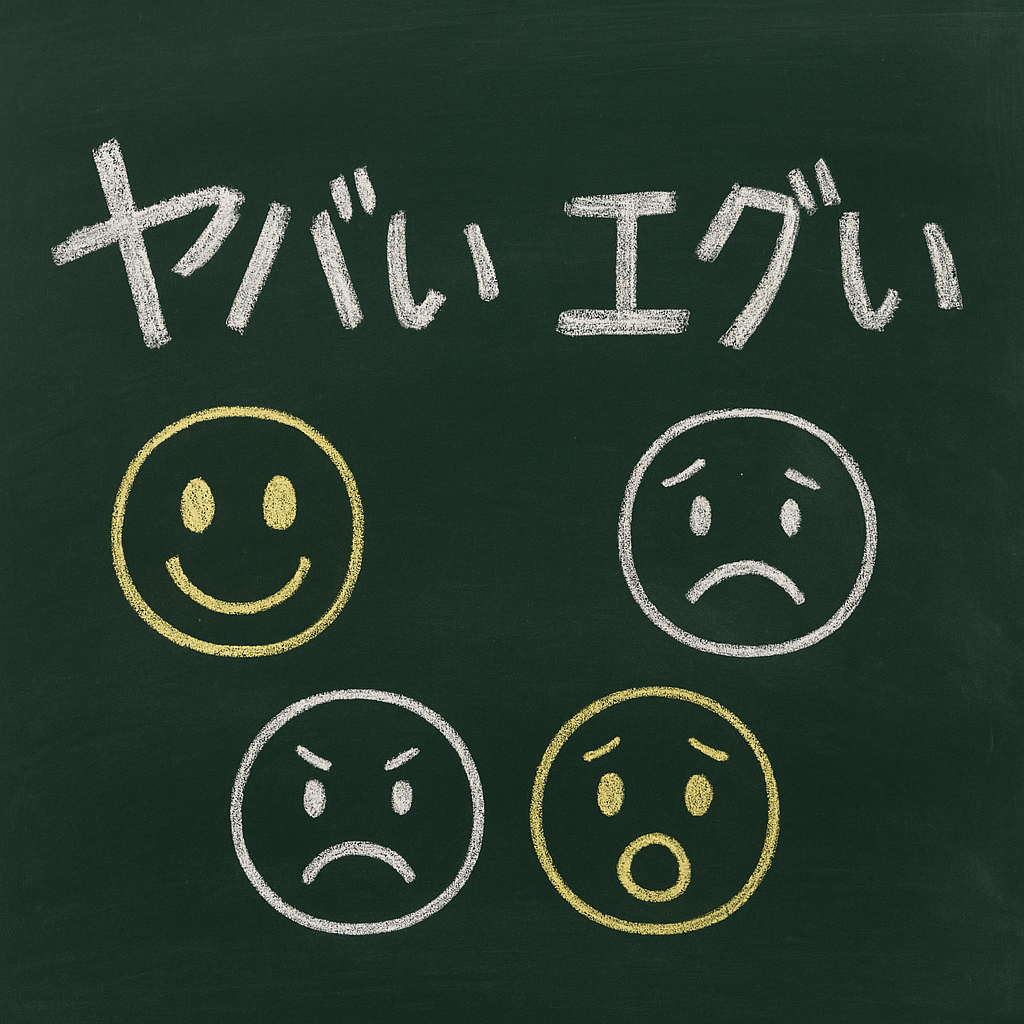

コメント