「“1兆円”を託された男 半導体ニッポン復活への闘い」
かつて日本は半導体分野で世界をリードしていました。1989年には売上高ランキング上位10社のうち6社を日本メーカーが占めていました。しかし今、世界のトップはアメリカのエヌビディアと台湾のTSMC。日本企業の名前は消えてしまいました。その背景には、開発から生産までを自社で抱える「自前主義」と、効率的に役割を分けた世界の流れとの差がありました。TSMCのように「ファウンドリ」に特化したモデルが主流になる中、日本は大きく遅れをとったのです。
こうした中、小池淳義さんが立ち上げたのがラピダス。国からの1兆円規模の資金を託され、最先端の2ナノ半導体を大量生産する国家プロジェクトです。社員は900人を超え、政治や経産省、製造装置メーカーとも連携しながら日本半導体復活に挑んでいます。
IBMとの技術協力
復活の第一歩は、IBMとの技術協力から始まります。IBM研究所が試作した新型トランジスタのGAAは、これまでにないほど性能が高く、省エネと高性能を両立できると期待されています。しかし、その構造は非常に小さく複雑で、安定した品質で大量生産することがとても難しいという大きな壁があります。そこで、この難題に挑むために、ラピダスは150名を超える技術者をIBM研究所に派遣し、日々研究と改良を重ねています。目標は2027年に量産をスタートさせることです。
一方で、最大のライバルであるTSMCは、すでに年内にも量産を開始する見通しを立てています。つまり、技術の完成度を高めながら、スピード勝負でも遅れをとらないことが重要で、まさに時間との戦いが続いているのです。
さらに小池淳義さんは、この厳しい競争を勝ち抜くために「完全自動化」の工場構想を掲げています。これは人の手をできる限り減らし、機械とAIで効率的に作業を進めることで、低コストかつスピード感のある生産を実現しようというものです。もしこの仕組みが成功すれば、単に追いかけるだけでなく、他社との差別化につながり、日本の半導体産業に新しい強みをもたらす大きな一歩になると考えられています。
日本独自の製造装置開発
ラピダスは、海外の技術や装置に頼るだけでなく、日本ならではの強みを生かした独自の装置開発にも力を入れています。その中心人物のひとりが、日立製作所時代から小池さんと一緒に挑戦を続けてきた舟橋さんです。舟橋さんは、半導体製造に欠かせない洗浄装置の分野で世界的に認められた技術者であり、その知識と経験をもとにプロジェクトを支えています。
現在進められているのは、シリコンウエハーの表面を均一に整える装置の開発です。半導体は、目に見えないほど細かい回路を正確に刻み込む必要があるため、わずかな凹凸や不純物でも性能に大きな影響を与えてしまいます。そのため、この装置は高精度な回路形成を可能にするための土台とも言える存在です。
つまり、ラピダスが掲げる日本発の半導体復活において、この取り組みは欠かせない要素のひとつ。海外企業に依存せず、日本の技術力を最大限に活かす姿勢こそが、他国との競争の中で優位に立つための大切な戦略となっています。
EUV露光装置の導入と国際協力
2025年、北海道千歳の工場に、ついにASML製のEUV露光装置が搬入されました。最先端の半導体製造には欠かせないこの装置は、なんと1台500億円以上という超高額な設備で、まさに国家プロジェクトだからこそ導入が可能になったものです。開発に携わってきたASMLのフーケCEOは、「長年みんなが不可能だと思っていた夢が、今まさに実現しつつある」と語り、小池淳義さんの揺るがない強い意志を高く評価しました。
さらにラピダスは、ベルギーのimecや東京大学とも手を組み、国際的な研究・開発のネットワークを広げています。世界中の最先端研究機関や大学と連携することで、単に海外から技術を持ち込むのではなく、日本が積極的に技術を磨き、発信していく仕組みを築こうとしているのです。
小池さん自身も「日本はものづくりの深い考え方と、生産技術に対する新しい視点で世界に大きく貢献できる」と語っています。これは、ただ世界の流れに追随するのではなく、日本独自の強みを打ち出し、存在感を取り戻そうという強い決意の表れです。つまり、ラピダスの挑戦は単なる技術競争ではなく、“日本の半導体復活”を象徴する国際協力の舞台になっているのです。
試験的生産と国民への説明
2025年6月16日、ついに日本国内で初めての2ナノ半導体の試験生産がスタートしました。工場ではAIを導入した最新システムが稼働し、生産工程を正確に管理。わずか12日後には試作チップが完成しており、日本の技術者たちが短期間で大きな成果を出したことが分かります。
ただし、この過程は徹底した秘密保持の中で進められていました。取材陣も自由には撮影できず、ディレクターが「国民の税金で成り立っているプロジェクトなのだから、もっと公開すべきではないか」と問いかけたところ、小池淳義さんは「普通の人にとって何でもない映像でも、ライバルにとっては極めて重要な情報になる」と強調しました。この言葉から、半導体産業が直面するシビアな国際競争の実態が強く伝わってきます。
また、資金面でもプロジェクトは大きく膨らんでいます。スタート時は1兆円規模でしたが、すでに1兆7000億円にまで拡大し、最終的には3兆円を超える見込みとなっています。これだけの巨額投資が行われるのは、日本が再び世界の最先端に追いつくために避けて通れない挑戦だからです。
そして7月、ついに2ナノ半導体が初めてメディアに披露されました。これは日本の半導体産業が「復活に向けて動き出した」という明確なメッセージであり、世界へ向けた大きな一歩となったのです。
海外企業との連携と未来への展望
小池淳義さんは、シリコンバレーに拠点を置くテンストレントという新興企業に注目しました。ここは、伝説的な半導体エンジニアとして知られるジム・ケラーCEOが率いており、AIや高性能チップの分野で急成長を遂げている企業です。小池さんはこの会社と協業契約を締結し、将来的にエヌビディアの独走を食い止める存在として大きな期待を寄せています。これは単なる技術的な挑戦にとどまらず、日本が再び国際半導体市場に確かな存在感を示すための戦略的な布石といえます。
さらに、世界の最先端を走るASMLは、今よりもさらに微細な回路を描ける次世代EUV露光装置の開発を進めています。小池さんは、その新技術をいち早く日本に導入するため奔走し、同時にimecなどの研究機関や海外企業との連携をさらに強化しています。こうして築かれる国際的なネットワークは、日本が世界の半導体産業で再び重要な役割を果たすための強力な基盤となっているのです。
まとめ
今回のNHKスペシャルは、日本の半導体産業が直面する現実と、再起をかけた壮大な挑戦を描いていました。小池淳義さん率いるラピダスは2ナノ世代半導体量産を目標に、IBMやASML、imecなどとの国際協力を進めつつ、国内の技術者とも力を合わせています。莫大な国費を投じたこの挑戦が実を結ぶかどうかは、今後数年の成果にかかっています。
半導体は私たちの生活を支える基盤技術。スマホや車、AIまですべてに関わるだけに、日本の未来に直結する挑戦です。今後もラピダスの動きは大きな注目を集め続けるでしょう。
2ナノ半導体が生活をどう変えるのか
2ナノ半導体は、これまでよりも小さく高性能なトランジスタを使うことで、省エネと処理能力の両方を大きく向上させます。これは私たちの身近な道具やサービスに直結し、便利で快適な生活につながります。
スマホの電池が長持ちする
2ナノ半導体は消費電力を大幅に下げられるため、同じ電池容量でもスマホを長時間使えるようになります。動画視聴やゲームなど負荷が大きい動作をしても、バッテリーの減りが遅くなります。これにより「充電切れの不安」が減り、持ち歩きがより安心になります。
自動運転車がより安全に動く
自動運転車はカメラやセンサーからの膨大な情報を瞬時に処理する必要があります。2ナノ半導体は処理速度が飛躍的に上がるため、道路状況や歩行者の動きをより早く判断できます。これによって事故を避ける可能性が高まり、安全性の向上に直結します。車の制御システム全体も小型化でき、燃費や電気効率にも良い影響を与えます。
AIがもっと高速で賢くなる
AIは大量のデータを処理して学習や判断を行います。2ナノ半導体を搭載することでAIの演算速度が格段に速くなり、これまで数時間かかっていた処理が数分で終わる可能性もあります。医療分野では画像診断の精度が上がり、教育や翻訳サービスでもより自然でスムーズな体験が期待されます。
生活への具体的な変化まとめ
| 分野 | 変化の内容 | メリット |
|---|---|---|
| スマホ | 電池が長持ち、省エネ | 充電回数が減り便利 |
| 自動運転車 | 情報処理が高速化 | 事故防止につながる |
| AIサービス | 演算スピード向上 | 医療・教育・翻訳が進化 |
このように2ナノ半導体は身近な生活をより安心で快適に変える力を持つ技術です。単なる産業の話ではなく、日常生活に直結する重要な進歩だといえます。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

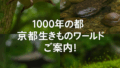

コメント