「命を診る 心を診る」
2025年7月13日、NHK総合で放送された「NHKスペシャル 命を診る 心を診る 〜小児集中治療室の日々〜」は、東京・世田谷にある国立成育医療研究センターのPICU(小児集中治療室)で過ごす子どもたちと、それを支える医療チームの姿を記録したドキュメンタリーです。命の危機と向き合う0〜15歳の患者たち、そしてその家族。小さな体に起こる大きな異変にどう向き合い、どう支えるのか。番組では、いくつもの命の物語が紹介されました。
肝臓に問題を抱えて生後すぐにPICUに入った太郎ちゃん
移植ができない小さな体に合わせた治療のはじまり
生まれてわずか4日目に、太郎ちゃんは東京都世田谷区にある国立成育医療研究センターの小児集中治療室(PICU)に入院しました。原因は肝臓の機能に深刻な問題を抱えていたためです。治療を担当した松本医師は、生後間もない太郎ちゃんの体の小ささではすぐに肝臓移植ができないと判断し、病気の進行を抑えながら、まずは体重を増やしていく方法を選びました。
しかしその治療中に容態が急変し、緊急で手術が行われることになりました。医師たちが開腹して確認したところ、小腸の約半分が壊死していることが判明。このまま放置すれば命を落とす恐れがあったため、迅速な処置が行われました。幸いにも手術は成功し、太郎ちゃんは命をつなぐことができましたが、腸が少なくなったことで栄養の吸収が難しくなる新たな課題が生まれました。
栄養確保と成長への取り組み、そして迫る時間
肝臓移植を目指すためには、太郎ちゃんの体重を目標の6kgまで増やす必要がありました。しかし、腸の大部分を失っていた太郎ちゃんには通常の経口摂取では限界がありました。担当の下島医師は、太郎ちゃんの残された腸に直接チューブをつなぎ、できるだけ効率的に栄養を吸収できるように工夫しました。
ところが、その後も細菌感染が繰り返され、腎臓の機能が低下。尿が出なくなってしまったことで、病状はさらに深刻になりました。PICUでは、太郎ちゃんに残された時間が多くないかもしれないという判断もあり、今後も積極的な治療を続けるべきか、それとも残された時間を穏やかに過ごすことを考えるか、医師たちは話し合いを重ねました。
この議論の内容は、そのまま率直に家族にも伝えられました。両親はこれまで一緒に歩んできた医療スタッフやソーシャルワーカーの佐藤さんの支えを受けながら、決断のときを迎えていきました。
父の夢と最期の時間
3か月が経ったある日、太郎ちゃんの父・里野立さんは、富山で開催される「全日本チンドンコンクール」に出場するため、遠方へと向かっていました。チンドン屋として芸を披露する姿を、いつか太郎ちゃんに見せることが夢だったからです。
その日、病院で太郎ちゃんの容態が急変しました。血圧が下がり、回復の見込みが立たなくなったため、PICUの一角に太郎ちゃんのための個室が準備されました。医療チームはすぐに富山と病院をオンラインで中継し、モニター越しに父の姿を太郎ちゃんに届けました。
PICUには、これまで太郎ちゃんの治療に関わってきた医師や看護師たちが静かに集まり、見守る中で配信が行われました。父の演奏と芸は、太郎ちゃんの目にもしっかり映ったはずです。そしてその夜、太郎ちゃんは静かに息を引き取りました。別れの場面でそっと母に声をかけたのは、緩和ケア科の余谷医師でした。太郎ちゃんの短い命は、PICUで関わった多くの人たちの思いとともに、そっと幕を閉じました。
長期入院の末に退院を迎えたゆうせいくんの挑戦
肝臓移植後に残ったもう一つの課題
ゆうせいくんは肝臓の移植手術を受けたあとも、長期間の入院生活が続いていました。その中で新たに直面したのが、肺を動かす筋肉の衰えによる呼吸機能の低下でした。自力での呼吸が難しくなり、人工呼吸器を外せなくなってしまったのです。常に喉の奥まで管が入り込んでいる状態が続き、違和感と不快感がゆうせいくんを苦しめていました。眠ることもできず、精神的にも体力的にも限界が近づいていました。
そんな彼のもとを訪れたのが、緩和ケア科の専門医・余谷医師でした。痛みや不快感、ストレスをやわらげることを専門とする余谷医師は、すぐに処方されている薬の種類や量を一つひとつ確認。場合によっては、薬の副作用が眠りを妨げることがあるため、薬の調整を提案しました。その結果、ゆうせいくんは久しぶりにぐっすりと眠ることができたのです。この一歩が、彼にとって大きな転機となりました。
筋力回復のためのリハビリと心理ケア
回復を進めるために重要とされたのが、肺の周りの筋肉を動かすリハビリでした。担当の壺井医師は、呼吸の主な働きを担う横隔膜や胸の筋肉を鍛え直すことが必要だと判断しました。しかし寝たままでは筋力は戻りにくく、体を起こすことが大切になります。そこで、医療チームは医療機器を付けたまま車椅子にゆうせいくんを乗せ、病院の中を散歩するリハビリを始めました。この作業は6人がかりの大掛かりなものですが、本人の気分転換にもつながるため、毎日のように続けられました。
その積み重ねのなかで、ゆうせいくんの体は少しずつ体力を取り戻していきました。ついに医師たちは、人工呼吸器を外す決断を下します。もちろん、ただ外すのではなく、不安を和らげるために子ども専門の心理スタッフがそばにつき、言葉をかけたり手を握ったりしながら慎重に対応しました。
退院の日、歩んできた道のりの先に
このようにして、ゆうせいくんは重い病気と、それに伴う長い入院生活という大きな壁を乗り越え、退院という大きな一歩を踏み出しました。その背後には、医師や看護師、リハビリスタッフ、心理ケアの専門職など、多くの人たちの連携と支えがありました。決してひとりでは越えられなかった時間を、みんなで支え合いながら乗り越えた結果です。
退院の瞬間は、病院全体がゆうせいくんの回復を喜ぶような空気に包まれたことでしょう。小さな体で、たくさんの苦しみに耐えたゆうせいくんの挑戦と成長は、多くの人の胸に深く残りました。
心臓の病と向き合うりんちゃんの決断と制約
心筋症による危機と心臓補助装置の選択
りんちゃんは、重い心筋症により突然心臓が止まる事態に見舞われました。医師たちはただちに心肺蘇生を行い、なんとか命を取り留めましたが、心臓そのものが十分な働きをできない状態に変わりはありませんでした。そこで、心臓の働きを支える装置「VAD(心室補助装置)」を装着するという選択がなされました。
VADは、血液を体に送り出すための補助を行う医療機器であり、命をつなぐためには必要不可欠です。しかし、この装置を一度つけると、自宅に戻るためには心臓移植を受けるしか方法がなくなります。つまり、VADの装着は、移植待機の道に入ることを意味していたのです。
子どもの心臓移植に伴う制限と不安
子どもの場合、移植が可能になるためには年齢や体の大きさが一致する提供者(ドナー)が現れる必要があります。しかも、日本国内では心臓の提供者そのものが非常に少ないのが現状です。2010年からは子どもの臓器提供が可能になりましたが、同意に至る家族は多くありません。そのため、心臓移植には平均で3年前後の待機が必要ともいわれています。
りんちゃんの家族は、この制約を受け入れながら、日々の生活を病院内で過ごす覚悟を迫られました。自宅に戻ることはできず、どちらかの親が24時間体制で付き添い続ける必要があります。この負担は、経済的にも精神的にも大きく、家族全体の生活にも影響が及びます。
専門家による家族支援と心のケア
こうした状況の中、家族の相談に乗っていたのが、伊藤さんという心理社会的支援を専門とするスタッフでした。彼は、病気のことだけでなく、姉への説明をどうするかという家族内の課題にも寄り添い、家族が無理をせずに話せる方法を一緒に考えていきました。
りんちゃんの姉も、急な環境の変化や、両親のそばにいられない寂しさを抱えているはずです。そんな中で、「なぜりんちゃんだけがずっと病院にいるのか」という疑問や不安に、年齢に合った言葉で丁寧に答えていく必要がありました。
病気に向き合うのは、りんちゃん本人だけでなく、家族全員の時間と心を支える長い道のりでもあります。その過程において、PICUでは医療だけでなく、家族の心の支えになる取り組みも大切にされていることが、番組を通して伝わってきました。
地方と都市の医療格差、そしてPICUの現実
少なすぎるPICUの設置数と偏り
日本国内で小児集中治療室(PICU)を持つ医療機関はわずか38か所にとどまっており、その多くが首都圏や関西圏に集中しています。つまり、地方に住む子どもたちは、重い病気やけがで集中治療が必要になったとき、すぐ近くに治療できる病院がないという現実に直面することになります。必要な治療がすぐに受けられないという状況は、命に直結する問題でもあります。
なぜ地方でPICUの設置が進まないのか。その背景には、運営にかかる高額な費用と、専門的な知識と技術を持つ小児集中治療医の不足があります。PICUの運営には医師だけでなく、看護師、リハビリ、心理ケア、緩和ケアなどの多職種が必要で、しかも24時間体制が求められます。こうした環境を整えるには人材も資金も多く必要となり、地方ではその確保が難しいのです。
命を運ぶ医療用ジェットの不足と資金の壁
地方から都市部のPICUへ患者を搬送するためには、医療専用のジェット機やドクターカーの活用が必要です。しかし、全国にある医療用ジェットはたった2機。重症の子どもが複数重なった場合、搬送が間に合わないという深刻なリスクもあります。
さらに、これらの搬送にかかる費用は公的支援だけではまかないきれず、NPOなど民間の団体や寄付に頼っている現状です。実際に医療ジェットで搬送された北海道の子どもが、都市部での緊急移植手術によって命を救われた事例が紹介されましたが、これは極めて限られた体制の中での対応でした。
表:日本のPICUに関する実情まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| PICU設置数 | 全国で38か所 |
| 分布 | 首都圏・関西に集中、地方では設置少数 |
| 小児集中治療医の数 | 約200人(必要な数の半分程度) |
| 医療用ジェット機 | 全国で2機のみ |
| 搬送の資金源 | 主に寄付や民間団体に依存 |
医療体制の脆さが突きつける課題
番組では、こうした体制の脆弱さがあらためて浮き彫りになりました。PICUを備えた病院の多くは、運営が赤字となっており、ドクターカーや医療機器の整備も寄付に頼っている状況です。それでも現場の医療者たちは、「今すぐ助けたい命がある」という強い思いで、限られたリソースの中で日々の対応にあたっています。
日本では、小児医療に対する公的な支援や社会の理解がまだ十分とは言えないのが実情です。子どもたちの命を守るには、都市だけでなく全国に安心して治療を受けられる体制が必要です。命を守る拠点をもっと広げるためには、社会全体での意識と支援の広がりが不可欠であると、番組は静かに問いかけていました。
医療と家族、それぞれの心に寄り添う現場の姿
PICUは、子どもの体だけでなく心のケアも大切にする場所です。苦しみや不安を和らげるために、緩和ケアやリハビリ、心理支援、家族への説明や相談まで、さまざまな専門家が関わります。ときには、医師たちが治療の方向性を話し合い、その内容を率直に伝える場面もあります。今回の番組は、そうした医療の現場をありのままに映し出し、命を守るとはどういうことなのか、改めて考えさせられる内容でした。
参考:NHKスペシャル『命を診る 心を診る 〜小児集中治療室の日々〜』(2025年7月13日放送)
取材協力:国立成育医療研究センター(東京都世田谷区)
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

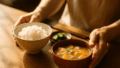

コメント