体臭タイプ別の対策ワザ&科学でニオイの謎を解明
2025年7月29日放送のNHK「あさイチ」では、夏の悩みのひとつ「体臭」に注目。専門家のアドバイスを交えながら、家でできる簡単なケアや、間違いやすいNG対策まで、わかりやすく紹介されました。また、茨城・大洗町からの中継や梅干し体験、人気コーナーの料理紹介もあり、実用的で親しみやすい内容が満載の回となりました。
夏の体臭、間違ったケアが逆効果に
夏は汗をかきやすくなるため、体臭が気になりやすい季節です。番組では、ついやってしまいがちな体臭対策の「やりすぎ」が逆にニオイの原因になってしまうと伝えていました。たとえば、乾いたタオルで汗を拭くと、皮膚の表面温度が下がらず、体温調節のためにさらに汗をかきやすくなるといいます。これはかえってニオイのもとを増やすことにつながるため注意が必要です。
さらに、制汗剤や消臭スプレーを何度も重ねて使うと、毛穴が詰まりやすくなり、皮膚に負担をかけることがあります。また、体をゴシゴシと強く洗うことで肌のバリア機能が低下し、逆に細菌が繁殖しやすくなることもあるそうです。清潔にしようとするあまり、やりすぎてしまうことがかえって逆効果になるケースが多いことが分かります。
年齢やニオイの種類で対策を変えることが大事
体臭には種類があり、それぞれに合った対策が求められます。番組では、体臭を3つのタイプに分けて、それぞれの特徴と対策方法を紹介していました。
| 体臭タイプ | 特徴 | おすすめ対策 |
|---|---|---|
| 汗臭 | 運動や気温上昇でかく汗が原因。菌とまざってニオイになる | 濡れタオルで優しく汗を拭く |
| ミドル脂臭 | 30~50代の男性に多く、後頭部やうなじから出やすい | シャンプーで頭皮をていねいに洗う |
| 加齢臭 | 皮脂が酸化して発生する特有のニオイ。男女問わず年齢とともに増加 | 肌を強くこすらずに洗う。紫外線対策で酸化を防ぐ |
加齢臭やミドル脂臭は、見えにくく気づきにくい場所から発生するため、毎日のケアがポイントになります。特に後頭部や耳の後ろなど、洗い残しやすい部分を意識してケアすることが効果的です。加齢臭に対しては、紫外線を浴びすぎることで皮脂の酸化が進むため、帽子や日傘などで日よけをすることも重要とされていました。
体臭対策はただ「よく洗えばいい」というわけではなく、自分のニオイのタイプを知って正しい方法でケアすることが一番の近道です。番組ではそのためのチェックリストも紹介され、体臭の種類を見極めることの大切さを改めて伝えていました。
お酢風呂でスッキリ消臭
番組で紹介された注目の対策が「お酢風呂」です。臭気判定士・松林宏治さんがすすめる方法で、体臭に悩む人に効果があるとされています。作り方はとてもシンプルで、湯船に穀物酢を200ミリリットル入れて混ぜるだけ。特別な道具や手間は一切必要ありません。
このお酢風呂は、お酢の抗菌作用により、体の表面にいる雑菌の繁殖を抑えることができるため、ニオイのもとを取り除くのに効果的です。さらに、お酢にはアンモニア臭を中和して消す働きもあるため、汗をかいた後の体臭も軽減されます。
実際に体臭が気になっていた人がこの方法を試し、入浴後に汗をかいた状態でも、2時間後の臭気レベルは「2(気にならない程度)」まで下がったという結果が紹介されました。これは、ニオイの強さを数値で測る「臭気強度」によるもので、効果の持続性もあるとされています。
お酢風呂の注意点
便利で手軽なお酢風呂ですが、使うお酢の種類や浴槽の素材によっては注意が必要です。正しく使用するためには、以下の点に気をつけましょう。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 使用するお酢 | 穀物酢のみOK。果実酢や調理酢はNG。酸の成分が異なり、肌への刺激になることも |
| 浴槽の素材 | 大理石やステンレス製の浴槽は避ける。酸による腐食の恐れがあるため |
| 追い焚き | 追い焚き機能は使わないこと。機械内部に酸が入り、故障の原因になる可能性あり |
お酢風呂は正しい方法で行えば、夏の体臭対策としてとても効果的で安全な方法です。入浴ついでに気軽に取り入れられるため、毎日のケアに取り入れてみるのもおすすめです。
靴のニオイにも簡単対策
家の中で特に気になるニオイのひとつが「靴のニオイ」です。番組では、すぐに試せて効果が出やすい靴の消臭方法が紹介されました。特別な道具を用意する必要はなく、水とドライヤーがあればできるという手軽さも魅力です。
方法は簡単で、靴の内側に軽く水をスプレーしたあと、ドライヤーでしっかりと乾かすだけ。これにより、湿気が飛び、雑菌の繁殖を抑えることができ、ニオイの原因を減らすことができます。天日干しのように時間がかからないため、朝出かける前や急な来客前にもすぐ対応できます。
さらに、革靴など水を使いにくい靴には、10円玉を使った消臭方法が効果的と紹介されました。10円玉に含まれる銅には抗菌作用があるため、靴の中にまんべんなく敷き詰めるだけでニオイを抑えられるとのことです。
| 靴のニオイ対策 | 方法 | 効果 |
|---|---|---|
| ドライヤー+水 | 軽く水をスプレーし、ドライヤーで乾かす | 即効で乾燥&雑菌の抑制 |
| 10円玉消臭法 | 靴の中に10円玉を敷き詰める(できるだけ新しいもの) | 銅の抗菌作用でニオイを防ぐ |
10円玉を使う場合は、なるべく新しいものを使う方が抗菌効果が高いとされていました。小学生でもできるくらい手軽な方法なので、靴箱や玄関のニオイ対策として、家庭内で手軽に取り入れることができます。毎日履く靴だからこそ、こまめなケアが快適さにつながります。
ストレスが原因?疲労臭に注意
番組では、夏場の体臭の中でも特に見逃されがちな「疲労臭」にスポットが当てられました。疲労臭はアンモニアを含む独特なニオイで、精神的なストレスや慢性的な疲れがたまったときに出やすくなるといいます。他の体臭と違い、汗を拭くだけではなかなか消えないのが特徴で、気づかないうちにまわりに不快感を与えてしまうこともあるため注意が必要です。
番組では、専門学校の非常勤講師や、施術後のセラピスト、小学生などに実際のアンモニアレベルを計測し、人によって大きな差が出ることが確認されました。特に、緊張やプレッシャーを感じやすい人や、睡眠が不足している人、お酒をよく飲む人などは、疲労臭が出やすいという結果に。
ミョウバン水スプレーが効果的
この疲労臭への対策として紹介されたのが、「焼きミョウバン」を使った手作りスプレーです。ミョウバンは消臭・制汗作用があるとされ、水に溶かしてスプレーボトルに入れるだけで、手軽にニオイ対策ができます。使い方は、ニオイが気になる部分にスプレーするだけですが、初めて使用する人は肌に合うか確認するため、必ずパッチテストを行うよう呼びかけられました。
疲労臭が出やすい人の特徴や、対策方法を以下にまとめました。
| 疲労臭が出やすい条件 | 対策方法 |
|---|---|
| 精神的ストレスが多い | ミョウバン水スプレー・公園などでの休憩 |
| 睡眠不足が続いている | 良質な睡眠・寝室環境の見直し |
| お酒をよく飲む | 飲酒量の調整・肝臓の負担軽減 |
| 疲れが抜けにくい生活 | 食事の改善・ビタミン補給・湯船につかる |
疲労臭は放置しておくと気づかぬうちに悪化していくこともあるため、日常生活の中でこまめにストレスケアを行うことが大切です。体に直接働きかけるスプレー対策と合わせて、心の疲れを癒す時間を作ることもニオイの改善につながると、番組では紹介されていました。
故人の写真が動く?最新お葬式テクノロジー
「ツイQ楽ワザ」のコーナーでは、AI技術を使った新しいお葬式の形が紹介されました。今回取り上げられたのは、故人の写真を元に、まるで生きているかのように表情や動きが加えられた動画を作成し、参列者へ向けたメッセージを伝えるという技術です。
このサービスでは、AIが写真から顔の動きや表情を自動生成し、音声をつけた故人の「メッセージ動画」を制作することが可能となります。実際の声ではなくAIが合成した音声ですが、まるで本人が話しかけてくれているような印象を与えるため、葬儀の場で大きな感動を呼ぶ可能性があります。
一方で、故人の意思が直接確認できないという点から、写真を動かすことへの違和感や、誰がこの映像の作成を依頼したのかという倫理的な問題も出てくるため、制作を受ける際には、依頼主と故人の関係性をしっかりと確認する手続きが取られているとのことです。
この技術はまだ開発段階にあり、一般向けの価格設定などは未定ですが、将来的には、家族や友人との思い出をより深く共有する手段の一つとして活用されていくことが期待されています。伝統的な葬儀に新しい選択肢をもたらす、注目のサービスといえるでしょう。
新企画「いまオシ!LIVE」で紹介される梅の体験スポット
番組では、茨城県大洗町にある「Ume Sonare oarai(ウメソナーレ大洗)」が紹介されます。ここは、1830年創業の老舗梅干し専門店・吉田屋がプロデュースした日本初の梅体験パークで、梅シロップ作りや梅酒作りが楽しめるスポットです。
体験では、梅・砂糖・お酒を自由に組み合わせて、自分だけの梅商品をつくることができ、その組み合わせは最大125通りにものぼります。体験時間は約40〜45分。梅シロップ体験は2,200円から、梅酒体験は2,640円からと、観光と食体験を両立した人気スポットです。
施設内にはキッチンカーやカフェ「ume café WAON」も併設されており、9種類の梅干しを使ったオリジナルメニューやスイーツも楽しめるのが魅力です。
「みんな!ゴハンだよ」には近藤幸子さんが登場
料理コーナー「みんな!ゴハンだよ」では、料理研究家の近藤幸子さんが登場予定です。近藤さんは、手間をかけすぎずに家庭でも再現しやすいレシピに定評があり、過去にはじゃがいものミルク煮や、しそみそ肉巻きなどの簡単で栄養バランスの取れた料理を紹介してきました。今回も、暑い夏にぴったりなさっぱりとした味わいのレシピや、火を使わずに作れる工夫が見られるのではと期待されています。
ソース一覧(外部リンク)
体臭タイプに合わせた食品選びで、におい対策をもっとわかりやすく
体臭が気になるときは、汗や皮脂の原因だけでなく、食事内容や腸内環境が深く関わっていることがあります。ここでは、体臭のタイプに応じておすすめされる食品とその理由を、表形式でわかりやすくまとめました。日々の食事を少し見直すだけでも、においの印象がぐっと変わる可能性があります。
体臭タイプ別におすすめの食品とその理由
| 体臭タイプ | 主な原因 | おすすめ食品とその理由 |
|---|---|---|
| 疲労臭(アンモニア臭) | ストレスや疲労で肝臓のアンモニア処理機能が低下し、汗に残る | シジミ・マグロ・チーズ・キノコ類(オルニチンが豊富) 梅干し・黒酢(クエン酸で肝臓サポート) ヨーグルト・納豆(腸内環境を整え善玉菌を増やす) |
| ケトン臭(酸っぱいニオイ) | 糖質不足や過剰なダイエットで代謝が乱れる | レモン・黒酢・梅干し(クエン酸が代謝を促進) 適度な糖質補給(バランスの取れたエネルギー供給が重要) |
| キャベツ臭(腐敗臭) | 腸内でたんぱく質が腐敗しアンモニアや硫化水素などを生成 | 豆類・葉野菜(食物繊維で腸内を掃除) 発酵食品(腸内の善玉菌を増やす) |
| ミドル脂臭・まくら臭 | 汗腺の働きが弱まり、乳酸が蓄積されて首や後頭部に特有のにおい | ウォーキングや入浴で汗腺を鍛える クエン酸食品(代謝と血流を助ける補助的な役割) |
| 加齢臭(ノネナール臭) | 皮脂が酸化して発生するノネナールという物質が原因 | シイタケ・オイスターなどのキノコ類(抗酸化成分であるエルゴチオネイン・スピルミジンが豊富) ナッツ・柑橘類・ごま(ビタミンC・E・ポリフェノールで酸化を抑える) |
食品による体臭対策の根拠と注意点
キノコ類は、抗酸化力のあるエルゴチオネインやスピルミジンが豊富で、加齢臭を和らげる働きがあると注目されています。週に数回、料理の副菜やみそ汁に取り入れるだけでも効果的です。
葉野菜やスピルリナなど、クロロフィルを含む緑の食品は、体内で発生するにおい物質を中和する働きがあるとされ、特に腸内環境の改善に役立ちます。
ヨーグルトや納豆などの発酵食品は、腸の善玉菌を増やすことで、体内でアンモニアや硫化水素の発生を抑えます。腸内が整えば、汗や皮膚ガスのにおいも穏やかになります。
クエン酸は梅干し、黒酢、レモンなどに含まれ、体内の代謝を助け、疲労物質やニオイの元になる成分の分解を促進してくれます。
また、赤身肉・にんにく・キャベツ・ブロッコリー・アルコール・香辛料など、においを強める食材を取りすぎないように意識することも大切です。特に硫黄系の野菜や肉の過剰摂取は、汗や呼気に強いにおいを残す可能性があります。
このように、自分の体臭のタイプに合った食品を日々の食生活に取り入れることで、外からのケアに加えて体の中からにおいをコントロールする方法が見えてきます。番組で紹介されるレシピや食材情報とも合わせて、放送後にさらに詳しい事例を追記予定です。においの悩みを減らし、より快適に過ごすためのヒントとしてお役立てください。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

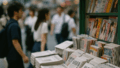

コメント