原発の“空の死角”が突きつける課題とは?急増するドローン脅威と安全対策のいま
この記事では、玄海原発で確認された“謎の光”をきっかけに、原発を含む重要インフラが抱える上空の脆弱性、そして世界規模で加速するドローン脅威の実態を整理します。読めば、今どこで何が起きていて、なぜ問題なのか、そしてどんな対策が必要なのかが具体的に理解できます。
NHK【みみより!解説】廃校データセンターからカワハギ養殖まで!文部科学省が動かす“学校再生”の最前線|2025年11月10日
玄海原発で何が起きたのか:夜空に現れた“光の正体が不明のまま”という問題
2025年7月26日21時頃、玄海原発の正門付近で警備員4人が「ドローンのように見える3つの光」を視認したとされています。
続く21時35分頃には、原発に常駐する原子力発電所特別警備部隊(原警隊)も同様の光を確認しました。
最終的には22時53分頃、発電所南側上空でも同様の光が確認され、その後視界から消えたと記録されています。
ここで重要なのは「光の正体が何か分からない」という点ではなく、「原発の警備体制では記録すら残せなかった」という現実です。
設備への影響は確認されなかったものの、監視網が“夜空の一部”を把握しきれていないという脆弱性が露呈しました。
九州電力は直後に、暗視スコープや投光器の追加設置などを打ち出し、夜間監視強化に踏み出しています。それでも、
・どこから飛んだのか
・誰が操作したのか
・目的は何だったのか
これらが一切わからないまま消えたという事実は、重要施設の「空の防衛」がどれほど難しいかを示す具体的な例となりました。
韓国・古里原発で続く“不審ドローン”の連続発生
玄海原発のケースと似た事象は、海外でも多発しています。
特に韓国の古里原発(Kori Nuclear Power Plant)では、2015〜2019年の間に複数のドローン侵入が繰り返し発生し、2019年だけで13件の不法飛行が報告されています。
そのうち6件は8月に集中し、原発周辺の空域に不審飛行が続いたとされています。
ここで共通するのが、
・捕捉の難しさ
・操縦者の特定が困難
・小型・静音ドローンの検出限界
という点です。
韓国でも「監視はしているのに、飛んできた機体を追い切れない」という課題が繰り返し指摘されています。
これは日本だけの問題ではなく、世界中の原発が直面している“共通の弱点”だと言えます。
ドローンの進化が“これほど厄介”になっている理由
原発の警備はもともと、
・敷地内への侵入
・フェンス越え
・テロ対策の強化
といった“地上のリスク”に重きを置いて構築されてきました。
しかし近年のドローンは、
-
手のひらサイズの小型化
-
羽音がほぼ聞こえない静音性
-
夜間飛行
-
GPSを使った自律飛行
-
望遠カメラやセンサー搭載
といった進化を遂げ、地上の対策では捕捉できない領域に入り込んでいます。
従来のレーダーは、鳥と小型ドローンの区別も難しく、監視カメラでは照度不足で夜間の小型飛行物体を映し切れません。
つまり、
“目視”と“カメラ”を中心とした警備体制には、技術的な限界がある
ということが、世界中の事例を見ても明らかになっています。
原発が狙われやすい理由:情報収集から妨害まで用途が多岐にわたる
ドローンが原発に接近する目的はさまざまです。
-
周囲の監視体制のチェック
-
施設や設備の撮影
-
特定の運動・団体による抗議
-
テロ目的の偵察
-
意図しない迷い込み
目的が不明な場合でも、重要インフラにとって「意図がわからない飛行物体」はそれだけで重大な脅威です。
一部の報告では、ドローンにセンサーを搭載して放射線量を測定する行為や、GPS妨害を試すような飛行が海外で確認された例も指摘されています。
つまり、
“ただ飛んでいるだけ”でも警備側には危険性が高い
というのが現代の状況です。
日本の現行法とその限界:法律はあるが“空の防衛”は追いついていない
日本には重要施設周辺でのドローン飛行を禁止する法律があります。
玄海原発周辺も「飛行禁止区域」に設定されています。
しかし、今回のように
・夜間
・低空飛行
・無灯火
・小型機
となると、違法飛行の“検知”“記録”“特定”を行うことが非常に難しいのが現実です。
法律で禁止されていても、
見つけられなければ止められない。
止められなければ操縦者も特定できない。
こうした「制度と現場のギャップ」が、安全保障上の課題となっています。
有効な対策はどこにある?世界が進める“多層防御”という考え方
現在、国際的に注目されているのが「多層防御」の概念です。
1つの対策ではなく、複数の技術を重ねて防御するという方法です。
例えば、
-
夜間対応の高性能監視カメラ
-
小型ドローン専用レーダー
-
LIDARによる立体的な検知
-
電波妨害(ジャミング)
-
強制着陸システム
-
ドローン捕獲装置(ネット等)
-
飛行ログの記録と解析
-
監視人員の増強
海外では“空のフェンス”を構築するようなイメージで、空域の安全確保に動き始めています。
日本でも玄海原発の事案をきっかけに、
「目視や通常カメラ中心の体制では限界がある」
という課題がはっきりしました。
原発の安全をどう守るのか:いま必要とされる視点
今回の玄海原発の騒動は、原子炉に直接影響が出たわけではありません。しかし、もっと大きな問題を浮き彫りにしました。
-
空の監視網に限界がある
-
不審飛行の記録が残らない
-
目撃情報に頼る体制では対策が遅れる
-
世界中で同じタイプの“空からの脅威”が増加している
つまり、“起きたこと”よりも“起きてしまった背景”が重要なのです。
原発の安全は、地上だけを守っていれば成り立つ時代ではありません。
空・電波・データ・ネットワークがつながった現代では、総合的な監視と防御が不可欠です。
まとめ
玄海原発で起きた“謎の光”は、単なる目撃情報ではなく、日本全体の原発警備に突きつけられた新しい課題でした。
海外でも、韓国の古里原発のように、不審なドローンの飛行が繰り返し確認されています。
小型化・静音化・夜間飛行など、進化したドローンは従来の監視では捕捉しきれず、操縦者の特定も困難です。
必要なのは、
・技術
・法律
・運用
を組み合わせた総合的な対策です。
この記事は放送前の情報をもとに構成しています。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

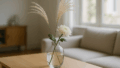

コメント