都市の病院が次々と閉鎖!?これからの医療のかたちとは
2025年6月2日に放送されたNHK総合『クローズアップ現代』では、「まさか都市部で…相次ぐ病院閉鎖・休止」という衝撃的なテーマが取り上げられました。東京都内、特に吉祥寺のような利便性の高い地域でさえ、救急対応の病院が診療をやめざるを得ない現実。医療を守るはずの病院が、なぜ今、苦境に立たされているのか。その背景と未来へのヒントを番組では掘り下げていました。
NHK【病院ラジオ(19)】サンドウィッチマンが見た子どもたちの本音|東京都立小児総合医療センター|2025年4月29日放送
都心でなぜ病院が休止に?吉祥寺の事例から見える問題
番組の冒頭で紹介されたのは、東京都武蔵野市・吉祥寺で実際に起きた病院の診療休止という出来事でした。ここは、住みたい街ランキングでも上位に挙げられる人気エリアですが、そんな場所で救急対応を行っていた病院が突然診療を休止したという知らせは、地域住民にとって大きな衝撃となりました。
このような出来事が起きた背景には、都市部の医療機関が抱える根本的な課題が隠れていました。最大の問題は、「医療を真面目に提供すればするほど赤字になる」という構造的な矛盾です。患者に必要な検査や治療を行っても、診療報酬だけではコストが賄えず、病院側の負担が大きくなる一方なのです。
実際にこの病院では、救急対応を含む高度な医療を地域に提供し続けてきましたが、その努力が収支改善にはつながらず、経営が悪化していたことが明らかにされました。
さらに、都市部特有のもう一つの大きな課題が施設の老朽化です。番組では、東京23区内にある病院の約29.7%が築40年以上であるというデータが紹介されました。これは病院の約3つに1つが老朽化している計算になります。
こうした古い建物では、以下のような課題が重なります。
-
耐震性能の基準を満たしていないため改修が必要
-
医療機器の搬入や更新が難しい構造
-
病室や廊下の幅が現在の医療基準に合っていない
-
空調や給排水設備などの更新費用が高額
改修や建て替えにかかる費用は数億円から数十億円に及ぶ場合もあり、医療の収入だけでこの負担をまかなうことは非常に難しい状況です。そのうえ、地域住民にとっては「便利な立地」として価値のある土地でも、病院にとっては固定資産税や維持費の負担が重くのしかかるという現実もあります。
こうした要因が重なった結果、吉祥寺の病院では診療の継続が困難となり、休止という選択をせざるを得なかったのです。都市に住んでいれば医療は十分に受けられるという安心感が、もはや通用しない時代が来ているのかもしれません。病院はただの建物ではなく、命を支える社会インフラであるという認識を、私たちも改めて持つ必要がありそうです。
医療提供体制の見直しと「集約化」の動き
番組の中盤では、これからの医療のかたちとして「役割分担」と「集約化」という考え方が紹介されました。登場したのは、公衆衛生の専門家として知られる吉村健佑さんです。彼は、すべての病院があらゆる診療に対応しようとするのではなく、地域ごとに本当に必要な医療サービスを見極め、機能を分けていくことの重要性を語りました。
つまり、地域の中で「この病院は救急を」「この病院はリハビリを」といったように、それぞれの医療機関が特定の分野に特化し、効率よく運営していくことで、医療の質と経営の両方を守る仕組みを作っていこうという提案です。
その具体的な例として紹介されたのが、大阪府で実施された先進的な取り組みでした。
-
経営が悪化していた公立病院
-
建物の老朽化が進んでいた民間病院
この2つの病院が、それぞれの課題を抱えたまま存続を模索するのではなく、連携して新しい病院を共同で設立するという選択をしました。
新体制では以下のように機能を分担しました。
-
公立病院は、地域で不足していた小児医療や周産期医療に特化
-
民間病院は、一部施設を回復期・リハビリ病棟として改修し、慢性期医療に対応
このように医療機能を明確に分けることで、それぞれの専門性を活かしながら、患者にもより質の高い医療を提供できる体制が整いました。加えて、新しい病院の建設費は両者で折半し、負担を軽減。お金の問題でも協力し合うことで、無理なく施設の再構築が可能になったのです。
この事例は、全国で広がる医療機関の経営難や建て替え問題に対して、実践的なモデルケースとなり得るものです。番組では、こうした役割分担と連携による再構築が、都市部の医療崩壊を防ぐ重要なカギになるとまとめられていました。
地域に必要な医療を、誰が・どこで・どう担うのか。データに基づいた戦略と、病院同士の連携こそが、これからの時代にふさわしい医療のかたちとして注目されています。
国の対応と報酬制度の課題
番組の終盤では、国の制度が医療の現場に与える影響について掘り下げられました。厚生労働省は現在、都市部の救急医療体制を維持するために、診療報酬の加算要件や評価基準の見直しを進めていると説明しています。2025年度の診療報酬改定もその一環であり、必要とされる医療にきちんと報酬が届くよう、制度の改善を目指しているとのことです。
しかしながら、医師の太田圭洋さんは、現場の実情として「必要な医療に、必要な報酬が与えられていない」という根本的な問題を指摘しました。患者のために丁寧な診療を行っても、そのコストに見合う収入が得られない。結果として、医療機関の経営は赤字に陥り、医師やスタッフの負担だけが増していくという悪循環が生まれています。
このような状況では、いくら制度の細部を調整しても、現場の疲弊を止めることはできません。太田さんの指摘は、単なる制度改革ではなく、医療そのものの価値をどう評価するのかという問いを私たちに投げかけています。
また、吉村健佑さんは、今後の医療行政に必要な視点として、データを活用した戦略的な判断の重要性を強調しました。
-
地域の人口動態
-
年齢構成や病気の傾向
-
医療機関の配置と機能
こうした情報を数値で把握し、それに基づいて「どこに」「どれだけの医療が」「どのように必要なのか」を明確にしたうえで、地域ごとに最適な医療体制を設計していくことが求められます。単に制度を変えるだけではなく、データに基づく医療の見える化と、行政や地域との連携による現場主導の改革が重要だという意見です。
番組では、これからの医療を考える上で、「制度」「報酬」「戦略」この3つの視点を同時に持つことが欠かせないとまとめられていました。目の前の課題に対応しながらも、未来を見据えた医療のあり方を構築するために、国と現場の双方向の連携が今後ますます必要になると示されています。
まとめ:私たちにできることは?
今回の『クローズアップ現代』は、単なる病院閉鎖のニュースにとどまらず、医療という社会基盤の危機を私たちに突きつける内容でした。
病院が経営困難になる理由の多くは、努力が報われない仕組みにあります。必要な医療が提供されるほど赤字になる、そんな構造を放置してはいけません。これからの医療を守るためには、国の支援だけでなく、私たち一人ひとりが医療の在り方に関心を持ち、声を上げていくことも重要です。
今後もこうした課題を見つめ直す番組が放送されることで、地域医療の未来に向けたヒントが増えていくことを期待したいと思います。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


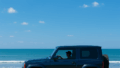
コメント