どうする?子や孫のSNS利用 世界で進む“禁止法”反対も
子どもたちにとってSNSは、日々の暮らしの一部になっています。友だちとつながることはもちろん、好きなことを発信したり、最新の情報を知ったりと、生活の中で大切な役割を果たしています。けれどもその一方で、SNSが原因でいじめに遭ったり、犯罪に巻き込まれたり、心の健康を損ねたりするケースが増えているのも事実です。2025年4月23日に放送されたNHK「クローズアップ現代」では、そうした問題に対し、海外ではどのような対応が進んでいるのか、そして日本では何ができるのかを掘り下げて紹介していました。番組に登場したすべての話題や事例をもとに、詳しくまとめてご紹介します。
世界で進むSNS年齢制限法とその背景
番組ではまず、オーストラリアの動きが取り上げられました。2024年12月に可決された「オンライン安全改正法」では、16歳未満の子どもがSNSを使うことを全面的に禁止することが定められました。対象となるのはInstagram、TikTok、Facebook、Snapchatなど、多くの若者が使っているSNSです。この法律は2025年中に運用が始まり、違反したSNS運営企業には最大で約50億円の罰金が科される可能性があります。
この法律の成立背景には、国民の約77%がこの禁止法に賛成しているという調査結果もありました。それだけ多くの人が、子どもたちのSNS利用に対して強い不安や危機感を持っているということがわかります。オーストラリアの首相アンソニー・アルバニージー氏も、子どものオンライン環境を守るための法整備を強く進めています。
アメリカ・フロリダ州でも、2024年に14歳未満のSNS利用を禁止する法律(House Bill 3)が成立しました。この動きのきっかけは、SNSをきっかけに自殺した子どもをもつ遺族に対し、IT企業の代表が議会で謝罪したことでした。世論の後押しもあり、法律が成立しましたが、施行は2025年1月からの予定だったものの、実際には開始されていません。その理由は、SNS企業の団体が「この法律は憲法で保障された表現の自由に反する」として訴訟を起こしたためです。
訴訟が始まったことで、SNS規制の是非は今も大きく揺れています。IT企業だけでなく、人権団体からも「若者のつながる権利を奪ってしまうのではないか」という声が上がり、議論が続いています。
子どものメンタルヘルスに及ぶSNSの影響
番組では、SNSが子どもたちの心と体に与える具体的な影響についても詳しく伝えられていました。アメリカ政府の調査によると、12〜15歳の子どもが1日3時間以上SNSを使っていると、メンタルヘルスに問題が起きるリスクが2倍になるという結果が出ています。SNSに長時間触れていると、不安や孤独感、自己否定の気持ちが強くなるとされ、集中力の低下や睡眠障害なども指摘されています。
この問題に本格的に向き合うため、全米21の研究機関が連携して、1万人以上の子どもたちの脳の変化や感情の動き、依存のしくみなどを長期的に調べる大規模プロジェクトが進められています。子どもがSNSに依存していく背景には、単なる「使いすぎ」では済まされない脳科学的な要因もあると考えられているのです。
日本でも、深刻な例が起きています。番組では、ある女子中学生がダイエット動画ばかりを見続けたことで摂食障害を発症し、体重が30kg台にまで落ちて入院したという事例が紹介されました。母親は「どうしたら止めさせられるのか分からなかった」と語り、家庭内での限界や対応の難しさが浮き彫りになっていました。
規制だけでは限界?家庭での役割とは
法整備が進む海外の例を見ても、子どもたちが抜け道を探したり、大人に隠れてSNSを使う可能性は常に残っています。番組に出演したつるの剛士さんも、「自分も子どものころ、ゲームを隠れてやっていた。法律だけでは防ぎきれない」と話しており、多くの家庭で共感を呼ぶコメントとなっていました。
こうした現実をふまえて、番組では家庭でのルール作りが重要であると強調されました。番組内で紹介された平井さんファミリーでは、親子で話し合ってスマホの使い方のルールを決めていました。
-
使う時間帯や場所を明確にする
-
SNSアプリの数や使い方について、子ども自身に選ばせる
-
親も同じルールを守ることで、子どもが納得して実行できるようにする
専門家の榊先生は、「前頭前野(自分をコントロールする脳の部分)を育てるには、ルールを自分で作って守る経験が欠かせない」と話していました。このように、親子で一緒に考えて取り組むことが、スマホ依存を防ぎ、自己管理能力を育てる大きなカギになります。
平井さんの娘・佑奈さんも、話し合って決めたスマホの使用時間より早く自ら使用を終えることができており、ルールを「守らされる」のではなく「自分で守る」感覚が生まれていたことが伝えられていました。
日本社会はこれからどう動く?
最後に番組は、日本の制度面についても触れていました。現在の日本では、SNS利用に関する明確な年齢制限を定めた法律は存在していません。ただし、2008年に施行された「青少年インターネット環境整備法」によって、18歳未満の子どもに対してはフィルタリング機能の導入が義務づけられているなど、最低限の保護策は設けられています。
こども家庭庁は現在、SNSの利用制限や年齢確認のあり方について検討を進めており、日本独自の対策が求められています。しかし、年齢確認の仕組みをどう作るか、法で制限したときに子どもたちが別の方法で抜け道を探すリスクをどう防ぐかなど、実際の制度運用にはさまざまな課題が残されています。
番組では、フランスやブラジルでもSNS年齢制限の導入が検討されていることに触れ、日本としても国際的な動きを参考にしながら、学校・家庭・行政が連携し、社会全体で子どもを支える体制が必要だと訴えていました。
SNSは今や、子どもたちの暮らしに欠かせないものになっています。その分だけリスクも大きくなっており、「ただ使わせない」ではなく、「どう使うか」を教えることがより重要になっています。大人たちが寄り添い、共に考えながら支えていくこと。それこそが、これからのデジタル時代に必要な子育てのかたちです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

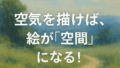
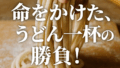
コメント