第4回「絵の中を歩ける!?奥行きのある風景
2025年4月29日、NHK総合で放送された「3か月でマスターする絵を描く」第4回では、「絵の中を歩けるような奥行きのある風景」をテーマに、遠近感を出すための具体的な描き方が紹介されました。出演したのは、絵の指導で知られる柴崎春通さんと、タレントの山之内すずさん。今回は、ただ遠くに物を置くだけではない、空気感を取り入れた風景表現の技法に焦点を当て、実際に筆を動かしながら学びました。
オープニング
番組の始まりにはオープニング映像が流れ、いつも通り爽やかな雰囲気でスタートしました。そのあと、柴崎春通さんが今回のテーマを紹介しました。第4回の題材は「奥行きのある風景」。ここで柴崎さんは、絵の中に遠近感を出すためには単純に遠く小さく描くだけではなく、「空気感を描き込むことが大切」だとポイントを伝えました。
遠近感を出すには空気感を描く

まずは基本となる「遠近感の出し方」について解説が行われました。柴崎さんは、遠くのものをただ小さく描くだけでは本物らしく見えないと指摘し、空気の存在を意識して描くことが必要だと話しました。そして、まずは下絵の制作に入りました。
-
遠景に向かって自然に薄くなるような線を引く
-
全体の構図を考えながらバランスを取る
-
どこに一番目を引くポイントを置くかを考える
下絵が完成すると、次に空と雲を描く作業に入りました。空の色は上が濃く、下にいくにつれて薄くすることで、よりリアルな奥行きが出ると説明されました。雲もふんわりと、遠くにいくほど小さく柔らかく描くのがコツです。
空気感を意識して遠い山を描く
次に、遠い山を描いていく工程に入りました。遠くの山は色を明るめにして、なおかつ輪郭をはっきりさせないことが大切です。柴崎さんは、「遠いものほど空気が間に入るから白っぽく見える」と説明し、特に山のふもとは空気の層が厚くなるため、より白みを強くすると自然に見えると教えてくれました。
-
遠くの山はグレー系、淡い色で描く
-
山頂よりふもとをより白く
-
線はぼかして柔らかくつなぐ
こうすることで、自然なグラデーションができ、見ている人に「遠くに山がある」と感じさせることができるのです。
空気感を意識して近い山を描く
続いて、近くにある山の描き方に取り組みました。ここでは、色の濃淡をうまく使うことが重要になります。柴崎さんは、「近い山でも、奥と手前で色を変えるとさらに奥行きが出る」と説明しました。
-
手前の山は濃い緑や茶色を使う
-
遠目の部分は少し色を薄める
-
影になる部分を濃く塗り分ける
山之内すずさんも、柴崎さんの指導を受けながら、手元で絵筆を動かしていました。近い山を描くときは、木の一本一本を描きすぎず、かたまりで捉えるよう意識することもアドバイスされました。
石や川を描く
次は、手前にある石や川の表現に移りました。ここでは、より具体的な質感を出すために、色をしっかりつけることが大事になります。柴崎さんは、「手前ははっきり、コントラストを強く描くとよい」と教えました。
-
石は光の当たる面と影の面をはっきり描き分ける
-
川は流れの方向を意識して線を引く
-
水面には空の色を映り込ませる
特に石の描写では、丸い石、角ばった石、さまざまな形を組み合わせることで自然らしさが出るとアドバイスされました。
手前の大地を描く
さらに手前の大地の描写に進みました。柴崎さんは、ここで「木の描き方」にもふれ、「木には必ず日向と日陰がある」と教えました。これにより、平面的だった絵に立体感と深みが生まれます。
-
木の葉はベタ塗りせず、影を意識する
-
大地も光の当たる部分と影の部分を描き分ける
-
道や小道を加えると奥行きがさらに強調できる
木を描くときは、葉っぱを一枚ずつ描くのではなく、かたまりとして捉え、光の当たる部分を明るめに塗ると自然に仕上がることがポイントです。
仕上げ~おつゆがけで空気を描く
すべてのパーツを描き終えたら、最後の仕上げに入ります。柴崎さんは「おつゆがけ」という技法を紹介しました。これは、絵全体に透明色を重ねることで、空気の層を再現する方法です。
-
薄めた絵の具を全体にさっと重ねる
-
色が強すぎる部分をなじませる
-
空気をまとったような柔らかい仕上がりにする
この工程を加えることで、絵の中に一体感が生まれ、まるで本当にその場所にいるような雰囲気を作り出すことができます。
今日のまとめ
番組の最後には、今日学んだことを振り返るまとめがありました。山之内すずさんは、「理解できると楽しいものですね」と感想を述べ、絵を描くことがさらに好きになった様子でした。柴崎さんも、「空気を描くことを意識すれば、誰でも奥行きのある絵が描けるようになる」と励ましの言葉を添えて締めくくりました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

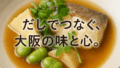
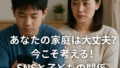
コメント