第6回「バランスのよい人物画〜顔より脚?〜」
NHKで放送中の『3か月でマスターする絵を描く』。2025年5月13日放送の第6回では、「バランスのよい人物画〜顔より脚?〜」がテーマとなりました。人物画に挑戦する上で大切なポイントは、実は“顔”ではなく“脚”にあるという興味深い切り口から始まり、人物を描くための基本的な比率や色の表現方法まで、柴崎春通さんの丁寧な解説とともに学ぶ内容でした。今回は出演者の山之内すずさんが実際に人物を描きながら、自分の描き方を見直していく工程も描かれ、初心者でも理解しやすい構成でした。すべてのエピソードを紹介しながら、1.5倍のボリュームで詳しく解説していきます。
今の実力を試す!人物画を描いてみる
番組の冒頭では、まず山之内すずさんが今の自分の実力で人物画を描いてみるところからスタートしました。モデルは画面に映し出された全身像で、細かい指示はなく、自由に描くという形式です。彼女は「どう描いたらいいのか迷う」と戸惑いながらも、手を動かし始め、真剣なまなざしでスケッチを進めていきました。このシーンでは、「まずはやってみる」ことの大切さが伝えられました。完璧でなくてもいいので、今の自分がどう描けるかを確認することから学びは始まるという姿勢です。
山之内さんが描いた絵には、バランスの違和感や脚の長さのズレなど、細かな点が見られましたが、それこそがこの回のテーマである“バランス”の課題に気づくきっかけとなります。
柴崎春通が教える「人体の比率」を知ることの重要性
絵の構成で大切なのは、全体のバランスです。柴崎春通さんは、人物を描くうえで基本となる人体の比率についてわかりやすく説明しました。
-
全身の半分が脚
-
脚の中心が膝
-
胴体の半分が胸、そのまた半分がへそと肩
このように身体をいくつかのパーツに分けて均等な比率で構成されていることを理解することが、正しい人物画を描く土台となるのです。この比率を意識することで、見た目の印象が大きく変わります。特に初心者にとっては、感覚に頼るのではなく、基本のルールを知ることで安定感のある絵が描けるようになるというメッセージが込められていました。
ここから、柴崎さんは比率を応用した下絵の描き方に進み、画面ではガイドラインを引きながら人物の全身を構成していく様子が紹介されました。体の各部位を正しく配置していくことで、顔や胴体、脚とのバランスが自然になっていく様子がよくわかりました。
肌の色づくりと洋服の描き方で立体感を出す
下絵が完成したら、次は色塗りの工程に入ります。最初に取り組むのが肌の色づくりです。柴崎さんは「肌の色は血の色を意識する」と解説しており、単なるベージュやピンクではなく、人間の肌にある血色や透明感を色で表現することが重要だと説明しました。
さらに肌の中には血管も見えるため、赤だけでなく青や紫、黄味などを混ぜて深みのある肌を作ることが紹介されました。この工夫によって、ただの平面的な塗りではなく、立体的で生命感のある肌に仕上がっていきます。
次に描かれるのは洋服です。洋服も形だけでなく、光と影を意識しながら塗ることで、素材感や立体感が出せるようになります。たとえば、シャツのしわや布のたるみ、光が当たる部分と影になる部分を塗り分けることで、実際に着ているようなリアルな印象が生まれます。
髪の毛の表現と仕上げのハイライトで完成度を高める
洋服まで塗り終えたら、最後の仕上げに向けて髪の毛を描いていく工程に進みます。髪の毛は一本一本描くのではなく、全体の流れや光の反射を意識して塗ることがポイントです。筆のタッチや濃淡のコントロールによって、自然な毛の流れが表現されていきます。
最後に行うのがハイライト(光の強調)の作業です。これは、光が最も強く当たる部分に白や明るい色を少しだけ加えることで、絵に立体感とツヤを加えるテクニックです。たとえば、髪の毛の一部や頬、洋服の折り目などにわずかに明るさを加えるだけで、絵全体が引き締まり、「完成された作品」に近づいていきます。
ここで柴崎さんは、**「人物画では顔に目がいきがちだが、実は脚をしっかり描くことが全体のバランスを整えるカギになる」**と伝えていました。番組タイトルの「顔より脚?」という意味が、この解説によって納得できる形で回収されました。
実際に描いて学ぶことの意義
今回の内容は、ただ技術を教えるだけでなく、描く前に観察し、描きながら気づき、仕上げていく過程を大切にすることの重要性が伝わってきました。とくに初心者は、顔ばかりに意識がいってしまいがちですが、人物画全体の構成を意識することが大切だと改めて学べる回でした。
-
自分の感覚で描くことで気づくことがある
-
比率を知ることで描きやすくなる
-
色の重ね方でリアルさが出せる
-
最後のハイライトで仕上がりに差が出る
-
脚をしっかり描くことで人物画の完成度が上がる
番組の終盤では、山之内さんの描いた人物画も完成しました。最初に描いたものと比べると、構造が整い、色にも深みが加わった作品に仕上がっていたのが印象的でした。特に脚のラインや肌のグラデーションの工夫に成長が見られました。
次回も、実践的な内容が期待されます。これから人物画に挑戦したい方、また基礎を見直したい方にとって、今回の回はとても役立つ内容となっています。3か月間でステップアップしながら絵を学んでいくこの番組は、これからも注目していきたいシリーズです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

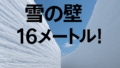

コメント