上野修が伝える“始末の料理”4品!だしの基本と春の味覚を家庭で再現
2025年4月23日(水)放送のNHK「きょうの料理」では、大阪の日本料理を代表する料理人・上野修さんが登場し、大阪の「始末の精神」に根ざした家庭料理を紹介しました。大阪・関西万博で注目を集めるこの時期、番組では大阪の魅力を“食”の側面から伝える特集が組まれ、昆布だしを基本とした本格和食が取り上げられました。上野さんが大切にしているのは、素材を余すことなく使い切る「始末の料理」。今回は、「基本の昆布だし」から始まり、「桜鯛とクレソンのバターあんかけ」、「鶏肉の柑橘くわ焼き」、「大阪漬け」という4品が登場し、それぞれに大阪の知恵と技が詰まっています。
基本の昆布だし
和食の味を決める“だし”。中でも大阪料理には、うまみが豊かで澄んだ味の真昆布のだしが欠かせません。今回紹介された「基本の昆布だし」は、上野さんが店でも実際に使っている方法をベースに、家庭でも作りやすい分量と手順で解説されました。
材料(つくりやすい分量)
-
昆布…45g(真昆布を使用)
-
水…1.2L
作り方
-
昆布はだしが出やすいよう、数か所に割れ目を入れます。
-
鍋に水と昆布を入れ、一晩(6〜8時間)浸けて戻します。
-
翌日、弱火にかけて沸騰させないように注意しながら30分間加熱し、昆布を取り出します。
家庭向けの簡易版として紹介されましたが、上野さんの店舗ではこの作業にさらに3時間をかけてじっくり加熱するとのこと。火加減を調整しながらじわじわと昆布のうまみを引き出すことで、深く澄んだ味わいに仕上げる工夫が施されています。このだしが、すべての料理の味の柱になります。
桜鯛とクレソンのバターあんかけ
春の代表的な食材「桜鯛」と「たけのこ」、そして鮮やかなグリーンの「そら豆」や「クレソン」を組み合わせた一品です。骨付きの鯛から出る旨みを煮汁に移し、その煮汁をさらにあんとして活用する、まさに「無駄のない料理」といえます。
材料(2人分)
-
たい(骨付き切り身)…2切れ(120g)
-
ゆでたけのこ(穂先)…100g
-
クレソン…25g
-
そら豆(さやから出す)…10個
-
木の芽…適量
-
バター…4g
-
塩…小さじ1/4+適量
<煮汁>
-
基本の昆布だし…カップ1
-
削り節…8g
-
酒…大さじ1
-
みりん・うす口しょうゆ…各小さじ2
-
塩…小さじ1
<水溶き片栗粉>
-
片栗粉…大さじ1
-
水…大さじ2
作り方
-
煮汁を作ります。だしに削り節を加え、火を止めて5分おいたあと、こしてから調味料を加えます。
-
たけのこは食べやすい大きさに切り、熱湯で1〜2分ゆでます。
-
そら豆は塩を加えた熱湯でゆで、冷水にとって薄皮をむきます。
-
鯛は皮側に切り目を入れて塩をふり、冷蔵庫で30分置いてから、熱湯にくぐらせてぬめりを除きます。
-
フライパンに煮汁を入れて中火で煮立て、鯛とたけのこを加えてふたをして5分間蒸し煮します。
-
クレソンとそら豆を加えてサッと火を通し、煮汁を切って器に盛ります。
-
フライパンに残った煮汁にバターを加えて温め、水溶き片栗粉を加えてとろみをつけたら、具材にかけて木の芽を添えて完成です。
とろりとしたバターのコクと、鯛の旨みが詰まっただしが一体となり、春の贅沢を存分に味わえる一皿です。
鶏肉の柑橘くわ焼き
大阪では昔から、あいがもを使った「くわ焼き」が親しまれてきました。今回はその料理を鶏肉で現代風にアレンジし、昆布だしのまったり味に柑橘の酸味を加えることで、軽やかさと深みを両立した一品に仕上がっています。
材料(2人分)
-
鶏もも肉…100g
-
大根…150g
-
グレープフルーツ…1個(他の柑橘類でも可)
-
グリーンアスパラガス…3本
-
スナップえんどう…10本
-
サラダ油…大さじ1/2
-
かたくり粉、塩…適量
-
ディル…あれば適宜
<たれ>
-
基本の昆布だし…大さじ1+2/3
-
みりん…大さじ1+2/3
-
うす口しょうゆ…大さじ1+1/3
-
酒…大さじ1
-
砂糖…小さじ1
-
はちみつ…10g
-
粒マスタード…小さじ2
作り方
-
グレープフルーツは果肉だけを房から取り出しておきます。
-
アスパラとスナップえんどうは塩ゆでして冷水にとります。
-
大根は厚めの輪切りにして電子レンジで加熱します。
-
鶏肉は一口大に切り、かたくり粉をまぶします。
-
たれの材料をすべて混ぜておきます。
-
フライパンに油を熱し、大根と鶏肉を焼き、脂をふき取ってたれを加えます。
-
アスパラ・スナップえんどう、グレープフルーツ、はちみつ、マスタードを加えて仕上げます。
昆布だしの旨みに、柑橘のさわやかさとマスタードの風味が重なり、食欲をそそる香りと味のバランスが魅力的です。
大阪漬け
最後は、まさに「始末の料理」の象徴ともいえる「大阪漬け」。だしをとったあとの昆布や、大根の皮など、本来なら捨てられがちな部分を使った浅漬けで、歯ごたえとだしのうまみを同時に楽しめる料理です。
材料(つくりやすい分量)
-
大根の皮…200g(千切り)
-
だしをとったあとの昆布…10g(細切り)
-
赤とうがらし(漬け込み用)…1本(種を除く)
-
赤とうがらし(あしらい用/小口切り)…適量
-
塩…4g(大根の重さの2%)
作り方
-
材料をポリ袋に入れ、しっかりもみ込んでなじませます。
-
空気を抜いて袋を閉じ、冷蔵庫で30分置きます。
-
汁気を切って器に盛り、小口切りのとうがらしをのせて完成です。
わずかな塩と昆布のうまみだけで、しみじみとしたおいしさが広がる一品で、食卓の箸休めにもぴったりです。
おわりに
今回の放送は、「始末の料理」というテーマを通じて、素材を大切に使いきるという考え方と、だしの力を中心に据えた大阪の味を丁寧に紹介していました。上野修さんのレシピは、どれも手順が明確で実践しやすく、なおかつ味は本格的です。
昆布だしを中心にした料理の広がりは、家庭の食卓に「ていねいに作ることの楽しさ」と「無駄のない調理の喜び」を届けてくれます。春の旬を取り入れた4品の料理は、季節感と大阪の心意気を同時に味わえる構成でした。どれも日常に取り入れやすい工夫があり、だしを学びたい方や、食材を大切にしたい方にとって参考になる放送でした。今後の「きょうの料理」も見逃せません。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

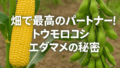
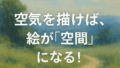
コメント