佐倉流・有機の力!トウモロコシとエダマメの甘い関係を徹底解説
2025年4月22日放送のNHK『やさいの時間』では、佐倉朗夫さんによる有機栽培シリーズ2年目の幕開けとして、「あま〜い関係!トウモロコシとエダマメ」をテーマにした実践的な内容が紹介されました。今回の放送は、混植による栽培方法や春の畑で見られる植物・生き物の観察まで、家庭菜園ファン必見の充実した構成となっています。
春の畑で観察できる野菜と草花たち

今回の「やさいの時間」では、春ならではの畑の風景が紹介されました。まず登場したのは、ホトケノザ、ナズナ、土筆(つくし)といった春の草花です。どれも身近な植物ですが、畑の中で見つけると、自然と季節の移ろいを感じさせてくれます。これらの草花が畑の片隅に咲いている光景は、まさに春の訪れを感じさせる風景でした。
観察されたのは花だけではありません。畑で育てている野菜たちにも春の変化が見られました。特に注目されたのはキャベツのとう立ちです。キャベツは本葉が10枚以上になり、1か月ほど寒さにあたると花芽が形成されるという特徴があり、それが畑で実際に見られたという解説がありました。
・とう立ちしたキャベツは、中心から茎が立ち上がり、やがて花を咲かせます。これは収穫のサインではなく、花を楽しむ段階に入った証拠でもあります。
・アブラナ科の野菜であるルッコラやコマツナの花も登場し、それぞれの風味を食べ比べるというシーンもありました。これらは菜花(なばな)として食卓に取り入れることができます。
・秋に植えたダイコンやルッコラをあえて少し残しておくことで、春に花を咲かせ、それを食べるという楽しみ方ができるという提案も紹介されていました。
こうした自然の変化に気づきながら過ごす畑の時間は、有機栽培ならではの楽しさでもあります。雑草と呼ばれがちな草花も、視点を変えれば畑の季節感を伝えてくれる“春のお知らせ役”として、やさしい存在になります。野菜たちの姿も、収穫のためだけではなく、花を咲かせるという一生の流れを学ぶ機会になります。
・ナズナの三味線のような種、ホトケノザの葉の重なり方、つくしの独特な形状など、子どもと一緒に観察するのにもぴったりです。
・それぞれの菜花には、ルッコラのピリッとした辛みや、ダイコンのやさしい甘さなど、異なる風味の違いがあり、味覚でも春を楽しめるというのが印象的でした。
春の畑には、見る、育てる、味わうという三つの楽しみが詰まっています。作物の成長だけでなく、周囲の自然の小さな変化に気づくことで、日々の畑仕事がもっと豊かで心地よいものになるのだと伝わってきました。
春限定!生き物観察も楽しめる

春の畑では、野菜や草花だけでなく、生き物たちの活動も活発になり、観察の楽しみが広がります。今回の放送では、そんな季節限定の生き物たちの姿が紹介されました。中でも印象的だったのは、モンシロチョウの登場です。春に見られる個体は夏のものよりもやや白っぽく、羽の透明感が高いのが特徴です。この微妙な色の違いにも、自然の繊細な変化が表れていて、じっくり観察すると楽しい発見があることを教えてくれました。
畑の周辺には、テントウムシの姿もありました。小さな体で害虫を食べてくれるテントウムシは、自然栽培においてとても頼もしい存在です。特にアブラムシを食べることで、農薬を使わずに野菜を守る役割を果たしてくれるため、畑で見かけると嬉しくなります。
・モンシロチョウの飛来は春の訪れのサインでもあり、花の咲くタイミングとも関係しています。菜の花などの蜜を吸いにくる姿は、畑に彩りを与えてくれます。
・テントウムシは、葉の裏や茎のあいだにひっそりと潜んでいて、見つけるたびに自然の力強さを感じます。
また、今回の放送では、畑の片隅で育てられていた緑肥植物のヘアリーベッチも注目されました。これは単なる草ではなく、畑の土を豊かにする力をもった頼れる植物です。花が咲くと見た目にも美しく、紫がかった小さな花が畑を彩ります。
・ヘアリーベッチは、根に空気中の窒素を固定する力があり、肥料のかわりになる栄養源を土に供給します。
・同時に、害虫の注意をそらす役割も持ち、メインの野菜を虫の被害から守ってくれます。
・ただし、他の種子の発芽を妨げる成分があるため、トウモロコシやエダマメなどを植える場合は、1か月前に刈っておくことが大切と紹介されていました。
このように、春の畑では作物だけでなく、草花、生き物、緑肥の働きがすべてつながっています。生き物たちが活動することで、畑が自然と整えられ、野菜がすこやかに育つ環境が生まれます。人が自然に手を添えるだけで、畑全体が調和しながら動き出す。そんな里山の知恵と、春の畑の奥深さが感じられる内容でした。
トウモロコシの栽培と土づくりの工夫
春のはじまりに育てる野菜として、今回番組で取り上げられたのはトウモロコシでした。イネ科に属するこの作物は、畑の中でも特に根の張り方が力強く、土を元気にする力を持った作物としても知られています。畑全体のバランスを考えたとき、トウモロコシのようなイネ科の存在は非常に重要です。
栽培を始める前の土づくりとして、まず注目されたのはヘアリーベッチの活用です。ヘアリーベッチは緑肥として畑の端で育てられ、土に窒素を供給したり、害虫の注意を引き寄せたりと、さまざまな役割を果たします。ただし、そのままでは他の植物の発芽を妨げる性質があるため、種まきの1か月前には刈って枯らしておく必要があります。
・ヘアリーベッチを刈り取ることで、その後に植えるトウモロコシがスムーズに発芽し、根を張りやすくなるように整えられます
・土を耕さずにそのまま植える方法、いわゆる「不耕起栽培」も実践されていました。これは土壌中の微生物や構造を守ることで、自然の力を活かした栽培ができるという考えに基づいています
また、トウモロコシを守るための工夫として、カラス対策にも配慮した種まきの方法が紹介されました。浅くまいてしまうと、芽が出る前に鳥に食べられてしまうリスクがあるため、種は5~6センチの深さにまき、しっかりと土を押さえておくことが推奨されていました。
・この「鎮圧」を行うことで、土と種のあいだにすき間がなくなり、毛細管現象により水分が保たれやすくなります
・結果として、乾燥しにくくなり、発芽率が向上するというメリットも得られるのです
こうした一連の作業には、自然のしくみに逆らわずに、むしろ寄り添うような姿勢が感じられました。耕さず、肥料も最小限にし、雑草や虫、鳥の存在とも共存しながら野菜を育てていく。それが佐倉流・有機栽培の大きな特徴であり、畑と自然が共に呼吸しているような風景がそこには広がっていました。
トウモロコシとエダマメの“あま〜い関係”
今回の放送で紹介されたメインテーマは、トウモロコシとエダマメの混植です。昨年の「トマトとバジル」のように、異なる野菜を一緒に植えることでお互いを助け合う「コンパニオンプランツ(共栄作物)」の考え方に基づいた組み合わせです。トウモロコシとエダマメは、それぞれの特性がうまく噛み合い、一緒に育てることでより良い環境が作られる理想的なペアとなります。
トウモロコシは成長の過程で多くの肥料成分、特に窒素を必要とする野菜です。一方で、エダマメはマメ科の植物で、根に共生する根粒菌が空気中の窒素を固定して土に供給する力を持っています。この性質を利用することで、トウモロコシにとっては自然に必要な栄養が得られるありがたい環境が生まれます。
・トウモロコシの根は旺盛に張り、周囲の土にたまった余分な栄養分を吸収する性質があります
・エダマメは、窒素が多すぎると葉や茎ばかりが成長してしまい、実がつかなくなる「つるボケ」になりやすいという弱点を持っています
・しかし、トウモロコシと一緒に植えることで、エダマメの根から放出される過剰な窒素をトウモロコシが吸収し、バランスが保たれるようになります
このように、お互いの特性が補い合う形になっており、まさに自然の中で生まれた“あま〜い関係”だといえます。
また、この組み合わせの利点は栄養バランスだけではありません。畝の端にエダマメを、中央にトウモロコシを植えることで、スペースを有効に使えるというのも大きなメリットです。限られた家庭菜園の区画でも、しっかり収穫を楽しむことができるため、初心者でも挑戦しやすく、育てる喜びと収穫の楽しさの両方を感じられる方法としてもおすすめされています。
・根粒菌が活動するためには土の温度や湿度も重要で、畑全体の環境づくりもポイントになります
・トウモロコシの葉がエダマメにほどよい日よけを与える効果もあり、乾燥や強い日差しから守ってくれる役割も果たします
このように、トウモロコシとエダマメは単なる“混植”の相手ではなく、互いを支え合いながら育つベストパートナー。自然の摂理に学んだ農法でありながら、家庭菜園にも応用しやすく、観察・学び・味わうの三拍子がそろった栽培法です。今回の放送を見て、このコンビを育ててみたいと感じた人も多いはずです。
まとめ:自然の力を借りて育てる喜び
『やさいの時間』の放送では、単なる育て方だけでなく、自然と向き合いながら野菜を育てる大切さが丁寧に紹介されました。植物や虫の動き、土の状態など、自然が教えてくれるタイミングやサインを感じながら進めていく畑仕事は、単なる作業ではなく、学びと発見にあふれた時間です。
これから家庭菜園を始めたい方、自然に寄り添った暮らしを楽しみたい方にとって、今回の放送は実践的で心に残るヒントが満載でした。
次回の放送も、佐倉朗夫さんがどのような野菜を紹介し、どんな工夫を見せてくれるのか楽しみです。
※番組内容は放送時点の情報に基づいており、変更される可能性があります。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

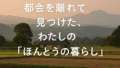
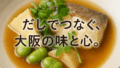
コメント