平安時代にも“終活ブーム”があった!?1000年前の人々が描いた「極楽への道」
私たちが今、「終活」という言葉を耳にするのは日常的なことになりました。遺言や葬儀の準備、エンディングノート、さらには心の整理まで——。でも、実はこの「死に向き合い、よりよく生きよう」という考え方が、1000年以上前の平安時代にすでにブームとして広がっていたのです。
2025年10月22日放送のNHK『歴史探偵』では、「平安の浄土信仰 “終活”ブームの謎を追え!」と題して、佐藤二朗、片山千恵子、小山聡子の3人が、その実態を探りました。藤原道長や後白河法皇ら、当時の貴族たちは何を恐れ、どんな希望を持って“終活”をしていたのでしょうか。
“阿弥陀様のお迎え”を信じた時代―命の最後に見る極楽
平安時代の人々は、臨終の瞬間に阿弥陀仏と二十五菩薩が迎えに来て、極楽浄土へ導いてくれると信じていました。その信仰を表す代表的な絵が『阿弥陀聖衆来迎図(あみだしょうじゅうらいごうず)』です。この絵には、臨終の人の枕元に阿弥陀仏が現れ、金色の糸を差し出している様子が描かれています。亡くなる人はその糸を握ることで、阿弥陀仏の導きによって極楽へ行けると考えられていました。
この“お迎え”を現実に再現する儀式が「迎講(むかえこう)」です。番組では、大阪の弘法寺で今も行われる迎講の様子が紹介されました。鎌倉時代に作られた仏像をそのまま使い、信者たちは念仏を唱えながら阿弥陀様の来迎を思い描きます。これこそが、平安時代の“イメージトレーニングによる終活”でした。
興味深いのは、当時の人々が「日常生活の中でも往生に備える」ことを意識していた点です。中には“鼻毛を抜いて心身を清める”という風習もあったといわれ、見た目の清潔ささえ“極楽往生”の準備の一つとされていました。貴族社会では“念仏サークル”のような集まりもあり、定期的に念仏を唱えて極楽をイメージする活動が行われていたのです。
平等院鳳凰堂―藤原頼通が託した「極楽のかたち」
平安時代の“終活ブーム”を象徴する建物といえば、やはり平等院鳳凰堂(びょうどういんほうおうどう)でしょう。建立したのは、藤原道長の息子である藤原頼通。彼がこの建物に込めたのは、極楽浄土そのものを地上に再現したいという願いでした。
鳳凰堂に安置される阿弥陀如来坐像は、優美な顔立ちで微笑みをたたえ、まるで“お迎え”の瞬間を表しています。その背後に描かれた壁画には、天から舞い降りる菩薩たちの姿。堂内全体が“極楽空間”として設計されているのです。
当時、人々は「釈迦が亡くなって1500年後に訪れる」と信じられた末法(まっぽう)の到来を恐れていました。釈迦の教えが弱まり、誰も救われなくなる——その始まりが1052年とされ、世の中は不安に包まれていました。飢饉、戦乱、火事など災いが続き、人々は現世の苦しみから逃れる“浄土信仰”に救いを求めたのです。
そんな中で頼通が建立した平等院は、宇治川を挟んで宇治上神社と向かい合っています。川を“この世とあの世の境界”と見立て、対岸に“極楽の宮殿”である鳳凰堂を置くという発想。沈みゆく夕陽を背に黄金色に輝く鳳凰堂を見た人々は、きっと「極楽は本当にある」と信じたことでしょう。
終活ブームの火付け役『往生要集』―源信が描いた“心の準備”
このブームを理論的に支えたのが、僧侶の源信(げんしん)です。彼が著した『往生要集(おうじょうようしゅう)』は、平安時代を代表する“往生マニュアル”。「どうすれば地獄を避け、極楽に行けるのか」を細かく記した本で、貴族から庶民まで広く読まれました。
特徴的なのは、冒頭部分に描かれた“地獄の恐ろしさ”です。血の池、針の山、火の海などの生々しい描写に、当時の読者は震え上がったといいます。しかしその恐怖こそが、「極楽に行くために生き方を正そう」という信仰を生み出しました。
宗教学者の釈徹宗氏は、「源信は地獄を見せつけることで“恐怖を与えたい”のではなく、心の修行を促した」と指摘しています。源信は若くして出家し、比叡山で修行を積みながらも、母の願いに応えようと懸命に生きました。彼にとって『往生要集』は、単なる宗教書ではなく“生き方の指南書”だったのです。
さらに源信は、“観想(かんそう)”という瞑想法を重視しました。仏や極楽の姿を心に思い浮かべ、そのイメージを明確にすることで心を清めるというものです。つまり、精神的な終活=“心の整え方”を説いたのです。
念仏と称名―庶民に広がった「声の終活」
とはいえ、“観想”は一部の修行僧しかできない高度な修行でした。そこで広まったのが、“阿弥陀仏の名前を唱えるだけで極楽に行ける”という**称名念仏(しょうみょうねんぶつ)**の考え方です。「南無阿弥陀仏」と声に出して唱えることで救われる——これが庶民にも広く浸透し、念仏を唱える人々が集まる“念仏サークル”のような集団も各地に誕生しました。
現代でいえば、「心を整えるマインドフルネス」や「瞑想会」のような存在です。彼らはただ死を恐れるのではなく、死を受け入れ、よりよく生きるための準備として念仏を唱えていたのです。
平安の“終活”が今に伝えるメッセージ
番組の最後で、小山聡子氏は次のように語りました。
「現代の終活は、生前整理や遺産分配など“物理的な側面”に偏りがちです。でも本来の終活は、心の整理、死をどう受け止めるかという“精神的な営み”でもあるのです。」
平安の人々が行っていた終活は、まさにこの“心の準備”でした。死を恐れるのではなく、死の先に希望を見出すこと。それは、現代の私たちが生きるヒントにもなります。
まとめ:1000年前の終活から学ぶ「生きる力」
この記事のポイントは次の3つです。
・平安時代にも「死に向き合う文化=終活ブーム」が存在した
・藤原頼通の平等院鳳凰堂は、極楽浄土を形にした建築だった
・源信の『往生要集』は、心の平穏を整える“精神的終活”の原点だった
1000年前の日本人は、死を恐れるだけではなく、死の先にある希望を信じていました。彼らの“終活”は、現代のように書類やお金を整理するだけではなく、「どう生き、どう旅立つか」を考える哲学的な行為だったのです。
現代を生きる私たちも、平安の人々のように、自分なりの“極楽”を思い描きながら、心を整えて生きていくことが大切かもしれません。
【ソース】
NHK総合『歴史探偵 平安の浄土信仰 “終活”ブームの謎を追え!』(2025年10月22日放送)
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


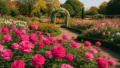
コメント