ゴジラ70年、科学と映画が解き明かす怪獣の魅力
あなたはなぜ『ゴジラ』が70年もの長きにわたって世界中の観客を魅了し続けているのか、考えたことはありますか?1954年の初代『ゴジラ』公開以来、その存在は単なる怪獣映画の枠を超え、日本文化を象徴するアイコンへと成長しました。放射能と核兵器の恐怖を背景に誕生したゴジラは、時代とともに意味を変えながらも、その迫力と普遍性を失わずに生き続けています。今回のNHK「歴史探偵」では、その“立ち姿”や“テーマ曲”を最新の科学技術で徹底的に分析。さらに山崎貴監督がゴジラの本質的な魅力について語り尽くします。この記事では番組内容を事前に整理しつつ、映画評論家の視点で深く掘り下げていきます。
ゴジラ誕生のきっかけは水爆実験と被爆事件
1954年に公開された第1作『ゴジラ』は、太平洋上で行われたアメリカの水爆実験と、それによって被害を受けた第五福竜丸事件に着想を得て誕生しました。冷戦下の核実験は日本に大きな不安をもたらし、被爆国としての記憶と恐怖が社会全体を覆っていました。その時代背景を受け、プロデューサーの田中友幸は「人類がつくった水爆に人類が復讐される」というテーマを据え、映画の根幹に据えました。
監督の本多猪四郎は戦地に赴いた経験を持ち、戦争での犠牲者の姿を作品に投影しました。劇中で避難所に逃げ込む人々や、親を失った子どもの姿は、その時代の現実と重なります。観客は怪獣の破壊をただのフィクションではなく、「戦争や核の恐怖」の象徴として受け止めたのです。
円谷英二と特撮表現の革新
ゴジラを映画史に残る存在に押し上げたのが、特撮の神様と呼ばれる円谷英二でした。彼は当時主流だったコマ撮りアニメーションではなく、100kgを超える着ぐるみを人間が着て演じる「スーツアクター方式」を採用しました。重厚な質感を出すため、撮影ではハイスピードカメラを用い、スロー再生によって巨大怪獣の重さを表現しました。
この試みは当時の映画界において大胆でありながら、見事に成功。破壊される街並みや火炎放射のシーンは、観客に強烈なリアリティを与えました。後に世界の映画人たちがこの手法を研究し、特撮やモンスター映画のスタンダードになったのです。
ゴジラの姿に込められたメッセージ
番組に出演した評論家の清水節は「ゴジラの顔はキノコ雲のような形をしており、その造形の中にメッセージ性が込められている」と語りました。白目や二足歩行など、人間的な要素を備えたデザインは、観客が感情移入しやすいよう工夫されています。金沢工業大学の渡邊教授による調査でも、「恐怖と力強さのなかに人間らしさを感じる」という回答が多く寄せられました。
ゴジラは人間を襲う存在である一方、水爆実験によって目覚めさせられた「被害者」として描かれています。その二面性こそが、多くの人々に複雑な感情を呼び起こしてきた理由なのです。
音楽がつくるゴジラの恐怖
ゴジラ映画を語る上で欠かせないのが音楽です。作曲家の伊福部昭は、戦時中に徴用され、放射線を浴びた経験を持っています。彼が作曲した『ゴジラのテーマ』は、不安と圧倒感を同時に感じさせる独特のサウンドで知られています。
重低音を響かせるコントラファゴットは当時国内に2つしかなく、さらに高音を担当するはずのバイオリンを低音で奏でるという異例の手法を用いました。この結果、生まれた音色はノイズを含み、押しつぶしたような重苦しさを伴い、まさに怪獣の存在感を音楽で表現することに成功しました。
また、桐朋女子中学校・高等学校の生徒600人が参加した合唱シーンは、破壊されゆく街の映像と重なり、観客の心を強く揺さぶりました。
ゴジラが映してきた社会の姿
ゴジラ映画は70年間、時代ごとの社会不安を反映し続けてきました。
・『ゴジラ対ヘドラ』(1971年):高度経済成長期の公害問題を怪獣に象徴化
・『ゴジラ』(1984年):冷戦期の核兵器使用の是非を問い、非核三原則を強調
・『シン・ゴジラ』(2016年):東日本大震災や福島第一原発事故を彷彿とさせる物語構成
このように、ゴジラは常に「その時代の人々が直面している不安」を怪獣という形で表してきました。
国際社会とゴジラ
アメリカで公開された『GODZILLA』は、日本版から核への批判的な台詞が削除されました。当時の米ソ間の核競争を背景に、政治的な検閲が働いたと考えられています。2014年のハリウッド版では、空母や戦闘機の撮影許可を得る条件として「原爆批判的な要素の削除」が求められたといいます。わずかに残せたのは「被爆した父親の時計を見せるシーン」だけでした。
この事実からも、ゴジラという作品が政治・文化的な意味を持つ存在であることがわかります。
『ゴジラ-1.0』が示した現代の共感
2023年に公開された『ゴジラ-1.0』は、敗戦直後の日本を舞台に描かれ、アメリカでも大ヒット。日本の実写映画として興行収入1位を記録しました。監督の山崎貴は「アメリカで受け入れられるか不安だった」と振り返りますが、観客から「我々は今、本当に戦争をしている国だから共感できる」という声が寄せられたといいます。
つまりゴジラは、核や戦争といった普遍的テーマを通じて、国境を超えて人々の心に届いたのです。
ゴジラが私たちに投げかける問い
評論家の清水節は「ゴジラは黙して語らないが、その存在自体が我々に警鐘を鳴らす」と語りました。70年間、ゴジラは社会や人間が抱える矛盾や不安を映し出し続けてきました。破壊者でありながら被害者でもある存在。それは人類自身の姿を投影した鏡でもあるのです。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
-
ゴジラは1954年の誕生以来、核と戦争の記憶を映す象徴である。
-
円谷英二や伊福部昭の革新が怪獣映画を芸術的表現に高めた。
-
各時代の社会不安を反映し、国際社会にも影響を与え続けている。
ゴジラを観ることは、単なる娯楽映画の鑑賞ではなく、時代の歴史や人類の矛盾に向き合う体験です。次にスクリーンで咆哮を耳にするとき、その背後にある「声なきメッセージ」にぜひ耳を澄ませてみてください。
ソース:
NHK 歴史探偵 ゴジラ 特集
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


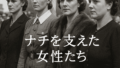
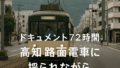
コメント