加賀百万石 前田家三代の闘い
2025年7月9日(水)NHK総合で放送される「歴史探偵」は、「加賀百万石 前田家三代の闘い」がテーマです。戦国の世から江戸時代へ、加賀藩がどのようにして“百万石”という巨大な力を築き、維持してきたのか。その鍵を握るのが、前田利家・利長・利常という三人の当主たちの知恵と行動でした。今回はその歴史に迫る内容です。
加賀百万石を築いた初代・前田利家の強さと知恵

前田利家は、もともと家督を継ぐ予定ではない家の四男でした。それでも武勇で名をあげ、信長や秀吉に認められて、少しずつ立場を上げていきました。彼の武器は、なんと約6メートルもの長槍。この長さの槍を使いこなすには、ただ力があるだけではなく、技術と身体能力が必要でした。
しかし利家は、武勇だけの人ではありませんでした。そろばんを持って戦場に立ち、自分で兵糧の計算をしていたというエピソードも残っています。戦で人を動かすためには、食べ物や物資の管理がとても重要です。そこにまで目を配っていたところに、利家の冷静さと実務力が見えます。
-
信長のもとで活躍し、その後秀吉に仕える
-
本能寺の変のあとは柴田勝家に従いながらも、最終的には秀吉の信頼を得る
-
能登で検地を行い、正確に石高を測ることで、秀吉に評価される
-
賤ヶ岳の戦い後に、加賀・能登・越中の三国を治める八十万石の大名となる
また利家は、ただの戦上手ではなく政治の場でも信頼される存在でした。秀吉が行おうとした「朝鮮出兵」に対して、家康と一緒に思いとどまるように説得を試みたこともありました。これは、戦の規模や結果を見通せる判断力があったからです。そして、政権を支える役職である「五大老」にも選ばれ、豊臣政権の安定に貢献しました。
そんな利家を支えたのが、妻のまつです。後に芳春院と呼ばれるこの女性は、夫を内助の功で支えただけでなく、家の政治的な動きにも関わっていたといわれています。利家が亡くなったあとも、彼女は江戸へ赴き、徳川家康に前田家の誠意を伝える役目も果たしました。
前田利家は、強くて頭もよく、家族の絆も大切にした人物です。彼の存在がなければ、加賀百万石の繁栄はなかったと言えるでしょう。
二代目・利長が導いた「百万石」への道
前田利長は、初代・利家が亡くなったあと家督を継ぎ、加賀藩をさらに大きく成長させました。戦場では1メートルを超える巨大な兜をかぶっていたことで有名で、その姿は人々の記憶に残るほど印象的でしたが、性格はとても繊細で、人への気配りができる優しい人物でもありました。
たとえば、農民から瓜をもらったときには、すぐに感謝の手紙を書いて送ったという話があります。これは、小さな出来事でも大切に思い、人と人とのつながりを大事にしていた証です。そんな利長だからこそ、家臣や領民たちにも信頼されていたのでしょう。
-
父・利家の死後、すぐに五大老のひとりに任命される
-
徳川家康との関係悪化を受け、何度も家臣を派遣して説明し誠意を示す
-
母・まつを江戸に人質として送り、前田家が敵意を持っていないことを証明
-
関ヶ原の戦いでは本戦に参加せずとも、西軍との戦いを先に始めたことで家康から高く評価される
このような対応のおかげで、利長は家康の信頼を取り戻すことに成功しました。戦いの後、加賀藩は20万石の加増を受け、石高が100万石を超える「加賀百万石」が完成しました。これは前田家の努力と外交の成果です。
そして利長は、自らの地位にしがみつくことなく、弟の利常に早い段階で家督を譲るという決断をします。これにより、徳川政権に対して「前田家は新しい体制に従っていく姿勢があります」と強く印象づけることができました。
このように、利長は武勇だけではなく、周囲との関係や将来の安定を考えた行動を積み重ねていきました。その姿勢が、加賀藩を「百万石」の大藩へと導いた大きな理由なのです。
三代目・利常が守った百万石の繁栄
三代目の当主・前田利常は、戦の時代から平和な江戸時代へと移り変わる中で、加賀百万石を維持しながら発展させた人物です。前田家が今の石川県や富山県にまたがる大きな領地を治めていくうえで、利常は武力よりも知恵と工夫で藩を支えました。
特に注目されたのが、一向宗との対立を和らげる対策です。この地域では、武士と宗教勢力が衝突することがたびたびありました。そこで利常は、農民の中でも信頼できる人を“十村(とむら)”に選び、年貢の管理や村の揉め事の解決を任せる仕組みを整えました。地元の人が地元の問題を解決できるようにすることで、不満がたまるのを防ぎ、一揆が起こりにくい環境をつくったのです。
-
一向宗との摩擦を避けるために“十村制度”を整備
-
農民にお金を貸して農具を買わせる支援
-
新しい田んぼの開発(新田開発)を推進し、米の生産量を増やす政策を実行
これらの取り組みによって、農村は豊かになり、加賀藩の経済は安定しました。また、こうした農業政策だけでなく、文化面でも大きな功績を残しています。
利常の時代には、現在でも広く知られる九谷焼や加賀友禅、加賀蒔絵といった美しい工芸品が生まれ、加賀の文化を全国に知らしめました。これらは武家だけでなく、町人や農民たちの暮らしにも彩りを与えるもので、文化の力で藩を豊かにするという利常の姿勢が表れています。
このように、前田利常は、ただ加賀百万石を「守った」だけでなく、人々の暮らしを支え、文化を育て、藩の未来を明るくした名君だったといえるでしょう。
放送情報
番組名:歴史探偵
放送日:2025年7月9日(水)
放送時間:22:00~22:45
放送局:NHK総合
出演者:佐藤二朗、片山千恵子(アナウンサー)、河合敦(歴史学者)
関連情報:
NHK 番組公式サイト(https://www.nhk.jp/p/rekishi-tantei/ts/9X5VJ2RW1M/)
NHK番組表(https://www.nhk.or.jp/tv/)
NHKプレスリリースより構成(https://www.nhk.or.jp/info/)
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

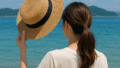
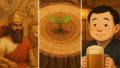
コメント