若冲と応挙が描いた奇跡の屏風と画風の秘密
2025年7月23日放送のNHK「歴史探偵」では、日本美術史において特に高い人気と評価を誇る2人の絵師、伊藤若冲と円山応挙を取り上げました。今回の特集は、昨年発見されたという2人の合作屏風にまつわる貴重な情報と、それぞれの画風や技術、そして生き方の違いを掘り下げる内容でした。単なる芸術紹介にとどまらず、江戸時代の京都という芸術文化の土壌や、2人が残した精神的な軌跡にまで踏み込んだ構成となっていました。
代表作から見える2人の方向性の違い
番組ではまず、若冲の「動植綵絵 南天雄鶏図」と、応挙の「雪松図屏風」という国宝を紹介。若冲は写実性と幻想的表現の融合が特徴で、南天の枝に止まる鶏一羽の描写にも命が吹き込まれたような存在感がありました。一方で、応挙は見る者に奥行きを感じさせる空間表現に優れており、紙の上にまるで現実の風景が浮かび上がるような錯覚を生み出しています。この対照的な表現手法が、後の合作にも絶妙なバランスで反映されていました。
合作が生まれた背景と発見の経緯
番組の中盤で紹介されたのは、大阪中之島美術館に所蔵されている合作屏風です。2024年に「日本美術の鉱脈展」で初めて公開され、専門家の調査により、若冲と応挙がともに筆を入れたことがわかりました。絵の中には、応挙の得意とする柔らかい光と空気感に包まれた風景、そして若冲ならではの緻密で鮮やかな動植物の描写が共存しており、2人の世界が融合した貴重な一作となっています。
美術史家・山下裕二氏は、若冲の作風を「極端にリアルだが、あえて現実離れした要素も交えている」と語り、応挙については「透視図法や陰影の使い方で、平面の絵を立体的に見せることが得意だった」と分析していました。展示されていた「梅鯉図屏風」「竹鶏図屏風」などと並ぶことで、合作の希少性と芸術的な完成度がより際立ちます。
絵師のルーツと育った環境に見る違い
伊藤若冲と円山応挙は、いずれも京都を拠点に活動した絵師です。若冲は中京区・錦市場近くの青物問屋の家に生まれ、家業を継ぎながら絵に親しみました。特に鶏を飼って日々写生を重ねたことで、細密描写の力を養いました。一方、応挙の生家も京都にあり、周囲には呉春、池大雅、与謝蕪村など、文化・芸術面で活躍する人物が多く集まっていました。
絵の需要が高かった京都の環境
江戸時代、京都には多くの寺社や大商人がおり、屏風や襖絵など絵画の注文が絶えず、絵師にとっては活躍の場が多く存在していました。三井家が呉服業で成功した際、下絵を絵師たちに依頼することで画才を磨く場が広がり、京都は自然と絵師が集まる土地となっていきました。
さらに、長崎から入った海外の美術品や学問は、京都を通じて全国へ広まるルートをたどっていたため、最新の知識や美意識が京都に集中していたのです。若冲も、中国の画家・沈南蘋の影響を強く受け、写実技術をさらに高めるために、日常的に動植物を観察・研究していたことが分かります。
本草学の流行と写生技術の向上
江戸中期には、本草学と呼ばれる自然科学の分野が流行し、動植物の形態や特徴を正確に記録することが求められるようになりました。応挙は、この流れに乗って友人の図鑑制作を支援し、より精密な写生に取り組んだとされています。香川県立東山魁夷せとうち美術館に残る作品からも、その努力の跡が見て取れます。
応挙が描いた3次元の世界と空間演出
円山応挙の最大の特徴は、平面に奥行きと立体感をもたらす空間表現にあります。日本に伝わった覗眼鏡の技術や、ヨーロッパの透視図法に着想を得て、応挙は京都の風景をモチーフに数々の作品を描きました。
実例に見る応挙の画力
「三十三間堂通し矢図」では、縦に伸びる柱の列や人々の動きを、遠近法を用いて巧みに表現しています。さらに「淀川両岸図巻」では、左右に広がる景観の中で奥行きを演出し、まるで現地に立って風景を眺めているかのような臨場感を生み出しています。
十文字学園女子大学の樋口一貴教授は「応挙は、あくまで平面という限界の中で、3次元の世界を再構成しようとした」と述べており、その努力は神戸市立博物館などに残る作品群でも確認できます。
応挙の最高傑作・大乗寺の間
応挙の空間表現が最も顕著に現れているのが、兵庫・大乗寺にある3部屋に描かれた40面以上の襖絵です。それぞれの部屋では、使用する金箔に含まれる銀や銅の配合を調整しており、部屋ごとの光の加減や雰囲気に変化を持たせる工夫がなされています。これはダ・ヴィンチの「遠景を青で描いて奥行きを演出する手法」とも似ており、応挙が自らの技術でその効果を実現していたことがわかります。
若冲の色彩と裏彩色という独自表現
伊藤若冲は、色の使い方にも強いこだわりを持っていました。特に注目されたのが、**絹の裏から色を差す「裏彩色」**という技法です。これは表面からでは出せない柔らかさと透明感が特徴で、若冲の作品に独特の神秘性と深みを与えています。
若冲の自由な発想が生んだ表現
「動植綵絵 老松白鳳図」では、色と構図が極めて精密に調和しており、まさに若冲の画業の集大成ともいえる仕上がりです。さらに「果蔬涅槃図」では、釈迦の入滅の場面を野菜や果物で描くというユニークな発想が紹介され、日常的な素材にも深い宗教的な意味を込めることができるという、若冲の感性の豊かさが伝わってきました。
晩年の若冲と名乗りの変化「米斗翁」
番組の終盤では、若冲が晩年に過ごした石峰寺にスポットが当てられました。ここには、若冲が彫ったとされる500体以上の羅漢像が残されています。若冲はこの時期、「米斗翁」と名乗り、米一斗で絵を提供するなど、質素な生活を送っていたと伝えられています。
売茶翁に学んだ人生観
禅僧の売茶翁のように、若冲は名声や富から距離を置き、心の豊かさや信念を重視する生き方に傾いていきました。萬福寺には、若冲が描いた売茶翁の肖像画が10点以上残っており、その思想に強く惹かれていたことがわかります。
スタジオ展示と日本美術の未来への継承
スタジオには、今回発見された合作屏風の複製が登場し、出演者たちがその技巧と表現を鑑賞しました。応挙は後進の育成に力を注ぎ、美術教育の礎を築いた人物であり、京都市立芸術大学の前身となる美術学校も彼の影響を受けて設立されました。
一方、若冲の画風はあまりに独特だったため、後継者は現れませんでした。それでも彼の作品は今も世界中で高く評価されており、日本の美意識を象徴する存在として語り継がれています。
今回の「歴史探偵」は、単なる美術紹介を超え、生き方や価値観をも絵に込めた2人の画家の姿を描き出した感動的な特集となりました。2人の芸術がこれからも日本文化を照らし続けることを、多くの視聴者が実感したに違いありません。
中之島美術館で合作屏風を楽しもう

ここからは、私からの提案です。2025年の夏、大阪中之島美術館では、若冲と応挙による幻の合作屏風を中心とした特別展「日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!」が開催されています。会場では、江戸時代の天才絵師たちが残した貴重な作品を、科学の目と現代の技術で紐解きながら鑑賞することができます。展覧会を実際に楽しむための情報を、ここで詳しくご紹介します。
展示期間・時間
「日本美術の鉱脈展」は2025年6月21日から8月31日まで、大阪中之島美術館の4階展示室で開かれています。開館時間は午前10時から午後5時まで(入場は午後4時30分まで)で、金曜日・土曜日・祝前日には午後7時まで延長される特別なスケジュールもあります(対象期間は7月18日〜8月30日)。
ただし、毎週月曜日は休館日となっており、祝日にあたる場合は開館されます。7月22日(月)は例外的に休館日となっていますので、来館前に公式サイトでカレンダーを確認するのが安心です。
観覧料・チケット
観覧料は一般1,800円(前売・団体は1,600円)、高校生・大学生は1,500円、小中学生は500円となっています。チケットは中之島美術館の公式サイトからのオンライン事前購入ができ、混雑時もスムーズに入場できます。割引料金も適用されるため、事前購入がとてもおすすめです。
| 区分 | 料金(当日) | 前売・団体 |
|---|---|---|
| 一般 | 1,800円 | 1,600円 |
| 高校・大学生 | 1,500円 | 同左 |
| 小中学生 | 500円 | 同左 |
アクセス
大阪中之島美術館は、公共交通機関でのアクセスが非常に便利です。主なアクセス方法は以下の通りです:
-
京阪中之島線「渡辺橋駅」2番出口から徒歩5分
-
地下鉄四つ橋線「肥後橋駅」4番出口から徒歩10分
-
JR東西線「新福島駅」および阪神「福島駅」からも徒歩約10分
-
JR大阪駅からは徒歩でもアクセス可能ですが、市バス(53・75系統)で「田蓑橋」下車後すぐのルートも利用できます。
美術館には駐車場がないため、公共交通機関の利用が推奨されています。
鑑賞のポイント
会場に入るとすぐ、今回の目玉である若冲と応挙の合作屏風が堂々と展示されています。若冲の極彩色の竹と鶏、応挙の写実的な梅と鯉が左右に並び、それぞれの特徴がはっきりと感じられる構成になっています。絵の前に立つと、まるで2人の技が会話しているような空間が広がります。
展示室内には、赤外線カメラによる解析画像や3Dスキャンの構造分析結果をまとめた解説パネルが複数設置されており、作品の裏側に隠された技法を視覚的に学ぶことができます。
また、俳優・井浦新さんがナレーションを担当した音声ガイド(レンタル料650円)も用意されており、耳からも絵の世界に入り込める工夫がされています。専門的な内容もやさしい言葉で説明されているため、子どもから大人まで楽しめる内容になっています。
さらに、会期中にはギャラリートークや親子向けワークショップも予定されており、展示を見るだけでなく、実際に体験しながら理解を深めることができます。
参考ソース
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

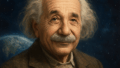

コメント