網膜の病気を見逃さないために!今日からできるセルフチェック法
最近、スマホやパソコンを見る時間が増えて「なんだか目が疲れる」「視界がゆがむ気がする」と感じたことはありませんか?それ、もしかすると“網膜の病気”のサインかもしれません。
年齢とともに増える加齢黄斑変性や、突然視野が欠ける網膜剥離など、放っておくと失明の危険もある病気です。
でも心配しすぎる必要はありません。早期発見と早期治療で進行を防ぐことができるのです。
この記事では、2025年10月22日放送のNHK『きょうの健康』で紹介された「目のセルフチェック法」をわかりやすく解説します。今日からすぐにできるチェック方法を知って、自分の目を守りましょう。
片方ずつチェック!簡単セルフテストのやり方
番組で講師を務めた上尾中央総合病院 特任副院長・飯田知弘先生によると、網膜の異常は両目で見ていると気づきにくいのが特徴です。右目の視野に欠けがあっても、左目が自動的に補ってしまうため、異常を感じにくいのです。そのため、日常の中で「片方ずつの見え方を確かめる」ことが、早期発見の大きな鍵になります。
番組では、キャスターの大川悠介さんが実際に片目を手で覆いながらチェックする方法を実演しました。特別な道具もいらず、場所を選ばずにできる簡単な方法です。
やり方は次の3ステップです。
- 片方の目を手で軽く覆う
- もう片方の目で周囲のものを見渡す
- 文字や線がゆがんでいないか、見えにくい部分がないか確認する
番組の画面下には「チェック① 自分の周りにあるもの」と大きく表示されていました。これは、日常の中にある風景や物の見え方を確認することを意味しています。
例えば、テレビの枠、カーテンの縦じま、棚のラインなどを見て、曲がって見える・ぼやけている・一部が欠けているなどの変化がないかをチェックします。こうした“わずかな違和感”が、実は網膜の病気の初期サインであることも少なくありません。
このチェックを毎日1回、1分だけでも行うことで、自分の目の変化に早く気づくことができます。特に40代以降の方や、強い近視を持つ方は、網膜の病気が起こりやすい傾向があるため、習慣化することが大切です。
また、文字や線のゆがみをより正確に確認したい場合は、眼科でも使われている「アムスラーグリッド」という格子状のシートを活用するのも有効です。インターネット上で無料配布されており、自宅で印刷して使うこともできます。
見え方の違和感を放置すると、気づかぬうちに病気が進行してしまうこともあります。たった1分のチェックが、視力を守る第一歩になります。
見逃さないで!網膜の病気のサインとは
番組では、網膜に起こる代表的な3つの病気が紹介されました。いずれも見え方に異常を感じる症状が特徴で、進行すると失明につながる危険性があります。
まず一つ目は網膜剥離(もうまくはくり)です。視野の一部が欠けたり、まるでカーテンがかかったように見えるのが典型的な症状です。原因としては、強い近視、加齢、外傷などで網膜がはがれてしまうことが多く、放置すると短期間で視力を失う危険もあります。視界に黒い影や飛蚊症(ひぶんしょう)が急に増えた場合は要注意です。
二つ目は黄斑円孔(おうはんえんこう)です。網膜の中心にある黄斑部が裂け、物がゆがんで見えたり、中心がぼやけるようになります。本や新聞を読むときに文字の一部が欠けて見えることもあります。主に加齢によって硝子体が網膜を引っ張ることで発生しますが、手術で回復が見込める場合もあり、早期発見がとても重要です。
三つ目は加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい)です。これは中高年に多く、視野の真ん中が暗く見える・色の区別がつきにくいといった症状が現れます。欧米では失明原因の上位にあり、日本でも患者数が増加しています。特に喫煙や高血圧、紫外線の影響がリスクを高めるといわれています。治療には抗VEGF薬の注射やレーザー治療などが用いられますが、進行してしまうと視力の回復は難しくなります。
番組ではキャスターの岩田まこ都さんが「ちょっとした違和感を軽く見てはいけない」とコメントしていました。多くの患者が「気づいたときにはすでに進行していた」と話すように、初期症状は痛みもなく、自覚しづらいのが特徴です。
目の健康を守る第一歩は、“おかしいな”と思った瞬間に行動すること。違和感を感じたら放置せず、できるだけ早く眼科で検査を受けることが大切です。毎日のセルフチェックに加え、年に一度の定期検診を続けることで、見え方の変化にいち早く気づくことができます。
早期発見がカギ!気づいたらすぐ眼科へ
番組では、異常を感じたらためらわずに眼科を受診することの重要性が強く呼びかけられていました。網膜の病気の中には、ほんの数日の遅れで視力が取り戻せなくなるほど進行が早いものもあります。「少し様子を見よう」と考えてしまうことで、治療のタイミングを逃してしまうケースは少なくありません。
番組に登場した飯田知弘先生は、「治療のタイミングが早ければ早いほど、視力の回復が見込める」と明言しました。特に、初期の段階で発見できれば、治療後も日常生活にほとんど支障をきたさずに済む場合もあるといいます。逆に、進行してからの受診では、網膜や視神経に永久的なダメージが残ってしまうこともあるため、早期行動が何より大切です。
また、糖尿病や高血圧などの持病を持つ人は、血管の状態が目にも影響しやすく、網膜の毛細血管が傷つきやすい傾向にあります。飯田先生は、こうした生活習慣病を抱える人ほど定期的な眼底検査を受ける必要があると説明しました。特に糖尿病では、進行すると糖尿病網膜症を引き起こすリスクも高く、放置すれば失明に至る可能性もあります。
さらに、近年では医療技術が大きく進化しています。AIを活用した網膜スキャンや、OCT(光干渉断層計)という機器を用いた検査により、網膜の構造をミクロン単位で立体的に解析できるようになっています。これにより、肉眼では見つけにくい初期の異常を画像データで正確に検出することが可能になりました。
こうした最新技術を取り入れた検査を定期的に受けることで、わずかな見え方の変化にもいち早く気づくことができます。特に50代以降の方や、強度近視の方、家族に眼の病気がある方は、年1回の検査を習慣にすることが勧められています。
たとえ今は異常を感じていなくても、「見え方の変化を自分で確かめ、医師の目で確認してもらう」ことが、将来の視力を守る一番の近道です。
まとめ:今日からできる「目の守り方」
この記事のポイントは次の3つです。
・網膜の病気は、両目で見ていると気づきにくい
・片方の目ずつ「周りのものの見え方」を毎日チェックする
・少しでも異常を感じたら、すぐに眼科を受診する
目は一生の財産です。
見え方の変化は、身体が発する“最初のSOS”かもしれません。
今日から1分、片目チェックを習慣にして、未来の自分の視界を守りましょう。
ソース:NHK『きょうの健康 網膜を守る!目の最新治療 必見!早期発見のためのセルフチェック』(2025年10月22日放送)
https://www.nhk.jp/p/kyounoryouri/
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

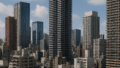

コメント