後醍醐天皇と南朝の激動の生涯をたどる特集
2025年6月11日放送のNHK総合「歴史探偵」では、鎌倉幕府の滅亡を導いた後醍醐天皇を特集しました。配流、脱出、倒幕、そして南北朝分裂から後南朝の影まで、波乱に満ちた生涯とその後を、最新の研究や貴重な資料とともに掘り下げました。後醍醐天皇が持っていた「時代を動かす意思の力」に焦点をあて、懐良親王や自天王といった後継者の動きも紹介されました。
二度の倒幕計画と隠岐への配流、そして奇跡の脱出

後醍醐天皇は、当時の政治の中心であった鎌倉幕府を倒そうと2度の計画を立てますが、いずれも失敗に終わり、45歳で隠岐の島に流されました。彼が属する大覚寺統と、もう一方の持明院統は交代で皇位を継いでいましたが、その選定権は幕府にありました。後醍醐天皇は、自らの系統が継続して皇位を保つためには、幕府そのものの存在を終わらせる必要があったのです。
隠岐では粗末な御所に住まわされ、常に監視下での生活を強いられていました。しかし、島民の協力により密かに脱出。鳥取の港へとたどり着いた後、幕府の追手から匿ってくれた人々に対して、天皇は感謝の証として名字を授けたと伝えられています。
脱出後、天皇は中国地方の船上山に拠点を築き、そこに約3ヶ月籠もって戦いました。ここで出された天皇の命令を記した文書「綸旨」が、各地の武士たちの心を動かし、多くが倒幕の戦いに参加しました。こうして、幕府は滅び、後醍醐天皇の理想が実現へと進んでいきます。
建武の新政と理想の崩壊、足利尊氏の反旗

倒幕に成功した後醍醐天皇は、建武の新政という新しい政治体制をスタートさせます。しかし、恩賞や土地分配をめぐる武士たちの不満は急速に高まりました。これにより、かつての協力者であった足利尊氏が反旗を翻し、再び戦乱の時代へと突入します。
天皇は吉野へと逃れ、ここに南朝を構えます。京都にいる北朝の天皇との間で「南北朝時代」が始まりました。この時代は、皇位をめぐる対立が続き、日本中が分裂状態になります。
懐良親王の九州遠征と戦い抜いた半生
後醍醐天皇の皇子である懐良親王(かねよししんのう)は、10歳の若さで南朝の代表として九州に派遣されました。九州には南朝の拠点がなかったため、最初は海賊たちの庇護を受けながら活動を続けていました。
父の崩御後も、親王は各地を転戦します。
・忽那島(くつなしま)で3年間身を寄せる
・薩摩国での内戦に5年半を費やす
・肥後国では13年半にも及ぶ戦いに参加
1359年、九州で「筑後川の戦い」が起き、懐良親王は戦場の最前線に立ち、深手を負いながらも兵を鼓舞して戦い抜きました。その2年後には太宰府を攻略し、九州を平定。南朝にとっての大きな勝利となりました。
南北朝合一と約束の反故
1392年には、南北朝が一時的に合一されます。これは、南朝の後亀山天皇が北朝の後小松天皇に三種の神器を譲渡することで成立しました。両者の間では「両統迭立(りょうとうてつりつ)」という、持明院統と大覚寺統が交代で皇位を継ぐ約束が交わされました。
しかしこの約束は守られることなく、以後は北朝が皇位を独占。後亀山天皇は再び吉野に戻り、南朝は地下へと潜っていきます。
奈良・川上村に受け継がれた後南朝の記憶
奈良県の川上村には、後南朝の武士たちが落ち延びてきたという伝承が今も残っています。この村では、毎年2月5日に「朝拝式」という儀式が行われますが、かつては568年間も一般には公開されずに続けられていたものでした。
1443年には、後南朝の軍勢が北朝の天皇がいる御所を襲撃し、三種の神器のうちの1つを奪取。この事件の後、幕府は刺客を送り込みます。村人が後南朝に関する情報を漏らしたことで、「自天王」と呼ばれる皇族が殺害されてしまいました。
この自天王は、後醍醐天皇の子孫とされ、村ではその死を悼んで朝拝式が行われています。参加者が榊の葉を口にくわえるのは、「自天王を守れなかったことへの自戒」を意味していると伝えられています。
応仁の乱と再び現れた後南朝の影
応仁の乱の最中、西軍は「西陣南帝」と呼ばれる人物を擁立しました。これは東軍が天皇や上皇を支持に立てたことに対抗する意味を持ちます。つまり、後南朝の血筋が再び政治の舞台に登場したのです。
番組では、こうした歴史を辿るために、秋鹿真人アナウンサーが険しい山道を歩いて取材を敢行しました。スタジオでは後醍醐天皇の強い信念と求心力が改めて評価され、南朝・後南朝に人生を賭けた人々の姿が浮き彫りにされました。
まとめ
今回の「歴史探偵」は、後醍醐天皇が時代にどう立ち向かい、どのように未来に影響を与えたかを深く掘り下げた回でした。隠岐からの脱出、船上山での抵抗、建武の新政の挫折、吉野での南朝樹立、そして懐良親王や自天王といった後継者たちの戦いまで、1人の天皇が引き起こした大きな歴史のうねりが、現代にも伝わっていることを丁寧に紹介していました。
特に、地方に残る南朝の記憶や儀式が、今も静かに受け継がれていることから、歴史は書物だけでなく人々の心の中にも生きているということが実感できる内容でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


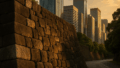
コメント