青山通りはなぜステキ?道のルーツに秘密あり
2025年6月14日放送の『ブラタモリ』(NHK総合)では、東京の中でも特に洗練された印象を持つ「青山通り」の秘密に迫りました。赤坂・青山・表参道という一等地を通るこの道は、見た目の美しさだけでなく、400年もの歴史を持つ江戸の街道「大山街道」にルーツがあるといいます。今回は、タモリさんと佐藤茉那アナウンサーが、三宅坂からスタートして赤坂、青山、渋谷へと歩きながら、青山通りに隠された過去を探っていきました。
【ブラタモリ】青山通りの秘密!赤坂・表参道の名坂と青山家の歴史に迫る|2025年6月21日放送
江戸時代から続く道の起点・三宅坂

番組は、現在の皇居の南側に位置する三宅坂からスタートしました。この場所は、今でこそ参議院議長公邸がある落ち着いたエリアですが、江戸時代には江戸城の外堀にあたる重要な地点でした。坂の途中には、かつての城の一部を思わせる高く積み上げられた石垣が今も残っており、その姿が過去をしっかりと伝えています。
この石垣がある場所は、もともと松平家の大名屋敷があった跡地です。江戸時代には、このように城のそばに大名の屋敷が並ぶことで、幕府に対する忠誠の証とされていました。
石垣の積み方は、「切り込み接ぎ(きりこみはぎ)」と呼ばれる技法です。この技法の特徴は、以下の通りです。
-
石を四角形に近い形に加工して使う
-
隙間ができないようにぴったりと組み合わせる
-
加工の精度が高く、目地(継ぎ目)が目立たない
-
積み上げた後も崩れにくく、風雨に強い構造
こうした丁寧な石積みは、単なる装飾ではなく、防御力のある構造としての役割を持っていました。重たい石を一つひとつ削って合わせる作業は、多くの人の手を必要とし、時間も技術も求められました。
また、三宅坂は地形的にも重要な場所です。坂道の上にあることで、城を守る防衛拠点の一部として機能していました。坂の下から登ってくる敵を上から見下ろせる位置関係は、戦いの時代において非常に有利な条件でした。
現在の三宅坂には、こうした歴史の痕跡が地形や建物にしっかりと残っているのが特徴です。何気なく通り過ぎてしまう場所かもしれませんが、実は江戸時代の政治と防御の要所だったのです。地名に「坂」が残っているのも、こうした地形の記憶を今に伝えている証しといえます。
赤坂御門と黒田忠之の歴史

赤坂御門は、江戸城の外堀を守るための城門のひとつであり、その中でも特に厳重な構造を持つ防御拠点でした。この御門が位置する場所は、現在の東京都千代田区の一角で、かつては江戸と郊外を結ぶ出入り口として機能していました。
この赤坂御門を築いたのは、福岡藩の藩主・黒田忠之です。彼は江戸幕府の命により、藩の総力を注いで約400年前にこの門を完成させたとされています。当時、江戸城の守りをいかに固めるかが重要視されており、赤坂御門もその戦略の一環として計画されたものでした。
御門には10メートルを超える高さの石垣が築かれており、この石垣が特に注目されるポイントです。
-
石垣は江戸時代の防御建築の粋を集めた構造
-
高さが10m以上もあり、上から敵を見下ろせる作り
-
現在でも形を保って残っている
このような高さと頑丈さは、当時の建築技術の高さを示しており、単なる門ではなく戦いを想定した要塞のような役割を果たしていたことがわかります。
現在では、この場所の上を首都高速道路が通っています。近代の都市開発によって姿は大きく変わりましたが、赤坂御門の石垣はそのまま残され、歴史の証人として今も街の一部に溶け込んでいます。
江戸時代における藩主の役割は、自領の運営だけでなく、幕府の命令による公共工事にも及んでいました。黒田忠之のように、他藩の地にあっても幕府の命に従い江戸を守るインフラ整備を担った例は少なくありません。その代表例として、赤坂御門は今も重要な歴史的場所として残り続けています。
青山通りの原点・大山街道

現在では洗練された都会のイメージが強い青山通りですが、その原点は江戸時代ににぎわった「大山街道」にあります。この道は、江戸の人々がこぞって出かけた神奈川県・大山への参拝「大山詣(おおやまもうで)」のための道として整備され、出発点は赤坂御門でした。
大山は山岳信仰の対象であり、特に農民や商人からの信仰が厚く、「雨乞い」や「商売繁盛」を祈る場として人気を集めていました。大山街道は、その大山に向かうための主要な参拝ルートとなり、多くの庶民が利用する生活と信仰が結びついた道でもあったのです。
道沿いには自然と人が集まり、以下のようなにぎやかな風景が広がっていたといわれています。
-
茶屋や料理屋、土産物店などが軒を連ねる
-
参拝のついでに立ち寄る客で終日活気があった
-
宿場のように泊まれる場所もあり、庶民の旅行気分を味わえる場所でもあった
こうしたにぎわいは、現在の三軒茶屋や渋谷といったエリアの成り立ちにもつながっています。たとえば、三軒茶屋という地名はまさに3軒の茶屋があったことが由来であり、それらは大山街道沿いに旅人の休憩場所として生まれたものでした。
また、当時の渋谷もすでに交通の要所であり、参拝客や商人たちが立ち寄る市場的な機能を果たしていたと考えられています。こうした歴史を知ると、今も人が集まるこれらの街に、大山街道の記憶が息づいていることがわかります。
つまり、現在の青山通りは単にモダンなショッピングストリートというだけではなく、江戸時代から続く信仰・交流・文化の道を受け継いだ、由緒あるルートでもあるのです。静かな街並みにも、かつての旅人たちの足音が重なっているような、そんな歴史の深さを感じられる場所です。
牛鳴坂に隠された風景

赤坂の町を歩いていると、近代的な建物の中にふと現れる坂道があります。それが「牛鳴坂(うしなきざか)」です。この坂は、現在の青山通りの原型でもある大山街道の一部として使われていた道で、今もその姿を留めている貴重な場所のひとつです。
名前の由来は、江戸時代にこの坂を通って荷物を運んでいた牛たちの声から来ています。坂道は傾斜があり、雨が降るとぬかるみやすくなっていました。
-
牛が重い荷車を引きながら坂を上ろうとする
-
泥で車輪がとられ、前に進めず牛が苦しむ
-
そのときに発する鳴き声があたりに響いていた
このような情景が、人々の間で語られるうちに「牛鳴坂」という名前が自然と定着していったといわれています。生活の中から生まれた地名であり、単なる通行路ではなく、そこには動物と人間の苦労がにじんだ歴史があります。
現代では舗装されて歩きやすくなっていますが、坂の傾斜や曲がり具合は今も昔のままで、歩いているだけで当時の風景が想像できるような趣があります。周辺にはビルが立ち並んでいますが、その中にぽつんと残るこの坂道は、まるで時間が止まっているかのような静けさをたたえています。
青山通りの整備にともなって多くの道が姿を変えていく中で、この牛鳴坂は、かつての旅路や日常の一場面を伝える、貴重な“生きた地形”として今も街に息づいているのです。坂道という小さな風景にも、歴史の積み重ねがしっかり刻まれていることが感じられます。
大名屋敷の面影と門の移築

青山通り周辺は、江戸時代には有力大名の上屋敷が集まる格式高い武家地として知られていました。将軍の近くに仕えるため、大名たちはこのエリアに広大な屋敷を構え、門や石垣、庭園などを整え、まさに武士社会の権威を示す象徴的な場所だったのです。
当時の青山通りはまだ存在しておらず、整備された直線の道ではありませんでした。現在のように道がまっすぐに通るのは近代になってから路面電車を通すために開かれたものです。それ以前の道は、屋敷や地形に沿って曲がりくねり、大山街道として人々の往来が続いていた歴史の道でした。
こうした背景のなか、2016年には、かつての大名屋敷の門のひとつが移築保存されました。
-
移築された門は、江戸時代後期に建てられた上屋敷の表門
-
移設先でも原形を留めた状態で保存
-
木材や屋根の造りが当時の建築技術をそのまま伝える
現在、東京都内に残る大名屋敷の表門はわずか3か所のみ。そのため、この移築された門は極めて貴重な存在であり、江戸の大名文化を今に伝える数少ない遺構として高く評価されています。
青山通りは、このような屋敷群を突き抜けるように整備された道路であり、その道筋は武家地の変化とともに形作られました。今ではビルや店舗が並ぶおしゃれな通りですが、かつてこの地に並んでいた屋敷の面影は、こうした門のような痕跡にひっそりと息づいています。
道を歩いていても気づきにくい歴史の名残ですが、立ち止まって見ることで、この土地に重ねられた時間の深さと、静かな誇りのようなものを感じ取ることができます。青山通りの整然とした姿の裏には、江戸の記憶と変わりゆく都市の姿が交差しているのです。
路面電車から始まった近代の青山通り

現在の青山通りは、洗練されたショップやカフェが立ち並ぶ東京屈指のおしゃれなエリアですが、その整然とした姿は明治時代以降に誕生した新しい道路計画によって形作られたものです。その原点は、路面電車を通すためのインフラ整備でした。
もともとの道筋は、江戸時代から続く大山街道で、道幅も狭く、地形や屋敷の配置に沿って曲がりくねった構造でした。そこに近代の都市化が進む中で、電車の運行に適した直線的で広い道が必要となり、青山通りが整備されたのです。
青山通りの特徴は以下の通りです。
-
路面電車用に設計されたため、道幅が広く、見通しが良い
-
曲がり道が少なく、輸送効率が高い
-
緩やかな勾配で、人や車が通行しやすい構造
番組では、江戸の時代から使われていた大山街道の旧道と、真っ直ぐに引かれた青山通りの新道が交わる場所を目指して歩きました。この交差地点は、過去と現在がつながる象徴的なスポットでもあります。
交差点付近では、かつての面影を残す小道や、石垣、わずかな段差などが点在しており、それぞれがかつての生活の名残を物語っています。まっすぐに整備された青山通りの姿と、その裏側に残る旧道の痕跡は、都市がどのように時代とともに形を変えてきたかを静かに語りかけてくれます。
青山通りは単なる交通のための道ではなく、都市の変遷と人々の暮らしの記憶が織り重なった空間です。道そのものが歴史資料のような存在であり、今の東京の姿を理解するうえでも重要な手がかりとなっています。
地形とつながる薬研坂の由来

番組の最後に登場したのが「薬研坂(やげんざか)」です。この坂は、地名として今も残っており、その由来は薬を粉にする道具「薬研(やげん)」の形にあるとされています。薬研は、V字型の金属の器具で、中央の溝に薬草などを入れてすり潰す仕組みです。
薬研坂は、その両側が高く、真ん中がくぼんだV字型の地形が薬研に似ていることから名づけられました。名前の由来からもわかるように、この坂は自然の地形を活かした道であり、現在の青山通りが高台を通る直線的な道として整備された背景とも深くつながっています。
薬研坂の特徴として、次のような点が挙げられます。
-
坂の中央が低く、両側が高い谷地形
-
地形に沿って道が曲がるため、昔ながらの風景が残っている
-
坂道の勾配が歩いて実感できるほど急
青山通りの一帯は、こうした高低差のある武蔵野台地の端に沿って発展した地域で、青山通りが「見晴らしがよくてステキ」と感じられる理由のひとつは、この高台の地形にあるといえます。見通しの良さや風の通りの良さは、古くから人々にとって住みよい条件でもありました。
薬研坂のような自然地形に沿って形づくられた道を歩くことで、青山通りがただの都市計画道路ではなく、昔の地形や暮らしの記憶を受け継いだ場所であることが実感できます。街の中に残る小さな坂にも、名前や形に込められた歴史の意味が詰まっているのです。こうした細部に目を向けることで、青山通りの“ステキさ”がより深く理解できるようになります。
まとめ
今回の『ブラタモリ』では、青山通りの「ステキさ」が、ただおしゃれな街を通っているからではなく、江戸時代の大山街道としての歴史や大名屋敷の跡地を通る特別な道であること、路面電車や地形を活かした整備が背景にあることが分かりました。現在の東京の街並みにも深くつながる道の成り立ちは、これまで何気なく通っていた青山通りに対する見方を変えてくれるものでした。放送を見逃した方も、ぜひ一度足を運んでその歴史の重みを感じてみてはいかがでしょうか。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


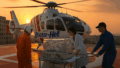
コメント