ドクターヘリが赤ちゃんを救った!熊本地震18時間の壮絶な搬送劇
2025年6月14日に放送されたNHK「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜」では、熊本地震でのドクターヘリによる赤ちゃんの救出劇が紹介されました。救急医療の最前線で命を守る医師や看護師たちが、限られた時間と資源の中で力を尽くした姿が描かれています。赤ちゃんの命を守るという強い思いが、多くの人々の行動を動かした感動のドキュメントです。
ドクターヘリの誕生と広がり

阪神・淡路大震災では、病院にヘリで搬送されたのはたった1人でした。当時、緊急車両は瓦礫に行く手を阻まれ、スムーズな救助ができない状況でした。その結果、ヘリコプターは救助活動よりも物資運搬に使われてしまい、救命に活かせなかったという現実がありました。これをきっかけに、現場に直接医師が向かい、すぐに治療を始められる「ドクターヘリ」の必要性が強く認識されました。
この考えは全国に広がり、ドクターヘリの導入が各地で検討されるようになります。しかし、運用には年間約2億円もの費用がかかり、自治体の財政を圧迫することもあって、なかなか全国的には普及しませんでした。特に鹿児島県では10年経ってもドクターヘリが導入されず、広い県内の中で地域によっては医療の格差が大きく開いていました。
この状況に行動を起こしたのが、鹿児島市立病院の医師・茨聡です。茨医師は、都市部なら助かるはずの命が、鹿児島では助からないという現実に長年向き合い、改善を目指してきました。鹿児島市立病院は、かつて日本で初めて五つ子が誕生したことで知られる病院であり、高度な新生児医療を担ってきた実績があります。そんな病院でさえも、新生児集中治療室(NICU)のベッド数が足りず、離島や遠方地域からの搬送には2時間以上かかるケースも珍しくありませんでした。
県内には2つの半島があり、地理的にアクセスが悪い場所が多く存在します。そこで茨医師は、「場所によって救える命が変わってはいけない」という思いから、まずは医師が直接現場に向かう「ドクターカー」の導入に踏み切ります。救急車と異なり、医師と看護師が同乗していて、到着と同時に処置が始められる体制です。
その後、茨医師はさらに一歩進め、空からの迅速な医療提供が可能なドクターヘリの必要性を訴えます。ドクターヘリがあれば、山間部や離島、交通の不便な地域に住む人たちも、救急医療の恩恵を受けることができます。
-
鹿児島県は地形的に南北に長く、広範囲に人が暮らしている
-
離島や山間部から病院までの搬送には長時間かかることが多い
-
新生児はちょっとした遅れが命に直結するため、迅速な搬送手段が不可欠
-
市民の間でも問題意識が高まり、署名活動には12万人が参加
こうした動きの中、茨医師は地域医療を守る強い信念のもと、医療現場と行政の橋渡し役を務めました。その結果、鹿児島にもようやくドクターヘリの導入が実現し、地域の救急医療が大きく前進することになったのです。
新生児専用搬送システムの誕生

2011年、鹿児島にドクターヘリが導入されると、医療現場ではさらなる課題が見えてきました。それは、新生児を安全かつ確実に搬送するための体制が整っていないことです。特に未熟児や重症の赤ちゃんは、ほんの少しの揺れや温度変化、酸素濃度の変化でも命に関わるため、通常の医療機器では対応できませんでした。そこで、鹿児島市立病院の救急科に所属する吉原秀明医師は、ドクターヘリによる新生児搬送に必要な専門装備の開発を提案します。
この提案に応えたのが、医師2年目だった平川英司医師です。彼は少年時代に成長ホルモンが十分に分泌されない難病を患い、長期間の入院と治療を経験しました。このときの医師や看護師の存在が、平川にとって医師を志すきっかけとなったのです。「今度は自分が誰かを救う番だ」との思いで、難しい新生児搬送システムの開発に挑みました。
平川医師は、呼吸器、保育器、生体情報モニターを一体化させたストレッチャーの設計に取りかかります。狭く揺れるドクターヘリの機内でも安定して赤ちゃんを守りながら搬送できるよう、複数の機能をコンパクトにまとめ、ワンタッチで救急用ストレッチャーと交換できる仕組みを考案しました。
吉原医師は、平川の開発を現場で活かすため、病院の一角にドクターヘリの機内を模した訓練室を自ら作りました。この訓練室では、限られたスペースの中での搬送や処置を再現し、医師・看護師・技師たちが何度も繰り返し動作を確認。空き時間を使ってもシミュレーションを行い、1分1秒を縮めるための動き方を体に染み込ませていきました。
-
機内の揺れに対応できるよう器具の固定方法を工夫
-
保育器の温度管理や酸素濃度の微調整が可能な設計
-
医療スタッフの動線を邪魔しない配置と操作性を追求
-
ストレッチャーの交換がワンタッチでできるよう改良
こうして、救急と新生児の専門チームが全国でも珍しい連携体制を築き上げました。この取り組みにより、赤ちゃんの搬送にはきわめて繊細な技術が必要という認識が広まり、全国に先駆けて高度な新生児搬送体制が整いました。
完成した新生児専用搬送システムは、導入からわずか5年で250件以上の出動実績を記録し、全国最多の搬送件数となりました。この数字は、日々の訓練と改良、そして何より赤ちゃんの命を守りたいという強い思いの積み重ねによって実現されたものです。平川医師のように、かつて助けられた命が、次の命を救う存在となったことは、医療の現場における大きな希望となっています。
熊本地震での18時間の救出劇
2016年、未明に発生した熊本地震は、広範囲に甚大な被害をもたらしました。その中でも特に危険な状況に置かれたのが、熊本市民病院の新生児集中治療室(NICU)に入院していた38人の赤ちゃんたちでした。建物は激しい揺れに襲われ、病院全体が停電。医療機器の多くが使えなくなり、赤ちゃんたちの命が危機にさらされました。
井上武医師は、看護師たちと連携してベッドを床に下ろし、天井の落下物から赤ちゃんを守るために身体を張って覆いかぶさりました。地震が続く中でも、赤ちゃんたちは体温調節ができない未熟児が多く、保育器から出して移動させることは大きなリスクを伴いました。中でも自力で呼吸ができない7人の赤ちゃんには、手動の人工呼吸を使って酸素を送り続ける必要があり、スタッフは交代しながら対応を続けました。
一方、鹿児島市立病院では、すぐに状況を把握し、ドクターヘリでの支援派遣が検討されました。現地にいち早く到着していた吉原秀明医師が正確な状況を報告し、鹿児島からの搬送支援が正式に決定されます。支援を送るにあたり、赤ちゃんの命を確実に守れる体制を整え、ヘリの準備が急ピッチで進められました。
-
鹿児島からの出動時刻は朝9時過ぎ
-
ヘリの着陸地は病院から約1キロ離れた江津湖の湖畔
-
病院から搬送地点までは手動人工呼吸を続けながらの移動
このとき、最も容態が心配されたのが体重951gの田中ゆきちゃん(仮名)でした。小さな体で自力呼吸ができず、すでに6時間以上、人工呼吸が続けられていました。赤ちゃんを抱えての移動中も、スタッフは一瞬も気を抜かず酸素供給を維持。到着したドクターヘリには新生児専用搬送システムが搭載されており、すぐにストレッチャーごと乗せ換えが行われました。
搬送チームは平川英司医師らで、赤ちゃんの状態を常にモニターしながら、揺れる機内で慎重な処置を続けました。地震による余震が再び発生する中、すぐにヘリは離陸し、10時34分に鹿児島市立病院に無事到着します。
この日は赤ちゃんたちの搬送が2回にわたって行われ、午後までに38人すべての赤ちゃんが県外の病院に無事搬送されました。合計飛行距離は1000km以上に及び、九州各地の病院も連携して受け入れを行いました。
現在、搬送されたゆきちゃんは9歳となり、運動会でリレーの選手に選ばれるほど元気に成長しています。当時の18時間にわたる救出劇は、多くの人たちの判断と行動、そして「赤ちゃんの命を救いたい」という一つの想いによって支えられていたことが、今も語り継がれています。
出産間近の妊婦の搬送

熊本地震の混乱の中、もうひとつの命のドラマがありました。保育士として働く宮田愛美さんは、地震後に子どもたちを連れて避難所へ向かいました。夫は消防団の活動で不在、余震が続く中で2人の子どもを一晩中抱きしめながら過ごし、ようやく自宅に戻った直後に破水。妊娠8ヶ月での出来事でした。
かかりつけの産院に駆け込み診察を受けたところ、このまま出産すれば赤ちゃんの命が危ないという判断が下されました。そこで、より高度な新生児医療が受けられる鹿児島市立病院への搬送が決まります。しかし、ドクターヘリの飛行には日没制限があり、離陸できるまで残された時間はわずかでした。
現場では「迷ったらやれ」という判断基準が背中を押し、出発が決定。ヘリの整備を担当するスタッフは、予測される事態に備えて燃料と必要機材をあらかじめ補充しており、対応はスムーズでした。
-
離陸時刻は午後6時10分、日没まで残りわずか
-
フライト中、愛美さんの体調を崩さないよう乗り物酔い対策の注射が行われた
-
出産時のいきみを避けるため、平川英司医師が吐き気止めを処方
機内では助産師の岩本さんが付き添い、出産の不安に揺れる愛美さんの手を握って励まし続けました。離陸直前には「ヘリに乗るまで一緒にいるからね」と声をかけて安心させ、その後の処置も連携して進めました。
鹿児島市立病院に到着したのは午後7時40分過ぎ。飛行のタイミングは日没2分前で、視界がぎりぎり確保できる中での搬送となりました。翌朝の早朝、愛美さんは早産となりましたが、赤ちゃんは保育器の中で無事に誕生し、NICUでのケアが開始されました。
この搬送は、ドクターヘリが救急だけでなく、周産期医療の現場でも大きな力を発揮できることを示す例となりました。限られた時間と資源の中でも、医療スタッフの連携と判断によって、新たな命が安全に守られたのです。
ドクターヘリの未来と平川医師の挑戦
熊本地震での経験をきっかけに、平川英司医師は視野をさらに広げ、災害時や医療資源の少ない地域でも使える新たな医療機器の開発に取り組み始めました。彼が開発したのは、電気を使わずにお湯で温められる保育器です。この装置は、電力の供給が不安定な被災地や途上国でも使用できるよう設計されており、赤ちゃんの命を守るための重要なツールとなっています。
この保育器はすでにラオスなどの東南アジアの国々で活用されており、現地の医療現場にとって大きな支えとなっています。通常の保育器は高価で取り扱いも難しいものが多い中、平川医師が開発した装置はシンプルで運用しやすく、世界中の命を救う可能性を広げています。
日本国内でも、ドクターヘリの運用体制は年々進化しています。1999年に日本で初めて導入されてから24年が経ち、現在では全都道府県で配備が完了。年間で2万人以上の患者が搬送されるまでに広がり、ドクターヘリは地域医療に欠かせない存在となりました。
-
ドクターヘリは、現場に医師が直接向かうことで即時の処置が可能
-
山間部や離島など、病院までの距離が長い地域でも救命率が向上
-
熊本地震の教訓により、各地で新生児や妊婦搬送の訓練も強化
現在も多くの医師、看護師、整備士たちが現場に立ち続け、1分1秒を争う状況で命と向き合っています。その根底にあるのは、「場所や環境によって救える命が変わってはいけない」という強い想いです。
平川医師が開発した保育器のように、技術と情熱が融合した取り組みは、これからの医療の可能性を広げる希望となっています。熊本地震での活動、鹿児島での挑戦、そしてそれを受け継ぐ次世代の医療人たちの存在が、日本の救急医療の未来を力強く支えています。今回の放送では、そうした人々の努力と、命に真正面から向き合う姿勢の大切さが丁寧に描かれていました。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

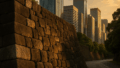
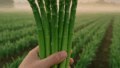
コメント