廃校寸前からの逆転劇〜高校生と熱血先生の宇宙食開発〜
2025年5月31日に放送されたNHK「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜」では、福井県小浜市にあった小浜水産高校の生徒と教師が15年にわたり挑んだ、世界初の高校生による宇宙食サバ缶開発の物語が紹介されました。地元で“最も荒れていた”と呼ばれ、廃校寸前だった学校が、地域の力と生徒の情熱によって生まれ変わった実話です。
小浜水産高校に立ちはだかった現実と教師の決意
2001年、福井県立小浜水産高校に赴任した小坂先生は、着任初日に強烈な現実を突きつけられました。「なんでこの学校に来たんや、もう潰れるで」と職員室で言われたのです。その言葉通り、学校全体には諦めと閉塞感が漂っており、生徒たちは授業に対してまったくやる気を見せない状況でした。
授業中に寝るのは当たり前。昼休みにはタバコを片手にたむろする生徒たちが目立ち、教師たちも見て見ぬふりをせざるを得ない雰囲気。中でも、食品工業科を担当する小坂先生の前には、特に手のかかる女子生徒3人組が立ちはだかります。教室内では私語が絶えず、実習にも参加しない。注意しても反応は薄く、授業が成り立たない日々が続いていました。
そんな毎日を支えたのが、ベテラン教員・桝田先生の存在でした。桝田先生は、生徒に寄り添う姿勢を崩さず、信頼を得ていました。小坂先生もその姿に影響を受け、自分も生徒と同じ目線で関わっていこうと心に決めます。
-
家庭に問題を抱え、登校が不安定だった生徒には、一緒に通学することで信頼を築いた
-
生徒たちの表情や言動を見逃さず、変化に気づいたらすぐに声をかけ、寄り添い続けた
-
教室で寝ている生徒にも、叱るのではなくまず話を聞くことを大切にした
そんなある日、小坂先生の耳に入ったのが、生徒の口から漏れた「うちらどうせアホやし」という言葉でした。この一言は、小坂先生の心を強く打ちました。生徒たちが自分自身を見限り、学ぶことに希望を持てなくなっている現実を突きつけられたのです。
そこで小坂先生は、何かひとつでも自信につながる経験を生徒に持たせたいと考え、学校の伝統である「サバ缶」の実習を本格的に導入することを決意します。
-
サバ缶実習は文化祭でも人気で、唯一生徒たちが「誇りを持てる瞬間」だった
-
実際の製造工程を通じて、衛生・加熱・包装といった専門知識を体験しながら学べる
-
先生と生徒が一緒に汗を流して作業する時間が、少しずつ関係を変えていった
この決断は、小坂先生にとっても、生徒たちにとっても、大きな転機となりました。教える側と教わる側の垣根を越えて、「信頼を積み重ねながら、学ぶ楽しさを取り戻す」第一歩がここに刻まれたのです。
地域実習とクラゲの研究で見えた希望
小坂先生は学校の外にも学びの場を広げようと考えました。教室では学べない「実社会の中での学び」を生徒たちに経験させたいという思いから、地元の漁師と一緒に行う漁業実習を提案します。しかし、生徒の問題行動が心配されていたこともあり、「連れ出せば何をするか分からない」と反対の声が多く上がりました。
そんな中、地元に顔が利く清水先生が「俺も面倒みますよ」と一言。小坂先生の熱意に共感し、自らも同行して支えることを申し出てくれました。この後押しによって、ついに地域と連携した実習がスタートします。
-
実習では生徒たちが漁師と一緒に網を引いたり、魚の選別を体験
-
現場でしっかり動けたことを漁師から褒められ、生徒たちに初めての“成功体験”が生まれた
-
その日から、教室での表情が少しずつ変わり、笑顔が見られるようになった
こうして自信をつけ始めた生徒たちは、次第に自発的に学びに取り組むようになっていきます。その中で、西さんを中心としたグループが、漁師との会話から新たな課題に気づきます。エチゼンクラゲの大量発生によって漁業に深刻な被害が出ていたのです。
生徒たちはその問題に対し、クラゲをただの厄介者とせず、「資源」として活用できないかと考え、研究を開始。
-
クラゲを粉末化し、コラーゲンを抽出することに成功
-
にがり成分も発見し、豆腐づくりに活用。試作を繰り返しながら形にした
-
成果を発表した北陸の水産高校大会で、見事最優秀賞を受賞
続いて挑戦したのは、海の水質を良くするための海藻の活用研究でした。ここでも、小坂先生は生徒たちと共に深夜までレポートを確認し、寝る間も惜しんでサポート。その結果、全国大会での優勝も果たしました。
しかし、手放しの成功では終わりませんでした。卒業後、進学や就職で一歩を踏み出せずに悩む生徒も現れたのです。ある卒業生からは「先生みたいな人がいなければ僕は何もできない」と言われ、小坂先生は胸を打たれました。
この言葉をきっかけに、小坂先生は自問します。「生徒にとって、先生が先回りしすぎていなかったか」「成果よりも、失敗しても自分で考える力を育てるべきだったのではないか」と。
この経験は、小坂先生にとっても大きな学びとなり、「教える」ではなく「ともに考える」教育への転換が始まったのです。生徒の変化と成長、そして教師自身の葛藤と変化。その両方が重なって、次の挑戦である「宇宙食開発」へとつながっていくことになります。
サバ缶を宇宙へ!JAXAとのやりとりと夢の継承
2007年、日本の宇宙開発において大きな節目となる有人宇宙施設「きぼう」の建設計画が動き始める中で、小浜水産高校の教室でもひとつの夢が芽生えました。ある生徒が放った「鯖缶を宇宙に飛ばせるんちゃう?」というひと言。それは、これまでの研究と実習で少しずつ自信をつけてきた生徒たちだからこそ出てきた、本気の挑戦への始まりでした。
小坂先生たちはすぐにJAXA(宇宙航空研究開発機構)に問い合わせを行い、鯖缶を宇宙に持ち込む可能性を探ります。しかし返ってきたのは、「缶は宇宙では使えない」という現実的な答えでした。理由は、缶が硬く、容器がかさばることや、無重力環境での液体の扱いが難しいこと。
それでも生徒たちは諦めませんでした。「缶詰じゃない方法で宇宙食を作ればいい」と発想を切り替え、過去のクラゲ研究で使った粉末技術を応用。
-
クラゲの粉末を使用して栄養価の高い成分を加え、保存性も確保
-
とろみをつけるために葛粉を用い、調味液が飛び散らないように工夫
-
密閉性と衛生を兼ね備えた特殊な容器を検討し、JAXAの審査に耐え得る仕様を研究
一方で、この頃には学校自体が福井県の高校再編計画の中で廃校の対象となっていました。生徒たちの未来を守るため、先生たちは地域住民や保護者とともに奔走。中学校にビラを配り、地域の人々の声を教育委員会に届けるために何度も会議に足を運びました。
-
「学校を残したい」という署名活動が始まり、卒業生や地元の人々も支援に加わった
-
教育委員会との協議の結果、小浜水産高校は若狭高校の「海洋科学科」として再出発することが決定
-
この判断により、学校としての命はつながれ、研究と実習の灯は消えずに受け継がれることとなりました
研究チームは、先輩たちの残した実験ノートや記録データを細かく読み込みながら、味の調整や保存性の向上に努めます。「誰が見ても納得できる宇宙食をつくる」という目標は、年を重ねるごとに世代を超えたプロジェクトへと進化しました。
そして2020年。ついにこの努力は宇宙へと届きます。国際宇宙ステーション(ISS)で、宇宙飛行士・野口聡一さんが開発されたサバ缶を試食。「うまい!」という言葉が、15年にわたる挑戦を締めくくる最高のご褒美となりました。
この一言は、「高校生でも本気になれば世界を動かせる」ことを証明した瞬間でもありました。技術、努力、希望、そしてつながる心。小浜の小さな教室から始まった夢は、本当に宇宙まで届いたのです。
宇宙から地上へ「若狭宇宙鯖缶」として未来へ
このプロジェクトは商品化へと発展し、2022年3月8日「サバの日」に、若狭宇宙鯖缶が全国で販売開始。宇宙食の開発技術を応用した製品は、小浜市の名産品として広く知られるようになりました。今では小坂先生の教え子・小畑先生が後輩を指導しながら、鯖缶作りの実習を継続しています。
番組のエンディングでは、「帰って来たいと思える町をつくることが、地方を元気にする」という地域代表・西野さんの言葉が印象的に紹介されました。
生徒と先生、そして地域の人々が15年かけてつないだバトンは、今も未来へと続いています。教育と地域が手を取り合ったことで、奇跡のような物語が生まれたのです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


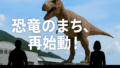
コメント