知られざる音の世界!大阪・平野区の町工場が作るシンバルの秘密
2024年11月2日放送の『探検ファクトリー』では、大阪・平野区にあるシンバル専門の町工場を訪ねました。この工場では、音楽の中で重要な役割を果たすシンバルを、たった4人の職人たちが手作業で作り続けています。番組では、シンバルの製造工程から音色の違いの秘密までを、細かく探りました。出演はすっちーさんと中川家の礼二さん、剛さん。工場で実際に見て、触れて、聴いて、その魅力をじっくり紹介しました。
町工場で作られる特別な音
大阪市平野区にあるこのシンバル工場では、プロのドラマーや吹奏楽で使われる200種類以上のシンバルを製造しています。見学した工場は、もともと農機具や家電、鉄道部品などを作っていた金属加工の現場で、1999年にシンバル製造をスタートしました。社長の小出さんは、金属加工の分野で50年以上の経験を持つ熟練の職人で、今も現場で第一線に立っています。
シンバルの音は一枚一枚違う
シンバルは、直径や重さ、厚さ、表面の仕上げ方によって音が変わります。たとえば直径が大きいほど音は低く、同じ大きさでも重い方が高い音になる傾向があります。しかも、同じ材料で同じ形に作っても、まったく同じ音にはならないという難しさがあるため、まさに一枚一枚が「世界に一つだけの音」となります。
職人技で音が変わる
この工場では、製造の最終段階まで人の手と耳を頼りにしています。どの音が「良い音」なのかの判断も、職人の感覚によって決まります。そうして作られたシンバルは、吹奏楽やプロのドラマーたちに選ばれています。
こだわりの製造工程に密着
番組では、実際に工場の中でシンバルが作られる様子を見せてくれました。ひと月でおよそ300枚のシンバルが生産されています。その工程は、5つの大きなステップに分かれています。
成型〜焼入れと冷却の工程
最初の「成型」では、銅・スズ・チタンなどを混ぜた合金を使います。これを高温の炉で焼いたあと、「水焼入れ」をすることで、粘り強くて丈夫なシンバルの土台が出来上がります。
削り〜重さと音の高さを調整
次に行う「削り」では、機械で表面を削って重さを微調整します。ここでだいたいの音の高さが決まり、軽くすると低い音、重くすると高い音が出やすくなります。
ハンマリング〜凹凸が生む深い響き
続く「ハンマリング」では、専用のハンマーでシンバルを叩いて凹凸を作ります。この作業で、音に奥行きや立体感が加わります。厚い部分と薄い部分をわざと混ぜることで、さまざまな振動と音の高さが生まれます。
寝かし〜時間が育てる音
「寝かし」は、ハンマリング後に行う重要な工程です。たたかれたばかりのシンバルは、内部に力が残っていて元の形に戻ろうとします。しばらく放置しておくとその力が抜け、まろやかで響きのよい音に変わります。社長は一度、完成したシンバルに納得がいかず、3か月間放置したところ、美しい音になっていたという経験を話していました。
レイジング〜美しさと音の仕上げ
最後の工程は「レイジング」。これはシンバルの表面に細かい溝を刻む作業で、見た目がきれいになるだけでなく、音の響きにも関わる繊細な仕上げとなります。
音を楽しむクイズコーナーも
工場見学のあとは、音楽の楽しさにふれるクイズ企画も放送されました。ドラムとシンバルの音を聴いて曲のイントロを当てるクイズが行われ、「アンパンマンのマーチ」「チェリー」「ファイト!」など、シンバルの音が印象的に使われている曲が出題されました。出演者と工場の社員が一緒にチャレンジし、シンバルの音に注目するきっかけとなりました。
今回の放送では、音楽の裏側で活躍する町工場の努力と工夫、そして音づくりに向き合う職人たちの姿がていねいに紹介されました。音楽が好きな人、ものづくりが好きな人、どちらにも楽しめる内容でした。音に心を込める現場の温かさが伝わる回でした。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


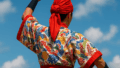
コメント