アメリカに渡った『はだしのゲン』が世界を動かす
2025年7月26日に放送された「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜」では、日本の戦後を描いた名作マンガ『はだしのゲン』が、アメリカに渡って世界へと広がっていった奇跡の物語が紹介されました。マンガがまだ世界に知られていなかった時代に、素人の翻訳チームが挑んだ前代未聞の取り組み。その背景には数々の困難と感動的な出会いがありました。
世界に向けて「ゲン」の声を届けた素人チームの挑戦
1977年、日本ではまだマンガが海外で読まれるという発想が一般的でなかった時代に、『はだしのゲン』の英訳に挑んだのは、専門家ではなく、大学生や在日アメリカ人を中心とした市民のボランティアチームでした。彼らが「Project Gen」と名乗り、独自に進めた翻訳活動は、出版の枠を超えて、マンガを平和のメッセージとして世界に届ける大きな流れを生み出しました。
「Project Gen」誕生の背景と出発点
活動のきっかけは、アメリカ人活動家が広島で『はだしのゲン』を読み、英語にして広めたいと感じたことでした。その想いに共感した大学生や研究者、英語教育関係者などが集まり、出版社に頼らず自費で翻訳を進めることに。1978年には第1巻の英訳が完成し、ニューヨークの平和団体へ1,000部を送付。このとき出版された『Barefoot Gen』は、世界初のマンガの市民翻訳プロジェクトとして歴史に刻まれることになりました。
手探りで進めた翻訳作業の日々
翻訳作業は決して簡単ではありませんでした。日本語の言い回しや、登場人物の感情、効果音の表現など、細かなニュアンスを英語でどう伝えるか。正確さと読みやすさの両立に苦労しながら、何度も訳文を見直していきました。当時は手書き原稿やタイプライターが主流で、翻訳と編集にかかる手間は大きく、完成には多くの時間と情熱が注がれました。
チームの多くは本業を持ちながら活動に参加し、作業は夜間や休日に行われていました。辞書や資料を囲みながらの議論はときに深夜に及ぶこともありましたが、誰一人途中で投げ出すことはありませんでした。それは、ゲンの物語がただのフィクションではなく、実際にあった戦争と人間の強さを伝える真実の物語だったからです。
広がり続ける翻訳の輪とその影響
やがて活動は日本国内だけにとどまらず、世界の他の言語への翻訳へと広がっていきました。英語版は長年かけて全10巻が完訳され、2009年にはすべての巻が出版されました。『はだしのゲン』は、英語をはじめ、フランス語、ドイツ語、スペイン語、韓国語など25以上の言語に訳され、世界中の学校や図書館で「戦争を知るための教材」として読まれています。
この翻訳活動の価値は、ただ本を広めたことにとどまりません。市民レベルの行動が、国や文化の壁を越え、多くの人々の心に届いたこと。そして、その根底にあったのが、「ゲンの声を世界に届けたい」という純粋な想いだったことが、今もなお語り継がれている理由です。
原爆を落とした国での反発と、奇跡のような出会い
英訳された『はだしのゲン』がアメリカで紹介され始めた当初、必ずしも歓迎されたわけではありませんでした。1970年代後半のアメリカ社会では、第二次世界大戦の勝者としての意識が色濃く残っており、原爆投下を「戦争終結のために必要だった」と考える人も多くいました。そのため、原爆の悲惨さや被害の実態を描いたこの作品に対して、「一方的な視点だ」といった反発や、「反米的だ」といった批判の声も少なくありませんでした。
誤解と偏見を超えた伝播の始まり
読者の中には、表紙や冒頭の描写だけで判断してしまい、内容をきちんと読み込むことなく否定する人もいました。特に、戦争に直接関わった世代の中には、「アメリカが悪者に描かれている」と受け取った人もいたのです。また、書店や図書館でも扱いが難しい作品とされ、なかなか流通の場が広がらず、販売数も限られたものでした。
しかし、翻訳チームの活動は止まることなく続けられ、限られた中でも読者に届くチャンスが生まれていきました。そして、運命を大きく変える出会いが訪れます。
元・原爆開発関係者との出会いと広がる輪
ある日、『はだしのゲン』を手に取った一人のアメリカ人老人がいました。彼はかつて、マンハッタン計画など原爆開発に関わった過去を持つ人物でした。戦後、自身の関与を深く反省し、平和活動に身を投じていた彼は、このマンガを読み、衝撃を受けました。
「これは、私たちが伝えなければならない本だ」と強く感じた彼は、すぐに行動を開始。教会や学校での読み聞かせ活動を行い、自らがゲンのストーリーを通じて語り部となりました。彼の誠実な語りは、多くのアメリカ人の心を動かし、作品の印象を大きく変えることとなりました。
やがて、彼の活動は口コミで広がり、各地の教育機関や市民団体へと広がっていきます。マンガという形式に偏見を持っていた層にも、平和を願うメッセージとして受け入れられるようになり、読者層が少しずつ広がっていきました。
この出会いは、翻訳チームの努力を後押しするものであり、同時に「過去の立場を越えて人と人がつながる」象徴的な出来事となりました。『はだしのゲン』という作品が国境を越えて届いた瞬間でもありました。
出典・情報ソース
・NHK「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜|アメリカに渡った漫画〜はだしのゲン〜」(2025年7月26日放送)
・SWET(Society of Writers, Editors, and Translators)公式記事「The Hadashi no Gen Project」
・Wikipedia「Barefoot Gen」
・The Comics Journal「Interview with Keiji Nakazawa」
・Cultural News「Barefoot Gen and Hiroshima Peace Education」
・Comics Forum「Early Manga Translations in the West」
・Kyodo News「Japan Wire: Hiroshima stories and translations」
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。


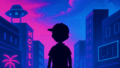
コメント