夢の海底道路はこうして生まれた!東京湾アクアラインの挑戦物語
あなたは東京湾アクアラインを通ったことがありますか?千葉と神奈川をわずか15分で結ぶこの道路。実は「土木のアポロ計画」と呼ばれた壮大な挑戦の末に誕生した、まさに日本の誇る技術の結晶です。
この記事では、2025年10月25日放送の『新プロジェクトX〜挑戦者たち〜 東京湾アクアライン〜土木のアポロ計画 海底トンネルに挑む〜』をもとに、知られざる奮闘の記録を振り返ります。
読めば、きっとあなたも“道をつくる人々”の情熱と絆に胸が熱くなるはずです。
首都圏の交通難を救え!一人の夢から始まった物語
1970年代、首都圏では急激な人口増加により、深刻な交通渋滞と物流の遅れが社会問題となっていました。道路や高速の整備が追いつかず、東京から千葉・神奈川方面への移動には何時間もかかることも珍しくありませんでした。そんな中、「東京湾を横断する道をつくれば、交通の流れが劇的に変わる」と考えたのが、内田恵之助でした。
当時、内田は国の土木計画を担当する技術者であり、誰もが不可能と思うような構想を打ち立てます。それが、東京湾アクアラインという巨大な海底道路構想です。東京湾の中央を突き抜け、神奈川・川崎と千葉・木更津を最短ルートで結ぶという大胆な計画でした。
しかし、湾の下には、地質学的にも特殊な“マヨネーズ層”と呼ばれる柔らかい地盤が広がっていました。まるで液体のように不安定で、重機を支えることも難しい環境。この海底にトンネルを掘るなど、当時の常識ではまさに「世紀の無謀」とさえ言われていました。関係者の間でも「崩れるに決まっている」「夢物語だ」と懐疑的な声が多く上がりました。
それでも内田は、「日本の技術力を結集すれば、必ずできる」と信じていました。その信念のもと、大手ゼネコンや機械メーカーなど、国内のトップ企業が次々と集結。鹿島建設、大成建設、熊谷組、西松建設、飛島建設、川崎重工業、三菱重工業など、総勢100社を超えるプロジェクトチームが結成されました。
各社が競うように新技術を持ち寄り、「人類が初めて月に到達した『アポロ計画』に匹敵する挑戦だ」と称されるほどのスケールになっていきます。やがてこの壮大な計画は、誰からともなく「土木のアポロ計画」と呼ばれるようになりました。
ここから、技術者たちの情熱と執念が交錯する、前人未到の海底トンネル建設の物語が始まったのです。
海底に挑む!100社の知恵と意地の結晶
1989年、ついに東京湾アクアライン建設という世紀の大工事が幕を開けました。プロジェクトの心臓部となったのが、神奈川県側の川崎人工島です。海上に浮かぶこの人工島は、直径およそ100メートル、深さ70メートルという巨大な構造物で、海底トンネルの掘削を開始するための発進基地として設計されました。
ここから4台のシールドマシンが、海底の泥と砂に覆われた地盤を少しずつ削りながら進むという、前人未到の挑戦が始まりました。直径14メートルもの巨大な掘削機を扱うこの作業は、まさに精密さと勇気の両方が求められる“極限の現場”。300人もの作業員が、毎日フェリーで人工島に渡り、昼夜を問わず交代で作業を続けました。
人工島の内部は常に機械の音が響き、気温や湿度の変化も激しい過酷な環境でした。そんな中、問題が起きたのは、各社が自社設備を持ち込み始めたことです。参加企業が100社を超えていたため、現場はそれぞれのやり方や機械が入り乱れ、効率が下がってしまいました。
この混乱を前に、現場をまとめるために立ち上がったのが米沢実でした。彼は冷静に状況を見極め、「全員が使える共有リフトを設けよう」と提案。掘削作業に必要な資材や機材を運ぶエレベーターをチームごとに分けるのではなく、共同で使うことで効率を高めようと考えたのです。
当初は各社の担当者が難色を示しましたが、鹿島建設の高野孝が「全体がうまく回ることが最優先だ」と後押ししたことで、4チームが連携する仕組みが動き出しました。こうして現場は見事に一体化し、人工島の作業は再び順調に進み始めました。
1993年、掘削は海底70メートル地点に達し、工事は順調に見えました。ところが突然、海底から大量の水が吹き出すという緊急事態が発生します。報告を受けた高野が現場に駆けつけると、鹿島建設の担当区域で許容量を超える出水が確認されていました。海の下という極限の状況では、一つの判断ミスが致命的な事故につながる危険もありました。
高野はチームを集め、「自分のことだけを考えるな。全体の最適を見ろ」と静かに言葉を発しました。その一言で現場の空気は一変します。各社が垣根を越えて協力し、海水をあえて上から注入して水圧で地盤を安定させるという逆転の発想を採用。地中から吹き上がる水の勢いを封じ込め、緩んだ地盤を高圧注入材で固める作業が続けられました。
数時間にわたる必死の対応の末、出水は止まり、トンネルの崩壊も免れました。この危機を乗り越えた瞬間、現場にいた作業員たちは互いに無言でうなずき合ったといいます。
この出来事は、東京湾アクアライン建設の転換点となり、「100社の力が一つになった瞬間」と語り継がれています。
家族への想いを胸に、技術者たちは掘り進む
1994年、東京湾アクアラインの建設現場に、待望の新しい機械が導入されました。川崎重工業と三菱重工業が共同開発した、当時世界最高性能を誇るシールドマシンです。直径14メートルにも及ぶ巨大な掘削機で、これまでの機械では不可能だった軟弱地盤での精密掘削を可能にしました。まさに日本の誇る最先端技術が結集した一台でした。
そのシールドマシンの開発チームの一員として現場に派遣されたのが、松田豊でした。彼は神戸からの出張者で、工場で培った知識と経験を活かし、現場での調整や整備にあたっていました。機械の性能を最大限に引き出すため、毎日の点検作業やデータ収集を欠かさず行い、仲間たちからも信頼を寄せられる存在でした。
しかし、そんな松田を思いもよらぬ悲劇が襲います。1995年1月17日、彼が現場で作業をしている最中に、突如として阪神・淡路大震災が発生しました。家族が暮らす兵庫県須磨区は激しい揺れに見舞われ、多くの住宅が倒壊。火災も広がり、街全体が混乱に包まれました。松田はすぐに家族の安否を確認しようとしましたが、通信が途絶し、電話もつながらない状況。遠く離れた川崎人工島の現場で、ただ祈ることしかできませんでした。
現場には、同じように被災地に家族を持つ作業員が多くいました。誰もが動揺し、重い空気が流れていました。そんな中、現場責任者の高野孝が静かに口を開きました。
「家族のもとへ帰れ。」
その言葉に、張り詰めた空気が一気に緩み、作業員たちは涙をこらえながら次々に帰郷の準備を始めました。
松田豊は仲間と話し合いの末、「自分は最後に帰る」と決めました。彼は機械の調整を続けながら、仲間が家族のもとへ帰るのを見送りました。全員を送り出したあと、ようやく彼も神戸へ向かいます。
故郷の須磨区に戻ると、街は瓦礫と煙の中にありました。幸いにも妻と子どもは無事でしたが、避難所生活を余儀なくされ、夜は車の中で過ごす日々が続いていました。松田は妻の手を取り、「完成したら一緒にアクアラインを渡ろう」と静かに約束しました。
その言葉どおり、彼は一週間後には再び現場に戻り、作業を再開しました。疲れ切った体を押しながらも、仲間と共にシールドマシンを再び動かし始めたのです。
震災で家族を想う気持ちと、仲間と築いた信頼。その両方を胸に、松田は海底トンネルの掘削という国家的プロジェクトに再び立ち向かいました。
後に松田は語っています。
「現場に戻るのは怖かった。でも、自分がやらなければ機械は動かない。仲間も家族も、それを理解してくれていた。」
この言葉には、技術者としての使命感と家族への愛情が込められていました。
震災を乗り越えた彼の再出発は、まさに日本のものづくりの底力を象徴するエピソードとして、今も多くの人の記憶に残っています。
壁を破る一瞬の決断、そして奇跡のドッキング
東京湾アクアラインの建設が進む中、次なる大きな壁が立ちはだかりました。川崎人工島からシールドマシンを発進させる直前、技術者たちは地中の壁が想定をはるかに超えて異常な硬さになっていることに気づきます。本来は柔らかいはずの地盤が、圧力と時間の経過によって固まり、まるで岩盤のような状態になっていたのです。
通常であれば、掘削機の刃を入れても進めないほどの硬さ。少しでも無理をすれば、マシンが損傷し、作業員の命を危険にさらすおそれがありました。現場は一時緊迫した空気に包まれ、誰もが次の手を迷っていました。そんな中、現場のリーダーである鹿島建設の高野孝が静かに口を開きます。
「発破でいく。」
その一言は、現場全体を震わせました。発破(爆破)とは、爆薬を使って地盤を破壊する方法。海底トンネルという極限の環境では、少しの誤差や振動でも大事故につながりかねない危険な手段でした。それでも高野は、これ以上の遅れが全体計画に影響することを冷静に判断し、あえてリスクを取る決断を下したのです。
慎重な準備の末、爆薬が設置され、現場には緊張が走りました。作業員たちは遠く離れた安全地帯に退避し、合図とともに爆音が海底に響き渡ります。しばらくして、粉じんが落ち着いたあと、掘削班が現場へ戻ると、厚く立ちはだかっていた壁は見事に突破されていたのです。
この瞬間、作業員たちは安堵の笑みを浮かべ、誰もが「やっと道が開けた」と感じたといいます。プロジェクトは再び動き出しました。
そして翌年、1996年。東京湾のほぼ中央に位置する海ほたるパーキングエリアの基礎工事が完成しました。海に浮かぶように見えるこの人工島は、トンネルと橋をつなぐ重要な中継地点。巨大なコンクリート構造物を海上に固定するため、精密な位置計算と耐潮設計が施されました。
残された最大の難関は、両側から掘り進めたトンネルを誤差わずか5ミリ以内でつなぐという、世界でも例のない精度を要求される作業でした。片方は川崎側、もう片方は木更津側。距離にして10キロ、わずかな角度のズレでも噛み合わないため、シールドマシンの進行方向を常にミリ単位で調整しながら掘り進めました。
ついに両側のマシンが接合点に近づいた瞬間、現場では誰もが息をのんで計測機の針を見つめました。計測結果は――誤差5ミリ以内。直径14メートルのシールドが、まるで設計図通りにぴたりと重なったのです。
この成功は、世界中の土木技術者を驚かせました。わずか数ミリの精度で海底の両端を結んだ技術力は、まさに日本の精密土木技術の象徴。現場では静かな拍手が起こり、誰もが胸の奥で達成感を噛みしめていました。
こうして、東京湾アクアラインは完成に向けて大きく前進したのです。
台風と停電、極限の現場で走った男
完成が目前に迫った東京湾アクアラインの建設現場に、最後の試練が訪れました。1996年秋、巨大な台風が本州に接近し、海上の現場を直撃。強風と高波に襲われた現場では、電力設備が損傷し、突如として停電が発生しました。
そのとき止まってしまったのが、トンネル工事を支える命綱ともいえる地盤凍結機でした。凍結機は、地中の水分を凍らせて壁のように固め、掘削中に水や土砂が流れ込むのを防ぐための重要な装置です。もしこの装置が止まれば、地中の凍土は急速に溶け出し、わずか数時間でトンネル内に大量の水が流れ込み、工事が崩壊する危険がありました。まさに“一触即発”の非常事態でした。
現場にいたのは、当直担当だった富田一隆。暗闇の中でアラームが鳴り響き、凍結機の警告ランプが一斉に点滅します。状況を確認した富田は、すぐに上司へ連絡。復旧班からは「8時間以内に再稼働できなければ、すべてが終わる」と告げられました。電気の復旧作業は始まったものの、制御系統が損傷しており、機械は自動では動かない。手動で再起動させるしか方法はありませんでした。
凍結機は4か所に分かれており、それぞれの距離は数キロ単位。暴風の中、富田は懐中電灯ひとつを頼りに走り出しました。足元はぬかるみ、潮風が顔を打つ。息を切らしながらも、1台目、2台目と順番に起動スイッチを回していきます。汗と雨で全身がびしょ濡れになりながらも、計器が「稼働」に変わるたび、胸の中にわずかな希望が灯りました。
3台目の凍結機を動かし終えたころには、すでに10km以上を走り抜けていました。体力は限界に近づき、足もふらつき始めます。そんなとき、近くに止めてあった自転車を見つけた富田は、それにまたがり、最後の凍結機へと向かいました。ペダルを必死にこぎながら、嵐の中を突き進みます。
ようやく到着した最後の装置では、配管が破損していました。富田は手作業で工具を握り、冷却管の継ぎ目を修理。手がかじかむ寒さの中、なんとか再接続を完了させました。そして起動レバーを押すと、重低音とともに凍結機が再び動き出しました。メーターが安定し、凍土の温度が下がり始めたのを確認した瞬間、富田はその場に崩れ落ちるように座り込んだといいます。
こうして危機は回避され、地中の凍土は保たれました。翌朝、電力が完全に復旧。現場では誰もが富田の行動に感謝し、彼の冷静な判断と行動力をたたえました。
そして1997年、東京湾アクアラインは無事に完成。10年に及ぶ“土木のアポロ計画”が、ついに形となりました。
後に富田は、「自転車が見つからなければ間に合わなかった。あの時は、とにかく走るしかなかった」と当時を振り返っています。
彼の勇気と責任感が、最後のピースをつなぎ、日本の土木史に残る偉業を完成へと導いたのです。
未来へ続く道、アクアラインが残したもの
東京湾アクアラインが開通してから28年。今では1日あたり5万台以上の車がこの海底道路を行き交い、千葉と神奈川を結ぶ「命の大動脈」として日本の暮らしを支えています。かつて“夢の道”と呼ばれたアクアラインは、今や物流・観光・防災の要として欠かせない存在となりました。
特にその価値が大きく実感されたのが、2011年の東日本大震災のときでした。地震によって多くの道路や鉄道が寸断される中、東京湾アクアラインは被災地支援のための緊急輸送ルートとして活躍しました。物資を積んだ大型トラックが昼夜を問わず行き交い、被災地へと救援物資を届ける。1日あたり9000台を超えるトラックが通行したと記録されています。建設当初に掲げられた「災害時の代替ルートとしての役割」が、まさに現実のものとなった瞬間でした。
この道の完成を見届けた技術者たちの中でも、忘れられない存在が鹿島建設の高野孝です。彼は、プロジェクトリーダーとして100社を超える企業をまとめ上げた人物でした。完成後も毎年、かつての仲間たちを食事会に招き、「よくやった。お前たちは本当によく頑張った」と笑顔で声をかけていたといいます。部下たちは、その優しさと厳しさを兼ね備えた人柄を今も語り継いでいます。
高野は晩年までアクアラインを誇りに思い、亡くなる7年前まで毎年欠かさず集まりを続けていたそうです。仲間の絆を何よりも大切にしたその姿勢が、いまも多くの技術者たちの心に生きています。
一方、建設当時に現場を支えた米沢実は、今でも高野の言葉を胸に刻んでいます。
「自分のことだけを考えるな。全体がうまくいくように判断しろ。」
この言葉は、ただの指示ではなく、チームを率いる者としての哲学でした。米沢は後に「この言葉が、自分の仕事の道しるべになった」と語っています。プロジェクト全体を見渡す視点を教えられたことで、彼はその後も多くの大規模工事でリーダーとして活躍しました。
そしてもう一人、松田豊にも忘れられない思いがありました。阪神・淡路大震災で家族を被災させながらも、「完成したら一緒に渡ろう」と妻に誓って現場へ戻った彼。アクアラインの完成後、約束どおり妻とハンドルを握り、神奈川から千葉へと走り抜けました。
海の上に浮かぶ海ほたるパーキングエリアで車を停め、二人で見た東京湾の景色。その時の松田の笑顔は、長い年月の苦労と信念、そして家族への想いがすべて詰まったものでした。
東京湾アクアラインは、単なる道路ではありません。そこには技術者たちの情熱、仲間との絆、そして家族への想いが刻まれています。彼らが築いた道は、今も静かに海の下を支え続け、日本の未来へとつながっています。
まとめ
この記事のポイントは以下の3つです。
・東京湾アクアラインは「土木のアポロ計画」と呼ばれた前人未到の挑戦だった
・米沢実、高野孝、松田豊、富田一隆らの人間ドラマが奇跡を生んだ
・今では1日5万台以上が通行する、日本の誇るインフラとして活躍している
この壮大な道は、単なる交通インフラではありません。
それは、人の絆と技術の結晶。
誰かの「不可能を信じない心」が、今日も東京湾の下で静かに息づいているのです。
気になるNHKをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。

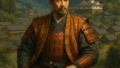

コメント